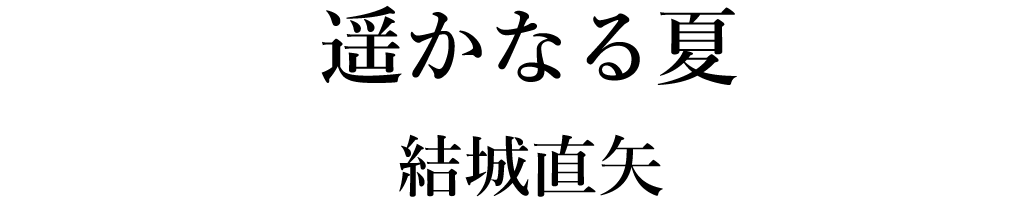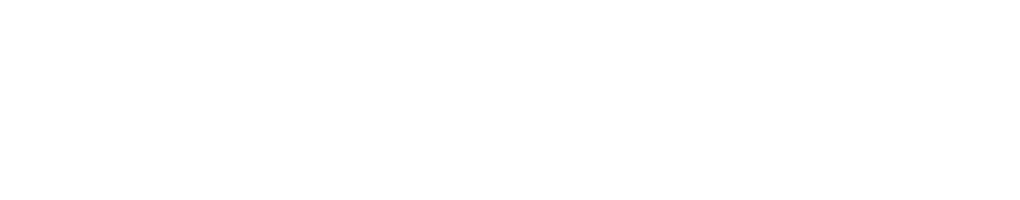No.7 辛かった、若き日に交わした約束
「和也、もうそろそろ起きないか」
ドアの開く音がして、そのわずかばかりの隙間から父親の顔が覗いているのが見えた。枕元の時計はすでに8時をまわっている。昨夜寝がけにうっかり目覚ましをセットするのを忘れていた。和也は慌ててベッドから飛び起き、身支度を始めた。
「学校には休むと連絡しておいたから、久しぶりに父さんと車でも飛ばさないか」
ドアの向こう側で正己の力のない声が遠のいていった。
車中で、和也は押し黙ったままだった。 「和也、友達は出来たか?……」 ぽつりと正己が小声で訊いた。 「昨日学校から連絡があった。お前が休んでるって。どこか具合でも悪いのかってきいてた」 無断で学校を休んだことは、いずれ正己の耳に入るものと予想はしていた。当然叱責されるものと和也は覚悟していたが、思ったより正己の口調は穏やかだった。 「どうして休んだんだ?……」 感情の高ぶりを押さえたような正己の声だった。 「あわないんだ……どうしても……」 それだけ言うのが和也には精いっぱいだった。 「帰りたいよ……東京に……」 しばらく間をおいて、物憂げに和也は言った。正己はハンドルを強く握りしめ、黙ったままでいた。その気づまりな空気から顔を背けるように、和也はウインドウの外に目を投じた。 正己と言葉を交わす気にもなれなかった。昨日……もう少しであのデパートの屋上からトモナガのように飛び降りるところだった……。 そうなってもおかしくないほど気分は暗澹として最悪だった。もう少しのところだった。幸いにも、理性がそれを押しとどめた。和也は背筋にヒヤリとしたものを感じた。 「昔、父さんと母さんが出会ったところに行ってみないか」ふと、正己は思い出したように言った。和也は上の空でそれを聞いていた。 正己は腕時計を見て、それから無言のままBMWを滑るように走らせた。緑のたなびく田園地帯を抜け、木々の濃い影の落ちた砂利道を走り、崖の迫る急坂になった曲がりくねった路を危なげに走行した。20分ほど過ぎた頃であろうか、ようやく目の端に海がかかってきた。 窓から、みずみずしい昼前の空と凪いだ静かな海が見えた。海岸では海開きを前に、数人の気の早い若者たちが波と戯れていた。 少しばかり湘南の海にも似ているが、どこでも目にするようなありふれた海岸線だ。右端に見える白いドーム型の建物はたぶん水族館にちがいない。小さな子供を連れた家族が列を成している。海岸は所々流木で覆われているが、地元の人々が定期的に掃除しているのだろう、荒れた印象はない。なだらかな砂山がゆったりとした曲線を遠くまで這わせている。 朝の淡い陽光を受けて踊る海面の小さな鋭角のさざめきを見ていると、不思議に和也の心はなごんだ。 正己は目的の場所に到着したことを確認すると、車を止めた。 2人は車から出ると、海の匂いを全身に浴び、ぬかるむ砂浜を歩いた。頬をよぎる微風に適度な温もりがあった。正己は両手を空に向かって伸ばし、太陽の光を大きく吸い込んだ。ふだんから足早な正己に和也は遅れがちになった。 「あそこに、建てるんだ。母さんの夢だった真っ白なレストランを」急に正己は立ち止まり、なだらかな砂山のその先に見える高台を指差した。 「なんとしてもその夢をかなえたいと思ってる」 微かに正己の声が震えて聞こえたのは、風のせいだけではないような気がした。砂を踏みしめながら、和也は母親の夢の産物を思い描いた。外観が白で統一され…けばけばしい装飾もなく…清楚で落ち着いた雰囲気…上品な感じの…たぶん、横浜のあのレストランと同じような・・・。 「和也。こっち、こっち」 ふと、顔をあげると、少し離れた所で正己の声が聞こえてきた。正己は砂の盛り上がりに座り、手招きしていた。 目の前では、青々とした大海原が余裕たっぷりの表情で横たわっていた。空は白い雲を一掃して自慢げに照り輝いている。 「和也。気持ちいいだろ」 「うん」 和也は日本海の潮の香りを鼻先に引き寄せながら正己の横に腰を下ろした。 「母さんと一緒になった時、2人でここに来たことがあるんだ。両方の親から結婚を反対されて、まいっていた時に、どこか旅行でもしようかっていうことになって」 正己は若き頃を感慨深げに振り返り、和也に語りはじめた。 「それでどこにしようかっていうことになって、どこでもよかったんだが、母さんがどうしてもここに来たがって……父さんと最初に出会った思い出の場所だからって……」 正己の顔はまるでその当時の大学生の顔だった。 「その時は母さんもここにレストランを建てようなんて思ってもなかった。ここを発つ最後の日だったかなあ……朝早く起きて夜明けの海岸を2人で歩いて……まだ薄暗くて誰もいなくて……砂浜には父さんと母さんの2人だけの足跡が点々と刻まれてた……その頃2人とも親から勘当されて駆け落ちでもしているような状態で、金もないし先行き不安だらけで……世間知らずの若い2人がうまく世の中を渡っていけるかどうか心配だった……振り返ると後ろには自分たちの歩いてきた足跡がしっかり砂の上に刻まれて道が出来ているのに、肝心の目の前には道らしい道はない……将来のことを考えると、不安だった……母さんはそんな父さんの心の内を察して……後ろ向きの生き方じゃなくて、前向きに生きなきゃって言って……それで何か自分たちの道しるべになる目標を持って生きていこうということになったんだ……その時に母さんがここに豪華な真っ白なレストランを建てようって言いだした……ほんとに夢みたいな話で、その時父さん思わず笑ったけど、でも母さんの目は真剣そのものだった……今は金もなく、力もないけど、いつか皆を見返してやろうじゃないかって……」 正己はそこまで言うと、一息ついた。 「母さんが亡くなった時、父さん何も手につかなくなってしまって……情けない話、父さんにもいろいろ計画があったんだけど……みんな途中でダメになって……どれ一つとしてまともにものにならなかった……悩んだよ、和也、父さんこれでも……そんな時ふと、母さんとここで誓った日のことを思い出したんだ……貧しかった若い頃に見た夢のことを……だからここに来たのはあの時の気持ちになってもう一度やり直すためでもあるんだ……」 正己は、胸に秘めた思いの全てを語りつくしたといった顔でゆっくり息を吐き、当時をなつかしむかのようにぐるりと砂浜を見渡した。 そこから50メートルも離れた砂の急斜面では、若者たちが色あざやかなコスチュームに身を包み、空に向かって伸びやかな奇声を放ちながら、勢いよくハンググライダーに飛び乗り、日本海から吹きつける風を利用して高く舞い上がり、つかの間の鳥の気分を満喫していた。 海の上では蛍光色の帆を立てたウインドサーフィンのボードがなめらかなすべりを見せていた。正己はそうした風景から目をそむけ、すぐ傍の砂地を這っている、何10年も根をはやし続けてきたようなコウボウムギの褐色の鞘をしばらく見つめていた。 「父さんの言ってることはわかるよ……でも」 「学校が合わないのか……」 和也は正己に胸の内を見抜かれたような気がして言葉に詰まり、何も答えることが出来なかった。 「わかるさ……父さんにも……それくらい……」 和也は返事に戸惑い、うつむいたまま手の平にのった砂が指の間からこぼれ落ちていく様をじっと見入っていた。 「ここにお前を連れてくることについては父さんもよく考えた……ほんとはお前を東京に残して父さんだけで来てもよかったんだが……」 正己も和也と同じように手で砂をすくった。 「和也、ほんと言うと、ここにお前を連れてきたのはお父さんたちの夢のためだけじゃない……母さん、亡くなる前に、和也、お前を一人っ子ということで過保護に育てたんじゃないかって言って……父さんはけっしてそうは思わなかったが、でも母さんはお前を自立できない弱い子にしたんじゃないかって心配してた……もちろんそうだとしたらそれは父さんや母さんのせいなんだが……それで母さん、父さんに託したんだ……和也を強い子に育ててくれって……どんな環境でもたくましく生きていける子にして欲しいって……それでお前も一緒に連れて行くことに決めたんだ。だから肌合いの違う人達の中でお前がいろいろな問題に出会って悩むだろうということはあらかじめ父さんも予測してた……」 「もう十分嫌な思いをしてるさ……」 手についた砂を振り払い、ふてくされたように和也は答えた。 「そんなことをされる覚えもないのに皆がぼくをイジメるんだ」 「なぜそんなことになったのかよく考えてみたのか?」 「なぜって、わからないよ。そんなこと……米多という奴がいて、そいつが皆をけしかけてるんだ」 「前の中学だって似たような生徒はいただろう」 「あそこは、ここほどじゃないさ」 「トモナガ君が身代わりになってくれたからか?」 「そんなんじゃないよ。とにかくここの連中ときたらやり方が汚いよ。みんなでよってたかってだもん」 「トモナガ君の時だってそうじゃなかったのか?みんなが見て見ぬ振りをして、知らんぷりをしてれば周り全部が敵にも見えてくるさ」 「いいかげん、頭がおかしくなりそうだよ」 もはや逃げ場のない所まで追い詰められたといった、切羽詰まった和也の声だった。 「東京に帰りたいよ」 「帰らない」 すぐに断固たる口調で、和也の訴えをはねつけるように正己が言い返した。 「お前がそんなふうなら、なおさら帰るわけにはいかない」 正己は横目で和也を見据えて言いきった。 「今、つらいからって、ここで逃げ出したら、やっぱり母さんの心配してた通りだって、自分から証明するようなもんじゃないか、和也。やっぱりぼくは、ひとりっ子の弱い人間でしたって、自分でそう言ってるようなもんじゃないか」 「父さんにはわからないさ。あいつらがどれだけ卑劣な連中か。ぼくじゃなくたって、ほかの人間だって耐えられないよ、きっと……ぼくは、ただちゃんと勉強がしたいだけなんだ……それなのにあいつら、邪魔ばっかりして……程度が低いんだよ」 「そんなふうに、心のどこかでお前が思ってるから、反感をかわれてるんじゃないのか?」 「そんなことないさ」 「和也、お前は勉強が好きだから、それを邪魔されれば頭にくるかもしれない。つらいかもしれない。思い通りにならなくて嫌になるかもしれない。でも、和也、この世の中に自分の思い通りになるようなものなんてあるだろうか?どんな金持ちだってどんなに偉い人だって、いろんな悩みをかかえながら、どこかでみんな不自由を感じながら、それでもみんななんとかやってるんじゃないのかなあ。実際、父さんだって仕事のことでいろんな妨害や嫌がらせをずいぶん受けてきた。でもそのたびに、がんばらなきゃって思って、今までやってきた。さすがに母さんが亡くなった時はショックで中々立ち直れなかったけど……」 「でも、もううんざりだよ、ここにいるのは……」 そう言って、手の平にこびりついていたわずかばかりの砂を和也はジーンズの裾で払った。 「和也、父さんはここに来て、お前のためにもよかったと思ってる」 正己のその答えは和也にとって意外だった。 「どういうこと?……」 「お前がここでつらい現実に直面してるということさ」 「どうしてそれがいいのさ」 「もし、お前が、子供の頃から何の苦労もなく、恵まれた環境の中で大きくなっていったとしたら……いざという時、足腰の立たない、根性のない、弱い人間になるんじゃないかって、そのほうがよっぽど心配だ」 「そんなこと言ったって、どうすればいいか、わかんないよ」 頭を垂れたまま、和也は困り果てたような顔で言った。正己は和也の苦悩に対する答えを頭のなかでしばらく探していた。そして顔を上げ、潮の香気を吸い込み、ふたたび和也のきめのこまかい肌の上に視線を固定させると、 「和也、例えば、父さんだったらこんなふうに考える。弱い自分をイジメて鍛えてくれてありがとうって。もしお前が強い人間だったら連中だって手だしできないだろ……だから連中がお前をイジメるのは弱い自分に目をかけて、強くなるまで鍛えてくれてるんだと思って……連中にイジメられてる間は自分にまだたくましさが欠けてるんだと思ってお前も頑張ればいいんだ……イジメっ子なんてのはもともと弱い子なんだ。自分の弱さを誰よりも知ってて自分に自信がないから、自分より弱そうな人間を見つけてはイジメて強そうにみせて虚勢を張ってるだけなんだ。だから連中にイジメられてる間はまだまだだとお前も思えばいいんだ。弱い人間がさらに弱い人間をイジメてるんだから。お前が強くたくましくなれば連中だって手だしできなくなるさ……弱い人間が強い人間をイジメられるはずがないんだから」 と、和也を元気づけた。 「……なんとなくわかったような気もするけど」 「それに、もし教室で1人で孤独だと思うんなら、孤独でも生きられるすべをそこから学べばいいんだ……わかるか、父さんの言ってることが……その場に合わせて生きられる心を養うんだ……この世に生まれて死ぬまでいろいろな問題にぶつかる……1人ぼっちの時があってもいいじゃないか……死ぬまで1人ぼっちなんて有り得ないんだから……その時は1人ぼっちの気分を味わうだけ味わってみればいいじゃないか……その時は辛いかもしれない……苦しいかもしれない……でもそんな状況の中でも平気で生きられる強い心を養ってほしいって父さん思ってるんだ……そのうち流れが変わる時が必ずやってくるさ……あの時は死ぬほど辛い経験をしたなあって、なつかしく振り返ることが出来る時が必ずやってくるさ……そんな経験を何度も重ねて人は立派な大人になるんだ……父さんの言う立派というのは人知れず苦労を重ねてきて人の痛みを自分の痛みと同じように感じられるという意味だ……そういう意味で大人になりきってない大人も世の中には大勢いるけど」 「耐えなきゃいけないってこと?……」 「立ち上がって、立ち向かっていかなきゃいけない時もある。もちろんある。だけど耐えることで学ぶことも多くあるということさ」 「でもツライよ。当人にしてみれば……」 「みんなツライのさ……和也、お前だけじゃない……父さんだって、誰だって……楽に生きてる人間なんてこの世にいるもんか……みんな悩みを抱えながら生きてるんだ……表向きはそんなふうに見えなくても……」 正己はそう言うとズボンについた砂を払い落としながら立ち上がった。 「和也、あのレストランの予定地まで走らないか?」 正己は満面の笑みを浮かべ、軽く和也の頭を軽く叩いて走り出した。 「やだよ。疲れるよ」そう言いながらも、おもむろに和也は立ち上がり、正己に遅れまいと駈け出した。 海から吹きつける風が濃い潮の香を運んできた。ともかく、ここで生きていかなきゃならない。後ろを振り向かず、前だけ見て歩くんだ……過去の澱みに足踏みばかりしてても未来は微笑みかけてくれるはずもない……和也はぬかるむ砂を強く踏みしめながら、歩を進めた。 広々とした日本海を眺めながら正己と話をして、胸に巣くっていた憂さがいくらか晴れたような気がした。淡い陽光が体温を少しずつ押し上げていくのを感じた。
No.8 4日ぶりに登校した学校
車中で、和也は押し黙ったままだった。 「和也、友達は出来たか?……」 ぽつりと正己が小声で訊いた。 「昨日学校から連絡があった。お前が休んでるって。どこか具合でも悪いのかってきいてた」 無断で学校を休んだことは、いずれ正己の耳に入るものと予想はしていた。当然叱責されるものと和也は覚悟していたが、思ったより正己の口調は穏やかだった。 「どうして休んだんだ?……」 感情の高ぶりを押さえたような正己の声だった。 「あわないんだ……どうしても……」 それだけ言うのが和也には精いっぱいだった。 「帰りたいよ……東京に……」 しばらく間をおいて、物憂げに和也は言った。正己はハンドルを強く握りしめ、黙ったままでいた。その気づまりな空気から顔を背けるように、和也はウインドウの外に目を投じた。 正己と言葉を交わす気にもなれなかった。昨日……もう少しであのデパートの屋上からトモナガのように飛び降りるところだった……。 そうなってもおかしくないほど気分は暗澹として最悪だった。もう少しのところだった。幸いにも、理性がそれを押しとどめた。和也は背筋にヒヤリとしたものを感じた。 「昔、父さんと母さんが出会ったところに行ってみないか」ふと、正己は思い出したように言った。和也は上の空でそれを聞いていた。 正己は腕時計を見て、それから無言のままBMWを滑るように走らせた。緑のたなびく田園地帯を抜け、木々の濃い影の落ちた砂利道を走り、崖の迫る急坂になった曲がりくねった路を危なげに走行した。20分ほど過ぎた頃であろうか、ようやく目の端に海がかかってきた。 窓から、みずみずしい昼前の空と凪いだ静かな海が見えた。海岸では海開きを前に、数人の気の早い若者たちが波と戯れていた。 少しばかり湘南の海にも似ているが、どこでも目にするようなありふれた海岸線だ。右端に見える白いドーム型の建物はたぶん水族館にちがいない。小さな子供を連れた家族が列を成している。海岸は所々流木で覆われているが、地元の人々が定期的に掃除しているのだろう、荒れた印象はない。なだらかな砂山がゆったりとした曲線を遠くまで這わせている。 朝の淡い陽光を受けて踊る海面の小さな鋭角のさざめきを見ていると、不思議に和也の心はなごんだ。 正己は目的の場所に到着したことを確認すると、車を止めた。 2人は車から出ると、海の匂いを全身に浴び、ぬかるむ砂浜を歩いた。頬をよぎる微風に適度な温もりがあった。正己は両手を空に向かって伸ばし、太陽の光を大きく吸い込んだ。ふだんから足早な正己に和也は遅れがちになった。 「あそこに、建てるんだ。母さんの夢だった真っ白なレストランを」急に正己は立ち止まり、なだらかな砂山のその先に見える高台を指差した。 「なんとしてもその夢をかなえたいと思ってる」 微かに正己の声が震えて聞こえたのは、風のせいだけではないような気がした。砂を踏みしめながら、和也は母親の夢の産物を思い描いた。外観が白で統一され…けばけばしい装飾もなく…清楚で落ち着いた雰囲気…上品な感じの…たぶん、横浜のあのレストランと同じような・・・。 「和也。こっち、こっち」 ふと、顔をあげると、少し離れた所で正己の声が聞こえてきた。正己は砂の盛り上がりに座り、手招きしていた。 目の前では、青々とした大海原が余裕たっぷりの表情で横たわっていた。空は白い雲を一掃して自慢げに照り輝いている。 「和也。気持ちいいだろ」 「うん」 和也は日本海の潮の香りを鼻先に引き寄せながら正己の横に腰を下ろした。 「母さんと一緒になった時、2人でここに来たことがあるんだ。両方の親から結婚を反対されて、まいっていた時に、どこか旅行でもしようかっていうことになって」 正己は若き頃を感慨深げに振り返り、和也に語りはじめた。 「それでどこにしようかっていうことになって、どこでもよかったんだが、母さんがどうしてもここに来たがって……父さんと最初に出会った思い出の場所だからって……」 正己の顔はまるでその当時の大学生の顔だった。 「その時は母さんもここにレストランを建てようなんて思ってもなかった。ここを発つ最後の日だったかなあ……朝早く起きて夜明けの海岸を2人で歩いて……まだ薄暗くて誰もいなくて……砂浜には父さんと母さんの2人だけの足跡が点々と刻まれてた……その頃2人とも親から勘当されて駆け落ちでもしているような状態で、金もないし先行き不安だらけで……世間知らずの若い2人がうまく世の中を渡っていけるかどうか心配だった……振り返ると後ろには自分たちの歩いてきた足跡がしっかり砂の上に刻まれて道が出来ているのに、肝心の目の前には道らしい道はない……将来のことを考えると、不安だった……母さんはそんな父さんの心の内を察して……後ろ向きの生き方じゃなくて、前向きに生きなきゃって言って……それで何か自分たちの道しるべになる目標を持って生きていこうということになったんだ……その時に母さんがここに豪華な真っ白なレストランを建てようって言いだした……ほんとに夢みたいな話で、その時父さん思わず笑ったけど、でも母さんの目は真剣そのものだった……今は金もなく、力もないけど、いつか皆を見返してやろうじゃないかって……」 正己はそこまで言うと、一息ついた。 「母さんが亡くなった時、父さん何も手につかなくなってしまって……情けない話、父さんにもいろいろ計画があったんだけど……みんな途中でダメになって……どれ一つとしてまともにものにならなかった……悩んだよ、和也、父さんこれでも……そんな時ふと、母さんとここで誓った日のことを思い出したんだ……貧しかった若い頃に見た夢のことを……だからここに来たのはあの時の気持ちになってもう一度やり直すためでもあるんだ……」 正己は、胸に秘めた思いの全てを語りつくしたといった顔でゆっくり息を吐き、当時をなつかしむかのようにぐるりと砂浜を見渡した。 そこから50メートルも離れた砂の急斜面では、若者たちが色あざやかなコスチュームに身を包み、空に向かって伸びやかな奇声を放ちながら、勢いよくハンググライダーに飛び乗り、日本海から吹きつける風を利用して高く舞い上がり、つかの間の鳥の気分を満喫していた。 海の上では蛍光色の帆を立てたウインドサーフィンのボードがなめらかなすべりを見せていた。正己はそうした風景から目をそむけ、すぐ傍の砂地を這っている、何10年も根をはやし続けてきたようなコウボウムギの褐色の鞘をしばらく見つめていた。 「父さんの言ってることはわかるよ……でも」 「学校が合わないのか……」 和也は正己に胸の内を見抜かれたような気がして言葉に詰まり、何も答えることが出来なかった。 「わかるさ……父さんにも……それくらい……」 和也は返事に戸惑い、うつむいたまま手の平にのった砂が指の間からこぼれ落ちていく様をじっと見入っていた。 「ここにお前を連れてくることについては父さんもよく考えた……ほんとはお前を東京に残して父さんだけで来てもよかったんだが……」 正己も和也と同じように手で砂をすくった。 「和也、ほんと言うと、ここにお前を連れてきたのはお父さんたちの夢のためだけじゃない……母さん、亡くなる前に、和也、お前を一人っ子ということで過保護に育てたんじゃないかって言って……父さんはけっしてそうは思わなかったが、でも母さんはお前を自立できない弱い子にしたんじゃないかって心配してた……もちろんそうだとしたらそれは父さんや母さんのせいなんだが……それで母さん、父さんに託したんだ……和也を強い子に育ててくれって……どんな環境でもたくましく生きていける子にして欲しいって……それでお前も一緒に連れて行くことに決めたんだ。だから肌合いの違う人達の中でお前がいろいろな問題に出会って悩むだろうということはあらかじめ父さんも予測してた……」 「もう十分嫌な思いをしてるさ……」 手についた砂を振り払い、ふてくされたように和也は答えた。 「そんなことをされる覚えもないのに皆がぼくをイジメるんだ」 「なぜそんなことになったのかよく考えてみたのか?」 「なぜって、わからないよ。そんなこと……米多という奴がいて、そいつが皆をけしかけてるんだ」 「前の中学だって似たような生徒はいただろう」 「あそこは、ここほどじゃないさ」 「トモナガ君が身代わりになってくれたからか?」 「そんなんじゃないよ。とにかくここの連中ときたらやり方が汚いよ。みんなでよってたかってだもん」 「トモナガ君の時だってそうじゃなかったのか?みんなが見て見ぬ振りをして、知らんぷりをしてれば周り全部が敵にも見えてくるさ」 「いいかげん、頭がおかしくなりそうだよ」 もはや逃げ場のない所まで追い詰められたといった、切羽詰まった和也の声だった。 「東京に帰りたいよ」 「帰らない」 すぐに断固たる口調で、和也の訴えをはねつけるように正己が言い返した。 「お前がそんなふうなら、なおさら帰るわけにはいかない」 正己は横目で和也を見据えて言いきった。 「今、つらいからって、ここで逃げ出したら、やっぱり母さんの心配してた通りだって、自分から証明するようなもんじゃないか、和也。やっぱりぼくは、ひとりっ子の弱い人間でしたって、自分でそう言ってるようなもんじゃないか」 「父さんにはわからないさ。あいつらがどれだけ卑劣な連中か。ぼくじゃなくたって、ほかの人間だって耐えられないよ、きっと……ぼくは、ただちゃんと勉強がしたいだけなんだ……それなのにあいつら、邪魔ばっかりして……程度が低いんだよ」 「そんなふうに、心のどこかでお前が思ってるから、反感をかわれてるんじゃないのか?」 「そんなことないさ」 「和也、お前は勉強が好きだから、それを邪魔されれば頭にくるかもしれない。つらいかもしれない。思い通りにならなくて嫌になるかもしれない。でも、和也、この世の中に自分の思い通りになるようなものなんてあるだろうか?どんな金持ちだってどんなに偉い人だって、いろんな悩みをかかえながら、どこかでみんな不自由を感じながら、それでもみんななんとかやってるんじゃないのかなあ。実際、父さんだって仕事のことでいろんな妨害や嫌がらせをずいぶん受けてきた。でもそのたびに、がんばらなきゃって思って、今までやってきた。さすがに母さんが亡くなった時はショックで中々立ち直れなかったけど……」 「でも、もううんざりだよ、ここにいるのは……」 そう言って、手の平にこびりついていたわずかばかりの砂を和也はジーンズの裾で払った。 「和也、父さんはここに来て、お前のためにもよかったと思ってる」 正己のその答えは和也にとって意外だった。 「どういうこと?……」 「お前がここでつらい現実に直面してるということさ」 「どうしてそれがいいのさ」 「もし、お前が、子供の頃から何の苦労もなく、恵まれた環境の中で大きくなっていったとしたら……いざという時、足腰の立たない、根性のない、弱い人間になるんじゃないかって、そのほうがよっぽど心配だ」 「そんなこと言ったって、どうすればいいか、わかんないよ」 頭を垂れたまま、和也は困り果てたような顔で言った。正己は和也の苦悩に対する答えを頭のなかでしばらく探していた。そして顔を上げ、潮の香気を吸い込み、ふたたび和也のきめのこまかい肌の上に視線を固定させると、 「和也、例えば、父さんだったらこんなふうに考える。弱い自分をイジメて鍛えてくれてありがとうって。もしお前が強い人間だったら連中だって手だしできないだろ……だから連中がお前をイジメるのは弱い自分に目をかけて、強くなるまで鍛えてくれてるんだと思って……連中にイジメられてる間は自分にまだたくましさが欠けてるんだと思ってお前も頑張ればいいんだ……イジメっ子なんてのはもともと弱い子なんだ。自分の弱さを誰よりも知ってて自分に自信がないから、自分より弱そうな人間を見つけてはイジメて強そうにみせて虚勢を張ってるだけなんだ。だから連中にイジメられてる間はまだまだだとお前も思えばいいんだ。弱い人間がさらに弱い人間をイジメてるんだから。お前が強くたくましくなれば連中だって手だしできなくなるさ……弱い人間が強い人間をイジメられるはずがないんだから」 と、和也を元気づけた。 「……なんとなくわかったような気もするけど」 「それに、もし教室で1人で孤独だと思うんなら、孤独でも生きられるすべをそこから学べばいいんだ……わかるか、父さんの言ってることが……その場に合わせて生きられる心を養うんだ……この世に生まれて死ぬまでいろいろな問題にぶつかる……1人ぼっちの時があってもいいじゃないか……死ぬまで1人ぼっちなんて有り得ないんだから……その時は1人ぼっちの気分を味わうだけ味わってみればいいじゃないか……その時は辛いかもしれない……苦しいかもしれない……でもそんな状況の中でも平気で生きられる強い心を養ってほしいって父さん思ってるんだ……そのうち流れが変わる時が必ずやってくるさ……あの時は死ぬほど辛い経験をしたなあって、なつかしく振り返ることが出来る時が必ずやってくるさ……そんな経験を何度も重ねて人は立派な大人になるんだ……父さんの言う立派というのは人知れず苦労を重ねてきて人の痛みを自分の痛みと同じように感じられるという意味だ……そういう意味で大人になりきってない大人も世の中には大勢いるけど」 「耐えなきゃいけないってこと?……」 「立ち上がって、立ち向かっていかなきゃいけない時もある。もちろんある。だけど耐えることで学ぶことも多くあるということさ」 「でもツライよ。当人にしてみれば……」 「みんなツライのさ……和也、お前だけじゃない……父さんだって、誰だって……楽に生きてる人間なんてこの世にいるもんか……みんな悩みを抱えながら生きてるんだ……表向きはそんなふうに見えなくても……」 正己はそう言うとズボンについた砂を払い落としながら立ち上がった。 「和也、あのレストランの予定地まで走らないか?」 正己は満面の笑みを浮かべ、軽く和也の頭を軽く叩いて走り出した。 「やだよ。疲れるよ」そう言いながらも、おもむろに和也は立ち上がり、正己に遅れまいと駈け出した。 海から吹きつける風が濃い潮の香を運んできた。ともかく、ここで生きていかなきゃならない。後ろを振り向かず、前だけ見て歩くんだ……過去の澱みに足踏みばかりしてても未来は微笑みかけてくれるはずもない……和也はぬかるむ砂を強く踏みしめながら、歩を進めた。 広々とした日本海を眺めながら正己と話をして、胸に巣くっていた憂さがいくらか晴れたような気がした。淡い陽光が体温を少しずつ押し上げていくのを感じた。