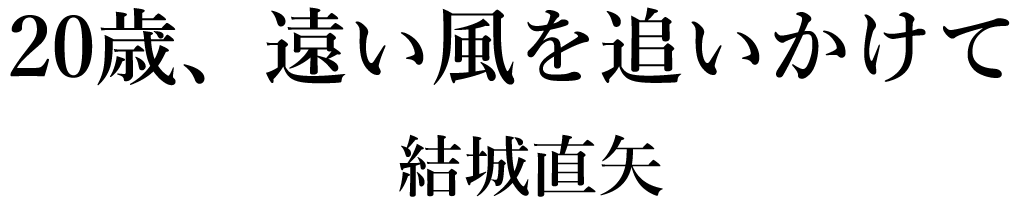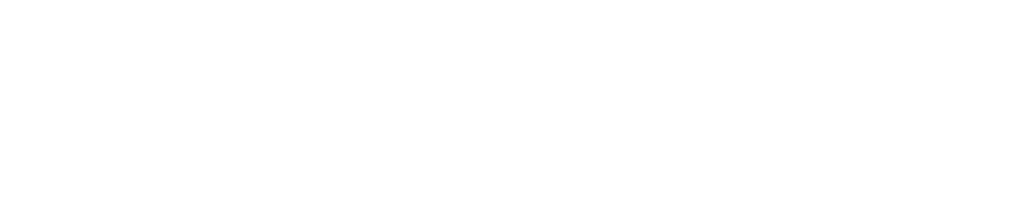No.14 別れ、旅立ちの日
9月に入ってすぐ警備会社から僕の替わりになる人が来た。8月に33歳になったばかりの石渡という背の低い童顔の気のよさそうな人だった。石渡さんは正社員ではなく、1ケ月ほど前に事務機器の会社を辞めた後、見習い待遇で警備会社に雇われていた。
僕は、2日ほど石渡さんに付いて、仕事の手順を教えた。石渡さんはのみこみが早く、半日で要領を覚えた。
「結構、荒っぽい運ちゃんもいますよね」肉まんのような福々しい顔に陥没した石渡さんの両目がうろついていた。
「中にはね、そんな人いますけど、最初だけですから、慣れると大丈夫ですよ。たまに缶コーヒーくれる人もいるし」
あと数日で、飯場での仕事も終わりかと思うと、ダンプのフロントで背中を押され、脅かされた日々が懐かしい。1日を無事に終えたことに感謝するかのようにクラクションを鳴らし、窓から手を振る運転手もいた。顔ぶれが中々定まらなかったが、おおむね気の良い人達だった。 誘導にもたつき、運転手と喧嘩しそうになり、杉町に助けられたのが昨日のことのようだ。奴は、どんな顔をして金沢の親に会ったのだろうか、と今でも思う。家出して、3年ぶりに帰ってきた息子を親はどんなふうに迎え入れたのだろう。歓喜にむせび泣いたのか、二度と敷居は跨がせないと、よくあるテレビドラマのように憤慨をあらわにしたのか、それとももうどこにも行かないでくれと懇願調だったのか、どうも想像がつかない。 飯場、といっても今にして思えば住めば都だ。木沼さんは雨の日も風の日も部屋ではいつも正座で大ぶりのヘッドフォンを耳に当て音楽を聞いていた。人は良いのだが、酒焼けのような赤ら顔に、半開きのだらしない口元が、どうしてもしまりのない警備を連想させる。 田牧隊長は英気を養うためのちょっとした息抜きだと言いつつ競輪に金というより、命を賭けていた。ひょっとしたら、木沼さんへの憤懣を疾走する選手らの背にぶちまけていたのかもしれない。 湯船の中でも『坂の上の雲』を読む川瀬さんの姿を湯気の向こうにしばしば見かけた。何度も読み返したらしく、司馬遼太郎がふやけて倍になっていた。僕はといえば3度の食事だけが心の支えだった。 旅立ちの日、僕はいつものように隊長のセットした目覚まし時計の音で6時に起きた。顔を洗うとすぐに、これで食い納めかと思いつつ食堂に行き、いつもの納豆に生卵に海苔に味噌汁の朝食を、勤務がないにもかかわらず、なにくわぬ顔でガツガツと腹に詰めた。頬ばりながら、飯場での初めての夕食を思い出した。 空腹の極みに立たされ、寒空にバイクをひきずりながらふらついていたあの時、飯場の人々の親切と温かい夕食の味がしみた。これから先、どんなに豪勢な食事を前にしてもあの日の夕食を忘れることはないだろう。 部屋へ戻ると、珍しく木沼さんが制服を着て、身支度を済ましていた。
「早いですね。今日は」
そう言うと、木沼さんは、
「制服を着たまま寝てたからね」
とまじめな顔で答えた。
「クズミくんさ、可愛い女の子に見とれて事故を起こしちゃだめだよ」
傍で笑みを浮かべながら隊長が声をかけた。
「それより、熊に襲われそうになったらどうする、クズミくん」
モトクロスパンツをはいていると、木沼さんが尋ねた。
「心配はいりません。北海道に着いたら熊のぬいぐるみに着替えてバイクに乗りますから」
僕は余裕で答えた。2人とも名案だと言って納得したようにうなずいた。 旅支度を済ませると、僕は正座し、隊長と木沼さんに別れの挨拶をした。
「隊長、木沼さん。ありがとうございました。ウソついて転がり込んだ僕を助けてくれて。あの時は本当に助かりました」僕の言葉に、2人とも無言で、照れたように顔を見合わせていた。 急に、隊長が思い出したように、「クズミくん、これ昼ごはんに」と言って、アルミホイールに包まれたおむすびらしき物を僕に差し出した。昨夜シーちゃん女将に無理を言ってにぎらせたのだろうか。さすがに、締める時はきちんと締める。尊敬に値するりっぱな大人だ。9月の澄み渡る空の下で、シーちゃん女将の可憐な指が触れたおむすびを頬ばるのも悪くない。にんまりしていると、「角さんがクズミくんがいなくなると淋しいねって、愛情を込めてにぎってくれたから」と隊長。……まあ、腹にいれてしまえば同じことだ。多少げんなりしながら、「大事に食べます」と礼を言った。 すると、木沼さんも急にそわそわして、その辺にあった先週のTVガイドをニコニコしながら僕に手渡した。一体それをどうしろというのだろうか。とりあえず、「大事に見ます」と言い、頭を下げた。 ふと戸口を見ると、川瀬さんがそこに立っていた。少しばかり目をにじませ、暇な時にこれを読みなさいと言って、僕に司馬遼太郎の真新しい帯付の文庫本を差し出した。そして、「あんたの得意な、打ち込める物さ見つけて、一生懸命やって、一番になんなさい。そうすればどこにいっても飯は食えるさ」と言い、微笑みながら軽く僕の肩に手を置いた。僕の中で何かが吹っ切れたような気がした。頭の中を一瞬、軽やかな風が通り抜けた。僕は、川瀬さんに深々と頭を下げた。 オフロードブーツを履いて外に出ると、量感のある雲の群れの間から太陽が細い光を滴らせ、辺りにはほどよいぬくもりが出来ていた。 僕は貴重品を入れたウエストバックを腰につけ、衣類やら日用品を詰め込んだサイドバッグをバイクの後部にしっかりとくくり付け、ネジを締め、最後の点検をおこなった。 全ての調整を済ませると杉町のいる部屋に行き、別れの挨拶をした。
「杉町、そいじゃあな。北海道に行ってくるから」
杉町は寂しそうに聞いていたが、別れ際にそこまで送ると言ってついてきた。 ヘルメットをかぶり、飯場に来た当初のことを思い出しながら宿舎をぐるっと見渡し、エンジンをふかしていると、2階の窓から木沼さんが顔を出し、手を振っているのが目に入った。 僕は右手を高々と上げ、Vサインを作ってそれに応えた。そして、その手を大きく振りながら、「ありがとう、行ってきまーす」と大声を放ち、ゆっくりバイクを前に転がした。杉町も後からバイクでついて来た。杉町は僕と同じ型のバイクをほんの数日前に買ったばかりだった。 バイクを走らせながら、ふと後ろを振り返るとまだ木沼さんが窓から顔を出し、手を振っていた。僕は一旦バイクを停め、もう一度大きく手を振って木沼さんに応えた。木沼さんとの日々を思い出し、飯場を離れるのが無性につらくなった。別れの寂寞感がこんなにも胸にしみたことはない。これから幾度こんな思いをしなければならないのだろうか。
振り切るように、再びエンジンをふかし、バイクを前へと進めた。 5、6分ほど走り込んだあたりで、バイクを止め、もうこの辺でいいからと杉町に言った。杉町はヘルメットから顔を出すと、微笑み、口もとを小さく開いて、「気をつけて行ってこいよ」と忠告した。
「これから、どうする」杉町とこのまま別れるのが名残り惜しかった。
「クズミのおかげでバイクにも乗れるようになった。俺はこれであの人を探す。これがあれば日本中どこへでも行けるから……」
杉町は顔を上げると僕の目を真っ直ぐ見て答えた。
……ちがう、そうじゃないだろう。何故か僕の中でこみあげるものがあった。
「杉町、オヤジさんが本当にお前に望んでるのはそんなことじゃねえだろう。俺は半ぱもんで、偉そうなことは言えないけど、お前は金沢に帰って本当の父親に頭下げて、政治家やりますって、もう一度出直せ。お前ならきっといい政治家になると思うぜ」
杉町はうなだれるように聞いていた。
「お前がりっぱになった姿を、オヤジさん、どっかの飯場のテレビで見たらきっと喜ぶだろうよ」念を押すように僕は言った。
杉町は口もとに笑みを浮かべ、「そうだな」と言って、軽くうなずいた。
「みんなわかってたんだよ。俺やお前の下手な芝居を。みんな知ってて、それでも何も言わずに、温かく迎え入れてくれてたんだ」俺も、お前もここで、無学でも心やさしい人たちに拾われ、救われた……だからいつか。そう言おうとしたが、そのまま口をつぐんだ。何も言わなくても杉町もわかっている。 僕は、ふたたびヘルメットをかぶると、エンジンをふかし、ゆっくりとバイクを走らせた。バックミラーにはいつまでも手を振っている杉町の姿が次第に小さくなって、遥か彼方へと遠のいていった。 広島の田舎から上京する時の両親の姿がふと瞼に浮かんだ。元気でね、なにかあったら電話するのよ。いつまでも心配げに、手を振りながら見送る母親がいた。電車の窓から、次第に小さく遠のいていく両親。僕は大学に入って、授業をさぼり、スロットに興じ、遊び呆けていた。醜いカサブタばかりを身につけてしまった。 私は無学で飯場を渡り歩く生活ですが、あの子には学校を出て人並な生活を送ってもらいたいと思います……杉町のオヤジさんの手紙の中にあったあの言葉。土埃で、目が霞んだ。 目の前には、乾いた土と石ばかりの道が続いていた。奥歯をグッと強く噛み、突き出た石を避けるようにジグザクにふらつきながら突き進んだ。 急に、両脇の林が視界からはずれ、明るい空の色が目に飛び込んできた。僕はアクセルを回し、スピードをあげ、風の中を突っ切った。 9月の涼風が大挙してブルゾンのジャケットに押し寄せてきたが、それをまともに受け止め、バイクを前へ前へと進めた。見上げると夏の残りの暑気が麗かな天空で渦巻き、目の前では垢抜けした陽光が縦横無尽にほどよく乾いた大地を飛び交っていた。 はたち、の……旅立ちか……。まだ見ぬ北海道の雄大な地に思いを馳せた。
完
「結構、荒っぽい運ちゃんもいますよね」肉まんのような福々しい顔に陥没した石渡さんの両目がうろついていた。
「中にはね、そんな人いますけど、最初だけですから、慣れると大丈夫ですよ。たまに缶コーヒーくれる人もいるし」
あと数日で、飯場での仕事も終わりかと思うと、ダンプのフロントで背中を押され、脅かされた日々が懐かしい。1日を無事に終えたことに感謝するかのようにクラクションを鳴らし、窓から手を振る運転手もいた。顔ぶれが中々定まらなかったが、おおむね気の良い人達だった。 誘導にもたつき、運転手と喧嘩しそうになり、杉町に助けられたのが昨日のことのようだ。奴は、どんな顔をして金沢の親に会ったのだろうか、と今でも思う。家出して、3年ぶりに帰ってきた息子を親はどんなふうに迎え入れたのだろう。歓喜にむせび泣いたのか、二度と敷居は跨がせないと、よくあるテレビドラマのように憤慨をあらわにしたのか、それとももうどこにも行かないでくれと懇願調だったのか、どうも想像がつかない。 飯場、といっても今にして思えば住めば都だ。木沼さんは雨の日も風の日も部屋ではいつも正座で大ぶりのヘッドフォンを耳に当て音楽を聞いていた。人は良いのだが、酒焼けのような赤ら顔に、半開きのだらしない口元が、どうしてもしまりのない警備を連想させる。 田牧隊長は英気を養うためのちょっとした息抜きだと言いつつ競輪に金というより、命を賭けていた。ひょっとしたら、木沼さんへの憤懣を疾走する選手らの背にぶちまけていたのかもしれない。 湯船の中でも『坂の上の雲』を読む川瀬さんの姿を湯気の向こうにしばしば見かけた。何度も読み返したらしく、司馬遼太郎がふやけて倍になっていた。僕はといえば3度の食事だけが心の支えだった。 旅立ちの日、僕はいつものように隊長のセットした目覚まし時計の音で6時に起きた。顔を洗うとすぐに、これで食い納めかと思いつつ食堂に行き、いつもの納豆に生卵に海苔に味噌汁の朝食を、勤務がないにもかかわらず、なにくわぬ顔でガツガツと腹に詰めた。頬ばりながら、飯場での初めての夕食を思い出した。 空腹の極みに立たされ、寒空にバイクをひきずりながらふらついていたあの時、飯場の人々の親切と温かい夕食の味がしみた。これから先、どんなに豪勢な食事を前にしてもあの日の夕食を忘れることはないだろう。 部屋へ戻ると、珍しく木沼さんが制服を着て、身支度を済ましていた。
「早いですね。今日は」
そう言うと、木沼さんは、
「制服を着たまま寝てたからね」
とまじめな顔で答えた。
「クズミくんさ、可愛い女の子に見とれて事故を起こしちゃだめだよ」
傍で笑みを浮かべながら隊長が声をかけた。
「それより、熊に襲われそうになったらどうする、クズミくん」
モトクロスパンツをはいていると、木沼さんが尋ねた。
「心配はいりません。北海道に着いたら熊のぬいぐるみに着替えてバイクに乗りますから」
僕は余裕で答えた。2人とも名案だと言って納得したようにうなずいた。 旅支度を済ませると、僕は正座し、隊長と木沼さんに別れの挨拶をした。
「隊長、木沼さん。ありがとうございました。ウソついて転がり込んだ僕を助けてくれて。あの時は本当に助かりました」僕の言葉に、2人とも無言で、照れたように顔を見合わせていた。 急に、隊長が思い出したように、「クズミくん、これ昼ごはんに」と言って、アルミホイールに包まれたおむすびらしき物を僕に差し出した。昨夜シーちゃん女将に無理を言ってにぎらせたのだろうか。さすがに、締める時はきちんと締める。尊敬に値するりっぱな大人だ。9月の澄み渡る空の下で、シーちゃん女将の可憐な指が触れたおむすびを頬ばるのも悪くない。にんまりしていると、「角さんがクズミくんがいなくなると淋しいねって、愛情を込めてにぎってくれたから」と隊長。……まあ、腹にいれてしまえば同じことだ。多少げんなりしながら、「大事に食べます」と礼を言った。 すると、木沼さんも急にそわそわして、その辺にあった先週のTVガイドをニコニコしながら僕に手渡した。一体それをどうしろというのだろうか。とりあえず、「大事に見ます」と言い、頭を下げた。 ふと戸口を見ると、川瀬さんがそこに立っていた。少しばかり目をにじませ、暇な時にこれを読みなさいと言って、僕に司馬遼太郎の真新しい帯付の文庫本を差し出した。そして、「あんたの得意な、打ち込める物さ見つけて、一生懸命やって、一番になんなさい。そうすればどこにいっても飯は食えるさ」と言い、微笑みながら軽く僕の肩に手を置いた。僕の中で何かが吹っ切れたような気がした。頭の中を一瞬、軽やかな風が通り抜けた。僕は、川瀬さんに深々と頭を下げた。 オフロードブーツを履いて外に出ると、量感のある雲の群れの間から太陽が細い光を滴らせ、辺りにはほどよいぬくもりが出来ていた。 僕は貴重品を入れたウエストバックを腰につけ、衣類やら日用品を詰め込んだサイドバッグをバイクの後部にしっかりとくくり付け、ネジを締め、最後の点検をおこなった。 全ての調整を済ませると杉町のいる部屋に行き、別れの挨拶をした。
「杉町、そいじゃあな。北海道に行ってくるから」
杉町は寂しそうに聞いていたが、別れ際にそこまで送ると言ってついてきた。 ヘルメットをかぶり、飯場に来た当初のことを思い出しながら宿舎をぐるっと見渡し、エンジンをふかしていると、2階の窓から木沼さんが顔を出し、手を振っているのが目に入った。 僕は右手を高々と上げ、Vサインを作ってそれに応えた。そして、その手を大きく振りながら、「ありがとう、行ってきまーす」と大声を放ち、ゆっくりバイクを前に転がした。杉町も後からバイクでついて来た。杉町は僕と同じ型のバイクをほんの数日前に買ったばかりだった。 バイクを走らせながら、ふと後ろを振り返るとまだ木沼さんが窓から顔を出し、手を振っていた。僕は一旦バイクを停め、もう一度大きく手を振って木沼さんに応えた。木沼さんとの日々を思い出し、飯場を離れるのが無性につらくなった。別れの寂寞感がこんなにも胸にしみたことはない。これから幾度こんな思いをしなければならないのだろうか。
振り切るように、再びエンジンをふかし、バイクを前へと進めた。 5、6分ほど走り込んだあたりで、バイクを止め、もうこの辺でいいからと杉町に言った。杉町はヘルメットから顔を出すと、微笑み、口もとを小さく開いて、「気をつけて行ってこいよ」と忠告した。
「これから、どうする」杉町とこのまま別れるのが名残り惜しかった。
「クズミのおかげでバイクにも乗れるようになった。俺はこれであの人を探す。これがあれば日本中どこへでも行けるから……」
杉町は顔を上げると僕の目を真っ直ぐ見て答えた。
……ちがう、そうじゃないだろう。何故か僕の中でこみあげるものがあった。
「杉町、オヤジさんが本当にお前に望んでるのはそんなことじゃねえだろう。俺は半ぱもんで、偉そうなことは言えないけど、お前は金沢に帰って本当の父親に頭下げて、政治家やりますって、もう一度出直せ。お前ならきっといい政治家になると思うぜ」
杉町はうなだれるように聞いていた。
「お前がりっぱになった姿を、オヤジさん、どっかの飯場のテレビで見たらきっと喜ぶだろうよ」念を押すように僕は言った。
杉町は口もとに笑みを浮かべ、「そうだな」と言って、軽くうなずいた。
「みんなわかってたんだよ。俺やお前の下手な芝居を。みんな知ってて、それでも何も言わずに、温かく迎え入れてくれてたんだ」俺も、お前もここで、無学でも心やさしい人たちに拾われ、救われた……だからいつか。そう言おうとしたが、そのまま口をつぐんだ。何も言わなくても杉町もわかっている。 僕は、ふたたびヘルメットをかぶると、エンジンをふかし、ゆっくりとバイクを走らせた。バックミラーにはいつまでも手を振っている杉町の姿が次第に小さくなって、遥か彼方へと遠のいていった。 広島の田舎から上京する時の両親の姿がふと瞼に浮かんだ。元気でね、なにかあったら電話するのよ。いつまでも心配げに、手を振りながら見送る母親がいた。電車の窓から、次第に小さく遠のいていく両親。僕は大学に入って、授業をさぼり、スロットに興じ、遊び呆けていた。醜いカサブタばかりを身につけてしまった。 私は無学で飯場を渡り歩く生活ですが、あの子には学校を出て人並な生活を送ってもらいたいと思います……杉町のオヤジさんの手紙の中にあったあの言葉。土埃で、目が霞んだ。 目の前には、乾いた土と石ばかりの道が続いていた。奥歯をグッと強く噛み、突き出た石を避けるようにジグザクにふらつきながら突き進んだ。 急に、両脇の林が視界からはずれ、明るい空の色が目に飛び込んできた。僕はアクセルを回し、スピードをあげ、風の中を突っ切った。 9月の涼風が大挙してブルゾンのジャケットに押し寄せてきたが、それをまともに受け止め、バイクを前へ前へと進めた。見上げると夏の残りの暑気が麗かな天空で渦巻き、目の前では垢抜けした陽光が縦横無尽にほどよく乾いた大地を飛び交っていた。 はたち、の……旅立ちか……。まだ見ぬ北海道の雄大な地に思いを馳せた。