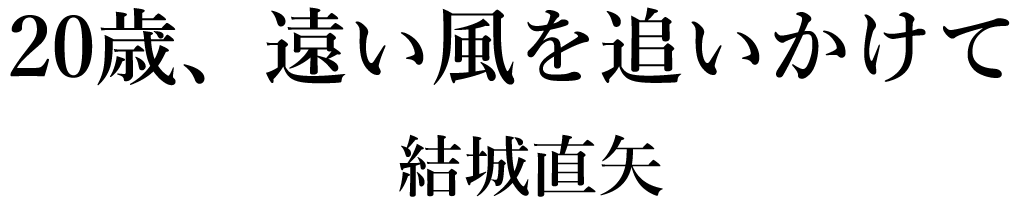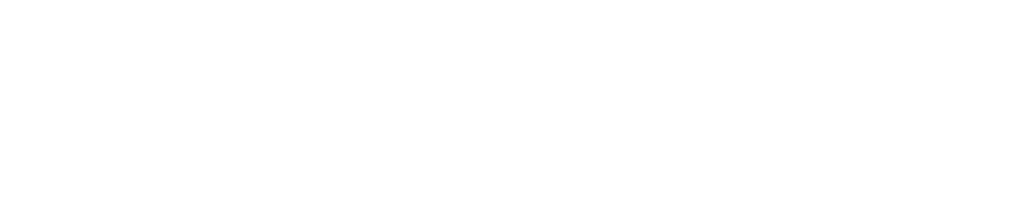No.8 木沼さんの誘導ミス
6月半ば。田牧隊長と交わした2ケ月という就業期間があと10日ほどで終わろうとしていた。
もうすぐ、お別れか・・・。窓を叩く大粒の雨の音でふと目が覚め、布団の中で飯場での日々を振り返った。あと数日かと思うと少しばかり寂しくもあった。
隣で寝ている木沼さんがにんにく臭い寝息をたてて寝返りをうった。昨夜、木沼さんは少しばかり冷えるからと、飯場から10分ほどの国道沿いにある馴染みの居酒屋で酒をあおり、 11時近くに足を忍ばせ、布団にもぐっていた。
窓ガラスの隅が白く霞んでいた。今日は本降りかな・・・。食堂で朝食をとっていた時のことだった。
「大変だ、木沼くんが、やっただ」
川瀬さんが荒い息を吐き、血相を変えて食堂に飛び込んで来た。メガネが白く曇り、長靴は泥にまみれ、透明な雨合羽から幾筋もの細い雨が垂れていた。
「あんたさ、隊長さ知らんか」
誘導灯を持つ川瀬さんの手が小刻みに震えていた。
「とんでもねえことやらかしただ、木沼くんさ」
川瀬さんはうろたえ、口を尖らせひとりごとのように口走った。
「部屋にいませんか」
「んにゃ、いねえ」
困惑した顔で、川瀬さんは首を横に振った。周りで食事をしていた作業員たちも川瀬さんの取り乱した様子を物珍しげに見入っていた。 そのうち食堂の外がにわかにあわただしくなって、建設会社の幹部たちが雨合羽をはおり、大声をはり上げながら、塊になって駆け出して行くのが窓ガラス越しに見えた。 外のざわめきに気づき、川瀬さんは彼らのあとを追おうとした。
「何かあったんですか」
急ぎ足で食堂から出ようとしている川瀬さんに尋ねると、
「バスさぶつけた」
吐き捨てるように川瀬さんは答え、外に飛び出して行った。 思わず、味噌汁を床にこぼすところだった。本当だろうか。急いで朝食の残りをかき込み、食堂を出た。 外は昨夜からの雨が途切れなく降り続き、小さなぬかるみがあちこちにできていた。歩くたびに足を取られそうになった。路面を叩くような勢いのある雨はおさまり、梅雨時特有の降り出したら中々やまないようなねばついた雨が遠くまで白く走っていた。 階段を駆け上がると、部屋の前に川瀬さんがいた。その奥で、うかない顔で、隊長が雨合羽を着込んでいた。 事故が起きたのは6時半を少し回った頃だった。現場は正面ゲートのすぐ手前で、その日は川瀬さんが早出で6時から立ち、6時半から食事交代で木沼さんと替わることになっていた。2人が交代した直後に、バスとダンプの接触事故が起きた。 その日の朝、酒臭い息を吐きながら眠そうに目を腫らせ勤務場所に現れた木沼さんに、路面が雨で見通しが悪く、滑りやすくなっているから誘導に気をつけるようにと川瀬さんがさとしたその矢先の事だった。ドカン、ガシャンという鈍い金属音が辺りに轟き、振り向くと、空を見上げるように立ちすくむ木沼さんがいた。 僕は、急いで雨合羽をはおり、自転車に飛び乗り、隊長たちの後を追った。現場は雨で濡れそぼった人々でごったがえしていた。正面ゲートのすぐ脇にパトカーが2台横づけされ、入り口付近にはダンプのしりにぶつかった観光バスがフロントを銀色に裂かれ、立ち往生していた。路面にはガラスの破片が散乱し、朝の薄曇りの日差しを受け、冷たい光を放っていた。 バスから降りてくる乗客は危なげな足取りでゲート内へと避難し、建設会社の社員たちは頻繁に往来し始めた朝の通勤車両の交通整理にやっきになっていた。 ひとだかりの中から遠目に木沼さんを探した。木沼さんは正面ゲートのすぐ手前で、警官や工事関係の物物しい男たちに取り囲まれ、事情聴衆を受けていた。すぐ横には、生気を失った顔で雨にたたられている隊長の姿が見えた。 「こんなことになると思っとった。いつか……」
僕の横で、川瀬さんが小さくつぶやいた。
「怪我人はいるんですか」
「さぁ、どうだかなぁ」
川瀬さんは小声で首を横に振った。バスはフロントガラスが大きくひび割れ、前面に鋭い亀裂が走っていたが、死傷者はいない様子だった。 川瀬さんと事故の様に呆然としていると、正面ゲートの所にいたふだん見かけない建設会社の幹部らしい太った年輩の男が僕達を見つけ、大声で交通整理せんかと遠くから怒鳴った。 その声で、僕達は我に返り、ゲート前のぶつかったバスの前後に別れて立ち、一般車両を誘導した。これじぁ、たぶん午前中は仕事にならないだろうな。足元に小さな震えを覚えながら、無性に切ない思いといつまでもやみそうもない恨めしい小雨を振り切るように車をさばいた。 「木沼くんさ。もう酒はやめとけ。今日みたいなことがあると木沼くんだけじゃない。ここにいるみんなが迷惑するんだから」
穏やかな声で隊長は木沼さんにさとした。木沼さんは正座をし終始うなだれたままで隊長の言葉を神妙に聞いていた。 その日の夜、隊長に皆が呼ばれ、急きょ反省会となった。事故の原因はバスの運転手の脇見運転ということで木沼さんは過失を免れたが、隊長はそもそも木沼さんの普段の素行に今日のような事故を招く遠因があったとして、風呂には毎日入れとか、衣類は定期的に洗濯して清潔にしておくようにとか事故とは直接関係のないようなことまでこまごまと挙げ、木沼さんを戒めた。 淡々とした抑揚のないいつもの福島なまりの口調ではあったが、その夜の隊長のそれは鋭利さを含み、木沼さんはそれを喉もとに突き付けられた刃物のように感じていたようだった。 「木沼くんさ、こんなに始末書を書かされたんだから」
隊長はそう言って、大袈裟に親指と人指し指を広げて見せた。隊長の口もとは幾分緩んではいたが、相変わらず目元はりんとしていた。
「すいませんでした。これから気をつけます」
うなだれ、何度も木沼さんは隊長に詫びを入れた。
「んなさ。木沼くんさ。隊長の言うこと、よう聞いとけ」
そう言って、隊長に加勢するかのように川瀬さんが割って入った。隊長の勧告はまだまだ手緩いといった顔をしていた。
「ともかく、木沼くんさ、酒はもうだめだよ。もしどうしても飲みたかったら休みの前の晩だけにしとくんだよ、いいね」
隊長は最後に木沼さんに釘を刺すと、きりがないからもうお開きにしようと言ってトイレに立った。木沼くんには糠に釘かもしれない。隊長はそんな顔もしていた。 反省会を終え、そろそろ就寝の時刻になろうかという頃、木沼さんはうなだれたままタオルを手に持ち、部屋を出て行った。隊長に言われたことが身に沁みたのだろう。しばらくぶりに、風呂場へと向かったようだった。 僕も木沼さんの後について行った。
飯場の風呂場は、4、5人も入ればいっぱいになるようなステンレスの浴槽で、一仕事を終えた男たちが埃や汗を落とすと、すぐに取り替えなければいけないほど湯は濁った。
「木沼さん、湯かげんはどうですか」
と、問い掛けると、立ち昇る湯気の向こうから、
「ちょうど、いいよ」
と、木沼さんの力のない声が返ってきた。
僕は制服を脱ぎ、裸になってガラス戸を開け、中に入った。夜も遅いせいか、浴槽に浸かっているのは木沼さん1人だけだった。
「背中流しましょうか」
僕がそう言うと、木沼さんは恥ずかしそうな顔をして拒んだ。遠慮しないでいいですよと言って勧めたが、木沼さんは背中を隠すようにして回り込み、それを拒んだ。 霧のような湯気が僕の目の前で少しばかり晴れた時、木沼さんの右肩から背中にかけて手の平ほどの醜い火傷の跡が目に入った。僕は目をそらして見て見ぬ振りをした。 「昨日から雨ばっかりだったでしょ。あのせいですよ。滑りやすくなってて」
僕は湯船に肩まで浸かりながらとっさにそう言って、気をそらした。
「僕のせいだよ。やっぱり」
木沼さんは湯船に顔を映してつぶやいた。
「元気出してくださいよ。木沼さん」
すっかりしょげかえっている木沼さんをどうなぐさめたらいいものか戸惑った。
「そんなに自分を責めないでくださいよ。木沼さんが悪いわけじゃなかったんだし」
そう言っても、木沼さんは晴れない顔でいつまでもうつむいていた。 どのように、この場をやり過ごそうかと思った。あと数日で、木沼さんたちと別れることになる。今まで嘘をついていたことへの罪悪感もあった。
「元気出してくださいよ、木沼さん。木沼さんのおかげで助かった人間もここにいるんだから」
なぜか、ふとそんな言葉が漏れた。木沼さんは怪訝な顔で僕のほうを振り向いた。
「木沼さん、俺ね、ほんとのことを言うと、広島からバイクで来たって言ったでしょ。あれ、嘘なんです。本当は、木沼さんと会ったその日の朝、女にふられたショックで、金も持たないで、中野からふらりとバイクで旅に出てきて……いままで嘘ついてて悪いと思ってたんですけど、もう、あと、何日かで木沼さんやみんなとお別れだし、……俺、あの時、ほんとに助かりました。金は一銭もなかったし、もしあの時木沼さんに会ってなかったらどっかで腹をすかして野宿でもしなきゃならなかったんですから」
木沼さんはぼんやりと僕の言葉に耳を傾けていた。
「ほんとに、俺なんか親のすねをかじって遊んでばっかりいて、勉強もろくすっぽしないふざけた学生で」
「でもクズミくんは仕事をちゃんとやってるんだから」
「嘘ついたぶん、みんなに悪いと思って」
「クズミくんはいいよ……頭いいし、学校出ればちゃんとした仕事もあるし」
「え……」
「僕は学校も出とらんし、頭も悪いから、仕事もない。死ぬまでこんな暮らしだ」
木沼さんはそう言うと、顔を伏せて、湯船に映った悲しげな自分の顔を見つめていた。木沼さんのその言葉に僕は胸を突かれ、そのあと何も言えなくなってしまった。
No.9 杉町という男
窓ガラスの隅が白く霞んでいた。今日は本降りかな・・・。食堂で朝食をとっていた時のことだった。
「大変だ、木沼くんが、やっただ」
川瀬さんが荒い息を吐き、血相を変えて食堂に飛び込んで来た。メガネが白く曇り、長靴は泥にまみれ、透明な雨合羽から幾筋もの細い雨が垂れていた。
「あんたさ、隊長さ知らんか」
誘導灯を持つ川瀬さんの手が小刻みに震えていた。
「とんでもねえことやらかしただ、木沼くんさ」
川瀬さんはうろたえ、口を尖らせひとりごとのように口走った。
「部屋にいませんか」
「んにゃ、いねえ」
困惑した顔で、川瀬さんは首を横に振った。周りで食事をしていた作業員たちも川瀬さんの取り乱した様子を物珍しげに見入っていた。 そのうち食堂の外がにわかにあわただしくなって、建設会社の幹部たちが雨合羽をはおり、大声をはり上げながら、塊になって駆け出して行くのが窓ガラス越しに見えた。 外のざわめきに気づき、川瀬さんは彼らのあとを追おうとした。
「何かあったんですか」
急ぎ足で食堂から出ようとしている川瀬さんに尋ねると、
「バスさぶつけた」
吐き捨てるように川瀬さんは答え、外に飛び出して行った。 思わず、味噌汁を床にこぼすところだった。本当だろうか。急いで朝食の残りをかき込み、食堂を出た。 外は昨夜からの雨が途切れなく降り続き、小さなぬかるみがあちこちにできていた。歩くたびに足を取られそうになった。路面を叩くような勢いのある雨はおさまり、梅雨時特有の降り出したら中々やまないようなねばついた雨が遠くまで白く走っていた。 階段を駆け上がると、部屋の前に川瀬さんがいた。その奥で、うかない顔で、隊長が雨合羽を着込んでいた。 事故が起きたのは6時半を少し回った頃だった。現場は正面ゲートのすぐ手前で、その日は川瀬さんが早出で6時から立ち、6時半から食事交代で木沼さんと替わることになっていた。2人が交代した直後に、バスとダンプの接触事故が起きた。 その日の朝、酒臭い息を吐きながら眠そうに目を腫らせ勤務場所に現れた木沼さんに、路面が雨で見通しが悪く、滑りやすくなっているから誘導に気をつけるようにと川瀬さんがさとしたその矢先の事だった。ドカン、ガシャンという鈍い金属音が辺りに轟き、振り向くと、空を見上げるように立ちすくむ木沼さんがいた。 僕は、急いで雨合羽をはおり、自転車に飛び乗り、隊長たちの後を追った。現場は雨で濡れそぼった人々でごったがえしていた。正面ゲートのすぐ脇にパトカーが2台横づけされ、入り口付近にはダンプのしりにぶつかった観光バスがフロントを銀色に裂かれ、立ち往生していた。路面にはガラスの破片が散乱し、朝の薄曇りの日差しを受け、冷たい光を放っていた。 バスから降りてくる乗客は危なげな足取りでゲート内へと避難し、建設会社の社員たちは頻繁に往来し始めた朝の通勤車両の交通整理にやっきになっていた。 ひとだかりの中から遠目に木沼さんを探した。木沼さんは正面ゲートのすぐ手前で、警官や工事関係の物物しい男たちに取り囲まれ、事情聴衆を受けていた。すぐ横には、生気を失った顔で雨にたたられている隊長の姿が見えた。 「こんなことになると思っとった。いつか……」
僕の横で、川瀬さんが小さくつぶやいた。
「怪我人はいるんですか」
「さぁ、どうだかなぁ」
川瀬さんは小声で首を横に振った。バスはフロントガラスが大きくひび割れ、前面に鋭い亀裂が走っていたが、死傷者はいない様子だった。 川瀬さんと事故の様に呆然としていると、正面ゲートの所にいたふだん見かけない建設会社の幹部らしい太った年輩の男が僕達を見つけ、大声で交通整理せんかと遠くから怒鳴った。 その声で、僕達は我に返り、ゲート前のぶつかったバスの前後に別れて立ち、一般車両を誘導した。これじぁ、たぶん午前中は仕事にならないだろうな。足元に小さな震えを覚えながら、無性に切ない思いといつまでもやみそうもない恨めしい小雨を振り切るように車をさばいた。 「木沼くんさ。もう酒はやめとけ。今日みたいなことがあると木沼くんだけじゃない。ここにいるみんなが迷惑するんだから」
穏やかな声で隊長は木沼さんにさとした。木沼さんは正座をし終始うなだれたままで隊長の言葉を神妙に聞いていた。 その日の夜、隊長に皆が呼ばれ、急きょ反省会となった。事故の原因はバスの運転手の脇見運転ということで木沼さんは過失を免れたが、隊長はそもそも木沼さんの普段の素行に今日のような事故を招く遠因があったとして、風呂には毎日入れとか、衣類は定期的に洗濯して清潔にしておくようにとか事故とは直接関係のないようなことまでこまごまと挙げ、木沼さんを戒めた。 淡々とした抑揚のないいつもの福島なまりの口調ではあったが、その夜の隊長のそれは鋭利さを含み、木沼さんはそれを喉もとに突き付けられた刃物のように感じていたようだった。 「木沼くんさ、こんなに始末書を書かされたんだから」
隊長はそう言って、大袈裟に親指と人指し指を広げて見せた。隊長の口もとは幾分緩んではいたが、相変わらず目元はりんとしていた。
「すいませんでした。これから気をつけます」
うなだれ、何度も木沼さんは隊長に詫びを入れた。
「んなさ。木沼くんさ。隊長の言うこと、よう聞いとけ」
そう言って、隊長に加勢するかのように川瀬さんが割って入った。隊長の勧告はまだまだ手緩いといった顔をしていた。
「ともかく、木沼くんさ、酒はもうだめだよ。もしどうしても飲みたかったら休みの前の晩だけにしとくんだよ、いいね」
隊長は最後に木沼さんに釘を刺すと、きりがないからもうお開きにしようと言ってトイレに立った。木沼くんには糠に釘かもしれない。隊長はそんな顔もしていた。 反省会を終え、そろそろ就寝の時刻になろうかという頃、木沼さんはうなだれたままタオルを手に持ち、部屋を出て行った。隊長に言われたことが身に沁みたのだろう。しばらくぶりに、風呂場へと向かったようだった。 僕も木沼さんの後について行った。
飯場の風呂場は、4、5人も入ればいっぱいになるようなステンレスの浴槽で、一仕事を終えた男たちが埃や汗を落とすと、すぐに取り替えなければいけないほど湯は濁った。
「木沼さん、湯かげんはどうですか」
と、問い掛けると、立ち昇る湯気の向こうから、
「ちょうど、いいよ」
と、木沼さんの力のない声が返ってきた。
僕は制服を脱ぎ、裸になってガラス戸を開け、中に入った。夜も遅いせいか、浴槽に浸かっているのは木沼さん1人だけだった。
「背中流しましょうか」
僕がそう言うと、木沼さんは恥ずかしそうな顔をして拒んだ。遠慮しないでいいですよと言って勧めたが、木沼さんは背中を隠すようにして回り込み、それを拒んだ。 霧のような湯気が僕の目の前で少しばかり晴れた時、木沼さんの右肩から背中にかけて手の平ほどの醜い火傷の跡が目に入った。僕は目をそらして見て見ぬ振りをした。 「昨日から雨ばっかりだったでしょ。あのせいですよ。滑りやすくなってて」
僕は湯船に肩まで浸かりながらとっさにそう言って、気をそらした。
「僕のせいだよ。やっぱり」
木沼さんは湯船に顔を映してつぶやいた。
「元気出してくださいよ。木沼さん」
すっかりしょげかえっている木沼さんをどうなぐさめたらいいものか戸惑った。
「そんなに自分を責めないでくださいよ。木沼さんが悪いわけじゃなかったんだし」
そう言っても、木沼さんは晴れない顔でいつまでもうつむいていた。 どのように、この場をやり過ごそうかと思った。あと数日で、木沼さんたちと別れることになる。今まで嘘をついていたことへの罪悪感もあった。
「元気出してくださいよ、木沼さん。木沼さんのおかげで助かった人間もここにいるんだから」
なぜか、ふとそんな言葉が漏れた。木沼さんは怪訝な顔で僕のほうを振り向いた。
「木沼さん、俺ね、ほんとのことを言うと、広島からバイクで来たって言ったでしょ。あれ、嘘なんです。本当は、木沼さんと会ったその日の朝、女にふられたショックで、金も持たないで、中野からふらりとバイクで旅に出てきて……いままで嘘ついてて悪いと思ってたんですけど、もう、あと、何日かで木沼さんやみんなとお別れだし、……俺、あの時、ほんとに助かりました。金は一銭もなかったし、もしあの時木沼さんに会ってなかったらどっかで腹をすかして野宿でもしなきゃならなかったんですから」
木沼さんはぼんやりと僕の言葉に耳を傾けていた。
「ほんとに、俺なんか親のすねをかじって遊んでばっかりいて、勉強もろくすっぽしないふざけた学生で」
「でもクズミくんは仕事をちゃんとやってるんだから」
「嘘ついたぶん、みんなに悪いと思って」
「クズミくんはいいよ……頭いいし、学校出ればちゃんとした仕事もあるし」
「え……」
「僕は学校も出とらんし、頭も悪いから、仕事もない。死ぬまでこんな暮らしだ」
木沼さんはそう言うと、顔を伏せて、湯船に映った悲しげな自分の顔を見つめていた。木沼さんのその言葉に僕は胸を突かれ、そのあと何も言えなくなってしまった。