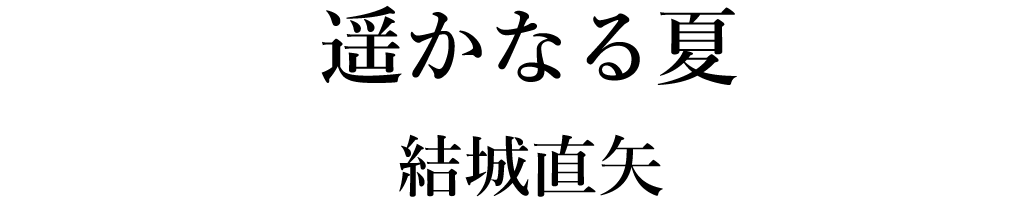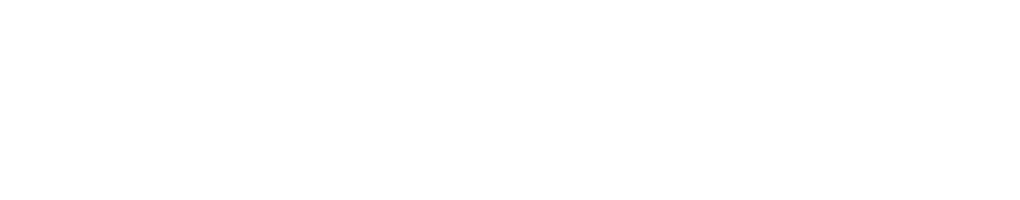No.10 影の正体をつかむ
何度打ち消しても、もしかしてと湧きあがる思い……和也は、それを現実と照らし、はてし無い推測を重ねた。が、どうしても、それが一つの方向へと集約された。< やはり米多たちは影の正体を知っている……ひょっとして、影は案外自分の身近にいる人間かもしれない >。どうしてもそう考えなければ、つじつまが合わなかった。
まず、米多や片倉があの日以来自分に指一本触れようとしなくなったこと自体奇妙だった。校内で顔を合わせるとまるで関わり合うことを避けるかのようにして離れていく。あれだけ徹底して傷めつけられたのだから、報復に出てくることは当然考えられた。ところが、それもない。まるで影の見えざる力がいつも自分を守ってくれているかのようだ……もしかして、影はこの学校にいるのでは?……どうしても、そう思えて仕方がなかった。
和也は自らの直感を信じ、休憩時間になるとそれらしき人物を求めて校内を歩き回った。放課後には、グラウンドが見渡せる石段に立ち、野球や陸上競技で汗を流す生徒たちを目で追い、あの夜見た肩幅が広くがっしりとした体格の持ち主を捜した。
数日後、それらしい人物を何人か見つけることができた。だが、何か違う、何だろう……どうしても納得できなかった。確かに背恰好はあの夜見た影と酷似してはいた。が、あの日、影に背負われた時に伝わってきた全身からみなぎるような気迫や深い孤独感。彼らにはそれが、皆無だった。
結局、数日校内を捜し歩いたものの、期待していたような成果は得られなかった。
懸命な影捜しも徒労に終わってしまった。
(やはり思い過ごしなのかもしれない……)
長らく待ちぼうけをくらわされたうえに約束をすっぽかされたような気分だった。影はこの学校以外の人間で、何らかの形で米多たちに影響力を及ぼしている、ということも考えられる。もしそうだとすれば気の遠くなるような忍耐力と時間を費やして影捜しに取り組まなければならない……和也は頭をかかえ込んでしまった。
---が、その出口をふさがれた暗いトンネルのような膠着状態から抜け出す手立てを、数日後、ひょんなことからつかんだ。何も難しく考えることはなかった。だが、それには少々勇気が必要だった。しかしそれ以外にもう方法はない、と思った。
もし、米多が影の正体を知っている?……としたら……
「いつか、ぼくを助けてくれた人が君に会いたいって言ってるんだけど」
そう言って、下校時に和也は米多を呼び止めた。のるかそるか捨て身の賭けだった。米多の狼狽ぶりはまさに見ものだった。その時、< え、せら >という言葉が米多から漏れた。和也はそれを聞きもらさなかった。米多は、セラと言った。確かにそう言った。喉の奥で詰まったような声ではあったが。
やはり米多は影を知っていた。
「あ、うん、でももし、都合悪かったらぼくがそのことをうまく伝えておくから」
和也は嘘をさとられないよう落ち着き、あらかじめ考えておいた言葉を慎重に用いた。
「そ、そうしてくれ。今日はちょっと早く家に帰らんといけん」
米多は顔をひきつらせ、どもりながら答えた。
「あ、そう、じゃあ、そう伝えておくよ。それじゃあ」
和也はそう言うと、身を強張らせて立ちすくんでいる米多をそのままにして足早に教室を出た。溜飲が下がって、嬉しさのあまり天にも昇る心地がした。
セラ、セラ、セラ……和也は米多の漏らした< セラ >という名前を何度も頭の中で繰り返した。一体、どんな字を書くんだろう。この学校の生徒かどうかわかったわけではないが、かりにそうでなくとも名前さえわかれば捜し出すのはさほど骨の折れる作業ではない。遠からずその人物に会えるに違いない……和也は歓喜した。
その日の夜、和也は正己から地元の地形が克明に描写され、そこに住む家屋の世帯主の名前まで詳細に記載された地図を借り、米多たちに乱暴された場所近くに< セラ >の姓を名乗る家がないかどうか調べた。地図にはその現場のすぐ傍になだらかな山を背にした漁村の集落が載っており、その中央付近にはあの夜泊まった魚将という名の魚工場もあった。世良、瀬良、世羅……鱗状に密集している漁村の家々を一軒一軒丹念に指でなぞり、夕食も忘れ、< セラ >という名の家を夢中で捜した。
-----が、何度見直しても< セラ >の姓の家は地図には見あたらなかった。疲れた目を擦りながら地図に顔を近付け、漁村の家々を全て正確に暗記するほど見渡した。しかし、どんなに目を血ばしらせ調べてみても< セラ >という姓の家を捜し出すことは出来なかった。苦労して、米多から影の名前を聞き出したものの、またぷっつりと手掛かりが跡絶えてしまった。
確かに米多は< セラ >と言った、確かに……何度も溜め息がもれた。まるで深い霧の中に足を踏み入れ、まさに実体のない影を捜しているようだった。和也はすっかり落胆してしまった。
うっとうしい6月がすぐそこまできていた。
6月に入ってすぐ、S中で仲の良かった泉という友人から嬉しい知らせが届いた。親類の葬儀で隣県に来た帰りに、立ち寄りたいという。久しぶりの懐かしい友人の来訪に和也は高揚した。
日曜の朝、旅に疲れた様子もなく溌刺とした顔で泉が訪ねてくると、さっそく和也は彼をバスに乗せ、景勝地を案内した。
「もう、すっかりここの人になったんじゃない。何でも知ってて」
まるで地元の人間のようなそつのない和也の案内ぶりを泉はからかった。
「そんなことはないさ」
憤慨した口調で和也はやり返した。
「いつ帰ってくるの」
「父さんの仕事が軌道に乗るまで当分帰れそうにないよ」
「ふうん。いつか言ってた、あのメルヘンの世界か。白い宮殿の」
「まあね」
適当にそう答え、和也は泉をまともに相手にしなかった。
「それよりみんなどうしてる?」
「もう、みんな、大変さ、いろいろあって、東京は屍の山さ」
泉は眉間にシワをよせ、真顔で答えた。冗談にせよ、その言葉に和也は敏感に反応した。
「嘘にきまってるでしょ。みんなピンピンしてるさ。ゲームに夢中でそんな暇もないさ」
引きつった顔の和也をなだめるように泉は言った。
「トモナガのこと……覚えてる?」
気を取り直して、和也は訊いた。
「ああ、ショックだったよ。あの時、俺、落ちてきたすぐ近くにいたんだもん」
「夢で見たんだ。トモナガのこと」
「よせよ、もう。奴のことは。みんなもう忘れたぜ。かわいそうだとは思うけど」
「結局ぼくらが殺したのかもしれない」
「藤樹、よせよ、そんなふうに考えるのは。運命だよ。そうなる運命だったんだよ」
「そう言ってしまえば簡単だけど……追いつめた責任はぼくらにもあると思う」
「そうかなあ。ちょっと考えすぎだぜ。確かに奴がイジメられてても誰も助けようとしなかったけど」
「あの時、誰かが手をさしのべてたらって思ったんだ」
「そんなこと言ったってみんな自分のことだけで精いっぱいで、他人のことなんかに関わってるヒマなんてあるもんか」
「そうかもしれない……でも……」途切れがちに和也は言った。
「それに……トモナガがイジメられてるのを見て、みんなで楽しんでるようなところがあったから。わざと知らん振りして……」
「けっこうつらいんだ。それ……」和也は自身の体験を振り返った。
「へぇ、わかったようなこというじゃないか」
「いや、もし、自分がそんなふうに周りから無視されたらって思って」
「結局、誰か犠牲になる奴が必要なんだ。残酷な言い方だけど……そうでもしなきや、欲求不満の晴らしようがないもんな」
「それでトモナガがみんなのうさ晴らしの的になったってわけ……」
「そうかもね」
そっけない泉の言い方は、和也の表情を険しいものにした。
「そんなに暗くなるなよ、藤樹。もう済んだことなんだし……あんまりそう考え込むと世をはかなんでトモナガみたいになっちゃうぜ」
情に欠けた泉の言葉に和也は棘立った視線を泉に向けた。
「そんなに怒るなよ。ただいろんなことがあって……つまりトモナガにも人にはわからないいろんなことがあって……学校のことだけじゃないかもしれないし……それは本人しかわからないことで……それで結果的には死を選んだようなことになって……だからまわりでいろいろ考えてもわかんないよ、ほんとのことは、本人しか」
「泉は人間が冷たいんだ」
「そりゃ、ないさ。藤樹が寂しがっているだろうと思ってわざわざ遠回りして寄ったのに」
「悪かったよ」
「それより、うまくいってんの?こっちの連中と」
「え、うん、まあね」
「どうした。なんかわけありだね。その顔は」
新しい中学に転校して、様々な虐待にあったことを和也は泉には話せなかった。和也のなかのささやかなメンツがそうさせたのかもしれない。そのことから故意に話題をそらそうとして和也はバスの外の風景に目を投じた。
バスはやわらかな陽光の落ちた田舎の家並みを縫い、長く真っ直ぐな車の往来の少ない道を滑り、山に挟まれた光彩の薄れた風景の中を駆け抜けると、打って変わって重みのある波が脈打つ海の見える海岸線へと出た。目の醒めるような海の深い青が急に和也の瞳に飛び込んできた。
和也には初めて目にする所だった。海老の腹のような複雑に入り組んだ人工の湾に沿って、漁業を生業とする家々が厳めしい面持ちで立たずみ、背後にも家々が階段状に積み上げられ、窮屈そうに密集していた。瀟洒な装いを嫌う老人のような頑なさがそこにはあった。動かぬ時が憮然としていた。
泉はそんな漁村の風景にしばらく関心を払った。
「藤樹、ほら、見ろよ」
朝から歩き回ったせいか、心地よいバスの揺れに、和也はうとうとしかけていた。
「あれだよ。藤樹、ほら、あれ」
そう言って、泉は窓の外に広がる風景の一角を指差した。和也は眠い眼を開けて、泉に言われるままに窓の外に目を向けた。
泉は港の桟橋に停泊した古びたイカ釣り漁船の上で太いロープを網のように組んでいる半袖シャツ姿の初老の漁師を指差していた。なにげなくその男を見やった時、和也は自分の目を疑った。白髪混じりの髪を短く刈り込んだ男の右腕は無残にも根本からすっぽりと切り取られて、無かった。
男は船上にあぐらをかいて座り、脇目も振らず、作業を左腕一本で器用にこなしていた。斜めに照りつける太陽が男の褐色の首筋に深いシワを刻みつけ、男は時々むずがるようにして肩をすくめた。所々油で薄汚れた白いシャツを着た男の後ろ姿は片腕がないだけに余計哀れみをそそった。
----- が、和也が驚いたのはそれだけではなかった。
それ以上に彼の気を動転させることがあった。腕の無い男の横でかいがいしく仕事を手伝っている色黒の体格のよい少年。その少年に和也の目は釘付けになった。白いランニングシャツからはみ出したその少年のたくましい筋肉質の肩に和也の全ての神経が集中した。そのうち失っていた記憶のかけらを取り戻したような感激が和也の中で広がった。
いつしか和也は目がしらに熱いものを感じていた。( あの夜の……あの夜の影……)
次第にバスはそこから遠のいて、少年の姿も小さくなっていったが、視界にその姿がある間、いつまでも和也は窓越しに中腰になって彼から目を離さなかった。ほんの数秒間ではあったが、その間に和也はその少年の特徴を潤んだ目にしっかりと焼きつけた。堂々とした見栄えのする身体に黒く陽にそまった肌。短く刈り込んだ頭に精悍な面構え。機敏そうな身のこなし。鋭い光を束ね始めた太陽の下で、少年の体は強い生命力にみなぎっていた。和也の直観を否定するようなものは何もなかった。
あの夜見た影……間違いない……あの、影……。
「そんなに珍しいかよ」
呆けたように身を乗り出して、窓の外を見ている和也を見て、泉が不思議そうに言った。放心状態の和也には泉の言葉も耳に入らなかった。
やっと……見つけた……。
座席に腰を下ろし、和也は今しがた見た情景をあらためて思い浮かべた。初老の片腕の男……その傍に少年……親しそうに話をしている様子から親子のようにもとれる……がっしりとした肩の上にのった少年の顔……どことなくあどけなさがあって……自分と同じ年ごろのようにも思える……彼がセラ……座席に深く腰を落とし、揺れるバスの中で、いつか米多から聞き出した< セラ >という影の名を何度もつぶやいた。
泉と別れたその日の夜、和也は正己から前に借りた地図をもう一度机の上に広げ、昼間バスで通り過ぎた漁村の集落に< セラ >の姓を名乗る家がないか、しらみつぶしに探した。が、やはり、セラの性の名乗る家はどこにも見つからなかった。椅子に持たれ、深い吐息をつきながら、和也は自分と同じ年頃のあの少年のことを思い出した。腕の無い男と親子だろうか……どこの中学だろう、それとも高校生だろうか……。
立ち上がり、窓を開け、外の風景に疲れた目を癒し、暗闇の中で影に背負われた自分の姿を和也は思い浮かべた。その時、何かが、頭に引っ掛かった。再び机の上の地図を見やった時、< 瀬田 >という性の字が、目に飛び込んできた。セラ……セダ……、もしかして、セダをセラと聞き間違えたのだろうか?あの時、とんでもなく焦っていた。米多の口の動きをもう一度思い出した。もしかしたら、米多は< セラ >ではなく、< セダ >と言っていたのかもしれない……。
漁村の集落の中には< 瀬田 >という姓の家が何軒かあった。しかもその漁村は和也の通う中学の通学区域内にあった。もし、あの少年が瀬田という名で、ずっと捜し求めていた影だとしたら……、いや、おそらく間違いないだろう。和也は泉に感謝した。もし泉が片腕の男に目を止めなければ、何事もなくそこを通り過ぎているところだった。
翌日、和也は< 瀬田 >という少年について調べるため、親しくなったクラスの何人かにそれとなく探りをいれてみた。もちろん、それを米多たちには悟られないように。
瀬田くんのこと知ってる?---、どんな人---。
和也の予想に反して、彼らの答えは意外に明快なものであった。なんともあっけないほど簡単に< 瀬田 >についての概要をうかがい知ることが出来た。それほど< 瀬田 >の存在は彼らの間では知れ渡っていた。
< 瀬田 >という少年は、Y中の卒業生ではなく、在校生で、しかも学年は和也と同じ中2であった。が、傷害事件を起こし、それ以来学校には出たり出なかったりしているということもわかった。とりわけ和也にとって印象的だったのは、< 瀬田 >について語る彼らの態度であった。まぎれもなく誰もが< 瀬田 >を畏怖していた。
No.11 いちばん苦手な泳ぎに挑む >