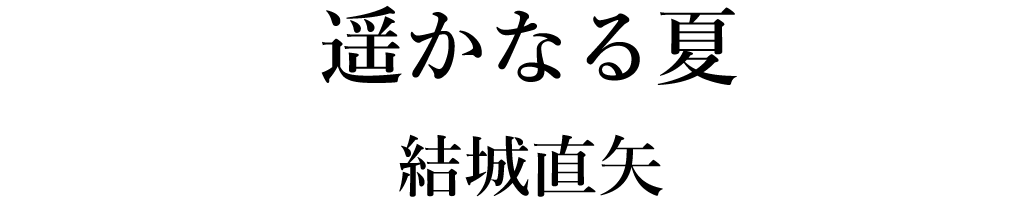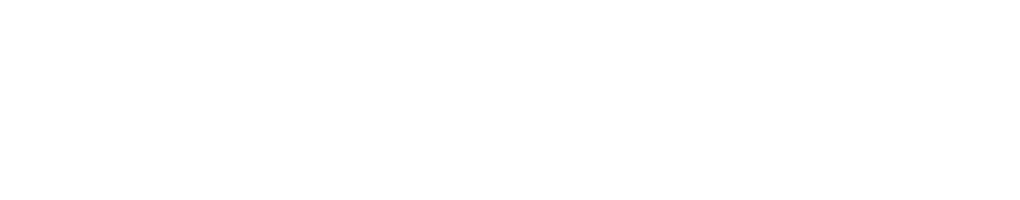No.11 いちばん苦手な泳ぎに挑む
その漁村の大方を把握しているという自信が和也にはあった。
学校帰りに漁村まで自転車をとばし、階段状に積み上げられた家々を端から一つひとつを目で追い、頭に刻みつけるように通りすぎた。
6月半ばの日曜日。その日、空は爽快に晴れ渡っていた。6月初旬から引きずっていた湿った大気は、乾いたそれに変わり、薄い雲を空の端へと追いやっていた。太陽のまばたきを懐深く受け止めた日本海は所々に光のひだを毛羽立たせながら、のびやかに凪いでいた。
和也は見晴らしのきく小高い岩の上から、色黒の体のがっしりした少年が勢いよく海に飛び込む様子を見ていた。少年は海面に体を突き立てるように頭から落ちると、しばらくして浮上し、波をけたて、まるで黒い蝶のように海面を跳躍し、たくましい両肩を黒光りさせながら沖の方へと泳いでいった。青い海原を滑るように泳ぐ少年の姿に和也は見惚れた。
時の経つのも忘れ、固い岩の上にじっと座ったまま、少年が浜にあがって来るのを待ち続けた。突き出た小さな岩が尻に当たって、長時間座っているのが少々こたえた。Tシャツの脇は、吹き出した汗でひんやりと湿っている。
吸い込まれそうな青い海に太陽が熱い吐息をふきかけ始めた昼前のことだった。
海と戯れるようにひと泳ぎした後、少年は浜辺に上がった。和也は急いで少年のもとへと息を弾ませながら駆け寄った。突然目の前に現れた和也を見て、少年は驚いたような顔をした。
「セ、セダさんですか?」
どぎまぎしながら目の前の体格の良い少年に、和也は訊いた。少年は真直ぐ和也の目を見据えると、
「そうだ」とはっきり答えた。
「あ、あの時はありがとうございました」
和也は深々と頭を下げて瀬田に礼を言った。瀬田の口もとがほころび、そこから白い歯が見えた。笑った瀬田の顔にはどこか世慣れぬ幼さが残っていたが、身体は同世代の少年たちとは比べものにならないほどたくましかった。背は高く、和也とちょうど頭一つ分ほどの身長の差があった。太陽の照射を充分吸い取ったような肌はどこもむらなく黒ずみ、盛りあがった両肩も、太い腕も、緊まった腹も、どこもかしこも筋張った筋肉で弾み、起伏に富んだ瀬田の肉体は堂々として、その存在は真上で輝く太陽と対等だった。
瀬田を間近に見ながら、地元のヤクザまがいの連中と暴力ざたを起こし、学校に出て来なくなったというクラスの生徒たちの話を思い起こした。
が、目の前の涼しげな眼差しの少年からはそうしたすさんだ雰囲気は伝わってこなかった。
「あんまり、お前が弱いんで」
いたずらっぽい笑みを目の端に浮かべ、ぶっきらぼうに瀬田は答えた。
「あいつら、もうお前に手え出せんだろ。徹底的にやったけ」
「え、ええ、もう、あれから」
「父ちゃんに喧嘩止められとるけど、米多や片倉が1人をよってたかってやっとるけ。久しぶりに遊んだるかって」
「あの後、ぼく、気を失ってしまって」
「ああ、たまたま父ちゃんの仕事であそこを通りかかったけど、俺んちまで遠いし、父ちゃんに見られるとまた喧嘩したかって怒られるし……」
「それで、あそこに……」
「あのおっちゃん親切だし。死ぬような怪我じゃなかったけ」
「とても親切にしてくれました。あれから米多たちにも嫌がらせされなくなったし、みんな瀬田さんのおかげです。どうしてもお礼が言いたくて、ずっと捜していました」
瀬田は和也の話を無表情で聞き流していた。
「ぼく、藤樹って言います。東京から転校してきたばかりで……」
「ふうん、転校生か、お前」
なぜ学校に出て来ないのか瀬田に訊こうかとも思ったが、立ち入ったことに触れるベきではないとも考え、和也はそれを控えた。
「お、泳ぎうまいですね」
何を話していいかわからず、ついそんな言葉が和也の口から出た。
「見てたのか」
「ずっと見てました。ぼくカナズチですから、全然泳げなくて」
和也は夏になると体育の授業がいつも憂鬱だった。水泳の技能の段階分けでは、常にクラスの4、5人の仲間と最低のCクラスに甘んじていた。
「そういやあ生チロイな、お前。だけ、あいつらにやられるんだ」
「泳ぎ方教えてくれませんか。ぼくも真黒になってたくましくなれば、みんなも見直すかもしれないし」
真剣な目で和也は懇願した。が、瀬田は全く見込みがないといった顔をして首を横に振り、和也の頼みを退けた。
「俺、父ちゃんの仕事があるし、たまにここで泳いどることもあるけど、やることあるんだ。これでも」
瀬田は面倒臭そうに答えた。だが、断られてもなお和也はそれを瀬田に頼み込んだ。瀬田のように惚れ惚れする男らしい身体になって米多たちを見返してやりたいと思った。しかし、
「そんなに強くなりたきゃ、自分でやりゃあええんだ。人をあてにせんでも」
と、瀬田は冷たく言い放ち、和也を砂浜に1人残したまま立ち去って行ってしまった。
次の日、和也は学校から帰るとすぐ、海パンをはき、Tシャツとジーンズという軽装で自転車に股がり、昨日瀬田が泳いでいた海岸へと向かった。
陽炎のようなまどろんだ大気の浮かぶ夕暮れの海辺は、端から端まで淡い均質な陰りにつつまれていた。Tシャツを通して肉に伝わる大気も、足裏をなぞる砂の熱も老いさらばえたものになりつつあった。
和也は砂浜に自転車をねかすと、服を脱ぎ、泳ぐ準備をした。海パンだけになると、白いのっぺりした体があらわになり、いたたまれない恥ずかしさを覚えた。浜辺に瀬田の姿はなかったが、むしろそのほうがよかったとほっとした。
太陽の褪せた色が物憂げに海面に広がり、ゆらいでいた。海水に足を浸すと、身を切るような冷たさに思わず立ちすくんでしまった。少しずつ体を海水に浸し、胸のあたりの深さまでいくと、学校で習った模範的な泳ぎのフォームを思い出し、海に体をあずけ、手足をばたつかせて海面を横切った。
プールと違って口が塩辛い。鼻から入った海水がツンと脳天まで突き上げてくる。涙に海水が混ざった。ともすると、海への生来の恐怖感が頭をもたげ、体がこわばった。
海面に浮くこともままならなかった。瀬田のように海を自在に泳ぐことなど、驚嘆にあたいすることであった。
その日は20分ばかり海に浸かっていただけで早々に引き上げてしまった。
翌日も学校から帰ると、和也は海岸に向かった。その日も瀬田の姿は海辺にはなかったが、1人海に入って波と奮闘した。幾度もうんざりするほど海水を飲み、その度に泳ぎを覚えようと発奮する気概が削がれた。
そんなふうにして、毎日和也は学校が退けると海に行って泳ぎの練習をした。白く弱々しかった体は夕暮れの薄日でうっすらと黒ずんでいった。
海で泳ぎ始めて1週間ほど経った頃。次第に海水の塩辛さにも慣れ、その日、和也は20メートルほど先に見える岩場を目標に、懸命に手足をバタつかせていた。思うように海面に浮かず、あえぎながら必死に、半分ほど泳ぎきった頃だった。急に何かに片足を掴まれ、そのまま強い力で海中に引きずり込まれてしまった。突然のことにあわてふためき、いやというほど海水を飲み込んでしまった。海中でうろたえ、もがきながら、きつく閉じていた目を開け、その原因を探った。瀬田であった。濃い青の揺らぎの中を、黒いサメのように瀬田が潜行していた。
無我夢中で海面に顔を出し、岸に向かって必死に泳ぎ、ようやく胸が海面から出る所まで行き着くと、和也は背中を折り曲げ、飲んだ海水を吐き出そうとした。瀬田の姿は海上にはなかった。が、ほっとしたのもつかの間で、ふと足元を見ると瀬田はすぐ傍まで来ていた。
和也は身をよじるようにして浅瀬へと走って逃げ、瀬田の追撃をかわした。そのうち瀬田もその悪戯に飽きたとみえ、ふざけてクジラが潮でも吹くかのように口から海水を吹き上げ、海中から真黒な顔を出した。
「ひ、ひどいですよ。死ぬかと思った」
咳き込みながら、遠くで和也は訴えた。苦しそうにむせいでいる和也を見て、瀬田は声をたてて笑った。
「どうだ。塩辛かったか」
「心臓が止まるかと思った」
口を開けて大きく息を吸い込み、胸の高鳴りをおさえながら和也は言った。
「ここはプールと違うからな。板子一枚地獄の底ってところだ」
「でも、ひ、ひどいですよ。急に」
飲んだ海水で声が詰まった。
「あれからずっと来てたのか?」
「来てました。毎日」
「いくらか泳げるようになったか?」
「いえ……まだ……」
「そんなに泳げるようになりたいか」
「はい、どうしても」
和也は瀬田を見る目に力をこめた。
「ようし、それなら、俺の言うとおりにできるか?」
瀬田はそう言うと、近くに来いというように和也に手招きをした。和也は嫌な予感がしたが、泳ぎを覚えたい一心で、こわごわ従った。
瀬田は和也がすぐ傍まで来ると、不敵な笑みを浮かべ、再び海中に顔を隠した。そして、和也の背後に廻ると、海中から太い腕を出して和也の首に巻き付け、そのまま片手で海を掻き分け、沖に向かって泳いで行った。強い力で首を掴まれ、自由を奪われた和也は、海の上で瀬田にされるがままだった。和也の不安をよそに、瀬田は沖へ沖へと有無も言わさぬ強い力で和也を引っ張って行った。そのうちに岸が遥か遠くに、手の平にのるほどの小さな風景になった。
「どこまで行くんですか?」
首を捻じって、おびえたような声で和也は瀬田に訊いた。周りでは紺碧の海がまるで獲物を待ちかまえていたかのような顔でゆったりとうごめいていた。
「ここら辺にしとくか」
そう言うと、瀬田は和也の首に巻き付けていた腕を放した。ふいに、腕の支えをなくした和也は、その拍子に頭から海に呑み込まれてしまった。瀬田はそんな和也を放ったまま、近くの島へと泳いで行ってしまった。
またしても、瀬田にしてやられた。和也は海面に顔を出そうと、必死で海を掻き分けたが、あがけばあがくほど体は硬直し、さらに海の底に沈んでいくような気がして恐怖に神経が引きつった。海は暗い藍色の腹の内をさらけ出し、奈落の底へと引きずり込もうとしているかのようだった。瀬田は離れた所で、心地よいハンモックに横たわっているかのように波に体を預け、和也の狼狽ぶりを笑いながら見ていた。
「おぼれろ。おぼれろ。そうやってみんな泳ぎを覚えるんだ」
瀬田の薄情な声が海面に響いた。足がつって自由がきかなくなり、和也は手だけで息も絶え絶えに海面に這い上がろうとした。瀬田は溺れる和也を遠くでただじっと見守っているだけだった。
和也は力の限界を感じた。体からしなやかさが抜き取られ、柔軟な筋肉は骨にぴったりと貼り付いてしまったかのようだ。これ以上体を動かすのは無理なような気がした。そのうち完全に力尽き、和也の筋力を失った体は海の底へと沈んでいった。
和也の姿が海上から消えると、瀬田はすぐさま流麗な泳ぎでそこに行き、和也を海の底からすくい上げ、そこに連れてきた時と同じように和也の首に腕を巻き付け、浅瀬へと泳いで行った。
瀬田にかつがれ、砂浜に上がると、和也はそのままそこに仰向けに大ノ字になってのびてしまった。
「まあ、今日はこんなところかな」
風になぶられ、ぼろぼろに痩せ細ったかかしのように体中の力がしぼんでしまった和也を見下ろしながら瀬田が言った。そのあまりに乱暴な瀬田のやり方に、返す言葉も和也にはなかった。
それからほとんど毎日のように、和也は瀬田から泳ぎの特訓を受けた。瀬田の教え方は、学校で教師がついて教えるような手取り足取りの生半可な教え方ではなかった。とにかくいつも、和也を気の遠くなるような沖合に連れて行っては、そこに1人残し、自分は見晴らしの良い島の小高い所に座って、溺れる寸前の和也を見ては楽しんでいるといった具合だった。和也のうろたえ方が、素晴らしいといっては手を叩き、はしゃいだ。それでも和也が実際に溺れそうになると海に飛び込んで助けに来た。
ある時は、サメだ、サメだ、フジキ、逃げろ、後ろにでかいサメだ、早く逃げろ、と瀬田は騒いだ。そういえば、そんな映画もあったけど、騙されるもんか、と和也が平然としていると、今度は、クラゲの化けもんだ、あ~、すげ~クラゲだ、この辺じゃ、見たこともねえ、よそもんの毒クラゲだ、俺は用事を思い出したから帰る、とまくしたて、波をけたてはるか遠くへ泳いで行ってしまった。クラゲならありえる、クラゲに毒があったっけ、でも刺されたら、体中腫れ上がりそうだ。瀬田のクラゲ注意報を真に受け、和也は必死の形相で、近くの岩場まで泳いだ。
毎日そんな調子だった。が、そうした特訓の甲斐があってか、3日もすると和也は以前よりずっと長く、しかもさして疲労を感じることもなく海に体を預けられるようになっていた。
すでに海開きになった海岸は、沖で1人顔をひきつらせ、手強い海と取っ組み合っている和也とは対象的に、波打ち際で砂の山を作って戯れるいとけない子供たちや、ウインドサーフィンのボードを海面で器用にあやつるサーファーや、雲間からちらりと顔をのぞかせた夏に胸をときめかせ、降り注ぐ強い陽ざしに本格的な夏の到来を期待して、波間に呆けた顔を浮かべている若者たちでざわめき始めていた。
7月に入って、初めてこの地で迎える夏休みをどうして過ごそうかと和也の頭の中はそのことでいっぱいになった。もちろん泳ぎの練習は毎日の日課に必ず組み込むつもりでいた。
「ずいぶん焼けたじゃないか」
夜、食事をしている時、正己は驚いたように言った。
「うん、毎日泳いでるからね」
「いちばん苦手だった水泳をやってるのか。ちっちゃい頃から海が苦手で、怖い怖いって海を見るたびに言ってたのに」
「うん、ちょっと、いろいろあってね」
正己は陽を浴びて、少しばかり男っぽくなった和也を満足げに見た。
「学校のほうはどうだ。みんなとうまくいってるか?」
「うん、まあね。いろいろあるけど。なんとかね。それより、レストランのほうはうまくいってるの」
「今まで着々と準備を進めてきたから、さしたるトラブルもない」
7月に入って、正己の事業計画も順調に進展していた。
「父さん。夏休みに入ったら、東京のみんなに会って来たいんだけど」
「ああ、いいとも。父さんも用事で一度帰らなきゃならない」
「絶対だよ」
「ああ、約束するよ」
あと3週間ほどで夏休みであった。久しぶりに懐かしい友人たちに会えると思うと、和也は時の経つのがまだるっこしくて仕方なかった。
No.12 瀬田の特訓が功を奏し