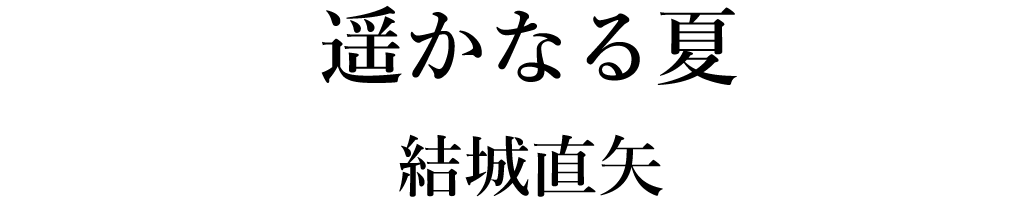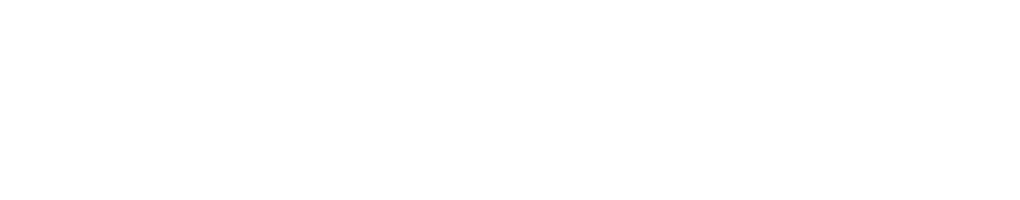No.12 瀬田の特訓が功を奏し
瀬田の特訓が功を奏し、和也はなんとか泳ぎの恰好だけはつけられるようになった。といっても、瀬田が模範的な泳ぎ方を丁寧に示したというわけではない。海面に浮く要領を覚えた和也が、先を泳ぐ瀬田に置いてけぼりにされまいと、瀬田の泳ぎを必死に真似ているうちに泳げるようになったにすぎない。だから全くの我流であり、それがまともな泳ぎ方なのかどうか和也にもわからなかった。
が、ともかく前に進む速さが以前と比べて早くなり、息つぎもさほど苦ではないことが実感できた。がむしゃらに泳いでいるうちに、海への恐怖心が徐々に取り払われていったのかもしれない。潮を吸い、うっすらと焼けた肌が、日々海に心地よく馴染んでいくのが和也にもわかった。
瀬田は和也が海に慣れると、次は素潜りで島の岩に張り付いた貝を取る方法を教えた。群青の海底でごつごつした岩に根付いてゆれる赤や緑の海藻や口を開閉しているイソギンチャク。岩場で奇妙にうごめく小さな軟体動物。最初、それらが、和也には不気味に映った。
が、岩影から群れを成した小さな魚たちが、急に目の前に現れ、海中に届いた陽光を背に乗せながら優雅に泳ぐ光景を見ていると、次第にそこに愛着を感じるようになっていった。
いつか映画で見た『グランブルー』の世界。例えて言うなら、意識までも浮遊し、海に溶け込んでいくような感覚。海中で瀬田とじゃれ合い、水中メガネを取られても、力みさえしなければ魚と同じだった。きっと誰もが、意識の深い底に海の記憶をかかえているに違いない、そう和也は思った。
ある日、瀬田は後部に小さなエンジンのついたボートをどこからか調達してきて、それに和也を乗せ、いつもと違う島の縁に停めた。そして、「大きな声じゃ言えねえが、ここが、カキの穴場よ」と和也に耳打ちし、ここ数年、密漁が増えて、監視船のせいで、サザエやカキがおおっぴらに採れなくなった、とこぼした。
「でも、まあ、ひとつぐらいはいいってことよ。おっちゃん、かんべんな」瀬田はそう言うと、ボートに和也を残し、海中深く潜った。そして数分後に両手にカキを掴み、海面に姿を現すと、「フジキが泳げるようになった祝いだ。おっちゃんも大目に見てくれるだろうよ」と言って、それをボートに放り投げた。
瀬田はボートに戻ると、ドライバーでカキの身を手早く取り出し、物珍しげに見ている和也に与えた。海で採れたての貝を食べるのは和也には初めての経験だった。
「おいしいね。新鮮っていうのは、ほんと、こういうのだよね」言いながら、和也は口いっぱいにカキを頬張った。
見上げると、空は青く照り輝き、雲はむくれ上がって勢いを増している。太陽がほのかに潮を含んだ風を光でまぶしている。カキの水っぽいしょっぱさとひんやりした甘味が口いっぱいに広がった。
「なんてたって、採れたてが一番よ、フジキ」そう言って、ニヒルに顔をゆがめる瀬田は、まるで海の底で、魚という魚を手当たり次第かぶりつき、食い散らかしている魚人-ギョジン-のような姿にだぶった。瀬田なら、クジラに抱きつき、その太っ腹を食いちぎっている姿だって容易に想像できる。海洋を我が物顔で遊泳する、この海の怪人には人喰いサメだって一目置くにちがいない。そんなことを空想していると、
「さあ、フジキ、腹ごしらえしたら、ひと仕事するぜい」瀬田は立ち上がり、遠方に目を向けると、海の荒くれ者のような顔つきになった。
一体、何を考えているのか、瀬田はボートのエンジンをめいっぱいふかすと、島巡りへと向かった。時々岩影に隠れていちゃついている若い男女を見つけると、瀬田は大声で奇声を放ち、波飛沫を上げてボートを飛ばした。うら若いカップルが瀬田の声にあわてふためき、急に稲妻でも落ちてきたかのように取り乱す様は和也にも見ものだった。そうやってふざけながら二人はまるで海賊にでもなったような気分で島々を廻った。
いつしか太陽は熟れて落ちかかった柿のような色をして、影を真っ直ぐ海面に映し出していた。残照を受けた瀬田の濡れた両肩は時おり焦茶色にぎらついた。
瀬田のことで前から気になっていたことをこの機会に訊いてみようかと和也は思った。
「なぜ学校に行かないんですか?」
勇気を出して和也は訊いた。
「学校?……」
和也の質問に、瀬田は余計なことを訊くなといった顔をして、
「俺の性に合わねえ」
と、短く吐き捨てるように答えた。
「いろいろ聞きました……」
「俺のことか」
「ええ、まあ……」
「言わせとけ。言いたい連中にゃあ」
腹立たしげに瀬田は声を荒げた。
「フジキ、お前、学校好きか。あんなこせいとこが」
「いえ、あんまり……」
「だろ、俺もこうやって海にいるほうが気が晴れる。あんなこまいところにちんまり座っとるのは気が腐る。喧嘩したくなった時だけだ。俺が学校に行くのは。それ以外は行かねえ。海が学校だ。俺には」
「ヤクザと喧嘩したって……」
和也はためらいながら瀬田に訊いた。
「そんなことまで知ってんのか。お前」
「ほんとうですか?……」
「ああ、あいつら父ちゃんの酒代の借金返せってうるせえから」
「お父さんて、あの、腕を怪我した?……」
「何でも知ってんだな。お前。どうして知ってんだ」
「前に一緒にいる所を見て、たぶん、そうじゃないかと思って」
「ふうん。俺とそっくりだろ。頑固もんで……3年前だ……漁に出て、船の機械に右腕はさまれて……根元からばっさりだ……それから仕事にならねえって、毎日酒ばっかりくらって……働きもせんで、借金ばかり作って……それが元で……母ちゃんも病気で死んで……」
和也は訊くべきではなかったと心の中で瀬田に詫びた。瀬田の黒い瞳は残光で茜色に染まっていた。
「すみません。余計なこときいて……」
「気にすんな……」
ぼそりと瀬田は答えた。
「そいでも父ちゃん、最近やる気になって。借金もようけあるけ、返さないけんし……父ちゃんの仕事の手伝いがあるけ、俺、学校に行っとる暇もない……」
そう言うと、瀬田は話に飽きたような顔をして立ちあがり、
「フジキ、俺について来い」
と言って、そのままザブンと波飛沫をあげて海に飛び込んだ。勢いよく瀬田がボートの縁を蹴ったため、ボートは大きく揺れ、バランスを失って和也は海に投げ出されてしまった。
海中にいったん沈んで、それから和也が海上に顔を出すと、瀬田は10メートルほど先で鉛色の海を二つに裂いていた。和也も海を掻き分け、瀬田の後を追った。が、どんなに頑張っても瀬田に引き離されるばかりで、距離は縮りそうもなかった。そのうちに瀬田はUターンをし、和也のすぐ近くまで戻り、気持ち良さそうに仰向けに浮かんでいた。
「けっこう泳げるようになったじゃねえか」
海面に、黒い顔と白い歯を浮かべて瀬田が言った。
「しごかれましたから」
「え、えへへ……」
瀬田は苦笑いをすると、海に身体を沈め、口から海水を空に向かって噴水のように吹きながら浮き上がってきた。クジラの潮吹きだと言ってはふざけてそれをよくやった。
「泳ぎも、素潜りも出来るようになったし、あとは飛び込みだけだな」
「飛び込みですか。飛び込みはいいですよ」
「遠慮するな。ついでだ」
「え、ええ、いや……」
立ち泳ぎをしながら、和也は遠回しにそれを拒んだ。高所恐怖症が災いしてか、プールの一段高い所から飛び込むことさえ足がすくむほどだった。
瀬田は和也をそこに残して、ボートに戻ると、それを島の岩場に付け、おもむろに岩を登り始めた。そして3メートルほどの高さのところに立つと、両手を夕暮れの空に向かって真っ直ぐ伸ばし、足で強く岩を蹴り、綺麗な放物線を赤錆色に染まり始めた風景に描き、わずかばかりの飛沫をあげて手の先から海に入っていった。見事な美しいフォームであった。
自分にはとうてい出来そうもないと和也は思った。高い所は幼い頃から苦手だった。瀬田に同じ所から飛べと言われても、身体がこわばり、足がすくんだ。「どうしても飛べ」と瀬田が言うので、瀬田に後ろから押されるようにしてぶざまな恰好で足から海に落ちると「おめえは女か」となじられる始末であった。
「こんなもんはなあ。度胸だ。度胸。飛んでしまえば何のこたあねえ。頭から飛んでみろ。頭から」
瀬田は踏ん切りの悪い和也をけしかけた。確かに瀬田の言うとおり、思い切って両足で岩を蹴ればいいだけのことであった。しかし、今一歩の所で岩肌を蹴る勇気が和也にはなかった。
「急に無理ですよ。飛び込めと言われても。こ、こころの準備も必要ですし、そ、それにもう暗いし、危ないですよ」
しどろもどろに和也は答えた。
「ぐだぐだぬかすな。いいからやってみろ」
岩場に貝のようにぴったりくっついて離れない和也を瀬田は引きはがそうとした。
「情けねえ野郎だ。しようがねぇ。飛び込みは夏休みに入ってからだ。徹底的にやったる」
瀬田のあきらめの言葉を聞いて、和也はほっと胸をなでおろした。
が、それもつかの間だった。瀬田が、
「目標はあれだ」
と言って、そこから10メートルほど離れた島の頂上を指差した。和也は瀬田の指先の方向を見て腰の力が抜けてしまった。ほのかに柿色に焼けた景色の端に、影絵のように平坦な黒いシルエットを浮かべてひっそりとそれはたたずみ、その真下では逆巻く波が異様に白く輝いていた。海面からゆうに10メートルはある。
「フジキ、あの島が俺を呼んでる。早く飛んでくれって」
ふざけた口調で瀬田が言った。
「昔な、といっても1年前だが、片倉の野郎をあそこから両足持って宙吊りにしてやった。それ以来、あいつ怖がって俺に近づきもしねえ」
片倉をロープでグルグル巻きにして---ついでに米多もだ---逆さづりにして、何度も海に漬けては引っぱり上げる、何度も海に放ってはサメの撒きエサにする。月夜の晩に恐ろしい形相でそんな拷問を飽きもせず繰り返すギョジンの姿を想像していると、
「俺もまだあそこから飛んだことはねえ。だから俺が飛ぶ前に、まずお前にためし飛びをやってもらおうと思う。そいで、もしお前が死んだら俺は飛ばねえ」
笑いながら、瀬田はまくしたてた。それに何も答えず、ぽかんと口を開けたまま、島の一番上と海面とを何度も和也は目で往復し、その距離を計った。そのうち鳥肌が立って、体中の毛穴からすうっと熱が逃げ、体が急に冷えていくのを感じた。さすがにその時ばかりは瀬田と知り合いになったことを後悔した。
「あの上のちょっと出っ張った所があるだろ。あれがどうもいけねえ。あそこに乗って飛んでくれって言ってるような気がするんだ」
「ぼ、ぼくには、そんなふうには、お、おもえませんけど……」
どもりながら和也は精一杯反論を試みた。
「いいか、耳を澄ましてよおく聞いてみな。そんなふうに聞こえてこねえか?」
「いや、ぼくには、全然……」
「お前はたぶん耳が悪いんだ。まあ、そうビビるな。俺の特訓でいつかお前もあそこから飛べるようになるから」
「い、いえ、ぼ、ぼくはいいです。た、高い所は、苦手ですから」
「何言ってんだ。ちょっとあそこから足を滑らせたと思えば何のこたぁねえじゃねえか」
瀬田の言葉にいつか死にたいと思った時のことを和也は振り返った。
「心配するな、フジキ。飛び込む時は俺も一緒に飛び込んでやるから。『せいの』で飛び込んで、一緒に心中してやるから」
瀬田はそう言って、声を立てて笑ったが、和也は顔がひきつって笑えなかった。たぶん瀬田はそれをやるに違いない……この男ならやりかねない……絶対やるぞ、こいつは……そうなると、空飛ぶギョジンだ……顔ばかりか、心臓までひきつるような思いだった。
「もうすぐ夏休みだろ。そしたらまた特訓だ。その前に、俺、父ちゃんと海に出なきゃいけん。だけ、それが終わって帰って来てからだ」
「ぼくも休みに入ったら、1週間ほど東京に帰るんだ」
「そいじゃあ。その後だ」
瀬田は和也に約束した。むろん和也は瀬田の指差した島の上から飛ぶつもりなどもうとうなかった。
No.13 瀬田との男の約束