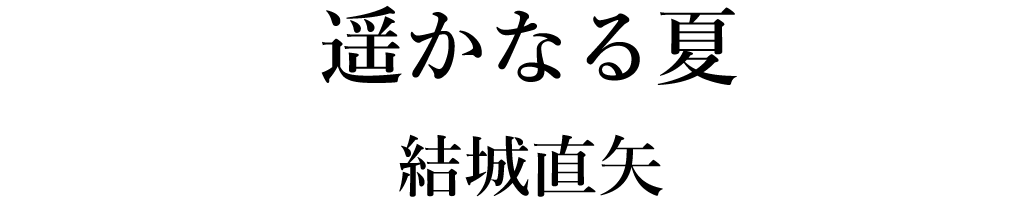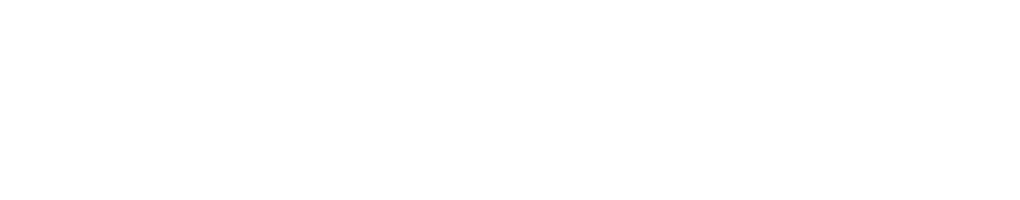No.13 瀬田との男の約束
それから2日ほど経った夕暮れ時。
正己は昼過ぎから建設中のレストランの厨房の水周りや外観の飾り付けを地元の工事関係者と打ち合わせし、それを終えた後も、1人居間で図面をにらみ、什器の配置やスタッフの手配に食事も忘れ、没頭していた。このところ、そんな正己の姿を和也はよく目にした。
何か食べ物をと、和也は台所に行き、冷蔵庫を開けて見た。しばらく調理をしていないと腕が鈍ると思ったのか、正己が買い揃えた魚や野菜がそこに窮屈におさまっていた。
すぐに口にできそうなものはないかと、冷蔵庫の中を覗き込んでいると、家の裏手で何か物音がしたような気がした。そのうち台所の戸口を軽く叩く音が聞こえてきた。時計は7時をまわっている。クリーニングの配達にしては遅い時刻だ。
台所に行き、戸口を小さく開けると、「おっ」と和也は小さくもらした。夜気に包まれ、浮かない顔で伏し目がちに立ちすくんでいる瀬田がそこにいた。以前、瀬田に大まかではあったが住まいを教えていた。
瀬田は、ランニングシャツに短パンにサンダルという軽装だった。長時間、自転車をこいで来たせいか、口元がかさついている。
「とうちゃんとケンカして……今日だけ、泊めてくれんか」
うなだれたまま、瀬田はぼそりとつぶやいた。
和也はすぐさま瀬田の腕をつかんで家に招き入れると、冷蔵庫からサイダーを取り出した。
「喉が渇いてるでしょ。これでいい?」
瀬田は黙ったままサイダーを受け取ると、旨そうに一気飲みした。浅黒い顔に、いつもの瀬田の笑顔が戻った。和也もにっこり微笑んだ。何か瀬田の役に立っていることが嬉しかった。
瀬田はほっと一息つくと、所在なげに深鍋やフライパンやら少しばかり様子の違う調理器具の揃った藤樹家の台所に目を這わせた。
「なんか……すげえな、お前えんち……。なんだ、このナベ、人でも煮るんか」
瀬田の冗談に笑いながら、和也は、「お腹は、ご飯は?」と訊いた。空腹感は悩みを増幅させる。とりあえず、何か胃に詰め込むことが先決だ。
「ああ……まだ」消え入りそうな声で瀬田が答えた。
そのうち、居間にいた正己が、台所があわただしいことに気づき、
「誰か、お客さんなのか」とドアを開け、顔をのぞかせた。 瀬田は、正己が台所に姿を見せると、あわてて椅子から立ち上がり、こんちわ、とぎこちなく頭を下げた。正己は自分と背丈のあまり変わらない、浅黒い顔をした野生児のような少年を見て、少し驚いたような顔をした。 「同級生の瀬田くん」間髪入れず和也は瀬田を紹介し、父親とケンカして家を出てきたことを正直に正巳に伝えた。 「学校でイジメにあった時に助けてくれたんだ。ほら、あの魚工場までぼくを運んでくれたのも瀬田くんなんだ」しおらしくしている瀬田を横目に見ながら和也は言った。 「水泳も教えてもらってる」 「そう、君が……、ありがとう。和也の恩人だ」 正己はそう言うと、深々と頭を下げ、瀬田に、「お腹はすいてないかい?」と尋ねた。 正己は瀬田の返事を待たず、「ともかく腹ごしらえだ」と言って、冷蔵庫を開け、中を覗き見た。そして、野菜に果物、肉に魚と、あるだけの食材を取り出し、調理に取りかかった。 正己は包丁を取り出し、手際よくマグロを切り分け、鍋にオリーブ油を敷き、少しばかりニンニクを加え、ガスの火であぶった。機敏な動きだった。 正己の後ろ姿にプロの気迫のようなものを和也は感じた。著名な料理評論家が店に来ても、こんなに真剣な表情は見せたことはない。目が据わっている。声をかけるのもはばかれるような面持ちだった。ナスにピーマンにたまねぎにパスタ、卵にアサリにバジリコ、それから上等の牛肉。食材の追加リストを正己から渡され、和也は近くのスーパーに買いに走った。 正己は、白ワインを目分量で計りながら、他の誰よりも先に瀬田という少年に自分の料理を口にしてもらえることをこの上もなく幸せに感じた。和也を助けてくれた恩人、そして若き頃、自分と和恵を励まし元気づけてくれた地元の人。パスタを手ごろな歯ごたえに茹であげ、味付けに精魂を込めた。これまでの人生の全てをそこに注ぎ込むかのように。 小1時間ほどして、正己は、居間でTVを見ていた和也と瀬田を食事ができたと呼んだ。テーブルの上には、大皿や小皿に盛り付けられた色とりどりのイタリア料理が並んでいた。オリーブ油の艶やかなパスタのアサリとペーストの和え。ケッパーとワインが染み込んだ口の中でとろけそうなマグロの切り身。一口大に切った牛肉の煮込みからは香辛料のかぐわしい香りが立ち上っている。チャンボッタというナスやピーマンやトマトを炒めた野菜料理もある。正己が得意としている料理の数々だ。 正己は、「さあ、瀬田くん、どうぞ、どうぞ」と言って、立ちすくんだままの瀬田をイスに座らせ、「さあ、食べようか」と快活に声をかけた。 瀬田は、テーブルの上の豪勢な料理にしばらく目を奪われていた。なにから手をつけていいのか、困惑したような瀬田の表情がそこにあった。浅黒い顔が心なしか紅潮してみえた。 「箸で……いいですか」戸惑ったような目で瀬田が言った。 「もちろん、さあ、遠慮しないで、いっぱい食べて」 正己は目を細め、笑みを浮かべて言った。 瀬田は手前の大皿にあった牛肉を箸でぎこちなくつまんだ。そして、口に入れて牛のように顎を動かして味わうと、「こんなうまいもん、はじめてだ」と満面を緩ませた。よほど味付けが気にいったのだろう。瀬田は、箸の手を休めることなく、そればかりを口に放り込んだ。 「たくさん食べて、瀬田くん、まだいっぱいあるから。私ができるのはこんなことくらいだから」 正己はそう言うと、瀬田にパスタのおかわりを勧めた。少しばかりガサツな瀬田の箸のつけ方を見ながら、この地の民宿で和恵が風邪を引いて寝込んでいた時、老夫婦が作ってくれた煮込みうどんのことを思い出した。老夫婦の親切が心にしみて、目を潤ませながら、和恵と一緒に額に汗をかきながらうどんを口に運んでいたあの日。 そのうち、瀬田の料理を口に運ぶ手がとまって、心なしか目元が潤んでいるかのように見えた。瀬田はテーブルに箸を置くと、 「これ、とうちゃんにも……食わせてえ……」と、しんみりつぶやいた。 夕方の食事時に1人残してきた父親のことを不憫に思ったのだろう。片腕の父親との日々の食事がどのようなものか、和也にも容易に想像できた。 「おとうさんのぶんもこれから作るからね。だから瀬田くんもいっぱい食べなさい」 正己は立ったままで、自分はほとんど口にせず、また料理作りに精を出した。 瀬田が口にした料理と同じものを作り、戸棚から大きめのタッパーを探し、間仕切りをして、料理をつめていると、 「あの……ついでに飯も……」と、か細い瀬田の声。 「ああ、そうだね、うん」正己は笑って答えた。和也はそのやりとりをほほえましく聞いていた。瀬田にはイタリア料理だろうが、フランス料理だろうがロシアの宮廷料理だろうが、どんぶり飯であわただしくかき込んでいる姿しか思い浮かばない。フォークを使う瀬田の姿などとても想像もできない。まさか、畑から大根を引き抜いて土のついたままかじりつくようなことはしないだろうが。それに近いことはやりそうだ。 正己は炊飯ジャーにあるだけのご飯をタッパーに詰め、瀬田に持たせた。瀬田はそれを正己から受け取ると、「すみません」と頭を下げた。 「ありがとな、うまかった。とうちゃん、腹すかしてるだろうから」 外に出て帰り間際に瀬田は和也に礼をいった。 和也には、今夜の料理も悪くはなかったが、前に瀬田とボートの上で真っ青な空を仰ぎながら頬ばったカキの味のほうが忘れられなかった。 「夏休みが終わったら、学校に出てくるでしょ」それとなく瀬田に訊いてみた。 「ああ……」とだけ言って、瀬田は苦笑いした。 「絶対だよ。約束だよ」和也はそのことを誓わせた。 和也は、瀬田の自転車の荷台に2段になったイタリア料理の詰まったタッパーをゴム紐でもう一度きつく締め直した。瀬田の住む魚村まで自転車でゆうに1時間はある。正己が久しぶりに腕を振るった自慢のイタリア料理も途中でスクランブルエッグのように混ざりあっているかも知れない。 「じゃあな、また鍛えてやっから」瀬田はそう言うと、わざと口をゆがめ、軽く和也の胸をこぶしでつつき、ペダルを踏んだ。 「学校でね。約束だよ。男の約束だよ」 和也は小さく遠のいていく瀬田の後を追いながら、そのたくましい背中に声をかけた。 「絶対だよ!本当だよ」 和也は大きく手を振り、瀬田が遠く闇にかき消え見えなくなるまで見送った。瀬田もそれに応えるかのように何度か後ろを振り向いて和也に手を振った。 家に戻ると、台所に正己がいた。まるで全力で100メートル走でもした後のように肩を落とし、呆然として。正己は料理を作ることに専念し、ほとんど何も口にしていなかった。和也も同じであった。2人とも、瀬田が嬉しそうに料理を頬ばる姿をずっと眺めていた。 2人は、パスタを無造作に鍋に放り込み、ゆで上がった傍から、まだ芯のある硬めのそれを呑み込んでは、顔を見合わせ微笑んだ。2人がこの地に来て初めて見せた会心の笑みだった。なぜかこのうえもない充足感で満たされていた。 それから2日後に、瀬田は父親と2人で漁に出た。そしてその3日後、和也の待ち望んでいた夏休みがやってきた。
No.14 胸さわぎ、不穏な知らせ
「誰か、お客さんなのか」とドアを開け、顔をのぞかせた。 瀬田は、正己が台所に姿を見せると、あわてて椅子から立ち上がり、こんちわ、とぎこちなく頭を下げた。正己は自分と背丈のあまり変わらない、浅黒い顔をした野生児のような少年を見て、少し驚いたような顔をした。 「同級生の瀬田くん」間髪入れず和也は瀬田を紹介し、父親とケンカして家を出てきたことを正直に正巳に伝えた。 「学校でイジメにあった時に助けてくれたんだ。ほら、あの魚工場までぼくを運んでくれたのも瀬田くんなんだ」しおらしくしている瀬田を横目に見ながら和也は言った。 「水泳も教えてもらってる」 「そう、君が……、ありがとう。和也の恩人だ」 正己はそう言うと、深々と頭を下げ、瀬田に、「お腹はすいてないかい?」と尋ねた。 正己は瀬田の返事を待たず、「ともかく腹ごしらえだ」と言って、冷蔵庫を開け、中を覗き見た。そして、野菜に果物、肉に魚と、あるだけの食材を取り出し、調理に取りかかった。 正己は包丁を取り出し、手際よくマグロを切り分け、鍋にオリーブ油を敷き、少しばかりニンニクを加え、ガスの火であぶった。機敏な動きだった。 正己の後ろ姿にプロの気迫のようなものを和也は感じた。著名な料理評論家が店に来ても、こんなに真剣な表情は見せたことはない。目が据わっている。声をかけるのもはばかれるような面持ちだった。ナスにピーマンにたまねぎにパスタ、卵にアサリにバジリコ、それから上等の牛肉。食材の追加リストを正己から渡され、和也は近くのスーパーに買いに走った。 正己は、白ワインを目分量で計りながら、他の誰よりも先に瀬田という少年に自分の料理を口にしてもらえることをこの上もなく幸せに感じた。和也を助けてくれた恩人、そして若き頃、自分と和恵を励まし元気づけてくれた地元の人。パスタを手ごろな歯ごたえに茹であげ、味付けに精魂を込めた。これまでの人生の全てをそこに注ぎ込むかのように。 小1時間ほどして、正己は、居間でTVを見ていた和也と瀬田を食事ができたと呼んだ。テーブルの上には、大皿や小皿に盛り付けられた色とりどりのイタリア料理が並んでいた。オリーブ油の艶やかなパスタのアサリとペーストの和え。ケッパーとワインが染み込んだ口の中でとろけそうなマグロの切り身。一口大に切った牛肉の煮込みからは香辛料のかぐわしい香りが立ち上っている。チャンボッタというナスやピーマンやトマトを炒めた野菜料理もある。正己が得意としている料理の数々だ。 正己は、「さあ、瀬田くん、どうぞ、どうぞ」と言って、立ちすくんだままの瀬田をイスに座らせ、「さあ、食べようか」と快活に声をかけた。 瀬田は、テーブルの上の豪勢な料理にしばらく目を奪われていた。なにから手をつけていいのか、困惑したような瀬田の表情がそこにあった。浅黒い顔が心なしか紅潮してみえた。 「箸で……いいですか」戸惑ったような目で瀬田が言った。 「もちろん、さあ、遠慮しないで、いっぱい食べて」 正己は目を細め、笑みを浮かべて言った。 瀬田は手前の大皿にあった牛肉を箸でぎこちなくつまんだ。そして、口に入れて牛のように顎を動かして味わうと、「こんなうまいもん、はじめてだ」と満面を緩ませた。よほど味付けが気にいったのだろう。瀬田は、箸の手を休めることなく、そればかりを口に放り込んだ。 「たくさん食べて、瀬田くん、まだいっぱいあるから。私ができるのはこんなことくらいだから」 正己はそう言うと、瀬田にパスタのおかわりを勧めた。少しばかりガサツな瀬田の箸のつけ方を見ながら、この地の民宿で和恵が風邪を引いて寝込んでいた時、老夫婦が作ってくれた煮込みうどんのことを思い出した。老夫婦の親切が心にしみて、目を潤ませながら、和恵と一緒に額に汗をかきながらうどんを口に運んでいたあの日。 そのうち、瀬田の料理を口に運ぶ手がとまって、心なしか目元が潤んでいるかのように見えた。瀬田はテーブルに箸を置くと、 「これ、とうちゃんにも……食わせてえ……」と、しんみりつぶやいた。 夕方の食事時に1人残してきた父親のことを不憫に思ったのだろう。片腕の父親との日々の食事がどのようなものか、和也にも容易に想像できた。 「おとうさんのぶんもこれから作るからね。だから瀬田くんもいっぱい食べなさい」 正己は立ったままで、自分はほとんど口にせず、また料理作りに精を出した。 瀬田が口にした料理と同じものを作り、戸棚から大きめのタッパーを探し、間仕切りをして、料理をつめていると、 「あの……ついでに飯も……」と、か細い瀬田の声。 「ああ、そうだね、うん」正己は笑って答えた。和也はそのやりとりをほほえましく聞いていた。瀬田にはイタリア料理だろうが、フランス料理だろうがロシアの宮廷料理だろうが、どんぶり飯であわただしくかき込んでいる姿しか思い浮かばない。フォークを使う瀬田の姿などとても想像もできない。まさか、畑から大根を引き抜いて土のついたままかじりつくようなことはしないだろうが。それに近いことはやりそうだ。 正己は炊飯ジャーにあるだけのご飯をタッパーに詰め、瀬田に持たせた。瀬田はそれを正己から受け取ると、「すみません」と頭を下げた。 「ありがとな、うまかった。とうちゃん、腹すかしてるだろうから」 外に出て帰り間際に瀬田は和也に礼をいった。 和也には、今夜の料理も悪くはなかったが、前に瀬田とボートの上で真っ青な空を仰ぎながら頬ばったカキの味のほうが忘れられなかった。 「夏休みが終わったら、学校に出てくるでしょ」それとなく瀬田に訊いてみた。 「ああ……」とだけ言って、瀬田は苦笑いした。 「絶対だよ。約束だよ」和也はそのことを誓わせた。 和也は、瀬田の自転車の荷台に2段になったイタリア料理の詰まったタッパーをゴム紐でもう一度きつく締め直した。瀬田の住む魚村まで自転車でゆうに1時間はある。正己が久しぶりに腕を振るった自慢のイタリア料理も途中でスクランブルエッグのように混ざりあっているかも知れない。 「じゃあな、また鍛えてやっから」瀬田はそう言うと、わざと口をゆがめ、軽く和也の胸をこぶしでつつき、ペダルを踏んだ。 「学校でね。約束だよ。男の約束だよ」 和也は小さく遠のいていく瀬田の後を追いながら、そのたくましい背中に声をかけた。 「絶対だよ!本当だよ」 和也は大きく手を振り、瀬田が遠く闇にかき消え見えなくなるまで見送った。瀬田もそれに応えるかのように何度か後ろを振り向いて和也に手を振った。 家に戻ると、台所に正己がいた。まるで全力で100メートル走でもした後のように肩を落とし、呆然として。正己は料理を作ることに専念し、ほとんど何も口にしていなかった。和也も同じであった。2人とも、瀬田が嬉しそうに料理を頬ばる姿をずっと眺めていた。 2人は、パスタを無造作に鍋に放り込み、ゆで上がった傍から、まだ芯のある硬めのそれを呑み込んでは、顔を見合わせ微笑んだ。2人がこの地に来て初めて見せた会心の笑みだった。なぜかこのうえもない充足感で満たされていた。 それから2日後に、瀬田は父親と2人で漁に出た。そしてその3日後、和也の待ち望んでいた夏休みがやってきた。