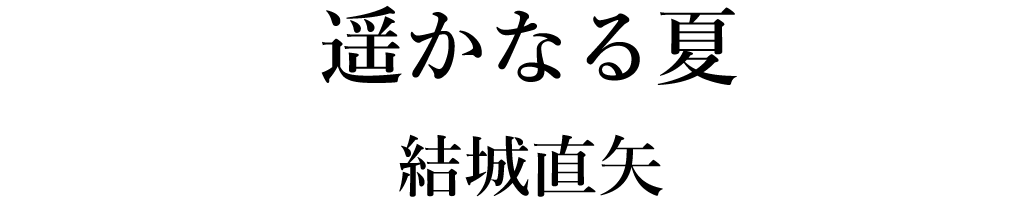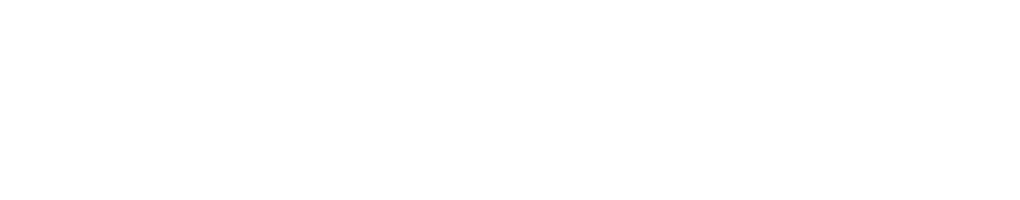No.14 胸さわぎ、不穏な知らせ
夜の9時過ぎ。2人はBMWで東京にたどり着いた。途中、何度かパーキングエリアに車を停め、食事をし、休憩や仮眠をとったが、さすがに正己は目を窪ませ、腰に手を当て、こわばった筋を何度もさすった。
住み慣れた家に到着し、ガレージに車を入れると、正己の会社の従業員たちが2人を出迎えた。若い調理スタッフに家の管理を条件に貸し与えていた。おかえんなさい、疲れたっしょ。そう言って、和也と仲の良い、23歳の調理見習いのタカさんが、暗がりから勢いよく飛び出して来て、車からの荷出しを手伝った。
玄関に入ると、檸檬エッセンスの懐かしい匂いに包まれた。和恵の好んでいたアロマライトがシューズボックスの上に置かれたままになっていた。オイルが常に補給されていたにちがいない。真新しい香りが心地いい。
2階の部屋に入ると、和也は愛着のあるベッドに横たわった。壁のポスターのアイドルが微笑んでいた。あの日もそうだった。あの時、父親から声を掛けられ、横浜へ行って、運命が一変した。まさか、転校先でイジメに会うとは思いもよらなかった。瀬田に会わなければ、今頃、どうなっていたか……。
瀬田のことは一生忘れることはないだろう。長旅で疲れた身体を眠りの中途に横たえながら、5ケ月あまりの日々を振り返った。
東京での滞在は1週間ほどだった。和也は車中でわくわくしながら書き込んだ予定表を見ながら行動した。1分たりとも時間を無駄にはできない。S中の友人に連絡を取り、映画を見て、ゲームセンターで戯れ、渋谷や原宿で買い物を楽しんだ。
「ずっと、そっちにいるつもり?」
アイスコーヒーをストローで勢いよく吸いあげながら荻島が訊いた。荻島は和也とは幼な馴染みで、中1の時は同じクラスだった。
「わかんない……父さんの仕事しだいさ」
「大変だよね。藤樹も振り回されちゃって」
「でもないさ……空気はいいし、海は青いし……」
そう言いながら、信号が青に変わり、揉み合うようなうねりを見せている横断歩道の雑踏に和也は目線を投じた。夏のうだるような暑さ。行き交う人々の顔には細い汗が光っていた。
「そうでも、ないんじゃないの?」荻島も同じように窓の外の夏の風景に目を止めながら言った。
「え、」
「泉が……藤樹に会いに行ったら、暗い顔してたから、ひょっとして向こうでイジメにあってるんじゃないかって」
「そんなことないさ」ぎこちない笑顔で、和也は否定した。
「ふうん、それならいいけど……ひょっとして藤樹、今ごろ登校拒否になってるかもって、泉と言ってたんだ」
「郷に入ってはなんとかってことわざがあるじゃないか、慣れちゃえばなんでもないさ」
「ふうん、でも、元気そうだし、心配することもないか」
荻島は横断歩道で信号待ちをしている黒のタンクトップを着たポニーテールの似合う同年代の少女の形のいい足を窓ガラス越しに見ながら、残り少なくなったアイスコーヒーをストローで一気にすすった。
渋谷の街は、上空にねっとりとした大気がはびこり、人々の足は、動くたびにまとわりつく空気に重たげだった。時間までもが炎暑に組み敷かれ、間延びしたかのような昼下がり。路上にはき出された騒音に、街中が埋め尽くされていた。
「橋田理絵……荻島、知ってたっけ?」
「え、ああ、橋田って、1年の時、隣のクラスだった?」
「うん、その橋田……」
「どうして?」
「う、うん、元気かなあって思って」
詰まりぎみに和也は答えた。そんな和也を荻島は横からすくいあげるように見ると、
「あ、そうか、橋田のこと、そうか、ふうん、そうだったの」
と、ハンバーガーを口一杯に頬ばったまま言い、
「藤樹、好きなんだ、橋田のこと」
と、何もかも合点したような目でうなずいた。
「そんなんじゃないさ」
「じゃなくて、いったいなにさ」
「いい子だなって思って」
顔をほのかに赤らめながら和也は答えた。
「だから好きなんじゃないか……へえ、藤樹がねえ……競争率高いぞ、橋田は、みんな目をつけてるから」
実は自分も橋田には前々から目をつけてたと、荻島も正直に告白し、和也は少しばかり困惑した。もう東京にいないんだから橋田はあきらめろ。そう言って、荻島は和也を説得にかかった。そうはいくもんか。遠距離恋愛ってのもあるんだ。和也も負けてはいなかった。2人は言葉の上で1人の少女を取り合った。
結局、その話に決着はつかず、荻島は最近購入したばかりのゲームソフトのことに話題を移した。すごいぜ、ありえねーぜ、あれ、銃撃戦のあのリアルな動きは、気がついたら4時間ぶっとおしでゲームやってて、あんた、その熱意を勉強に向けなさいよって、アネキにさんざん叱られたと、荻島はゲーム談義を延々とした。
中盤戦でつまずき、中々先に進めないゲームがあって、攻略のために朝方まで起きていて、翌日学校に遅刻し、徹夜がたたって体調を崩し、下痢になって授業中に何度かトイレに立ち、恥ずかしい思いをした、と店員の冷ややかな目線を気にすることもなく、特徴のあるよく通る声で、荻島は夢中で話し続けた。気のおけない友人とのはずむ会話に、和也は我を忘れた。
荻島と渋谷の駅前で別れたのは、空がうっすらとした鼠色に変わり、涼感が街を包み始めた頃だった。その日の夜、泉にも会いたいと思い、連絡をとった。
帰ってたんだ。いつまでこっち。会いたいけど、塾で絞られちゃって時間が取れそうにないよ。拷問だぜ、これは、フジキ。プール、行きてーよー。死ぬほど、女と泳ぎまくりてえー。暑い、とんでもなく暑いし。調子はずれの声で泉が嘆いた。電話口での泉の悲鳴にも似た口調が和也にはおかしかった。
そういえば、明日から塾でどこにも遊びに行けないって荻島も浮かない顔でいたっけ。久しぶりの友人たちとの再会を塾に阻まれ、少しばかり寂しさを感じた。
東京での滞在期間が詰まるにしたがい、瀬田のことが度々思い出された。西の空が赤く焦げ、夜のとばりがあたりから光沢を奪い始めた頃、残照で黄金色にあぶり出され、泣きさざめく海がとてもなつかしく感じられた。
2日続けて瀬田と海で戯れている夢を見た。
東京からの車中、和也はなぜか気分が晴れなかった。
「あれほど楽しみにしてたのに、ここ2,3日元気がなかったじゃないか。またしばらく東京を離れるんで寂しくなったのか?」
ふさぎ込んでいる和也に正己が訊いた。
「そんなんじゃないよ」
和也は立て続けに見た瀬田の夢がなぜか気にかかって仕方がなかった。
「陽に焼けてずいぶんたくましくなったって、みんな褒めてたじゃないか」
正己と話をするのもおっくうなほど和也の胸は重かった。
車が京都に入り、山々が涼しげに薄日に浮かんでBMWの窓に映り始めた頃。ぐったりと体を投げ出して後部座席に横たわっている和也と会話が途切れると、正己は所在無げにラジオのスイッチを入れ、無造作にチューニングし、好みの局を探した。
ラジオのスピーカーからは、おどけたようなコメディアンの濁声と、濡れそぼったような演歌を歌う女の声と、ニュースを読むアナウンサーの単調な声がこま切れに入れ替わり流れてきた。
和也は後部座席からぼんやりと、正己のチューニングを目で追っていた。充分に眠っていたため、目が冴えていた。そのうち正己はニュースを流している局を選び、抑揚のないアナウンサーの声にしばらく耳を傾けた。
その時、アナウンサーの告げる『セダ』『チンボツ』という声が和也の耳をとらえた。和也は、後部座席から身を乗り出し、正己にラジオの音量をあげるよう頼んだ。
……サクヤミメイ、オキオキデエンジョウ、チンボツシタ……ギョセン、ダイイチヒヨウマルノノリクミイン、セダマサオ、セダイサオオヤコ……イゼンショウソクフメイ……。アナウンサーはそう告げていた。
(もしかして……あの瀬田……)和也の頭の中で『セダオヤコ』、『エンジョウ』、『チンボツ』、『ショウソクフメイ』という音が羽をつけた虫のようにうるさく飛び回った。
( まさか……ありえない……そんなことが )湧き起こる疑念を何度も振り払おうとした。が、どうしてもアナウンサーの『セダオヤコ』という声が耳に付いて離れなかった。
あのセダくん?……まさか。そう言って、正己が心配げに和也のほうを振り返った。和也は顔を横に振り、正己の懸念を振り払おうとした。( ありえない……あの瀬田に、そんなことが…… )。
窓の外は、幾分青みの残った薄暗い空に夕焼けが裂け目を入れ、次第に赤黒い広がりを見せていた。
路上は、京阪神からの車の長い連なりができ、渋滞ぎみだった。目の前の観光気分の車にいらつきながら、一刻も早いBMWの到着を和也は願った。
No.15 東の空が青白く潤み