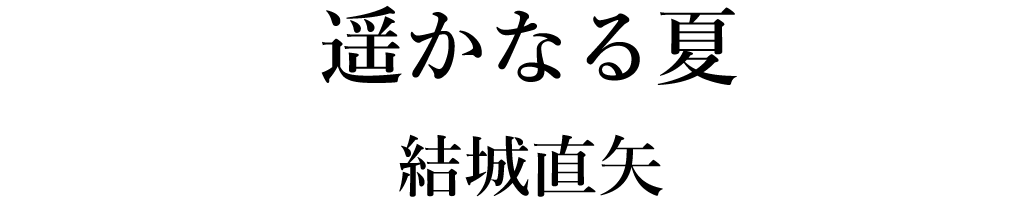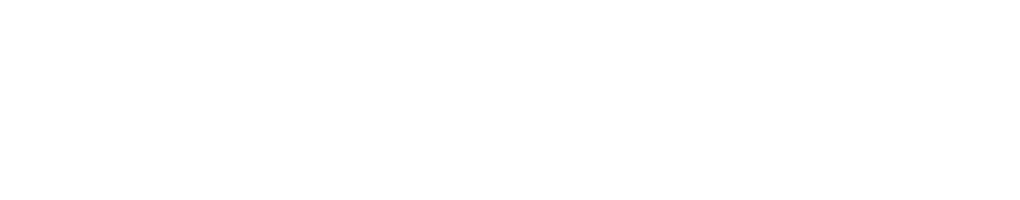No.15 東の空が青白く潤み
東の空が青白く潤み始めている。湿り気を帯びた重たげな大気が上空で幅をきかせ、空は一面、澱み、陰鬱な色をたたえている。かすかに揺らぐ淡い光と、水っぽいねばり気のある空気と、いつまでたっても光彩のはっきりしない朝の風景がそこにあった。
東京から帰った翌日、窓が青い濃淡で染まり始めた頃、和也はふと目が覚めた。しばらく、天井を見つめ、目覚めを促した暗澹とした気分と向かい合った。そのうち底知れぬ不安を含んだ想いが体をむしばみ始めた。唐突に、ニュースで報じられていたことを確かめるため、瀬田の住む漁村の漁業組合に行ってみては、という思いが湧いた。ベッドから起き、それを実行に移そうかと思った。
が、体がその気にならなかった。頭の先から足の先まで強張り、目覚めたばかりの虚ろな意識は途方に暮れていた。ニュースで報じられていた『セダ』が、もしあの瀬田だったとしたら。確かめることが怖かった。予定だと、明後日くらいに漁から帰ることになっていた。
目覚まし時計が部屋中を掻き回すような音を立て鳴り響いたが、和也はベッドから中々抜け出すことができなかった。手を延ばし、頭の芯に刺さるような音を葬ると、布団を頭からかぶってしまった。眠り続けられるところまで眠るつもりだった。しかし、まどろみの中で、何度も黒々とした海の底に沈む夢を見ては、目が覚めた。
気がつくと、時計の針はすでに午後の2時をまわっていた。首筋と背中が寝汗でぬめっと湿っていた。出入り口をふさがれ、行き場を失った夏の熱気が部屋中にたちこめていた。ベッドから身を起こすと、蒸し暑い空気の群れが一斉に顔や体に襲いかかった。
日中、机に向かっていても勉強する気になれず、音楽を聞いても、テレビを見ていても瀬田のことが頭について、何をするにも腰が座らなかった。
瀬田の安否を確かめねばという思いが、胸のあたりでくすぶり続けていたが、どうすることもできなかった。へたに触ると爆発してしまいそうな火薬にも、それは似ていた。といって、何もしないでいるのも、堪えられなかった。
気晴らしにと、台所に行き、冷蔵庫から肉や野菜や卵やら中に入っているものを全部取り出し、それを鍋の中に手当たりしだいに放り込み、香辛料を目一杯振りかけ、それまで作ったことのないような料理を作り、出来上がると大皿に盛りつけ、掻き込むように口に入れた。ペッパーが鼻につんときて泣きたくなったが、生煮えの肉も芯の残った野菜も何もかもむさぼるようにして胃の中に詰め込んだ。満腹になると部屋に戻り、倒れるようにして再びベッドに横たわり、そのまま寝てしまった。
目が覚めたのは、窓の外の景色が黒い粉でまぶされたように闇と同化し、すべてがのっペりとした影絵に変わろうとしている頃だった。和也は、ベッドから起き上がり、部屋を出ると、帰宅して居間にいた正己に外出すると告げ、玄関先に置いてあった自転車に股がった。
正己は、「気をつけて」とだけ言って、和也を送り出した。正己も瀬田の安否を確認することがためらわれたにちがいない。おそらくもう、という感情で顔を曇らせた正己がそこにいた。
舗道のアスファルトは夕方から降り出した小雨で濡れていた。街路灯のすすけた明かりが滑りやすくなったそれを危なげに照らしている。雨はほとんどあがっていたが、目の前の家々の間に薄っすらと靄がかかり、少しばかり気になった。Tシャツとジーンズだけで大丈夫かな、と思った。が、部屋に引き返す気にもなれなかった。そのまま和也は足先に力を込め、思いっきり自転車のペダルを踏んだ。
まるでどこかに思考力を置き忘れてしまったかのようで何も考えることが出来なかった。ただ頬に当たる澄んだ夜風が、起き抜けの冴えない頭から癒しきれない不安の数々を綺麗に拭い取ってくれるような気がして、懸命に自転車をこいだ。何度も海へ行くたびに通った慣れた道ではあったが、今宵ばかりはペダルを踏む足が絡みそうに重かった。まるで他人の足のようだった。
車とほとんど擦れ違うこともなく、ひっそりと寝静まったような原っぱや家族の団欒が窓に映った家々を横目に見ながら、暗い夜道をライトで照らし、ひたすら自転車を前へと進めた。
あの瀬田が……まさか……そんなことが……聞き間違いであって欲しい……いや、アナウンサーは確かにはっきりとセダと告げていた……とりとめのない不安と苛立ちが全身を駆け巡った。
先走った感情だけが和也の体を支配していた。次第にそれは抑えきれないほど膨れあがり、体中の養分を吸い取ったあげく、まるで生き物のように頭の深い所にどっかりと腰を据えてしまった。
青く、透明な海……サザエを手にいっぱい持って喜ぶ瀬田……米多たちを蹴散らし、助けてくれた……残光の漂う海を、沖に向かって泳ぐ瀬田……クジラの潮吹きを真似て無邪気に戯れ……島の上から放物線を描いて飛び込む瀬田……片腕の無い父親の仕事を手伝っていた……イタリア料理をおいしそうに頬ばってた……瀬田と見上げた夏のまばゆい空……青い空が隠れるほどむくんだ入道雲……2学期から学校に出ると約束した……遠くで鳴き騒ぐ海鳥の群れ……海面の隅々にまで光を振り撒いた真夏の太陽……まばゆい夏の輝き……。が、エンジョウ……セダマサオ、セダイサオオヤコ……ショウソクフメイ……アナウンサーの冷酷な声が耳の底でよみがえり、全ての光景がぷっつりと闇に呑まれてしまった。
いつも通りすがりに辟易する養鶏場の匂いもその夜は鼻につかなかった。そこをいつ通り過ぎたかどうかもわからなかった。いつもと違う道のようにも思えた。ゆるやかなカーブを描いた道に何度もハンドルをとられそうになった。まるでねじ曲げられた空間に放り出され、さまよっているかのようだった。
遠くに見覚えのある漁村の家々のシルエットが見えてきた。和也は爪先に力を入れ、前かがみになって一気にそこまで自転車をとばした。道路脇のどの家もその中心に薄明かりをふくらませていた。道路まで届いた明かりをたよりに自転車を前へと進めた。
漁業組合は漁村のほぼ中央の沿岸にあった。3階建ての鉄筋のその建造物は遠くからでもよく目についた。建物の1,2階ともまだ明かりがこうこうと灯っていて、窓辺には人影のようなものがちらついていた。その周囲に人けはなく、すぐ先の港には同じような形をした漁船が何隻も並び、黒い海面と同化していた。
漁業組合の玄関先に自転車を停め、人の顔の幅ほど開いていたサッシ戸を汗ばんだ手でゆっくりと押し広げた。中に入ると真先に生臭い魚の匂いが鼻をついた。思ったより広く、左手の隅に網の束や整然と積み上げられた木箱が淡い電球の明かりに照らされていた。入ってすぐ右手に受付の事務所があったが、蛍光灯が明々と中の机や計器類を照らしているだけで、そこに人影はなかった。
事務所の奥の脇に2階に上がる階段があって、その上から人の足音や話声らしきものが微かに聞こえてきた。階段の傍まで歩み寄り、見上げるようにして様子をうかがっていると、おりよく職員らしき年配の男が降りてきた。
「あの、すみません……」
ふいに階下から顔を出した和也に、男は驚き、階段の途中で足を止めた。
「あの……ニュースで聞いたんですけど……セダってひとの船が沈んだって?……」
「セダさんの知り合いか?……」
丸顔の気のよさそうな顔をしたその男は哀れむように和也に訊いた。
「え、ええ……」
「そうか、そりゃ、かわいそうなことしたなあ……」
「あの、セダ親子って聞いたんですけど……片腕のない……そいでぼくと同じくらいの年の?……」
一言一言黄色く濁った男の目を見て、確かめるように和也が訊くと、そのたびに男は目を伏せ、力なく首を垂れた。
「これから2人で精だしてやるようなこと言っとったのになあ。かわいそうに、勇雄ちゃんもお父さんの仕事、よう手伝っとったし……」
どうにもやりきれないといった男の濡れたような声だった。足が小刻みに震え、立っているのが和也にはやっとだった。やはり自分の知っている瀬田親子であった。
「波も高うて、しけとったし、なんで無理しょったんだか……」
和也は男の言葉を最後まで聞くことが出来なかった。2階で男を呼ぶ声がしたため、話の途中で男に頭を下げ、そのまま逃げるように事務所を後にした。
外に出ると微かに肌に感じる程度の小雨はすでに降り止み、息の詰まるような静寂が漁村をすっぽりと包み込んでいた。
何か熱い塊が胸のあたりでじわりと溶け出し、体中の血が細い血管の内側にべっとりとねばつき、流れが滞ってしまったような感覚が走った。どうしても納得のいかない気持ちと先程聞いた男の声が合わせられた同じ磁石の極のように反発し合っていた。黒い空に半分欠けた月が貼りついて見えた。漁村の家々は墓場のような静寂をまとっている。闇に馴染んだ漁業組合の黒々とした壁も、その前に停まっている遠距離用の大型トラックも、長方形に明かりを閉じ込め、ぽっかりと闇に浮かぶ公衆電話のボックスも、全てオブラートのような幕がかかって和也の視界に映った。港で重々しく揺れている漁船が、その周囲でゆったりと凪いでいる波が、耳元を撫でるように通り過ぎていく生ぬるい風が、暗い路をあてもなくうろついている野良犬が、何もかもがすべて一つ間違えば憎悪の対象となりかねなかった。
漁業組合の前に停めておいた自転車に再び股がると、ハンドルを瀬田とよく泳いだ海岸の方角へ向けた。男の言葉を素直に信じ切れるほど和也の頭の中は澄み渡っていなかった。川の底を掻き回したような混濁がそこに広がっていた。海岸へ行けば、そこに瀬田がいて、真っ黒な顔に白い歯をのぞかせ、笑いながらいつもの挑発的な目で迎えてくれるような気がした。
起伏に富んだ、雨がまだ乾ききっていない夜道を無心に和也は自転車をこいだ。所々水たまりが出来ていて、危うく滑って転倒しそうになった。
漁村の集落を抜けかけた頃であろうか。突然曲がり角からまばゆいライトの光とともに乗用車が踊り出て来て、とっさのことに方向感覚を失い、擦れ違いざまによろめき、道路脇の草むらに投げ出されてしまった。暗がりに映える赤い色のその車は罪の意識のかけらも残さず、勢いよく放たれた矢のように闇を切り裂いて、行ってしまった。
幸い、たいした怪我はなかった。が、手の甲が少し擦り剥けて、血がにじみ、ハンドルを握って自転車を立て直した時、ひりつく痛みを感じた。自転車はハンドルとペダルが土にまみれ、少しばかり歪んでいた。
自転車についた泥を取り、手足についた土挨を払い、周りに目を凝らすと、ふたたび和也は自転車のペダルに足をかけた。ペダルとハンドルがぎくしゃくして中々前へ進まなかった。このヘボ自転車、なんで、動かないんだ。なにもかも放り投げてしまいたいようないらだちが何度も腹の底からつき上げてきた。
瀬田とよく泳いだ馴染みの海岸に着いたのは、思い通りにならない自転車に全く愛想がつきかけた頃だった。
海岸ではさざ波が砂にしみ、夜の底で小さな寝息をたてていた。海は遠く彼方までざらつき、無数の波の薄気味悪さが闇の底でうねっていた。その海と空との境に赤い落ちた流れ星にも似た輝きがあった。イカ釣り漁船の集魚灯の明かりであった。
自転車を浜辺にねかせると、和也は波打ち際まで駆けて行った。沖合では集魚灯の小さな丸い光が消え入りそうに波の上でうつろっていた。
どうしても瀬田が海で亡くなったなどとは考えられなかった。たとえどんな災難に襲われようとも、泳ぎのうまい瀬田がそれを避けられないはずがないと思った。
(瀬田にかぎって……あの瀬田が死んだりするもんか……)
海上の灯火がいつしか和也の視界にぼやけて二重に映った。涙で潤んだ和也の瞳の奥に、片腕のない父親を抱きかかえながら、暗く冷たい海の底を必死で泳いでいる瀬田の姿が浮かんできた。
No.16 このままで終わるものか