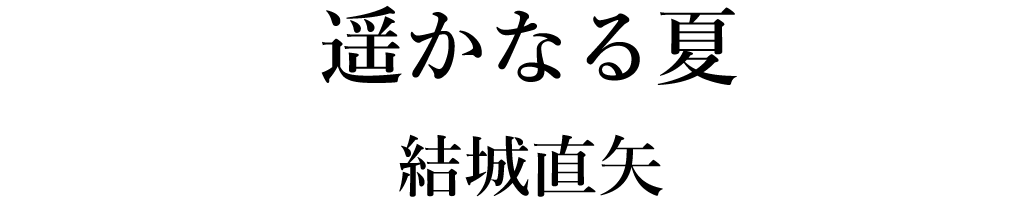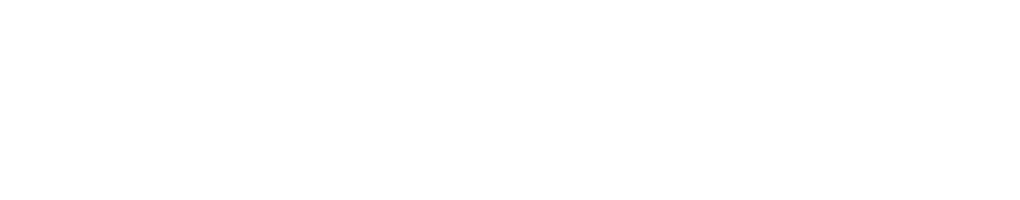No.16 このままで終わるものか
瀬田親子の消息は依然として不明で、生存の可能性はほとんど絶望的だった。
悪夢のただ中で硬直しているような日々だった。重い時がまとわりつき、うんざりするほど1日が長く感じられた。登りかけていた階段の途中で急に足元をすくわれ、真っ逆さまに転がり落ちていくような気分だった。
意気消沈し、日ごとに瀬田と出会う以前のような状態に和也は戻っていった。生活もだらしなくなり、昼過ぎまでベッドに横たわり、まるで手のほどこしようがないほど病状が悪化し、医者に見放された患者のようなうちひしがれ方で、覇気のない日々を過ごした。
そんなある日。和也は自転車に乗ってふらりと瀬田の住んでいた漁村に向かった。瀬田親子の家を探すのが目的だった。瀬田とはいつも海岸で落ち合うだけで、彼の家には一度も行ったことがなかった。
その日、空は暗く、雨雲がまだらに群がり、いまにも鳴咽しそうな険しさが陰鬱な大気の移動とともに広がっていた。横なぐりの刺々しい風が自転車にぶつかり、時々ハンドルをとられそうになった。
漁村に着くと、複雑に入り組んだ坂道を自転車を押して歩いた。家々が斜面に積み上げられ、魚の鱗のようにおり重なっていた。
どの家も身を寄せ、支え合うようにして窮屈そうな面持ちでたたずんでいた。漁村全体が一軒の家だった。テレビからの音が開け放した家々の戸口から漏れ、苔むした石段の上に流れ出し、その音に混じってどこからか乳呑み児の跳ねるような鳴き声が聞こえ、犬のわななく声が耳に届いた。
魚臭い磯の臭気と湿った熱気が家々の間にこもっていた。割烹着姿の中年の女たちが3人ほど戸口に立ち、人目もはばからず、よもやま話に花を咲かせている。生計を支えている男たちは皆出払い、明日の朝、朝日が東の空をほんのりと赤く染め始める頃、港に新鮮な活気をもたらすためにそれぞれの持ち場についているようだ。
狭い路地で小学生たちが夏休みで暇を持て余している近所の仲間を誘い合い、通りを占領し、ボールを蹴ってサッカーの真似事をしたり、わずかばかりの空き地にたむろし、ソフトボールに光る汗をしたたらせていた。
和也は、しばらく立ち止まって彼らの粗野な声の調子に耳を傾けた。そのうち少年たちが足で受けそこなったサッカーボールが和也の足もとに転がってきた。和也はそれを自転車のタイヤで受け止めると、ボールを求めて駆け寄って来た少年に、それを放った。上半身裸の少年はボールを受け取ると、浅黒い顔にえくぼを浮かべ、申し訳程度に頭を下げ、仲間たちの方へ走り去って行ってしまった。どことなく挑むような少年の目の配り方がどこか瀬田に似ていると思った。
坂道を登りきった見晴らしのよい所に、削り取った崖を背に、同じような外観をした見すぼらしい平屋建ての家が2軒並んでいた。どれもまるで物置小屋のような簡素な作りだった。屋根瓦が所々はがれ、いまにも崩れ落ちそうになっている。ガラス戸は厚い埃でおおわれ、風避けのために家の脇に置いてあるトタン板は潮で錆び、風にはためき、きしんでいる。人を拒むような、すさんだ気配があたりに漂っていた。が、目当ての家だった。確信はなかったが、どちらかが瀬田親子の住んでいた家のように思われた。
(ここに瀬田が……)トタン板が風に揺れるたびに和也の胸が痛んだ。
廃屋のような家にもかかわらず、表札がかかっていた。近付いてよく見ると、間違いなく瀬田の姓であった。確かに誰かがそこで生活を営んでいるように思えなくもなかった。が、2軒ともしんみりと静まりかえり、玄関口に立ってそっと耳を澄ましても、中から物音は一切聞こえず、人のいる気配はまるで感じられなかった。家にぶつかる潮を含んだ冷たい風が中空で舞い、大気を逆立て、そのあたりで唯一ざわめいているだけだった。あまりに物寂しい周囲の気配に、次第にそこにいるのがいたたまれなくなった。来なければよかったとさえ思った。
そこにいつまでいても目の前の荒れた家が瀬田親子の住んでいた家だという確信を深めることはできなかった。いや、それを認めたくなかったのかもしれない。地図に載っていた瀬田の姓の家を求め、最初にそこにたどり着いたというだけだ。瀬田の姓を名乗る家は他にもまだ何軒かある。ちがう……こんな寂しい家じゃない……瀬田が住んでいた家はここじゃない……否定的な思いが胸のうちで渦巻いた。どうしてもそこを瀬田の家だとは認めたくなかった。
背を向け、自転車のハンドルを力なく握り、帰ろうとしている時だった。何か白い物が視界の隅でちらついた。家の脇でぱたぱたと風になびく白い布のようなものが目に入った。気になって、そっと忍び足で家の脇に回り、恐る恐る奥をのぞき込むと、物干し竿に白いランニングシャツが掛かっているのが見えた。何日もそこにそうしたままであったらしい。白いシャツは埃っぽい風になぶられ、揺らいでいた。
しばらく立ちすくんだまま、和也はじっとそれを見やった。そのうち何故かそれが初めてバスの中で瀬田を見た時に、瀬田が着ていたランニングシャツのように見えてきた。シャツにはいくら洗っても取れないようなしつこい油のシミ跡が所々うっすらと残っていた。まるで瀬田の形見のように思えた。
見上げると、真夏の太陽の強い直射が瞼を突いた。瀬田と戯れた初夏の海が青々とよみがえった。大地がぐらりと溶け、風景が斜めに切り取られてかしいだような感覚が走った。
気がつくと、和也はシャツを物干し竿から抜き取り、左腕にぐるぐる巻きにして、自転車のペダルに足を掛けていた。自分が何をしたのかまともに判断できないほど気が高ぶっていた。自転車に飛び乗ると、坂道を転がるように漁村の狭い路地を走り抜けた。時々路地で遊んでいる小さな子供たちにぶつかりそうになり、ブレーキが悲鳴のようにきしんだ。前屈みで目を血ばしらせ、疾走する和也に誰もが驚き、道を開けた。腕に巻きつけていたシャツがほどけ、旗のように風にひらひらとなびいた。
もしあの家に人が住んでいて、このことを知ったら……でもあの様子からしてとても人が住んでいるようには思えない……あの家がほんとに亡くなった瀬田の家だとしたら?……このシャツは当然自分が引き取らねばならない物だ……あのままさらして放っておくのは、あまりにもかわいそうだ……。
あの家が瀬田親子の住んでいた家かどうか、確かめることは簡単だった。近所の誰かに訊けば、それですむことであった。だが和也にはそれができなかった。確かに片腕のない父親と陽に焼けたたくましい少年の暮らしていた家だと誰かの口から聞くのが怖かったのだ。
漁村の集落を逃げるような思いで抜けた頃、気の高ぶりも幾分おさまった。首や肩をほぐすようにうごめかすと、冷たい汗が一斉に背中を這った。見上げると、空は相変わらず冴えない濁りを浮かべ、シワのようなゆがんだ雲を何本も走らせていた。
家に帰り着くと、和也は持ち帰ったランニングシャツをハンガーに掛け、しばらく見続けた。シャツは和也の体の一回り以上の大きさがあった。見れば見るほど、瀬田が着ていたもののように思えてならなかった。
その夜、和也は中々寝つけなかった。昼間の興奮で、身体の芯にすくった緊張がとれなかった。明け方、窓辺が青白く色褪せ始めた頃、壁に掛かったランニングシャツに何げなく目を止めると、外の薄明かりにそれが白く浮かび、五体をともなった白い人影のように見えた。
翌日、夏の陽ざしが一気に高まり、本格的な暑さが窓ガラスをあぶり始めた頃、和也はベッドから抜け出すと、瀬田と泳いだ海岸に向かった。あの夜以来、浜辺に行ってなかったが、何故か無性にそこに行ってみたくなった。
7月下旬の海辺は海水客で溢れ、砂浜には色とりどりのビーチパラソルが所狭しと打ち立てられていた。灼熱の太陽のもとで肌を色濃く焼く若者たちや、波打ち際で砂遊びを楽しむ家族連れで浜辺はむせかえっていた。海上には、ボートが何隻も浮かび、波間にかん高いはしゃぎ声が飛び交っていた。
瀬田とよく泳いだ島の付近に、和也は行ってみた。そこは遊泳区域から外れた所で、海水客が好んで戯れ、たむろするような所ではなかった。
そのあたりに人影はほとんどなかったが、ボートが2隻島の先に張り付き、若者たちがその上で耳をつんざくような騒がしいロックの音楽に興じ、ふざけ合っていた。
しばらくして、海中に潜っていた彼らの仲間が海上に顔を出した。貝を求めて潜ったが、収穫がなかったのであろう。ボートにいた濃いサングラスをかけた若者が手に持っていたスイカの食ベカスを八つ当たりでもするかのように海に投げつけた。そのうち、憤慨したように、ボートを島から離すと、若者たちはどこかへ行ってしまった。
こんなもんを捨てる奴がいるから海が汚れるんだ。いつかそう言って、瀬田が海の底で海藻に絡みついているカップラーメンの容器を拾い上げてきては怒っていたのを思い出した。
(あいつら……)まるで彼らに瀬田との思い出を足蹴にされ、つばでも吐きかけられたような気分になった。瀬田がこよなく愛した青く澄んだ海を心ない連中に汚され、やりたい放題にされているような気がして、無性に腹が立った。いつか片倉や米多に徹底的にいたぶられた時の感情さえもぶりかえした。
( 瀬田のためにも負けてたまるか……このままつぶされてたまるか……)憤りは自分自身にも向かった。このままで、終わるもんか、絶対に、みてろ。
強烈な陽光を受け、方々で刺立った光の乱舞する真昼の海を見ながら、自分を鍛えてくれた瀬田のためにも……強く生きなければ、と和也は自らに言いきかせた。
翌日、早朝の、どこもかしこもゆったりと均一に揺れる静かな海に和也は出向いた。そして、着ているものを脱ぐと、海パンだけになり、朝の灰色がかった凪いだ海に入っていった。
空にはむくんだ雲が眠たげに重くたれこめ、砂浜にはまだ充分な陽の光が漏れてはいなかったが、次第に東の空から雲が割れ、そこから淡い桜色の空が顔を出し、いつもと変わらぬ夏のまばゆい日差しが降り注ぎ、海の色を本来の青みに変え、跳ねるようなきらめきを海面いっぱいに敷き詰めそうな気配があった。
内臓まで引き締まりそうな冷たい朝の海に胸まで浸かると、和也は瀬田のフォームを思い出しながら、泳ぎの練習を始めた。太陽が空の中心にさしかかり、空腹を感じても、家に帰らず、午後もそのまま泳ぎ続けた。黙々とひたすら泳ぎ続けた。泳ぎ疲れ、くたびれた雑巾のように体中の筋肉がのびきってだるくなり、へとへとになると、近くの島に上がり、死んだように仰向けに寝そべり、いくらか回復すると、また海に飛び込み、遮二無二泳ぎ続けた。
毎日、そうして泳いだ。午前中に勉強を済ませ、昼から海に出て光の痕跡が海面からすっかり消えるまで泳いだ。無我夢中で、亡くなった瀬田への悲しみを振り切るように泳ぎ続けた。瀬田を無情にも呑み込んでしまった海が憎かった。好きな海で死ねて瀬田は本望かもしれないが、大事なものを自分から奪っていった海がどうしても許せなかった。満足に泳げなくて海に翻弄されている自分自身にも腹が立った。その怒りを海にぶつけるかのように、来る日も来る日も狂ったように泳ぎ続けた。
毎日夕暮れ時まで海で過ごし、和也は自らを鍛えた。そんな日々の努力が次第に強靭な精神力と、しなやかな筋肉と、自信にみなぎった顔つきを与え、さらに何でも懸命にやれば必ず力はつくものだという信念を植えつけていった。
陽がとっぷりと暮れ、深い闇が辺りに迫った頃、くたくたに疲れきった体で誰もいなくなった海辺を1人歩いていると、今日も限界までやり遂げたという充足感に浸ることが出来た。辛く苦しかった1日をしめくくる何物にも代え難い無上の喜びだった。
が、時に、天空を暗褐色に裂いた夕焼けを目にすると、息の詰まるような胸の重苦しさを覚えた。全てのものに必ず終焉が訪れることを知らしめるかのような、そんな色だった。心臓を手掴みにされたような苦痛が走った。
死にもの狂いで海に立ち向かっていったためか、和也は日に日に泳ぎがうまくなっていった。白く貧相だった体は、毎日真夏の容赦のない陽ざしで、まんべんなく焼け、筋肉もいくらか増したかのようで、以前とは見違えるほど緊まった体つきになっていった。泳ぐ際に前髪が目の前に垂れ、邪魔になるためばっさりとそれを切り、瀬田のように頭を短く刈り込んでしまった。
かつての色白でひ弱な少年は短期間にまるで別人のように変貌していった。和也の変わりように正己は言葉を失い、ただ驚くばかりであった。
「ずいぶん焼けたな。まるで地元の人みたいじゃないか」
夜、食事をとっている時、そう言って正己は和也をからかった。
確かに父親の言う通りかもしれないと和也は思った。鏡の前に立っても、以前の顔色の悪い華著な少年はもうそこにはいなかった。腕や背中の皮が汗を含んで剥がれ、肌がまだらになったものの、その上に何度も太陽の直射を浴びるものだから、すっかり地肌が黒く染まっていた。
No.17 和也が自身に課した泳ぎの特訓