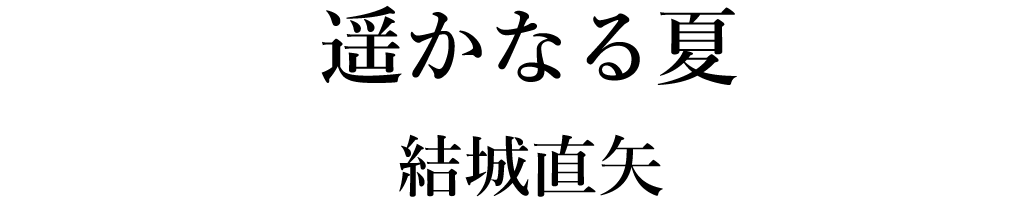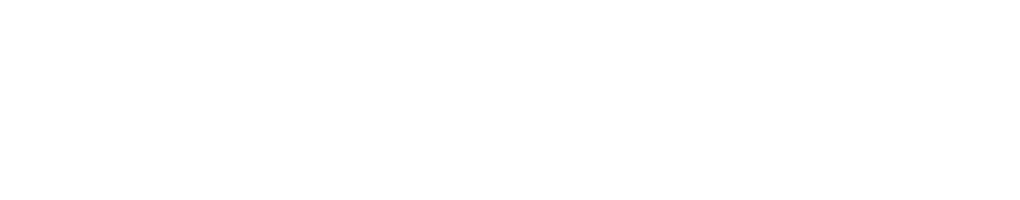No.2 転校、母の夢のために
年の瀬も押し詰まった週末。和也は学校から帰ると、窮屈な学生服を脱ぎ捨て、厚手の白いセーターとジーンズに着替え、ファンヒーターを適温に調節し、靴下をはいたままベッドに仰向けになり、漫画本を読みながら、音楽に耳を傾けていた。
「そろそろ出かけるぞ」
張りのある若い声が庭先から聞こえてきた。愛車のBMWにワックスがけをしている父親の声だった。いつになく軽やかな響きがある。
「うん、すぐ行くよ」
バラード調の歌に、しだいにまどろみかけていた体をベッドから起こすと、和也は2階の窓を勢いよく開け、車磨きに夢中になっている父親に返事をした。
その日の夕方、久しぶりに父親の正己と横浜で食事をする約束をしていた。めずらしくそれは正己からの提案だった。
特にめかしこむ必要もないだろうと、和也はそのままの恰好で、机の上にあったスナックを口いっぱいに頬ばり、階段を駆け降りて行った。
「戸締りを忘れるなよ」
戸口から、父親の乾いた声が聞こえてきた。その声に和也はあらためて、父親と2人きりの生活を実感させられた。母親が生きていた頃には出かける前の心得など他人の家のことのようだった。
和也は2階の自分の部屋へ駆け上がり、窓に鍵を掛け、再び1階へ降りて部屋から部屋へと外への出入り口をふさぎ、火元の確認をし、すべて万全と自らに言い聞かすと、正己の待っている玄関先へと急いだ。
玄関のドアを開け、隙間から陽のかげった外に顔を出すと、そこにはまるで購入したばかりのように艶やかに磨き込まれたBMWが玄関の明かりを鋭く跳ね返し、和也を待ちかねていた。
年末の環状8号線は予想通り大変混み合っていた。街道沿いのファミリーレストランは、どの店も沸きあがった熱湯のように週末の夜に繰り出した客であふれ、そこから次々にはき出されてくる車は、ただでさえ見通しの悪くなった路面にさらに苛立ちを加えた。
----- が、それでも玉川ICで第3京浜に乗り換え、しばらくするとBMWはようやく流麗な疾走を取り戻し、道路の両脇にひしめくネオンを色とりどりに脈打つ光の波に変えていった。
母親の和恵が元気だった頃、夕方から3人で横浜に繰り出し、港を眺めながら食事をしたことを和也は思い出した。ガラス越しに浮かぶ港の夜景を望みながら、和恵は横浜で正己と知り合った頃の思い出を少女の顔で話し、その横で正己は照れ笑いしながら、料理を口に運んでいた。
和恵が他界して、すでに2年の歳月が流れていた。和恵が亡くなって以来、正己は和也を横浜へ誘うことはなかった。
「母さんとこの辺りをよくデートした……元町あたりをぶらついて……山下公園で休んで……いつも最後は港の見える丘公園で夜景を眺めた……おきまりのコースだった……母さん、夜の港が好きで……」
桜木町らしい見覚えのある街並みがBMWの両脇に見え、海岸通りにさしかかり、港に停泊している船の明かりが車の窓に夜光虫のようにうつろい始めた頃、正己は遠い昔の記憶をたぐるような目で和也に話しかけた。
「その頃の母さん、どんなだった」
「ああ、綺麗だった……とても……父さん一目惚れだった……」
こもったような声で正己は言うと、山下公園通りをスピードを落としてBMWを走らせた。黒い艶やかな髪に、ふだんはほとんど化粧っ気のない顔。和恵は38歳で他界したが、学生時代の母親の姿が和也には容易に想像できた。
右手に、赤と緑のイルミネーションに彩られたマリンタワーが吃立しているのが見えた。
「和也、覚えてるか。お前がまだ小さかった頃、母さんと3人であそこへ上がって、わんわん泣いて大変だったのを」
「え、そんなことあったっけ」
とぼけたように和也は答えた。が、確かにそうしたことがあったことを微かに覚えていた。
和也は車の窓に頬を当て、夕暮れの港を眺めた。遠く水平線と空との交わりが見境もつかぬほど虚ろになって、しだいに薄暗い闇が港を呑みこみ、海面は湾岸の灯を笑みのように浮かべ、ゆっくりと夜の底に沈み始めていた。
地上10メートル以上もある展望台から見たあの時の薄闇に包まれた海は何故か和也にはうす気味悪いものに映った。岸辺の街の灯が湾上に百花繚乱のごとく灯り始める前の、どんよりとした灰色の鈍い光をちらつかせた海のうねりは、底知れぬ不気味さをたたえ、鉛色の水面を揺らぐ波の蛇行は、まるで日が暮れて海の底から得体の知れない魔物が現れ、その異容を身悶えさせながら、うごめいているようにも見えた。
和也が高い所が苦手なのはその時の体験に起因していた。
すっかり深い闇に放り込まれた夜の横浜の湾岸はペットショップのような落ち着かないざわめきに満ちていた。週末のデートに胸をときめかせ、上気させた顔で、はずむような白い息を夜のとばりに吐き出し、人目をはばかることなく腰に手をまわしている恋人達。コートの襟を立て、忘年会の席での無礼講をそのまま路上に持ち込んだような乱れ方で群れている中年の酔ったサラリーマン。高価な毛皮のコートに身を包み、きらびやかなアクセサリーをちらつかせ、爪先から頭まで虚飾で塗り固めたような有閑マダムふうの化粧の濃い女性。デパートの紙バッグを幾つも重そうに両手に下げ、それでもなお小さな子供に何かねだられ、困ったような顔で帰宅を急いでいる家族づれ。コンパの始まりを待ちながら、好みの異性と隣合わせになることを望み、それらしい視線を相手と交わしながら店の前でたむろしている大学生たち。そのどれもが年の暮れに似つかわしい著しく自制心に欠けた顔をしていた。
正己は本牧の倉庫街を手慣れたハンドルさばきで通り過ぎると、根岸方面へと車を向けた。ほどなくして、正己は山手に立つ白い洋館の前でBMWを右折させると、そのレストラン専用の駐車場へBMWを滑らせた。和恵の好んでいた店だった。
全席が予約制になっているその店は、窓側の席を一つだけ残してすべて客で埋まっていた。黒々とした海面に揺れる湾岸の光がほんのりと映った窓ガラスのその奥には、白とコバルトの店内の彩色に染まった若い男女のときめきに酔った姿があった。
店内は静かな煙のような音楽がほのめき、典雅で清楚な雰囲気が漂い、客たちの柔らかな語らいは店内の洗練された装飾品とほどよく溶け合っていた。
和也は正己とあらかじめ予約しておいた窓側の空いている席に腰をおろし、ライトに照らされた壁の絵画や座り心地のよい椅子の感触を懐かしんだ。窓辺から港の風景が一望出来た。
正己は椅子に座ると、窓ガラス越しに港の夜景をぼんやりと眺めた。波間に浮かぶ大型船や、すっかり闇に浸かった岸辺のコンクリートや、湾岸の明かりを受けて黒光りしている波のゆらぎや、いくらか前髪に白いものが混じった窓ガラスに映った自分の顔を正己はしばらく見ていた。そして急にふいっとそれから顔を背けた。窓ガラスには、夜の港の中で食事をしている小さな男の子を連れた家族が映っていた。それを横目で見ている正己の顔は、12月の冷えきった夜の外気に包まれ、白く潤んでいた。
窓の外は昼間虚空に潜んでいた星たちが、夜の深まりとともにその姿をあらわにし、いっせいに黒い波間にけがれない輝きを放っていた。なめらかな海面をなぞるように、寒々とした大気はその隙間に忍び込み、穏やかな揺らめきに時おり亀裂を与えているかのようだった。
和恵が元気だった頃、3人でこの横浜の山手にあるレストランで食事をするのはほとんど毎年の恒例になっていた。正己と和恵の結婚記念日には決まってここへ赴いた。
「ここから見る景色、母さん好きだった…」
「うん、好きだったね」
「もう、2年か…」
「うん…」
「和也、母さんが生前言ってたことを覚えてるか?」
正己は和也の顔を覗き込むようにして言った。
「父さん、実現させようと思う…」
どこか遠慮がちだが、その声には強い意志が感じられる。話の内容は和也にも大体見当がついていた。
「母さんの夢だったから。かなえてやりたいと思う」
「う、うん」
気のない返事を和也は返した。一度言い出すと後へ引かない父親だけに、必ずそれを実行に移すに違いない。母親の夢を実現させること自体、異存はなかったが、そのために生じるかもしれない身の周りの変化のことが和也には気がかりだった。
運ばれてきたディナーのあかざ海老やピッツア・ソースののった牛フィレ肉のステーキに和也は視線を移し、意識的に正己の話を遠ざけようとした。そんな和也の気乗りしない態度を正己は見てとると、口に出した話をいったん胸の内にしまい込み、目の前に並べられたディナーに関心を払った。
テーブルの上のイタリア料理は物心ついた時から口にしているものだけに、正直なところ和也には少々食傷気味の感があった。正己は丁寧に一つひとつ料理を口に運び、独特の味つけを舌で味わい、満足げであったが、和也の口の中ではピッツア・ソースのケイパーの酸味と苦みが複雑に入り混じっていた。
「母さんと父さんが出会った思い出の場所にレストランを建てるってことでしょ」中断していた話を和也から切り出した。
「2人とも学生で、父さん、ひと目で母さんにひかれて」食事の手を休め、正己は当時を懐かしむように頬を緩めた。
正己は大学の夏休みに友人の帰省先に立ち寄った。日本海に面したその漁村に、観光資源といえるほどのものはなかったが、岩肌が鋭く削り取られたリアス式の海岸は国定公園に指定され、夏の間、京阪神からの観光客で小さな賑わいを見せていた。確かに、海岸線に沿った遊歩道から見下ろす紺碧の日本海は悠揚として、見る者にこのうえもない開放感を与えた。将来の目標を見い出せず、無為の日々を送っていた正己の憂さを吹き飛ばすには十分過ぎるほどの景観だった。
正己と友人は、海岸沿いの洋風のレストランでお茶を飲んでいる女子大生のグループに声をかけた。その中に和恵がいた。友人は彼女たちを遊覧船での島巡りに誘い、観光案内を買って出た。正己はどこか父性本能をかきたてるようなしとやかさを秘めた和恵にすっかり心を奪われ、東京での再会を約束した。
「母さん、学生の頃から将来小さなレストランを持ちたいという夢を持ってて」正己は、フォークを置いて、視線を窓の外に移した。
「授業の合間をぬっては、横浜のイタリアレストランでバイトしてた。そんな一途なところも好きで、母さんのいるレストランに、勉強もそっちのけで毎日のように通ったものさ」
「そこで、イタリア料理を覚えたの?」
「その頃は、母さんのほうに一生懸命だったから、料理より、イタリア人のように母さんにアプローチしたものさ」次第に正己の口調が滑らかになった。
「どんなふうに」
「う~ん。こんなふうかな。夕暮れの夏の渚で肩を寄せ合って……狐色に焼けた枯れ葉の踊る秋の公園のベンチで木枯らしに頬をしのばせ……街中がシャボン玉のように夜空に浮かんだクリスマスイブの港町で体を温め合った……。ちょっとキザだったかな」
「完璧にイタリア人してるね。フランス人も入ってるかも」和也は正己の言い回しがどこか可笑しかった。
が、2人の結婚には多くの障害が立ちはだかったことを和也は和恵から聞いて知っていた。
2人とも卒業と同時に結婚を望んだ。世の中のすべての人々が自分たちに好意的で、当然それを祝福してくれるものと思っていた。
しかし、周囲はそんな2人の思惑を一蹴した。結婚はまだ早いというのが双方の親たちの言い分だった。大学を出たばかりで、まだその時期ではないという意固地なまでの親たちの見解を押しつけられ、2人は結婚をはばまれた。
親たちの言う事も表向きはもっともらしく聞こえた。しかし、その裏に身分の不釣り合いといった若い2人にはどうにも拭い取ることの出来ない、かび臭い通念が立ちはだかっているのを感じていた。
正己は東京で生まれ、中小企業の中間管理職といった一介のサラリーマンの父を持つ平凡な家庭で育ったが、和恵は地方の名門といわれる良家に生まれ、その土地の風習やらしきたりといったものに首までつかったような家柄で育った。婚姻相手は本人の意志よりむしろその家に代々継がれてきた格式がそれを選り分けるといった観念が根強く残っていた。
「父さんが本格的にイタリア料理の勉強を始めたのは、母さんと結婚して、共通の目的を持つようになってからさ。大学を卒業して、駆け落ち同然で、アパートを借りて、部屋代の支払いにも事欠いたけど、共通の夢があったからなんとかやっていけた。母さんの夢に引っ張られて、父さんも料理の道に進んで…だから、ここまでやってこれたのも母さんのお陰なんだ」正己は当時を振り返った。
正己はさまざまなレストランを転々とし、8年ほどイタリア料理の修行を積んだ。32歳になったその年に、正己はそれまで蓄えた資金を元手に念願のイタリア料理店を開いた。が、開店して数ケ月は客足も跡絶えがちで、赤字続きの帳簿を見ながら2人で悲嘆に暮れる日々だった。しかしそれに屈することなく、2人は不眠不休で店作りに取り組んだ。
そうして無我夢中で1年が経ち、疾風のように2年が過ぎていった。
夜を日に継ぐ2人の懸命な努力が実を結び、運を呼び寄せたのかもしれない。いつしかクチコミで店の名が知られるようになり、著名人が好むイタリア料理の名店としてマスコミにも度々取り上げられるようになった。
マスメディアの宣伝効果というものは絶大なものがあった。急転して、店は賑わいを見せ始め、店の外にまで客が列を成す状態になっていった。
その頃からだった。辛酸をなめた修行時代に培われた野心が正己の中で目覚め、実業家としての才覚が頭をもたげ始めたのは。
その後、正己は飽くなき飛躍の夢にとりつかれ、追い風に乗ったような勢いで意気揚々として精力的に事業の拡大に乗り出した。他店から優秀なスタッフを引き抜き、およそ5年ほどの間に軽食、ピザの店も含め8店舗ほどの店を統括するまでに至った。なにもかも全て順調に正己の構想通り事は成就し、得意の絶頂にあった。
そしてさらに、正己は発展を夢見て、10年以内に関東一円にチェーン店を張り巡らす計画を立て、その布石を固め、一気に事業の拡大を図ろうとした。
そんな矢先のことであった。
それまで正己と労苦を共にしてきた和恵が突然癌で他界したのは……。
「東京を離れるの?……」
しぼり出すようなしめっぽい声で和也は訊いた。
「2年ほどになるかな……」
固い決意を秘めたような正己の口調だった。
「僕、どうするの……」
それが和也にとって最も重大な問題だった。
「お前も一緒に連れて行きたい」
フォークをテーブルの上に置いて、正己は真剣な眼差しを和也に向けた。
自宅へ向かう間、正己は無言のまま夜の果てまで延びているような国道にBMWを滑らせていた。擦れ違う車の規則的な往来がしばし和也をまどろみに誘った。
通り過ぎる対向車をぼんやり数えながら、暗がりから突然現れては消えていくその鋼鉄の塊の中にはいろんな喜びや悲しみがあるに違いない…闇の中を駆け抜ける車を横目で追いながら、和也はつかの間とりとめのない幻想に浸った。
擦れ違う車が何台目かわからなくなった頃であった。いきなり正面から直進してきた大型トラックが、目も眩むようなライトの瞬きを残して通り過ぎて行った。
その一瞬の閃光が白く光る玉のような残像となって和也の網膜に焼き付いた。トモナガが飛び降り自殺をした日に見たあの空の異様な輝き。
その時---。
それまで黙っていた正己がそんな和也の想いに呼応するかのようにトモナガのことを訊いた。何が自殺の原因だったのか、と訊いた。が、半分まどろみに浸っていた和也は、「わからない」とだけ答えた。<あの日は特別よく晴れていたから>とまるで自分を納得させるかのような答えを自身に返した。
きっと空がまぶしすぎたんだよ…トモナガには…それであの青い空に向かって思いっきり翔んでみたかったんだよ…きっとそうだ…和也は声にならない声で何度も自答した。
そのことはもう誰にも触れてもらいたくない。耳をふさぐような思いで和也は正己の声を振り切ろうとした。
フロントガラスにぽつんと水滴がはね、ついで周りから密かに世界を煮沸しているような音が聞こえてきた。
いつしか車は、白い噴煙のような霧に包まれ、針の先のように細やかな雨を斜めに受けていた。まるで哀しみが夜のふちを縫っているような風景が窓の向こう側に広がっていた。
正己が毛並みを揃えたようにフロントガラスに溜まった水滴をワイパーで拭い取ると、夜の天幕に潤んだ雨が蛇紋のように和也の目に広がった。
和恵の夢というのは、正己との思い出の地に白亜のレストランを造ることであった。
控え目な和恵は、正己が全ての夢を達成した後でいいと言った。が、その想いも虚しく和恵は他界してしまった。最愛の伴侶を失って2年間というもの正己はまるで人が変わったように事業への意欲を失ってしまった。
関東一円にチェーン店を張り巡らすという計画も頓挫したままで、どうにも身動きの取れない運命の迷路にはまってしまったかのようだった。泥酔して帰宅することも度々で、立ち直るきっかけを手探りで模索しているような正己の姿が、和也の目に時に痛ましくも映った。
さまざまな思いが和也の胸の内を交錯した。父親と一緒にそこへ行けば、東京での高校進学は無理かもしれない……正己の考えていることが全く理解出来なかった。
現在の8店舗の店の経営状態もけっして思わしいものではない。そんな時にいくら母親の夢を実現させるためとはいえ、2年も東京を離れ、田舎に居を移すなどというのはあまりに無謀すぎるような気がした。
なにもこんな時期にというのが和也の正直な思いであった。ひょっとして愛するものに先立たれたショックで正常な思考もできなくなったのだろうかと和也は横目で正己を一瞥した。
41歳になったばかりの正己は、そんな和也の心の内をおもんばかるような素振りさえ見せないで、フロントガラスの先に延びた白い霧のたちこめる国道に愛車を走らせていた。
薄氷を踏むような想いで、和也はじっと正己のハンドルさばきを見つめた。
遠まきに音をたてていた雨足がしだいに耳元まで駆け寄ってくるにつれ、和也の中でいっそうやる瀬なさがつのった。手探りで前へ進んでいかなければならないようなもどかしさが車が前へ進むにつれ、行きつ戻りつしてた。それにしても見通しのきかない暗い路が不安とともにどこまでも延びているような気がした。
降りしきる雨の国道を、街路灯が等間隔に運命の淵を照らすかのように灯っていた。暗然としたこの路の先々にいつまでもそれが灯り続けていることを和也は心から願った。
No.3 海際まで迫り出した山の背に