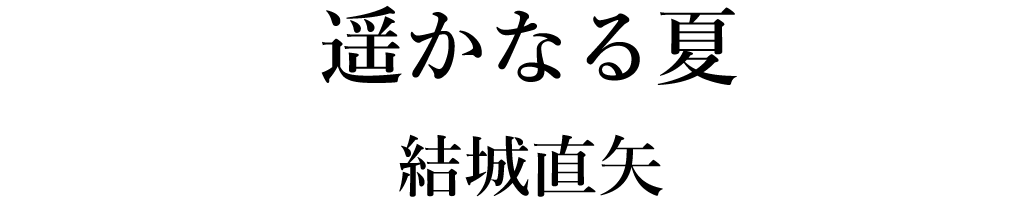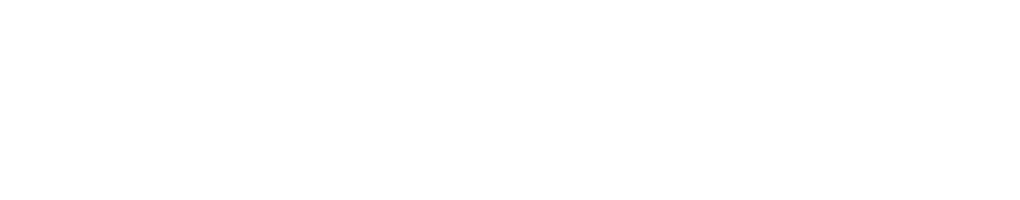No.3 海際まで迫り出した山の背に
海際まで迫り出した山の背に貼り付くようにして、漁村の家々が窮屈に肩を寄せ合っている。どの家も日本海から吹き上げてくる潮風にさらされ、景色の真ん中で灰色にくすみ、たたずんでいる。
バスは大通りで遊ぶ小さな子供らを狭い路地へ追いやると、その懐に分け入って行った。
重々しい澱んだ海が見えた。
港では油をたっぷり含んだ濃緑の海が、居並ぶ漁船を静かにくゆらせていた。漁船の上で、横たわった棒に垂れさがった膨らんだ集魚灯が昼前の陽光を白い刺立った光に変え、目を射抜いた。
海沿いの路上では数メートルにわたって、イカやアジが天日にさらされ、焦げ茶色にひからびた腹をみせている。家々のいたるところに潮風の痕跡が赤さびとなり、いつか一度にボロボロと剥がれ落ちていきそうな危うさがあたりに漂っている。
和也は喉元を締め付けられるような思いでバスの窓から漁村の風景を眺めた。まだ冬の気配の濃い日本海に面した漁港は、季節の衣替えを心待ちにしながら、漁に湧く、めくるめく日々の到来を待ち望んでいるかのようだ。海の生活に明け暮れる港の漁師たちの掛け声もどことなく精彩を欠き、沈滞ぎみだ。
その日、和也は磯の匂いを鼻先に感じながら海岸沿いをひと歩きし、土産物屋で小さな砂時計と絵ハガキを買い、バスにゆられ、借家に帰りついた。久しぶりに太陽の下を歩き回ったせいか体の隅々に脱力感が取り付いたようで、部屋に入るとすぐ、体をベッドに投げ出した。体中の血液がまるで湯気のように毛穴から立ち昇っていくような感じがして、間もなく足の先から眠りにおちていった。
目を覚ましたのは、太陽が窓辺に寄りかかり、隣家の屋根の影が和也の顔の上に長く落ちた頃だった。
体の底にはまだ疲労感が残っていたが、気分は悪くなかった。ベッドから身を起こすと台所へ行き、冷蔵庫から冷えたジンジャエールを1本取り出し、一気に飲み干した。喉の入り口ではじける炭酸の刺激が、微熱で緩んだ身体をきりりと引き締めた。
しばらく気の抜けたようにぼんやりと台所に座っていると、夕食のことが気になってきた。引っ越して、10日ほど経っていたが、父親と台所で料理を作って食べることはなかった。面倒くさいのか、それとも他のレストランの調理の妙を求めてか、正己は市内見物を兼ね、毎日のように和也を外に連れ出しては食指の動く店に立ち寄った。それ以外はインスタント物か時には出前のようなもので安直に済ませていた。
冷蔵庫の中身をあらためて見て、男所帯のわびしさをつくづく痛感した。入っているものといえば、数日前に近くのスーパーで買い込んだレトルト食品の類ばかり。誰が見ても、この家の主人がイタリア料理に精通したプロとは思わないだろうと和也は肩をすくめた。
台所をぐるりと見渡すと、東京から持って来た食器やら調理器具が棚の上にだいぶ出揃っているのがわかった。とびきり旨いパスタでも作って父親を驚かしてみようかと思った。
スーパーの駐車場に自転車を置いて、夕食の買い出しの主婦たちで賑わう商店街を料理の献立のことをあれこれ考えながら和也は散策した。調理人の息子としての真骨頂を発揮して、その腕前に父親がうなっている姿を想像しながら料理に使う具材を選んで歩いた。
主婦たちの買い物籠の脇から顔を出して、生きのいいアサリやタコを物色し、シイタケとニンニクとパセリを1回の調理分だけ求め、パスタを選び、最後に酒屋で白ワインを買い求め、自転車に乗って靴ずれの足を気にしながら家に向かった。
パスタはゆで加減で決まると確信していた。
深鍋の中で煮立った湯に塩を適度に加え、パスタをよくほぐし、ほんの少し最後に芯が残るよう火加減を調節し、目じりにシワをよせて微笑む父親の顔を思い浮かべながら、ゆっくりと掻き回した。
「父さんより上手くなったじゃないか」
目を細め、正己は和也の創作和風スパゲティを美味そうに口元に運んだ。
「けっこう時間かけたからね」
パスタを少しゆで過ぎたのと、タコを厚めに切り過ぎたせいか、味が全体的に水っぽくなったのを和也は舌先で感じていたが、お世辞とわかっていても父親に褒められると悪い気はしなかった。
「今日、海岸を歩いてきたんだ。気持ちよかったよ、とても」
昼間見て来た海辺の風景を、和也は事細かに正己に話した。
「あそこに建てるんだ。真っ白な宮殿のようなやつを」
「母さんも天国でそれを楽しみにしてるかもね」
「ああ、夢だったからな」
「でも、レストランが出来て上手くいくようになったら東京に帰るんでしょ?」
さりげなく和也はそのことにふれてみた。
「まだ、来たばかりじやないか。もう帰りたくなったのか?」
「え、うん、そういうわけじゃないけど」
しどろもどろに答えながら、和也はパスタを呑み込んだ。正己はしばらく黙ったままで自分でビールをついで、感傷的な空気を振り払うかのように勢いよく飲み干した。
正己の顎のあたりの髭が色濃くなっているのに和也は気づいた。数日来、髭を剃らないでいるらしい。端正な正己の顔に影が射し、どことなく世俗離れした面貌で、そんな正己がまるで自分のあずかり知らぬ他人のように映った。
ビールが入るたびに、正己の口のすべりは増し、何かに取り憑かれたようにレストランの構想を饒舌に語った。
正己が将来の展望を闊達に語るほどに和也の心は行き場を見失った。正己の旨そうに飲んでいるビールをなにげなくコップについで一口嘗めてみた。苦いと思った。知らない世界が舌に滲んで、口の中で広がった。父親の考えていることを理解するには、もう少し大人になる必要があるかもしれない。
明後日には地元の中学への転入が控えている。しっかりしなければと和也は自らに言いきかせた。
眠りの浅い夜を過ごしたという思いが頭の片隅で目覚めを拒んでいた。その日、和也は中々ベッドから起き上ることが出来なかった。
同年代の女性歌手のポップな歌声を目覚まし時計代わりにしばらく聞いたが、甘ずっぱいけだるさが体中に染みて、かえってベッドから起きるのが辛くなってしまった。それでもそのまま横になっていると気のせいか胃のあたりが差し込むような気がしてきて、やむなくベッドから跳ね起きた。
風呂場に行き、熱いシャワーを浴び、冷たい水であまり血色の良くないむくんだ顔を引き締め、成長するにつれ父親の顔に似てきた鏡の中の自分の顔を複雑な思いで見つめながら歯を磨いた。
父親はまだ隣の部屋で寝息を立てて眠っていた。時計を見ると、出発の時刻までに1時間もないことがわかった。急いで台所に行き、冷蔵庫から昨夜の夕食の残りを取り出し、電子レンジに入れ、その間にフライパンの上に卵を数個割って、目玉焼きを作った。そして立ったまま口いっぱいにパンを頬ばり、できあがった料理から中途半端にテーブルに座ったまま口に運んだ。和恵が病気になって以来ずっとそんなふうにして和也は同じような朝を過ごした。異郷の地でも、あわただしい朝の習慣は変わりそうもなかった。
和也は1人だけの味気ない朝食を胃の中に押し込むと、簡単に食器を洗い、部屋へ戻って筆記具や教科書や必要な物がカバンの中に入っているか確認し、洋服ダンスから真新しい学生服を取り出し、学校へ行く準備をした。
洋服ダンスの扉の裏に取り付けられた鏡には、新しい学生服を窮屈そうに身にまとって緊張した顔が映っていた。2,3度大きく深呼吸すると硬い表情がいくらか和らいだような気がした。
どことなく夢見心地の4月の微風を頬に受けながら、薄茶色の木立の影を踏むようにして、和也はバス停まで急いだ。
ほの暗い小道に添って流れる小川の冷涼なせせらぎは、あたりに繁茂した草木の深い緑に適度な湿りを与え、そこから立ち昇る清新な大気は都会育ちの彼の足をしばし止めるほどの清気を放ち、肌に刺すような自然の息吹を感じさせた。東京では気づくことのなかった自然との一体感が確かにそこにはあった。
和也たちが住む借家は、市内から少し外れた静かな山間にあった。透き通った清流のゆらめき、どこからか聞こえてくる小鳥のさえずり、風になびく草木の間に家々は点在し、時を刻む針は悠揚と動いていた。都会の喧騒で疲れた体を癒すには充分な環境といえた。
しばらくここで暮らしてみるのもいいかもしれない。小走りで駆け抜けながら、木立の間から射し込む朝の日差しに少しばかり温かみを感じた。
No.4 新しい中学での第1日目