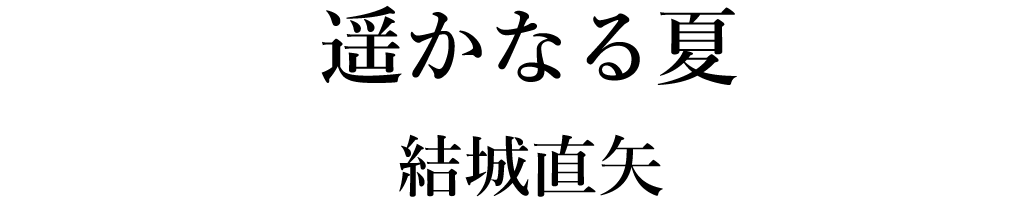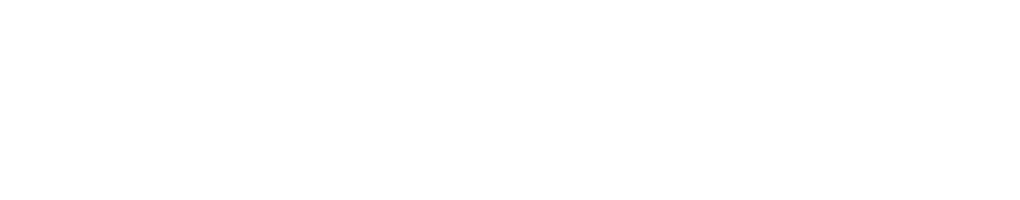No.4 新しい中学での第1日目
新しい中学での第1日目、和也は1日中重苦しい胸のつかえが取れなかった。
痩せて細い目をした担任に呼ばれ、壇上に上がった時、和也の胸は鼓動を高めた。初めて目にするクラスの生徒たちの一人ひとりの顔がやけに堂々として、自分より数段大人びて見えた。
小柄な担任が筋張った手で藤樹和也と白いチョークで黒板に大きく書き、生徒たちの視線がそこに集まっている間、時間が突風に吹き飛ばされるように、一気に過ぎ去っていってくれることをどれほど望んだことか。
自己紹介が終わり、席に戻っても、まだ壇上にいるような気がして落ち着かず、醜態をさらしてしまったという思いがいつまでも胸の奥でくすぶっていた。
緊張の数時間から解放され、家に帰り着いた時、息苦しい拘束からやっと自由になったという安堵感で、体の力が抜け、何をするにもおっくうで仕方がないといった有り様だった。
転校先のY中は、男女共学で、全校生徒数は5百人を若干上回る程度であった。広大な敷地に建てられた校舎の背後には、深い緑をたたえた山々が迫り、目にしみ入るほどの光彩を放っていた。
窓を開けると、樹々の間を飛び交う野鳥のさえずりが教室の中にまで入ってきた。S中と違って、車の吐き出す噴煙も騒音も、灰色の大気の澱みも無縁だった。
慣れない土地での戸惑うばかりの学校生活ではあったが、1週間もすると新しい中学の大方の様子が把握できた。
学校の県下での偏差値レベルは中程度で、東京の塾でかなり上のランクにいた和也には物足りなかった。剣道部と野球部が県大会で常に上位の成績をおさめていて、教師たちは部活に参加することをこぞって奨励していた。
校内の風紀はさほど乱れた様子もなく、校内暴力に教師たちが手をこまねいているふうもなく、なにかにつけて校則を押し付けようとする教師も、いましばらくその出番を待ちかねているかのようだった。
生徒たちの印象はと言うと、皆一様に素朴でけれんみのない田舎の中学生といった感じだった。
----- が、クラス替えになって誰もがまだその本性を真新しい学生服の中に押し隠しているようにも見えた。
「和也、学校はどうだ。みんなとうまくやっていけそうか?」
夕食を終えて片づけをしている時、ふいに正己は和也に訊いた。正己は風呂上がりの湯気立った体を上半身はだけてテレビの前に横たえ、旨そうにビールを飲んでいた。
「うん、まだわからないけど。でも、なんとかなりそうだよ」
たっぷり泡立てた中性洗剤で皿を洗いながら、和也は答えた。
「そうか…、帰りたくなってないかと思って…」
飲んでいるビールのためか、和也の耳の手前までしか届かないような、口ごもった正己の声だった。
「うん、やっぱり生まれた街だもん」
どうかすると両親の夢のために、振り回されているという被害者意識さえ和也の中で湧き起こることがあった。
「いつでも帰れるさ…」
「いつって……いつごろ?…」
「うん、父さんの仕事の目鼻がついたころ…」
「いつごろ?…」
いつになく執拗な和也の追求に、正己は風呂上がりの上気した顔に戸惑いの色を浮かべた。
「とにかく…ここにきたばかりなんだから、ここで暮らしていくことを考えなきゃ……」
正己は和也の質問にまともに答えないで、言葉を濁した。
「それより、和也、父さんのズボンと青いワイシャツ、クリーニング屋に出しておいてくれないか」
正己は話題を切りかえ、和也の矛先をかわそうとした。それ以上そのことにふれても無駄なような気が和也にはした。ここに住んでいるのは、夢を実現するためであって、これが目的ではないんだ。正己の背中を見ながら、自らを納得させるかのように胸の内でつぶやいた。
それから1週間ほど経ち、授業が終了して教科書をカバンに詰め、帰り支度をしている時、和也は同じクラスの米多という生徒から声を掛けられた。米多は口八丁手八丁といった調子者で新しいクラス替えになって、まだ気心のわからない生徒たちの間に立ち、巧みに仲介役を買って出ていた。
「あのう、すまんけど、ちょっとバス代貸してくれんか」
白いのっペりとした子牛のような顔の上で、黒目が落ち着きなく動き、米多は上目使いに和也の表情をうかがった。
「うん、でも、どうして?」
「バスの定期券落としたんだ」
間髪を入れず、米多は早口で言葉を返した。
「帰りのバス、一緒だけ」
なんとなく意味ありげな米多の表情ではあったが、親しく話せる友人がクラスに一人でも欲しかったので、和也は心良く受けた。
バスの中で、和也は米多の質問責めにあった。少々辟易がちな和也に容赦なく、矢継ぎ早に米多は東京のことを訊いた。米多の一方的な話は、この年頃の少年であれば誰もが抱くありふれた都会への憧れにすぎなかったが、あまりに滔々とまくしたてる米多に和也はいささか閉口してしまった。時折米多の話を聞くふりをしながら和也は窓の外の風景に目を転じた。
バスの周りには、ひなびた緑の平原が眠気をさそうような大気の中に広がっていた。
「新宿とか原宿とか知っとるか。芸能人がいっぱい歩いとるんだって?」
米多はしつこく食い下がり、和也の気を引こうとした。
「え、うん、まあ」
和也は生返事をして、米多の問い掛けを適当に流した。
「誰か知っとるんか?芸能人を」
米多は知っている限りのアイドル歌手の名を口に出し、いらだったように和也を問い詰めた。これも肌合いの違う土地の少年たちと親しくなるために必要なことかもしれない。和也は思い直し、街でたまたま見かけたり、コンサートで目にした歌手のことを詳細に話した。完全に米多のペースに乗せられ、訊かれるままに何でも答えた。芸能人の話題が尽きると、米多の関心は和也自身のことへと移っていった。
「どうして、転校してきたんだ?」
「父さんの仕事の関係で」
「どんな?」
米多は執拗にそれを訊きたがった。和也は最初それを他人に話すことをためらった。が、両親の描いた夢が果たして地元の人間の目に現実性を帯びたものに映るかどうか、反応を見たいという気持ちも強く働いた。和也は、以前の暮らしぶりから、ここに来た経緯まで正己になり代わったような気で詳しく語った。
「ふうん、金持ちなんだなあ」
米多は鼻でそう答えた。意外にその話には興味を示さなかった。そのあっけない米多の態度に和也は拍子抜けしてしまった。
「国語の先生きびしそうだね」
学校のことを少しでも知りたいと思い、そう言って和也は米多の関心をそこに向けさせようとした。
「ああ、あのヒステリーか。あれじゃあ、嫁さんにいけんて、みんないっとる。メガネとったらちいっとは見られる顔になるかもしれんけど、メガネザルって呼んでる、みんな」
そういえば、いつか宿題を忘れた時の怒り様はすごかったと和也は思った。
「でも、ほんとはいい先生かも……」
「ええか、あれが、八つ当たりばっかりしてんだ、あのセンコウは。できる奴だけえこひいきするし」
「前の中学にもいた……同じような先生が……」
「どこでも一緒、一緒、センコウは。全国共通の図書券だ」
米多は少し凄味をきかせた声で意味不明なたとえを口にした。
「でも、わけがあって先生も怒るんだから」
「へん、そんなもんじゃありゃせんど、勉強できん奴にゃ、冷てえぞ、校則、校則ってうるせえし、便所コオロギなんか」
「便所コオロギって?……」
「お前、知らんのか、便所コオロギ、風紀のセンコウだ。顔が似とるだろう。便所のすみっこで鳴いとるコオロギに」
「へえ……」
「美術がスカシッペで、理科が色気ジジイ、体育がタゴサクで、担任の数学は水呑み百姓だ」
米多は得意げな顔をして、教師たちのあだ名を次々あげつらった。S中でも同じように教師にあだ名をつけて、友人と呼びあっていたことを和也は思い出し、可笑しくなった。
それからしばらくして、バスは大きくブレーキの軋む音をさせ、米多の家の近くの停留場に止まった。せわしく動く黒目で米多は確認すると、カバンを小脇に抱え、和也から借りたバス代の礼も言わず、吊り皮につかまって立っている乗客を掻き分け、そそくさとバスを降りて行った。
後方の窓の外に、和也から受けた小さな恩義など意にも介さないといった様子で足早に帰宅を急ぐ米多の猫背がちな後ろ姿が一緒に降りた乗客の中に混じって見えた。視界から外れるまで米多の後ろ姿を追うと、バスのまき散らした排気ガスの噴煙の奥の、そのあたりでひときわ目立つ堂々とした門構えの屋敷の中に米多が入って行くのが見えた。
翌日、米多は教室で和也にあっても借りたバス代のことなど一言も触れず平然としていた。そのことに和也はあまりこだわりたくなかったが、礼儀に欠ける米多の行為に身勝手さを感じ、少しばかり後味の悪い思いをした。
それからさらに数日が過ぎて、クラスの生徒たちの自我を覆っていた殻が徐々に取り払われ、生徒同士の気心が通い始めた頃……和也は休憩時間に誰かにじっと見られているような不穏な気配を感じるようになった。
新しい環境に慣れないせいで、自意識過剰になっているのかもしれない。自らに言い聞かせてみたが、それにしてもそのただならぬ空気は日増しに濃くなっていくような気がして、落ち着かなかった。どんよりと膨れあがった鼠色の雲に空の青みが次第に狭められていくような空模様にもそれは似ていた。
間もなく、それが和也の思い過ごしではなかったことをはっきりと知らされる日がやってきた。
帰り間際。
「ちょっと、藤樹。ちょっと」
教室の後ろの戸口のところで、米多のおさえた低い声が聞こえてきた。和也が気づくと、米多は顎をひねって、ついて来るようにと合図した。どこか投げやりな米多をいぶかしく感じたが、彼に何か恨みを買われる覚えもないと、そのまま米多に付いて行った。時おり米多は目をしばたきながら辺りを見渡し、和也が後から付いて来ているかどうか気にしながら歩いた。
下校時の校舎はクラブ活動に急ぎ足で向かう生徒やら、連れ立って帰宅する生徒たちであふれ、グラウンドは1日のうちで最も活気を見せ、力まかせに張りあげられた声が校庭のいたる所で飛び交っていた。
和也は米多に体育館の裏側の死角になって人目のつきにくい所に連れていかれた。背後にはらくだ色の削り取られた山の斜面がむきだしになって迫り、校舎の影が落ちた砂場には、一見してこの学校の問題児と思われる生徒たちが3人ほど米多の到着を待ちかねていたかのようにたむろしていた。どの生徒も目もとに険悪さをただよわせている。彼らの足元にはタバコの吸い殻が何本か見えた。一体彼らが何を求めているのか、彼らの口から聞くまでもなく、固くいかめしい表情と、冷やかな目のくばり具合で十分察っしがついた。
「遅いじゃねえか。待たせやがって」
ボタンが取れ、胸元が開き、そこから黄色いシャツがのぞいたリーダー格の大柄な少年が和也のもとへにじり寄ってきた。
「お前か、東京から来た転校生ちゅうのは」
少年はわざと口元を歪め、残忍な光を目にたたえ、凶暴な面構えを作って、和也を見下し、すごんだ。
「金持ちだってな。ちょっとだけでいいから金貸してくれんか」
「い、いま、持っていません」
和也は腰が頼りなくふらついて、足が鉛のように重くなるのを感じた。腹の底から絞り出すようなかすれ声で答えた。和也の言葉に嘘はなかった。必要もないのに多額の金銭を持ち歩いているはずもなかった。
「持ってねえわけが、ねえだろ。米多から何もかも聞いてるぜ」
「ほんとに、持ってません」
首元を少年につかまれ、和也のびくついた心臓が喉元まで駆け上がった。
「ふざけんじゃねえぞ。調べろ」
吐きすてるように、リーダー格の少年が仲間に言った。仲間の1人が素早く和也の手からカバンを剥ぎ取ると、もう1人が和也を背後ではがい絞めにして身動きのとれない状態にした。瞬時のことだった。逃げ出す隙さえなかった。彼らの手でカバンが開けられ、中に入っていた筆記具やらノートが無残にも砂の上にばら撒かれた時、和也は悔しさにうち震えた。彼らはカバンだけでは飽きたらず、和也の上着やズボンのポケットまで入念にまさぐり、サイフが入ってないかどうか確かめた。だが彼らの目当てのものはどこにもなかった。
「け、ほんとに持ってねえのか」
そう言ってリーダー格の少年はさんざん捜し回ったあげく、自分たちの望みのものがないとわかると、和也を砂場にうち捨てた。
「誰にも言うんじゃねえぞ。わかってるな」
刺すような荒い声を和也に投げつけると、少年たちは不満げに肩をいからせ、口々に何かつぶやきながら、部活で汗を流す生徒たちののびやかなざわめきの中へ消えていった。恐怖が全身を貫き、和也はしばらく砂場に尻もちをついたまま、立ち上がることができなかった。ぼろぼろの汚れた雑巾のような雲が遠目に見えた。心臓が張り裂け、あふれた血で胸のあたりが熱く火照っていくようだった。
(なんて奴らだ…)
和也はカバンの奥にある小さな内ポケットのファスナーを開けて中を確かめた。そこには日常生活に最低限必要な小銭が定期券などと一緒に窮屈に押し込められていた。彼らの目にそれが触れなかったことに安堵した。それにしてもここへ連れて来た米多のことが腹立たしかった。米多は和也が恐喝されている間に、いつの間にか姿を消していた。
(奴らの手先か、あいつ)
いつかバスの中で自分の素性を全て米多に語ったことを和也は後悔した。何もかもその時から仕組まれていたに違いない。屈辱に唇を噛みしめながら、砂場に落ちた鉛筆やらノートを拾い集め、砂を払った。周りの風景が急に色彩を失い、黒ずんで見えた。
No.5 翌日、学校へ行くのが憂鬱だった