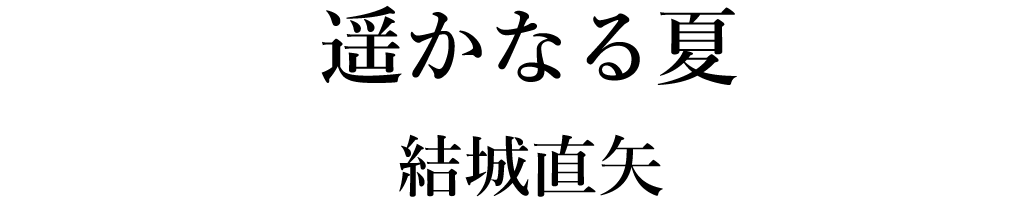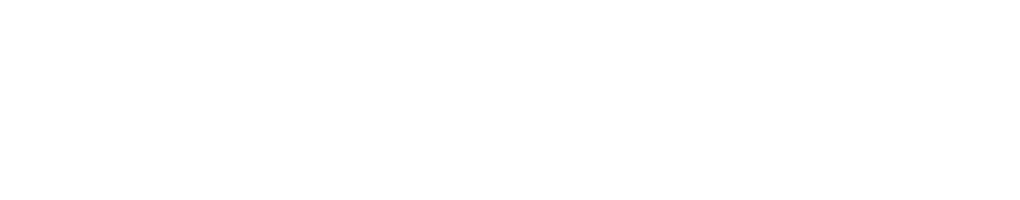No.5 翌日、学校へ行くのが憂鬱だった
翌日、和也は学校へ行くのが憂鬱だった。転校して日も浅いうちに屈辱的な仕打ちを受けるなど想像すらしないことであった。先のことを考えると、学校の内情がよくつかめていないだけに、ともすると胸の内で不安がとめどなく広がり、身がすくみがちになった。そうした恐怖に立ち合わせた米多をどうしても許すことができなかった。
その日、米多は教室で和也と会っても悪びれた様子もなく、昨日のことなど他人事のような態度で平然としていた。そのふてぶてしい素振りに和也はあきれ、授業もまともに耳に入らなかった。
3時間日の授業が終了し、休憩時間になって皆思い思いに過ごしている時---。
和也は勇気をふるって教室の隅で数人のクラスの仲間たちと談笑している米多を捕まえ、問い詰めた。
「なぜ、僕をあそこに連れて行った」
ふいに和也に詰問され、米多はうろたえ、その場から立ち去ろうとした。が、和也は逃げようとする米多の袖をつかみ、引き止めた。周りにいた生徒たちは、何が起こったのか呆然として推移を見守っていた。
「知らねえよ。うるせぇ」
血相を変え、米多は和也の腕を振り切ろうとした。その時、強引に米多に腕を引っ張られ、その拍子に和也はバランスを失い、前につんのめってしまった。
周りの椅子や机はそんな2人のいさかいで雑然と乱れ、騒ぎを聞きつけた生徒たちが2人を取り囲むように群がった。教室はにわかに生じた意外な展開を興味本位で見入る生徒たちで異様な空気につつまれた。
和也は転倒して、床に手をつき、しばらく立ち上がることが出来なかった。周囲には黒い人だかりができ、一様に好奇な目がぐるりと取り巻いている。次に和也がどのような反撃に出るか固唾を呑み、待ちかねているような目だった。そのまなざしに和也はのまれてしまった。見つめる生徒たちの瞳はまるでスポイトだった。戦意がすベて吸い取られてしまった。彼らのまじろぎもしない目に完全に気圧されてしまった。S中でトモナガが飛び降りた時に校舎から見下ろしていた瞳と同じものを、彼らの中に見たような気がした。
あの時、トモナガを見つめていた目…弱者に憐れみをかけながらも、自己の優位性を再認識しているかのような……。そうした目で見られている自分がショックだった。
それからすぐに校舎中に響き渡るような授業の開始を告げるベルが鳴った。次の時限の教師の姿が戸口に見えると、和也を取り巻いていた生徒たちは何事も起こらなかったことに当てがはずれたような顔をして足早に自分の席に戻って行った。数人の女生徒たちが乱れた椅子や机を手際よく直し、それを教師はいぶかしげに見た。
和也はクラスの全員が平然と席についた後、立ち上がって前の方へと歩いて行き、どうしても彼らと相容れないものを感じながら、席についた。
その日の放課後、2人は担任に呼び出された。
「何をお前たちやってた。米多、藤樹」
きつい目をして、担任の香村が2人を問い詰めた。その横で答案の添削をしていた若い国語の女教師が時々手を休めては、うなだれた2人を見やった。
職員室には和也たちの授業を担当している教員も何人かいて、タバコをくゆらせながら離れた所から2人に時おり視線を投げかけていた。
「藤樹は転校してきたばかりで、学校のこともようわからんのだから仲良くせにゃいけんだろうが、え、米多」
香村は細い目をつりあげ、憤りに近いものを含んだ視線を米多につきつけた。
「こいつが急に俺の腕を引っ張るもんだけ、そいで…」
「そいで、どうした」
「そいで、頭きて」
「わけもなく、そうされたんじゃ、ありゃせんだろう、そうされるようなことをしたからだろう」
適当ないいのがれでは容赦しないといった香村の目だった。
「どうした。米多」
米多は冷水をあびせられたような顔でしおれ、口を閉ざしたままでいた。
「藤樹、何があった?」
「米多君に校庭の裏に連れていかれて…そこに3人いて…それで…」
「それで…それで、金を巻き上げられそうになったというわけか」
和也が全て答えるまでもなかった。おそらく他にも同じような被害を受けた生徒がいたにちがいない。
「片倉たちか?…米多、え?…」
すべてを承知しているといった目で香村は訊いた。
米多は黙秘権でも行使するかのように黙りこくっていた。つかの間、ぎくしゃくした重い空気が流れた。その緊張の場に1人の教師が割って入った。米多が便所コオロギと呼んでいた風紀係の教師だった。黄土色のかさついた肌に後退した生え際。少しばかり飛び出した目と、ぬめっと湿った赤く薄い唇が攻撃的なその性格をよくあらわしていた。
富山というその教師は香村の横に立って、まるで品評会に出された牛でも見るような目つきでしばらく米多と和也を交互に見比べた。そして腰を屈め、香村から事の顛末を聞くと、
「米多、お前んちは、お父さん、地主でお金もようけあるだろうが、なんで転校生から金を取らないけん」
と、米多を射抜くような目でにらみつけ、問い詰めた。
「こいつが、東京からきたって、いばっとるけ」
和也にとって予想もしなかった、意外な言葉が米多の口から漏れた。
「ぼくは…そんな…」
和也には納得のいかない米多の返答だった。東京から来たことをひけらかしたような覚えなど、まるでなかった。本心から米多がそう言ったのか、それとも返答に困り、そんなことを口にしたのか和也には判断がつきかねた。香村と富山の表情には困惑がひろがっていた。
「そういうヒガミ根性は男らしくないわよ。米多くん」
そう言って、息づまるような沈黙を破ったのは、香村の隣で彼らの話の一部始終に聞き耳をたてていた国語の女教師だった。津田というその教師は赤いサインペンを指先で回しながら、鼻柱の強そうな顔とガラスの先のような視線を米多に向けた。
「先生らにゃ、わかりゃせん…なんも…」
3人の教師の視線に、身をすくめていた米多がぼそりとこぼした。その言葉ですべての決着がついたかのようだった。もはや感受性の錆びついた教師たちには、思春期の少年たちの何かにつけて口から漏れるその言葉に出会うと、ただじっと遠い記憶を奥歯で噛み殺している以外、手がなくなる。少年たちはまるでそれを免罪符のように効果的に使うツボを心得ていた。教師たちはお互いに視線を交わし合いながら、その場しのぎの暗黙のやりとりを続けるしかなかった。
「片倉には、先生からも注意しとくし、もう二度とバカげたことやるな、ええな、米多」
米多の言い訳に気負いを削がれ、太刀打ちできなくなっている自分に苛立つかのように、富山は、語気を強め、頭ごなしに米多を叱りつけ、そうすることで、ふたたび教師としての威厳を保とうとした。
怒られているのは米多のはずなのに、とがめられている加害者のようなすっきりしない感情が和也の胸のうちに残った。と同時に片倉たちに仕返しに合うかもしれないという懸念もわいた。が、それでも全てを話したことで、担任たちが心の重荷を担ってくれそうな気がして、いくらか胸のつかえがとれた。
しかし、それで終息したわけではなかった。担任の言葉のうえでの庇護など、全くあてにならないとつくづく思い知らされるような陰湿なイジメが和也を待ち受けていた。
米多とのいさかいがあった日を境にしてクラスの雰囲気が一変した。生徒たちの自分を見る目が、以前と明らかに変わったのを和也は敏感に感じた。まるで米多の悪辣な意志が生徒たち一人ひとりに乗り移ったかのようだった。
米多は数人の生徒を巻き込んで徒党を組み、事あるごとに和也を威嚇するような意味ありげな態度をあからさまにとるようになった。和也が何かをしようとすると、いちいち彼らが干渉して、これがこの学校のやり方だと言ってはささいな事にまで口をはさみ、それを押し付けようとした。最初、和也はそれを学校の内情に疎い自分に対する彼らの親切と善意に解釈した。が、日を重ねるにつれ、次第に自分たちの力を顕示し、服従させようとする米多たちの意図的な悪意をそこに感じるようになった。
クラスの大勢はそうした米多たちの悪辣な意志のもとに動いていった。
そうして一つの勢力がクラスの中に形成されると誰も彼らに面と向かって対峙できなくなった。力あるものになびき、自らの保身をはかろうとする姿勢は、子供たちの世界にあっても大人たちのそれとなんら変わりなかった。
いやむしろそれ以上であったかもしれない。教室という一つの隔離社会に押し込められて、そこで出来あがった大勢にそわないということは、即ち孤立を意味する。1日の大半を外部から隔絶されたような教室という閉鎖空間で過ごさなければならない彼らにとって、それは何にもまして堪え難いことであった。
和也はそんな視野の狭い、幼い理性で形成された社会からはじき出された。気の合いそうな生徒に声をかけても、誰もがよそよそしかった。
何故そんなことになったのか、和也はそれまでの日々を振り返ってよく考えてみた。米多が言っていたように東京から来たということで彼らを見下したような言動をとっていなかったか、深く顧みた。しかしどう考えてみても彼らに排斥されなければならないような覚えはなかった。そもそもの事の発端は、全て米多の一方的な悪意から発しているように思われた。
それから数日経ったある日---。教室に入って席につこうとした時、米多たちの仕業と思われる陰湿な小変が和也を直撃した。椅子の下や机の中に、砂やじゃりに混じった犬か猫のような小動物の排泄物が撒かれていた。校庭にあったそれを誰かが持ち込んだに違いない。和也は屈辱に震えながら、雑巾でそれを拭いた。
誰がそんな悪戯をしたのか、クラスの生徒たちに問い正すまでもなかった。和也はそれを米多たちの戦線布告と受けとった。遠くで睨みをきかすだけでは飽きたらず、直に自分たちの力を誇示してきたのだ。
そして、その日から目にあまる米多たちの和也への虐待が始まった。ある時和也が背中で妙な音がすると思って手をあててみると、そこには思わず顔を赤らめるような卑猥な言葉が書かれた紙が貼ってあった。時には学生服のうえにチョークでじかに屈辱的な言葉を書かれたりということもあった。
米多たちの悪質な悪戯は日を追うごとに、さらにエスカレートしていった。体育の時間に靴箱から運動靴を取り出し、それに履きかえようとすると、その中からガラスの破片が出てきて、危うく怪我をしそうになるということもあった。トイレのドアの裏に和也を中傷するような言葉が書かれたりということもたびたびあった。米多たちはありとあらゆる方法で和也をいたぶった。
和也は心底から米多たちの愚劣な行為に憤怒した。弱い立場にある1人の人間を多勢でよってたかって排撃し、裏でほくそえんでいる彼らに怒りがつのった。
----- が、和也がどれほど米多たちに足蹴にされていようともクラスの生徒たちは見て見ぬ振りをしているだけで、誰も支援の手を差し延べようとしなかった。関わり合って、イジメに巻き込まれるのを恐れたのかもしれない。誰もが鬱積して行き場のない10代の少年たちの攻撃的なエネルギーのはけ口となることを避け、和也を自分たちの身代わりに差し出すことで我身の保全を計ろうとしていたのかもしれなかった。
和也はそうしたクラスの雰囲気の中で疎外感にうちひしがれながら長い孤独な1日を過ごさねばならなかった。担任の擁護など全く幻想に等しいものであった。
米多たちは教師の目に触れぬよう巧妙に立ち回り、自分たちの仕業と判らぬよう狡猾にもくろみ、動き回っていた。和也は彼らの尽きることのない心ない仕打ちに半ばノイローゼになっていった。
そしてそんなある日。1限目の授業が終わって、休憩時間に入り、席に付いて教科書に目を通している時・・・ふいに和也は誰かに後頭部を強く叩かれた。すぐさま後ろを振り返って見たが、叩いた張本人の姿はすでにそこにはなく、誰がそれをやったのかまるでわからなかった。たぶん米多たちの嫌がらせに違いないと、半分開き直り、それを無視した。
だが、その悪戯はそれで終わらなかった。休憩時間はもちろん、廊下を歩いている時にまでもそれをされた。振り向いて、誰なのか確かめようとすると、微かにざわめく空気が背後にただよっているだけで、それらしき生徒の姿は見あたらず、周りの生徒たちは素知らぬ顔をし、平静を装い、何事もなかったかのように取り澄ましていた。
その一件で和也の忍耐の限度もその極に達した。数日来、起きぬけに腹部のあたりに感じていた痛みがぶり返して、その日和也は1日中ひきつるような胃の痛みに苦しんだ。
翌日、和也はどうしても学校に行く気になれなかった。学校でのことを正己に話そうかとも思った。が、母親の夢を実現させるため日々懸命に立ち働いている正己の姿を見ていると、余計な心配をかけさせたくないという思いが先に立ち、ためらわれた。耐えられるところまで耐えるつもりではいた。
----- しかし、その我慢の歯止めも限界に達しつつあった。
時間になっても起きてこない和也を心配して、正己が部屋を覗き込んだ。
「和也、学校に遅れるぞ」
和也の頭はひび割れそうに重かった。
「頭が痛いんだ…」
みぞおちのあたりにもまるでナイフで深く傷つけられたような痛みが走っていた。
「…いけないよ…学校…」
途切れ途切れに和也は歪んだ声で答えた。慣れない環境に神経質になっているのかもしれない…正己は和也の額に手をのせ、熱をみたが、さほどでもないと安堵した。
正己が部屋を出た後、和也は頭まですっぽりと布団でおおった。毎日米多たちに苛なまれ、ノイローゼ気味になっていた。クラスの誰もが皆、敵に見えるようなこともあった。総スカンにされ、鼻つまみ者にされているような気がして、自分が惨めだった。まるであの時のトモナガと同じだ…クラスの生徒たちに見下げられ、侮蔑され、未熟で思慮に欠けた彼らの手頃なフラストレーションのはけ口にされている。
布団の中で、東京にいた頃の楽しかった日々に思いを馳せた。懐かしい街並みや、友人たちと戯れた校舎や、帰りによく立ち寄ったファーストフードの店が次々と闇に浮かんだ。休みの日によく行った渋谷の映画館、原宿の表参道での買い物、そのどれもが記憶のひきだしの中に色あせることなく仕舞い込まれていた。
東京での日々を、千切れた紙を寄せ集めるように、まどろみの中で復元させた。遠い昔の幼い頃のことを思い出していると、いらついていた意識もしだいに落ち着き、緩んでいった。
----まどろみの中、トモナガの夢を見た。
S中の屋上が見えた----空は雲一つなく、不気味なほど照り輝いている----陽光をたっぷり吸い取った空の青さは正視するのに堪え難いほどだ----屋上でトモナガが空を指差している----『ぼくが先に風になるから君も後につづけ』-----そんなふうにトモナガが言ったような気がする----トモナガは金網に手をかけ、よじ登ろうとしている-----空がアルミ箔のようにぎらついて、眼を開けていられない---完全に真昼の真っただ中の光だ---トモナガは金網の上に座っている-----トモナガの頭の斜め上で、太陽がオレンジ色の鋭い光を放っている-----『君も早く、登ってこいよ』-----そう言って、トモナガが催促したような気がする-----さらに『君はそんな汚れた地上にいるべき人じゃないんだ』とも言ったような気がする-----生ぬるい澱んだ風が体を舐め回すようにまとわりついている------やけに、喉がひりついて、口がかわく-----『ぼくは、これから死ぬ。死ぬといっても、いったんこの肉体を脱ぎ捨てるだけで、ぼくは永遠に生きている。このできそこないの体はどうもぼくには合わないからね』-----トモナガの口からそんな言葉が漏れたような気がする-----さらに続けて『君もためらうことなんかないんだ。この地上で生きていくためには、それにふさわしい服装が必要なんだよ。だから、もう一度出直して、新しい服に着替え直してくるだけなんだから』と付け加えたような気がする----トモナガは金網の上から手を差しのべている----なめらかな透き通ったような手だ----強い光線に頭がくらくらする----差し出されたトモナガの手の甲に青白い血管が浮いて見える----時間が立ち止まったまま動かない----トモナガの手はさらに透けて、まるでくらげのように骨組みまで見える----その指が招いている----心臓が火であぶられたように火照っている-----頭の中を小さな虫がうるさく飛び交っている-----どこかで、サイレンの音が聞こえる-----大気を引き裂くようなけたたましい音だ-----グラウンドがやけに騒々しい-----黒い学生服が次々に校舎から飛び出し、波のようにうねっている-----黒くいびつな円が、グラウンドに学生服で描かれている-----その中心に赤い血を口からはいた学生が倒れている----屋上からでも、その生徒の表情は十分読み取れる---その少年はトモナガのようだが、どことなく横顔が自分にも似ている-----心臓が何か強い力で締めつけられたようで、息苦しい-----高鳴りが全身にいきわたる----冷たい汗が毛孔から吹き出し、体中をくまなくおおっている-----悪寒が背筋を貫き、胴ぶるいがする-----ふと、空を見上げると、金網の上にトモナガが座っている-----が、その少年はよく見るとトモナガとは違う-----体は埃をかぶってうす汚れ、顔全体が内出血したように紫色に腫れあがっている-----少年は顔中に薄気味悪い笑みを浮かべている-----『出直すなんて嘘さ。連中に思い知らせてやりたかっただけさ。ぼくをイジメた罪がどれほど重いものか。今日のことは連中の心の中に刻み込まれるのさ。そして、その罪の意識は死ぬまで連中の上に重くのしかかる。これがぼくの連中への報復さ』-----トモナガに似た少年がそんなふうにうそぶいたような気がする-----少年は、金網の上から待ちくたびれたように手を差しのべている-----『君も死んで、一人でもぼくらの仲間が多く出れば、彼らもそれだけさらに自分たちのやったことの罪の深さにさいなまれるはずさ』-----少年がそう言って口汚く毒突いたような気がする-----戦慄が白い血となって体を駆け巡る-----体が地面に根をおろしたように動かない-----走って逃げようとするが、体が固く強張って言うことをきかない-----体中のすべての筋肉が肉離れしたようにひきつっている-----体がどうしても自由にならない-----
現実との区別がつかない生々しい夢だった。目覚めてもなお、まだ夢の中で立ち往生しているような気分だった。吹き出した汗で背中のあたりがひんやりとしている。和也は頭を拳で叩きながら、ベッドからゆっくり起き上がり、這うように台所に行き、渇いた喉に冷たい水を注ぎ入れた。しばらく胸の奥がささくれだったままだった。
No.6 あなたに賭けをしている