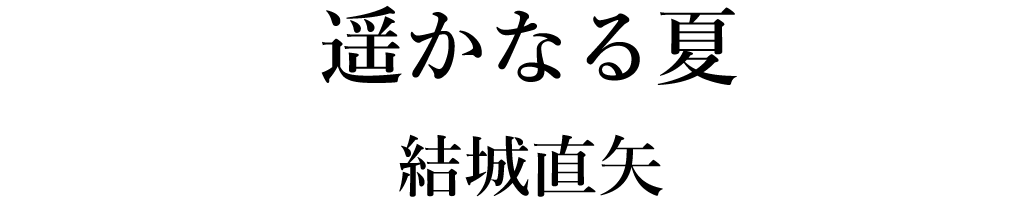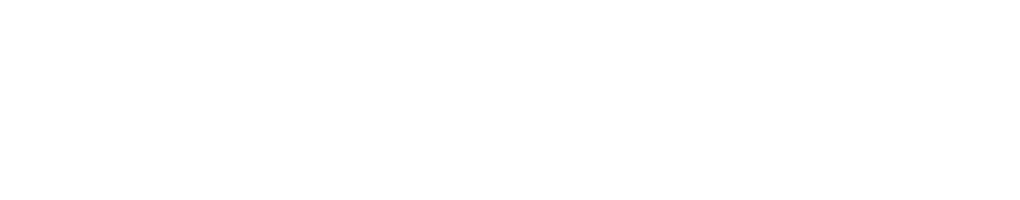No.6 あなたに賭けをしている
「みんなあなたに賭けをしているのよ。藤樹君の頭を叩くでしょ。それでそれを誰がやったかわからないようにうまくやったらお金がもらえるっていうの」
翌日、おぼつかない足どりで登校し、教室に入ると、北川という女生徒が近付いてきて和也に耳うちをした。北川はクラスの副委員長をしていた。
「みんな米多君たちの仕業よ。クラスの男の子たちをたきつけてみんなでおもしろがっているのよ」
憤りを白い頬の上にあらわにして北川は話した。
「ありがとう……たぶんそうじゃないかって思ってた」
すでにそのことは察しがついている。自分のことを心配してくれている人間がクラスに1人でもいることが、和也には嬉しかった。
「ちょっとやりすぎだわ、米多君たちも。藤樹君が黙っているのをいいことに、クラスのみんなも知らんぷりしてるし」
声をひそめ、北川は感情をむきだしにした。利発そうな黒い瞳には正義感が宿っていた。
「ありがとう……だいじょうぶだよ……」
和也は無理に笑顔を作り、北川に応えた。
始業開始のベルが鳴り、戸口に国語の女教師の顔が見えると、北川は和也を元気づけるかのように目くばせして、席についた。離れたところでその様子を米多がうかがっていた。和也は何ごともなかったように席につくと、教科書を開き、国語の女教師の教室の外まで通るような細く高い声に耳を傾けた。
北川の好意に少しばかり心が緩んだ。窓側の席のふだんあまり目立たない女生徒がしめった低い声で教科書を朗読している間、昨日見たトモナガの夢が頭の隅でちらついた。
S中でのトモナガに対する自身の態度を和也は顧みた。
クラスの皆にのけ者にされ、孤独に沈んでいたトモナガを率先してかばった者がいただろうか……。
誰もが遠目で見知らぬ振りをしていた……はたして自分もそんな人間の1人ではなかったか……。
クラスに話相手のいない和也にとって、昼休憩は長く、苦痛以外の何ものでもなかった。
その日、和也は向かい側の校舎のトイレに逃げ込んで昼休憩の時間をつぶした。そこは1年生たちのいる校舎で、同じ学年の生徒たちと顔を合わせることはなかった。
暗い湿ったトイレの中でじっとうずくまるようにして、同級生たちが無邪気に戯れている時間を、アンモニアの臭いに耐えながら過ごした。
ふと自分がみじめになったが、誰にも相手にされず教室で孤立し、息の詰まるような時間を1人悶々としているよりは、ずいぶんと気が楽だった。
鼻を刺す尿の臭いで頭が痛くなりかけた頃、和也はトイレのサッシ窓を開放し、新鮮な空気を呼び込んだ。開けた窓の向こうに、陽が斜めに射したクリーム色の校舎が見えた。校舎の屋上にはS中と同じような緑色の細かい網目のフェンスがぐるりと張り巡らされていた。
最近張り変えられたのか、数メートルもの艶めいた緑の帯が目にしみた。屋上から地上まではゆうに10数メートルはある。トモナガが飛び降りた高さと同じくらいだ。あそこから飛び降りたら、内臓は踏みつぶされたように原形を失い、血管は引き千切れ、血の海と化すに違いない。想像しただけでも吐き気がしそうだった。
トイレの窓から、休み時間に一様にうかれ騒ぐ生徒たちの姿が見えた。ついさっきまでいた教室の窓辺では、男子生徒が何かを取り合い、もつれ合うようにしてふざけている。窓から顔を出し、校庭でキャッチボールを楽しむ生徒に、野次を飛ばしている米多と仲のいい生徒の顔も見える。女生徒たちは教室の隅に3、4人でまとまり、話に興じている。どの生徒の顔にも屈託のない笑みがはじけている。
あの中に自分が降り落ちてきたらみんなどう思うだろう……あまりに突然のことで、何が起きたか把握出来ないで、呆然としたままかもしれない……自分を爪弾きにしてきた者たちは一体どんな反応を示すだろう……その時になって初めて、彼らは愚かなことをしてきたことに気がつくのだろうか……
昼休憩の終わりのベルが鳴っても、和也はトイレの壁にもたれかかったままで、中々そこから足が離れなかった。
次の日、和也はもう学校に行きたくないと思う気持ちをひきずりながら、なんとかいつもと同じ時刻にベッドから這い出し、いつもどおりの簡単な朝食を無理に口に押し込み、重苦しい気持ちで学校へ行く準備をした。そしていつものバスにいつもの時刻に乗り、曇った窓ガラスに頬をすり寄せ、見慣れた、混じりけのない緑ばかりの平坦な田舎の景色を、気の抜けたような目で追った。いつもの変わりばえのしない田畑ばかりのだらだらと広がる風景だったが、何故かその日は、薄い挨の被膜のかかった窓ガラスの外の景色が朝の陽光にあまねく溶け、キラキラ輝いて見えた。
気がつくと、和也はバスを降り、風のそよぐ緑の平原の真ん中に夢遊病者のように立ちつくし、いつもと違う行動をとっていた。虚ろな目で、土埃と排気ガスの入り混じった噴煙を撒き散らしながら、小さく遠のいていくバスを見ていると、いい知れぬ安らぎが胸に広がった。
バスを横目で見ながら、和也は学校とは違う方向に歩き始めた。どこへ行くといったあてがあるわけではなかった。とりあえず学校から遠ざかりたいという思いが和也の足をかってに動かしていた。
途中、白いヘルメットをかぶり、汚れたタオルを首にかけ、ゴム足袋をはいた5、6人の労働者が日に焼けた顔に汗をしたたらせ、挨にまみれながら黙々と、つるはしでアスファルトの歩道に穴を開けている現場を通り過ぎた。手押し車にクワやらカマを乗せて、畑仕事に向かう腰の曲がったのどかな顔をした老婆と擦れ違った。道いっぱいにもつれ合うように自転車に乗り、あどけない笑顔で言葉を投げ合いながら、学校へと急ぐ女子高生の集団とも出会った。
その一つひとつの光景がうらぶれて生気のない和也の瞳にまぶしく映った。
車の行き交う通りを外れ、心地よい日溜まりのできた畑のあぜ道に逃げ込み、肩を落とし、背を屈め、青くさい芳香とうららかな光の中をさだまらない足どりで歩いた。時おり立ち止まっては空を仰ぎ、うっすらとした筋雲を目で追った。
昼前の太陽は少しずつ空の中心に近付き、地上にある全ての物たちに均等に光を投げかけようとしていた。
憂え萎れた体を、あの光で焼きつくしたい、と思った。
思い出すのは郷里のことばかりであった。幼い頃によく遊んだ公園や、賑やかな駅前の商店街や、近所の家並みがふっと湧いては雲のように流れていった。高い所で取り澄ました空を見上げながら、むせかえるように膨れあがっては胸間を埋めつくす郷里への想いを、流れ行く雲に乗せた。
その日、結局和也は学校に行かないまま昼過ぎに家に帰り着いた。父親は外出していて、家は死骸のように静かだった。
次の日も学校に行くと言って家を出たものの、途中でバスを降り、学校には向かわず、後ろめたい気持ちを引きずりながら、1人あてもなくぶらぶらと無為の時を過ごした。どうやら本格的な登校拒否症が和也の中に根を下ろし始めたようだった。
その日は駅前の繁華街まで足を延ばし、ゲームセンターで時間を潰したり、本屋に入って立ち読みしたりしてぶらついた。昼前になると、デパートの前のファーストフード・ショップに入ってコーラとハンバーガーで空腹を満たした。
時々店員たちに中学生が昼前からぶらついているといった奇異な目で見られているような気がして、腰が座らなかった。サイフには貯めていたこづかいが十分入っていたので、どこか人目に付きにくい所で夕方近くまで過ごそうかと、適当な場所を探し歩いた。
駅前の商店街を脇に入ると、あたりに騒々しい音をまき散らすパチンコ屋があって、その隣にポスターやら立て看板で派手に飾り付けられた白塗りの古い映画館があった。上映している学園ものの邦画に、とりわけ興味を引かれたわけではないが、休みの日に渋谷や新宿でよく映画を見たのを思い出し、スクリーンの虚構の世界に一時的にせよ身を沈めていれば、嫌な現実から逃げられるかもしれないと、入場券を買って中へ入った。
館内は昼食時のせいか、ほとんど空席で、客は数えるほどしかいなかった。後ろの隅の席に座り、暗闇に慣れるまでしばらく目を閉じ、スクリーンからこぼれてくる軽快な言葉のやりとりに耳を傾けた。1、2分して目を開けると、中央のまばゆい光にあふれた画面から、同世代の若者たちの乱痴気騒ぎが洪水のようにあふれてきた。華やいだ学園生活がスクリーンいっぱいにはじけていたが、それに浸ることができなかった。それどころか何か無縁の世界を目の前につきつけられ、からかわれているようで、かえって気が滅入ってしまった。
映画を見終えて外に出たのは、5時を少し廻った頃だった。
街並みには、日盛りを過ぎた太陽の弱い光がうつろっていた。歩道に映し出された街の影は、輪郭を淡いものに変え、昼間太陽に照りつけられたアスファルトは生温い空気を地表に溜め、真夏日のけだるい夕暮れ時のように人々の足から軽やかさを奪っていた。
駅前は疲れきった顔で顎を前に出し、肩を落として歩くサラリーマンや、単調なオフィスワークから開放され、表情に華やかさを取り戻した若いOLや、紺色のバッグを肩にかけ、遠慮のない会話をぶつけ合いながらバス停に向かう男子生徒の集団や、デパートの横の喫茶店からバスの発車時刻を気にして、飛び出してくる人々やらであわただしく賑わっていた。
雑踏に紛れ、もつれそうな足どりで、孤独感をかみしめながらあてもなく歩いていると、周りを行き交う人々の足がやけに早くて、見知らぬ世界に1人置き去りにされてしまったような感覚におそわれた。腰から下はまるで意志のかよわぬ義足のようだった。彼らと歩調を合わせようとするけれど、最初から自分とはまるで異質な人間のように見えてきて、どうしてもそれが無理なように思えた。
始終、水をたっぷり含んだスポンジのような大地を歩っているようなもどかしさが体を駆け巡った。
日の陰った異郷の街は、ぬぐいきれない絶望感とともに暗然とした闇の彼方へとかき消えていきそうだった。
気がつくと、和也は駅前のデパートの前にぼんやりと立っていた。
夕暮れに上段から暗褐色に染まったそれは、まるであてもなく徘かいした末に立ちふさがった大きな壁のようにも見えた。トモナガのようにいっそあそこから飛び降りたら楽になるかもしれない……。
黒煙をかぶった煉瓦のような建物の屋上を、虚ろに和也は見上げた。
No.7 辛かった、若き日に交わした約束