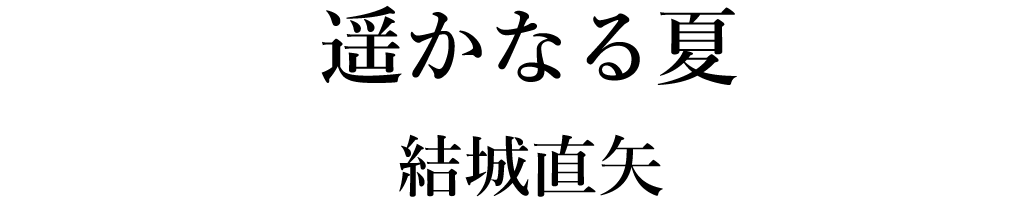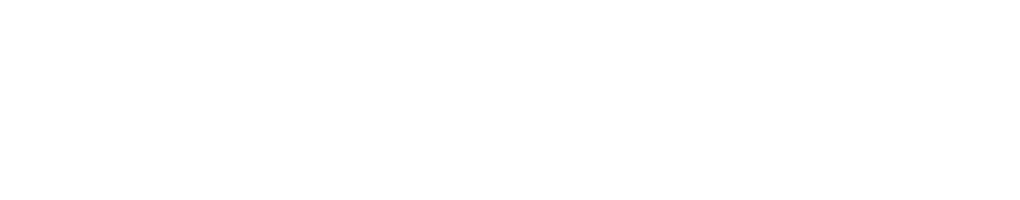No.9 窓の隙間から差し込む朝の光
窓の隙間から差し込む朝の光が、まるで蝶のようにゆらゆら飛びかい、蜘の巣のように顔の上で留まっている。何もかもカラカラに干上がった真夏の朝のようだ。
口の中が血生臭い。起きてすぐ、和也はそこが自分の部屋ではないことに気がついた。4畳ほどの広さに、小さな折りたたみのテーブルと14インチほどのテレビとそう大きくない和箪笥が、壁の隅に押しつけられるように置いてある。他にこれといったものはなく、生活の匂いがまるで感じられない。
警備員が寝泊まりする部屋のようにも見える。壁にアイロンのかけられた紺色の制服が何着か掛かっている。その横に学生服がハンガーに掛けられている。ところどころ土埃が染みつき、ボタンが2つよれて取れそうになっている。
「気いついたか。まだ横になっとってもええのに」
和也が起きたのを見て、60前後の男がガラス戸の隙間から陽に焼けた顔を覗かせ、潮風で錯びついたような声をかけた。
「どないした。喧嘩でもしよったか?」
開けたガラス戸の間に人のよさそうな顔をはさみ、眉を8の字にして、いぶかしげに男が訊いた。
「ここは、どこですか?……」
「もう、だいじょうぶなようやな。昨日のことは何も覚えとらんじゃろ。気い失っとったけ。見回りから帰ってきたらドアの所にあんたがもたれとって。服は挨だらけで、顔は腫れとるし」
「どうして、ぼくはここにいるんですか?……」
「なんも覚えとらんのか……」
ため息混じりに男がつぶやいた。
「いえ、ええ……」
どうやってここまで来たのか男の言うように和也には記憶がなかった。
「鞄に生徒手帳が入っとったけ、家のほうに連絡して、夜お父さんに来てもらったけどそれもわからんだろ。よう寝とんさったけ」
とりあえず父親が自分の居場所を知っていると男から聞いて、和也はほっとした。
「コーヒーでもいれよか。お父さんもう来ると思うけ、もうちょっと横になっとるとええ」
男の親切な言葉に、和也は初めて異郷の地で人の情にふれたような気がした。男は宿直の警備員らしい。着ている白いワイシャツと紺色のズボンが勤務明けでくたびれている。
ヤカンの湯が湧き立つと、男は慣れた手つきで硝子ケースの中からインスタントコーヒーを取り出し、スプーンで適量入れ、コーヒーを作り始めた。それが出来上がると、
「わしも若い頃は酒飲んで漁師仲間とよう喧嘩したけどなあ」
と言って、湯飲み茶碗に入った湯気立ったコーヒーを油のにじんだごつごつした手で差し出した。
和也は目でうなずいて男に礼を言い、口をすぼめて息を吹きかけ、冷ましながらそれを飲んだ。歯は折れてはいなかったが、口の中が切れていてコーヒーがそこを通るたびにヒリヒリしみた。
男に感謝しながらコーヒーを半分ほど飲むと、和也は枕元にそれを置き、ふたたび布団の上に動かすたびに悲鳴をあげる体を横たえた。そして雨漏りのようなシミのついた天井を眺めながら昨夜のことを思い返した。
いったい誰が気を失った自分をここまで運んでくれたのだろう?……。
腫れて疼く腰に手をあてながら、途切れた記憶をさかのぼった。米多たちにさんざん傷めつけられ……気を失いかけたところで……大きな黒い影が現れ……影は米多たちと格闘して、連中を蹴散らし……。
と、そこまでは不確かながらも覚えていた。たぶんその後、影が自分をおぶさってここまで来たにちがいない。
が、はたして-----。その影がどのような人物であったか和也にはまるで記憶がなかった。
暗がりの中で見た影の輪郭を懸命になぞったが、はっきりとした心象が浮かばなかった。わかっているのはおそろしく喧嘩の強い体格のいい偉丈夫ということだけだった。
それからしばらくして、警備室の前にBMWが止まり、そこから寝不足らしくまぶたを腫らした正己が顔を出した。ほんのりと赤みのさした和也の顔を見ると、正己は大きく息をついた。
「お父さん、ゆうべ病院に連れて行くいんさったけどそんな怪我じぁありゃせんから、このまま一晩寝かしときゃ今の若いもんだけ、じきようなるって、あんたをここに残して帰ってもらったけど、やっぱり気が気じゃあなかったみたいだで」
野放図に笑い、男は壁に掛かった制服を手に取り、和也たちの前で着替え始めた。正己は何度もその頭皮の薄くなりかけた年配の警備員に頭を下げ、礼を言った。
「ぼくは自分で歩いてここに来たんじゃないんです。誰かがぼくをここに連れてきてくれたんです。わかりませんか?……誰か……」
和也は着替え中の男に懇願するように訊いた。
「さあ、わからんなあ。とにかくきのうの晩、見回りから帰ってきたらあんたがドアの前にもたれて座っとってな。服もずいぶん挨かぶって汚れとったし、てっきり喧嘩でもして、ここまで来て往生したもんばっかり思うとった」
「気を失ったぼくをここまで運んでくれた人がいるんです」
真剣な目で和也が訴えると、男は、
「ほうぇ、そんじゃあ、だれかこの近所のもんかなあ」
と言って、狐にでもつままれたような顔をして目を虚ろに動かした。
和也はたどたどしい記憶がはがゆかった。何か手立てがないものか上目づかいに男を見ながら、考えあぐねた。
男が制服に着替え終わると、正己は車から菓子折りのようなものを取り出し、何度も頭を下げ、それを男に手渡した。男は遠慮しながらも浅黒い顔をゆるませ、正己と同じように丁寧に頭を下げ、酒の肴にさせてもらうと言ってそれを心良く受け取った。
警備室の外に出ると、朝の陽光が腫れぼったい瞼を貫き、和也は一瞬立ちくらみを感じた。警備室と道路を隔てた向かい側の海岸線では、整然と細竿に干されたイカが朝の細い陽ざしを受け、水っぽい光沢を放っていた。
朝の漁港はすっかり目ざめていた。水揚げされたばかりの新鮮な魚貝類を詰め込んだ重そうな行商の寵を背負った老婦や、魚工場をあわただしく出入りする灰色の地味な制服姿の作業員たちや、京阪神へ向かう大型トラックやらで活気づいていた。
港では濃緑の揺れる海面に漁船が何隻も停泊し、その上では地元の漁師たちが集魚灯のランプを取り換えたり、網を運んだりして忙しく立ち動いていた。和也と同年代の少年たちの陽に焼けた姿もそのなかにあった。作業の手を休め、澄み渡った晴れやかな空を仰ぎ見ながら、誰もが口ぐちに今日も暑くなりそうだとぼやいている。この近所の人間かもしれないという警備の男の言葉がふっと頭をよぎり、和也はしばらく彼らの一人ひとりを注意して見た。
ひょっとしたらあの中にいるかも……影に助け起こされ、そのたくましい両肩に背負われた時、ほのかに潮の香が漂ってきたのを鼻先が覚えていた。
「帰りが遅いんで心配してたんだ。電話を受けた時にはびっくりした。お前が気を失って倒れてるっていうんで」
そう言って、正己はドアの前で立ちすくんでいる和也に車に乗るよう促した。体を動かすたびに関節のきしむ音が聞こえてきそうだった。五体を走る痛みに耐えながら、不器用に腰を屈め、和也は車に乗り込んだ。
「動かさないほうがいいというんで、ここに泊めてもらうことにしたんだが、どうなることかと思った」
「もう、大丈夫だよ」
心配顔の正己に、和也は精いっぱいの虚勢を張った。
正己は後ろを振り向くと、サイドウインドウを開け、もう一度魚工場の警備の男に礼を言い、ゆっくりと車を走らせた。
ほとんど対向車と出合わない朝方の湿った路を、BMWは静かに突き進んだ。和也の身体を気にかけながらも、さきほどの警備員の気さくな声の響きを正己は頭の中で反芻していた。若い頃、この地で聞いた、どこか懐かしい響き。
「もう、だいじょうぶなようやの。ご飯を粥にしたけど、たくさんあるから遠慮なくおかわりしんさい」
70近い宿の主人が、風邪で病み上がりの和恵のために気をきかしてくれた。
「ご親切にありがとうございます。本当に助かります」主人の心遣いが正己の身にしみた。
結婚を反対され、憂さ晴らしから、2人は再び出会いの地を訪れた。不安を抱えた旅だった。和恵は着いたばかりの日に疲労からか風邪をこじらせてしまった。海岸沿いの遊歩道を歩きながら、寒気がすると身体をしきりにさすり、くしゃみをした。
「どうしよう。かなり熱があるみたいだ。もうすこし滞在しようか」正己は言い、和恵の身体を気使った。2泊3日の予定だったが、熱が引かず憔悴しきった和恵を無理に東京に戻すことがはばかられた。和恵の看病で、正己も体調を崩してしまった。風邪の兆候なのか、身体が熱っぽく、足元がふらついた。かといって、長期滞在できるほどの金銭的余裕もない。
「僕らお金の余裕がなくて……なんでもお手伝いしますから、しばらくここに居させてください」
民宿の老夫婦に自分たちの身の上を話すと、老夫婦は、宿泊代はいらないと、笑顔で快く答えた。その日の夜食は、正己が想像もしないような豪勢なものだった。採れたての新鮮なエビや食べ切れないほどのカニ、マグロやアジの刺身がテーブルいっぱいに並べられた。わたしらも同じだ、若い頃、両方から結婚を反対されて、誰にも祝福されんかった。あんたたちの気持ちがようわかる。そういって、2人の門出を祝った。
2人とも、病み上がりだったということもあったかもしれない。老夫婦の素朴な料理が心に染みわたった。どんな高価な料理にも勝る、美味なものに感じた。結局、そこに2週間ほど滞在した。「ええから、ええから、無理せんでもええから」と主人が制しても、2人は掃除や食事の配膳を手伝い、夜は海岸を散策し、澄み渡った夜空の星を眺め、病んだ体を癒した。
あれから16年……正己の脳裏に、親切だった老夫婦の面影が浮かぶ。
若き不遇の時、元気づけ、励ましてくれたあの老夫婦……生きる活力を与えてくれた料理やもてなし、もし自分たちにもできるなら……東京に戻ると、和恵はレストラン経営の勉強に、正己は料理修行に明け暮れた。
和恵が亡くなって2年ほどの間、正己は何度かこの地に足を運んでいた。すでに老夫婦は他界し、息子夫婦が民宿を土地ごと売り払い、跡地は観光客めあての瀟洒な喫茶店へと変わっていた。が、それでもそこを訪れるたび、なぜか正己には故郷に帰ってきたような安堵感があった。今ではいくらか人に知られるようになった料理の腕をこの地で活かし、人々に喜んでもらいたいと思った。
和也が中学でさまざまなイジメを受けていることは正己も気がついていた。
が、どこか不思議と腹が据わっていた。
ここから何もかも始まった ----- 。
和恵と出会い、そして再出発を誓った地。和也と自分にとっても、ここが再生の地である、という確信めいた思いがあった。
「喧嘩したのか?」
ふと我に返り、正己は訊いた。
「なんでもないよ。ちょっと転んだだけだよ」
「転んだだけでそんな怪我をするのか。気を失ったり」
「大丈夫だって、もう、なんともないから」
そう言いながら、和也は体の向きを変え、背中や腰に感じる痛みを少しでもやわらげようとした。車のミラーで、顔の傷がどの程度か見ると、右頬の口元のあたりが内出血して紫色に腫れあがっていたが、思ったほど見た目はひどくないことがわかった。
「学校、どうする?今日」
正己がつぶやくように訊いた。
「どうするって、行くよ、なんともないから」
言葉に力を込め、和也は答えた。
「そうか、行くか」
正己は歯切れ良くそう言うと、それ以上は何も言わずアクセルを踏んでスピードをあげた。
このままここで逃げたらもうだめになるに違いない。和也は覚悟を決めた。
昨夜の乱闘でいたぶられていた時、霞む意識の中に映った和恵の幻が、立ち直る気概を吹き込んだのかもしれない。闇の中で悲しそうな面持ちでたたずんでいた母の幻影が、強く生きることを懇願しているようにも見えた。
その日、和也は顔中にバンドエイドを貼り、きしむ体を気力でささえながら、午後の授業から出た。教室に入ると案の定、生徒たちの関心の的となった。その痛ましい姿に同情して興味本位に話しかけてくる生徒もいた。米多と何かあったに違いないと根掘り歯掘りしつこく訊こうとする者もいた。だが、転んで怪我をしただけだと彼らの好奇心をかわして逃げた。米多はその日、学校に出てこなかった。
そして次の日、クラスでちょっとした失笑が湧き起こった。米多が1昨日の夜に受けた顔の傷を隠すために、ファンデーションを特に紫色に腫れた部分に入念に塗りたくって来たのだ。目ざといクラスの生徒たちがそれを見過ごすはずがなかった。
おめえ、なんだよその化粧は。粉ふいてるぜ、顔から---。そういう趣味があったってわけか---。いいな、わたしも化粧してこようかしら---。いくら化粧してもごまかしきれない顔の歪み。ケンカの跡であることは誰にも一目瞭然だった。
米多は一転して嘲笑の的となり、男のくせに化粧をしているとか、はてはオカマとかはやしたてられた。
ざまあねえよな、米多も---。いや五分五分だぜ---。そうかな、俺は藤樹のほうが勝ってるって思うぜ。
クラスの生徒たちは2人を見て、ついに本格的に取っ組み合って喧嘩したと口々にささやき、怪我の程度を見比べては、どちらに勝敗があったかなどと面白おかしく取り沙汰した。
米多にとって、耳障りなことこのうえもなかった。詮索好きなクラスの仲間がうとましかった。
が、どうしても顔の厚い粉を落とすことが出来なかった。それを落とせば、和也以上に黒ずんだ傷跡むきだしになる。さんざんやられたと思われかねない。メンツを保つために、どうしても濃い化粧が必要になった。米多は休憩時間になるとトイレの隅でコンパクトを取り出し、汗で色落ちしたところを何度も塗り直し、それがまた物笑いの種となった。
教室で幅をきかすためには、顔の生々しい傷跡を皆の前でさらせない。といって、化粧をすると笑われる。米多はどうすることも出来ないジレンマの中で悶々と過ごさねばならなくなった。米多の醜態を見て、それまで徒党を組んでいた仲間たちも次第に離れていった。
次第に、和也は米多の煽動していた陰湿なイジメを受けることもなくなった。世渡り上手にみえた米多はうらぶれて見る影もなく、誰も彼をまともに取り合わなくなった。
いつか流れが変わる時が来るさ---。正己が海岸で話していたことを和也は実感した。日ごとに、好意的に話しかけてくる生徒も現れ始めた。和也は胸襟を開き、彼らの中に融け込んでいった。
平穏に時が過ぎ、以前のように疎外感を味わうこともなくなっていった。
虐待されていた日々が遠い昔のようだった。余計なことにわずらわされることもなくなり、勉強にも専念できた。
---が、一つだけ気になることがあった。そのことがいつも頭から離れなかった。
あの時、僕を助けてくれた黒い大きな影、一体、誰だろう……頭の隅にいつもそれがゆらめいていた。もしかしたら、あそこで息絶えていたかもしれない。あの時、あの影に出会わなかったら……。
時おり、和也は校内で片倉たちに出くわすこともあったが、何故か彼らは妙によそよそしかった。何かを恐れて故意に自分を避けているのでは、と思えるようなそぶりをした。何かが、自分を守ってくれている・・・まるで影の見えざる手がいつも自分を擁護してくれているかのような突飛な印象さえ、彼らの不自然な挙動から受けた。
日ごとに、影の正体を知りたいという思いが膨らんでいった。授業中もそのことばかりが頭を占め、ぼんやりと空想にふけることが多くなった。
ある日、和也は矢も盾もたまらなくなり、あの日と同じ時刻のバスに乗り合わせ、米多たちから暴行を受けた現場へと出向いた。影の正体を知る何か手掛かりがつかめないかと、付近を丹念に歩き回った。
辺りはうっそうとした松の群生がかさぶたのように大地をおおい、暗く湿っぽい松林を抜けると、地元の人間しか通らないような曲がりくねった狭い道がその先の海岸まで続いていた。岩に砕ける波の音を聞きながら、海沿いの坂道を10分ほど歩いていくと、漁村の集落に出くわした。漁村のちょうど中央付近にはあの日保護された魚の加工工場の警備室があった。----- が、わかったのはそこまでで、肝心の影の正体を知る手掛かりは何一つとして得られなかった。
どうすれば影を捜し出すことができるんだろう……帰りのバスの中で、和也は思いにふけった。あの時その人物に出会っていなければ……あそこで野垂死にしていたかもしれない……暗い松林の坂道を影に背負われている気を失った自分の姿を想像した。どうしても見つけ出し、立ち直るきっかけを与えてくれた礼を言いたいと思った。
数日、影のことを考えながらもすべてが闇にのみ込まれ、霧散していくような日々が続いた。影について何の手掛かりを得られないままいたずらに時を重ねていくもどかしさに耐えなければならなかった。
そんなある日、寝入りばなにあの夜のことを考えていた時----。ふとあることが頭をよぎった。
……あの時、米多たちが影に向かって何か声を掛けていたような気がした。あれは一体?……おどしのための罵声とも違う。ひょっとして、米多や片倉が影の正体を知って発した声だったのかも……少々突飛な想像かもしれないが何故かそのように思えてならなかった。
No.10 影の正体をつかむ