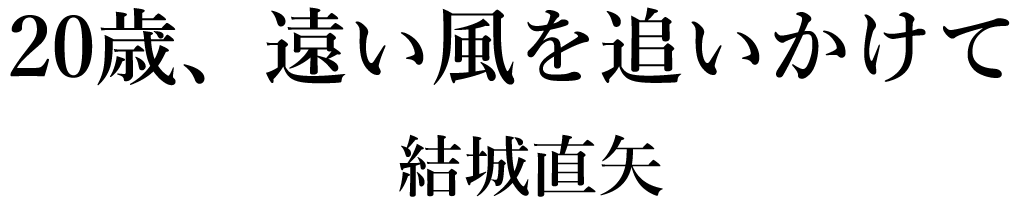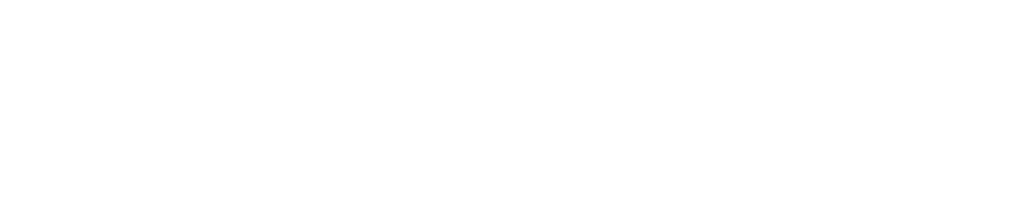No.1 失恋の果てに
全く、見通しのきかない闇だった。掻きわけても、掻きわけても、どこまでも延々と地の果てまでつながっているような、そんな 。
20歳の誕生日。僕は演劇部の仲間達と過ごした。
その日、夕方近く、中野の友人のマンションの一室は近所の酒屋から買い集めたウイスキーやビールや酒のつまみやたわいも無い戯言であふれ、わいた。
僕は19年間のさほど人に誇れるものもない、それまでの自分をとりあえず脇において、ウイスキーをストレートで一気飲みした。友人達は20歳になった日を境に何か突拍子もないことをしでかすかも知れないといった顔で祝杯をあげ、祭り気分で興じた。
少しばかり大げさな歓待だった。ほんとうのところ、仲間達の誰もが先の見えない20歳の闇を暇つぶしの余興で浮かれ騒ぎ、自身ではどうすることもできない撞着に、よってたかってケリをつけたかったのかもしれない。
この先、どこかで風穴が開くなんて、僕は期待もしていないし、仲間達も大半がそんなところだ。誰もが何かをやらなければという先走った思いで、頭の中はあふれかえっていたが、現実は遠く僕らの手のおよばないところにあった。
なんでもできるという跳ね上がった思い上がりは、常に現実という壁に押し戻され、実際はなにもできないという自家撞着にからめとられた。そのたびに、無残な敗北感のかけらが、また一つ小さな闇を加えた。
女の子のことを考えていることが唯一の救いだった。異性を美化し、恋焦がれることで、何かをしなければならないと、なぜかその闇を抜け出す力が沸き起こるような気がした。
遺伝子に刻み込まれた情報なのだろうか。結局のところ、その根源的なエネルギーに支えられ、「現実」にうちのめされがらも、なお精一杯の反撃を試みるしかなかった。そんな20歳の誕生日だった。
--- しかし、この日ばかりは、心の内にぬかるみのような闇がはてしなく広がり、ただうちひしがれるばかりだった。
が、せっかく集まってくれた仲間達だ。浮かない顔は見せられない。わざと快活に振る舞い、あまり強くない酒をたて続けにあおった。ハイペースな僕の飲みっぷりを見ても、おそらく感激して酒をあおっている、くらいにしか友人達は思っていなかったに違いない。
しかし、その下手くそな演技もせいぜい30分がいいところだった。部屋を提供してくれた親友の沢村は僕のいつにない心の振幅をとっくに見抜いていた。
「クズミ、お前、なんか今日変だぞ?」
沢村が心配そうに横で僕に声をかけた。演劇部に入った当初から奴とは気が合った。
「そう見えるか」
「お前はお世辞にも演技がうまいとは言えないからなぁ。お前の思ってるようなことは俺にはすぐわかる」
いつもならば演劇論でやり返すところだが、その日は沢村にそう言われても返す言葉がなかった。
「さてはまた、誰かにふられたな、おい、図星だろ」
「そんなことはないさ」
すかさず切り返したが、沢村のいうことはあたっていた。演劇部の友人の1人に笠間由里の結婚話を聞かされたばかりの僕はその日たとえて言うならば雷雨にたたられ濡れそぼった身体を乾かそうとやっきになっている野良犬にも似ていた。沢村だけじゃない。他の友人たちもそんな僕に気がついていたかもしれない。 僕は根っからの芝居好きの演劇青年というわけじゃない。演劇部に入ったのは人並み以上の自己顕示欲があったとか、将来その方面で活躍したいとか、そんな野心があったからではない。 大学に入ってすぐ部から勧誘があって、何げなく覗いてみておもしろそうだったからとか、広島から出てきたばかりで親しく話せる友人が欲しかったからとか、その程度の軽い動機だった。 だから、時折絵空事の芝居の中で無理をして演技をしていることが滑稽に思えたし、部の中に自分の居場所がないような違和感を始終覚えた。中途半端な自分に嫌気がさし、退部しようと思ったことも度々あった。 そんな僕が1年以上も部の活動を続けることができたのは笠間由里の存在があったからだ。彼女は演劇部の1年先輩で、僕は入部した時から彼女のことがなんとなく気にかかっていた。 笠間由里は15人ほどの女性部員の中でもとりわけ麗々しいとか才気煥発であるとかそんな類の女性ではなく、むしろどちらかというと控え目で古風な感じのする女性で、部の中にあっては僕と同じようにまるで場違いな所にいるような印象すら受けた。 彼女には他の部員を押し退けてでも自分のポジションを確保しようという浅ましさはなく、どんな役でも決められた配役をまるで定規で計ったように正確にこなしていた。 そのせいか彼女の演技には芝居をしている者から感じられる厭味が全くなかった。きっとすべてに分というものをわきまえて生きている大人の女性なのだと彼女を見るたびに思ったものだ。 そんな彼女にひかれていったのは確か大学1年の夏休み前頃だったろうか。夏休みに入って演劇部の総勢40名ほどが軽井沢で1週間の合宿を行い、その時にあらためて僕は彼女への思いの強さを認識した。 夏休みが終わり、大学に出る頃には、演劇というよりもむしろ彼女を見たくて熱心に部に通い詰めたものだ。日毎につのる彼女への思いを胸に、演劇部での彼女の一挙手一投足に目を配り、寝ても覚めても一途に思い焦がれるといったふうだった。 「クズミ……お前、ひょっとして由里さんのこと考えてんじゃねえのか?」
沢村が小さく声をかけてきた。
「ああ、、」
僕はあっさりとそのことを認めた。かなりアルコールがまわっていて、胸に秘めていた思いをすべて外に掃き出したいような心境だった。
「そんなことだろうと思ったぜ。いつかいってたもんな、お前、由里さんのこと」
「ああ、好きだ、好きだ、死にたいくらい俺は由里さんが好きだ」
僕は半分やけっぱちになって大声でそう叫び、手に持っていたグラスにウイスキーを自分でつぎ、一気にあおった。周りにいた仲間たちは僕の取り乱した様子を見てだいじょうぶか、と声をかけてきたが僕はうつむいたままこみあげてくる哀しみを胸の内に圧しとどめるのに精いっぱいだった。 笠間由里の結婚相手は彼女と同郷の京都に住む不動産会社の跡取り息子だと聞いていた。彼女の実家は嵐山の近くで小さな旅館を営んでいて、彼女は3人娘の長女として生まれた。たぶん、大学卒業後は京都に帰郷するのだろうと僕は思っていた。 が、母親が1年くらい前から心臓を患うという不測の事態が生じ、次第に容態が思わしくなくなり、彼女は学業半ばで休学届けを出し、半年ほど前から実家に帰っていた。 彼女の結婚願望がどれほどのものであったか推し測ることもできないが、母親が元気な間に花嫁姿を見せて安心させたいという周囲の思惑に押し切られ、結婚に踏み切ったのではないかと僕は勝手に推測していた。 僕は酔っぱらってさんざん沢村に悪態をついて奴の日頃の不品行をなじった。誰かに向かってうさを晴らさずにはいられなかった。そんな僕に沢村はただ笑ってうなずいてそうだそうだと言って相づちを打った。今時珍しいほど沢村は寛容な男だった。 夕方の7時くらいから始めて2時間ほど経った頃、僕は天と地の見さかいもつかないほど酔っぱらって、頭の中を柱時計の振り子のようなものが左右に揺れているような感じがして、耳なりと吐き気が5分おきくらいに襲ってきた。何度かトイレに立ち、その度に10分ほどそこから出て来ない僕を心配して仲間達が声をかけた。 真っ青な顔をしてトイレから出ると部屋の隅の沢村のベッドの上に仰向けになった。誰かが耳もとでがだらしねえぞとかしっかりしろよとか言って、泥酔している僕を揺すって起こそうとしたが、地球が壊滅して何もかもがこの世から消滅して無くなるまで眠っていたいような気分だった。 そのうち誰かの --- たぶん沢村の声だったと思うが --- これからナンパに行こうぜとか言っている声が聞こえてきて、クズミお前も行こうぜとかいう声が耳もとで響いて、誰かが僕の腕をつかみ、まだ寝るには早いぜと言って起こそうとした。 失恋し、意気消沈している僕をなぐさめようとしているのかもしれないと、アルコールに浸りきっ た頭で判断したが、その夜はそんな気にもなれなかった。 いつもなら沢村たちと夜の六本木や渋谷に誘われるままに繰り出して演劇部で培ったつたない演技で女の子たちとのやりとりに興じていたかも知れないが、彼らには取り合わず、寝返りをうってうつ伏せになり、枕に顔を付けて完全に酔いつぶれたふうを装った。 いや、実際に心身ともに最悪だった。マンションが火事で焼けたとしたらうつ伏せで焼けただれたままで発見されていたかもしれない。 沢村の部屋で目を覚ましたのは明け方の4時過ぎだった。起きるやいなや二日酔いで頭は地鳴りのように響いた。夢うつつで辺りを見回すと昨夜飲んで空にした酒の瓶やら食べ残しのつまみがガラステーブルの上に散乱し、部屋は明かりがついたままで友人たちの姿はなかった。 起き上がって台所に行き、冷たい水を何杯も飲んで喉を潤した。少しでも二日酔いをやわらげたいと思った。沢木たちはどこかに繰り出して、思い思いの夜を過ごしたに違いない。 窓を開けて淀んだ空気を外に出し、沢村の集めたジャズのレコードを適当に引っ張り出して音を絞って聞き、冷蔵庫からオレンジジュースを取り出し、タバコをふかしながら冷やかなそれを口にふくんだ。 開けた窓の隙間から清涼な風がレースのカーテンを押し上げ、二日酔いの冴えない頭を通り過ぎて行った。とても心地良くて頭の中に巣くったわだかまりまで一掃してくれそうな気がした。窓を開け広げ、顔を外に出して明け方の4月半ばの空を眺め渡した。 濃い空の青は東からほんのりとした赤みが広がり、その色あいを下から褪めたものに変えていた。明けていく空の彩りを見つめているとなぜか節制を極めた聖職者を前にしているようで、奇妙な罪悪感すら覚えた。しばらく呆けたように時の巡りを示す自然の色合いを見入った。 次第に闇がはれていく空を見ながら、これまで過ごしてきた人生とこれから過ごすであろう人生を交互に頭の中で描いてみた。過去の人生の上に未来のそれが構築されるとするならば、僕のこれからの人生はちょうど夜明け前の闇の中に立ちすくんだまま、目の前の届かない夜明けに手を伸ばそうとやっきになっているような、そんな人生かもしれない。 たぶんこのままではその想像通りの人生が展開するに違いない。何かを変えないかぎり、残念ながらその予測ははずれそうにない……。そんなとりとめのないことを考えながらジュースを飲んでいると微かに頭の痛みが薄らいでいるのがわかった。 ジュースを飲み干すと、バスルームに行き、熱いシャワーで酒臭い体臭を落とし、髪を洗い、二日酔いの頭をさっぱりさせた。 バスルームを出ると、ほとんど頭の痛みは消えていた。沢村に何か書き置きをして帰ろうかと思った。 電話の傍のペンと紙を取り、気のきいたことを書いてやろうと思った。が、適当な言葉が中々見つからなかった。なにげなく外を見ると、すでに空は青みが薄れて白くなり、一瞬、心にぽっかりと空白が出来た。その時、頭の中に「ある言葉」が浮かんだ。それを手短に書き、自分に納得させるように目でなぞると、部屋の隅に置いていたヘルメットを取って沢村の部屋をロックし、外に出た。 街はうっすらと目覚めたばかりで、朝靄にひっそりとして人影はなく、商店街はシャッターを降ろしたまま息をひそめていた。 僕は買ってまだ1ケ月も経ってない250CCのオフロードバイクに股がり、朝の澄んだ空を仰ぎ見ながらヘルメットをかぶった。部屋に戻った沢村が書き置きを読んでどう思うだろうか。奴が僕なら同じような心境になったかもしれない。 僕は単位の取得に汲々としている学生ではない。どちからというと不真面目で大学の存在意義さえ疑っているような中途半端な学生だ。「書き置き」の内容を実行する時間はたっぷりある。そのために大学を1年くらい留年してもかまわないとさえ思っている。自分をみつめ直すいい機会だ。とにかく僕は自分の中の何かを変えたいと思った。 書き置きには『しばらく旅に出る』とだけ書いた。買ったばかりのバイクで遠乗りをしてみたくなったのか、笠間由里へのどうにもならない想いを振り払いたくてそんな気になったのか、あるいは20歳になって自分を変えるための契機を何か見つけようとしていたのか、動機はさまざまのような気がしたが、そのどれもが一緒になって僕の背中を押しているような気もした。 それ以外に何かあるとすればたぶんあの夜明けの空のせいだ。闇夜を突き抜けたその先に何かが待っているような気がした。
No.2 バイクで成り行きまかせの旅
沢村が心配そうに横で僕に声をかけた。演劇部に入った当初から奴とは気が合った。
「そう見えるか」
「お前はお世辞にも演技がうまいとは言えないからなぁ。お前の思ってるようなことは俺にはすぐわかる」
いつもならば演劇論でやり返すところだが、その日は沢村にそう言われても返す言葉がなかった。
「さてはまた、誰かにふられたな、おい、図星だろ」
「そんなことはないさ」
すかさず切り返したが、沢村のいうことはあたっていた。演劇部の友人の1人に笠間由里の結婚話を聞かされたばかりの僕はその日たとえて言うならば雷雨にたたられ濡れそぼった身体を乾かそうとやっきになっている野良犬にも似ていた。沢村だけじゃない。他の友人たちもそんな僕に気がついていたかもしれない。 僕は根っからの芝居好きの演劇青年というわけじゃない。演劇部に入ったのは人並み以上の自己顕示欲があったとか、将来その方面で活躍したいとか、そんな野心があったからではない。 大学に入ってすぐ部から勧誘があって、何げなく覗いてみておもしろそうだったからとか、広島から出てきたばかりで親しく話せる友人が欲しかったからとか、その程度の軽い動機だった。 だから、時折絵空事の芝居の中で無理をして演技をしていることが滑稽に思えたし、部の中に自分の居場所がないような違和感を始終覚えた。中途半端な自分に嫌気がさし、退部しようと思ったことも度々あった。 そんな僕が1年以上も部の活動を続けることができたのは笠間由里の存在があったからだ。彼女は演劇部の1年先輩で、僕は入部した時から彼女のことがなんとなく気にかかっていた。 笠間由里は15人ほどの女性部員の中でもとりわけ麗々しいとか才気煥発であるとかそんな類の女性ではなく、むしろどちらかというと控え目で古風な感じのする女性で、部の中にあっては僕と同じようにまるで場違いな所にいるような印象すら受けた。 彼女には他の部員を押し退けてでも自分のポジションを確保しようという浅ましさはなく、どんな役でも決められた配役をまるで定規で計ったように正確にこなしていた。 そのせいか彼女の演技には芝居をしている者から感じられる厭味が全くなかった。きっとすべてに分というものをわきまえて生きている大人の女性なのだと彼女を見るたびに思ったものだ。 そんな彼女にひかれていったのは確か大学1年の夏休み前頃だったろうか。夏休みに入って演劇部の総勢40名ほどが軽井沢で1週間の合宿を行い、その時にあらためて僕は彼女への思いの強さを認識した。 夏休みが終わり、大学に出る頃には、演劇というよりもむしろ彼女を見たくて熱心に部に通い詰めたものだ。日毎につのる彼女への思いを胸に、演劇部での彼女の一挙手一投足に目を配り、寝ても覚めても一途に思い焦がれるといったふうだった。 「クズミ……お前、ひょっとして由里さんのこと考えてんじゃねえのか?」
沢村が小さく声をかけてきた。
「ああ、、」
僕はあっさりとそのことを認めた。かなりアルコールがまわっていて、胸に秘めていた思いをすべて外に掃き出したいような心境だった。
「そんなことだろうと思ったぜ。いつかいってたもんな、お前、由里さんのこと」
「ああ、好きだ、好きだ、死にたいくらい俺は由里さんが好きだ」
僕は半分やけっぱちになって大声でそう叫び、手に持っていたグラスにウイスキーを自分でつぎ、一気にあおった。周りにいた仲間たちは僕の取り乱した様子を見てだいじょうぶか、と声をかけてきたが僕はうつむいたままこみあげてくる哀しみを胸の内に圧しとどめるのに精いっぱいだった。 笠間由里の結婚相手は彼女と同郷の京都に住む不動産会社の跡取り息子だと聞いていた。彼女の実家は嵐山の近くで小さな旅館を営んでいて、彼女は3人娘の長女として生まれた。たぶん、大学卒業後は京都に帰郷するのだろうと僕は思っていた。 が、母親が1年くらい前から心臓を患うという不測の事態が生じ、次第に容態が思わしくなくなり、彼女は学業半ばで休学届けを出し、半年ほど前から実家に帰っていた。 彼女の結婚願望がどれほどのものであったか推し測ることもできないが、母親が元気な間に花嫁姿を見せて安心させたいという周囲の思惑に押し切られ、結婚に踏み切ったのではないかと僕は勝手に推測していた。 僕は酔っぱらってさんざん沢村に悪態をついて奴の日頃の不品行をなじった。誰かに向かってうさを晴らさずにはいられなかった。そんな僕に沢村はただ笑ってうなずいてそうだそうだと言って相づちを打った。今時珍しいほど沢村は寛容な男だった。 夕方の7時くらいから始めて2時間ほど経った頃、僕は天と地の見さかいもつかないほど酔っぱらって、頭の中を柱時計の振り子のようなものが左右に揺れているような感じがして、耳なりと吐き気が5分おきくらいに襲ってきた。何度かトイレに立ち、その度に10分ほどそこから出て来ない僕を心配して仲間達が声をかけた。 真っ青な顔をしてトイレから出ると部屋の隅の沢村のベッドの上に仰向けになった。誰かが耳もとでがだらしねえぞとかしっかりしろよとか言って、泥酔している僕を揺すって起こそうとしたが、地球が壊滅して何もかもがこの世から消滅して無くなるまで眠っていたいような気分だった。 そのうち誰かの --- たぶん沢村の声だったと思うが --- これからナンパに行こうぜとか言っている声が聞こえてきて、クズミお前も行こうぜとかいう声が耳もとで響いて、誰かが僕の腕をつかみ、まだ寝るには早いぜと言って起こそうとした。 失恋し、意気消沈している僕をなぐさめようとしているのかもしれないと、アルコールに浸りきっ た頭で判断したが、その夜はそんな気にもなれなかった。 いつもなら沢村たちと夜の六本木や渋谷に誘われるままに繰り出して演劇部で培ったつたない演技で女の子たちとのやりとりに興じていたかも知れないが、彼らには取り合わず、寝返りをうってうつ伏せになり、枕に顔を付けて完全に酔いつぶれたふうを装った。 いや、実際に心身ともに最悪だった。マンションが火事で焼けたとしたらうつ伏せで焼けただれたままで発見されていたかもしれない。 沢村の部屋で目を覚ましたのは明け方の4時過ぎだった。起きるやいなや二日酔いで頭は地鳴りのように響いた。夢うつつで辺りを見回すと昨夜飲んで空にした酒の瓶やら食べ残しのつまみがガラステーブルの上に散乱し、部屋は明かりがついたままで友人たちの姿はなかった。 起き上がって台所に行き、冷たい水を何杯も飲んで喉を潤した。少しでも二日酔いをやわらげたいと思った。沢木たちはどこかに繰り出して、思い思いの夜を過ごしたに違いない。 窓を開けて淀んだ空気を外に出し、沢村の集めたジャズのレコードを適当に引っ張り出して音を絞って聞き、冷蔵庫からオレンジジュースを取り出し、タバコをふかしながら冷やかなそれを口にふくんだ。 開けた窓の隙間から清涼な風がレースのカーテンを押し上げ、二日酔いの冴えない頭を通り過ぎて行った。とても心地良くて頭の中に巣くったわだかまりまで一掃してくれそうな気がした。窓を開け広げ、顔を外に出して明け方の4月半ばの空を眺め渡した。 濃い空の青は東からほんのりとした赤みが広がり、その色あいを下から褪めたものに変えていた。明けていく空の彩りを見つめているとなぜか節制を極めた聖職者を前にしているようで、奇妙な罪悪感すら覚えた。しばらく呆けたように時の巡りを示す自然の色合いを見入った。 次第に闇がはれていく空を見ながら、これまで過ごしてきた人生とこれから過ごすであろう人生を交互に頭の中で描いてみた。過去の人生の上に未来のそれが構築されるとするならば、僕のこれからの人生はちょうど夜明け前の闇の中に立ちすくんだまま、目の前の届かない夜明けに手を伸ばそうとやっきになっているような、そんな人生かもしれない。 たぶんこのままではその想像通りの人生が展開するに違いない。何かを変えないかぎり、残念ながらその予測ははずれそうにない……。そんなとりとめのないことを考えながらジュースを飲んでいると微かに頭の痛みが薄らいでいるのがわかった。 ジュースを飲み干すと、バスルームに行き、熱いシャワーで酒臭い体臭を落とし、髪を洗い、二日酔いの頭をさっぱりさせた。 バスルームを出ると、ほとんど頭の痛みは消えていた。沢村に何か書き置きをして帰ろうかと思った。 電話の傍のペンと紙を取り、気のきいたことを書いてやろうと思った。が、適当な言葉が中々見つからなかった。なにげなく外を見ると、すでに空は青みが薄れて白くなり、一瞬、心にぽっかりと空白が出来た。その時、頭の中に「ある言葉」が浮かんだ。それを手短に書き、自分に納得させるように目でなぞると、部屋の隅に置いていたヘルメットを取って沢村の部屋をロックし、外に出た。 街はうっすらと目覚めたばかりで、朝靄にひっそりとして人影はなく、商店街はシャッターを降ろしたまま息をひそめていた。 僕は買ってまだ1ケ月も経ってない250CCのオフロードバイクに股がり、朝の澄んだ空を仰ぎ見ながらヘルメットをかぶった。部屋に戻った沢村が書き置きを読んでどう思うだろうか。奴が僕なら同じような心境になったかもしれない。 僕は単位の取得に汲々としている学生ではない。どちからというと不真面目で大学の存在意義さえ疑っているような中途半端な学生だ。「書き置き」の内容を実行する時間はたっぷりある。そのために大学を1年くらい留年してもかまわないとさえ思っている。自分をみつめ直すいい機会だ。とにかく僕は自分の中の何かを変えたいと思った。 書き置きには『しばらく旅に出る』とだけ書いた。買ったばかりのバイクで遠乗りをしてみたくなったのか、笠間由里へのどうにもならない想いを振り払いたくてそんな気になったのか、あるいは20歳になって自分を変えるための契機を何か見つけようとしていたのか、動機はさまざまのような気がしたが、そのどれもが一緒になって僕の背中を押しているような気もした。 それ以外に何かあるとすればたぶんあの夜明けの空のせいだ。闇夜を突き抜けたその先に何かが待っているような気がした。