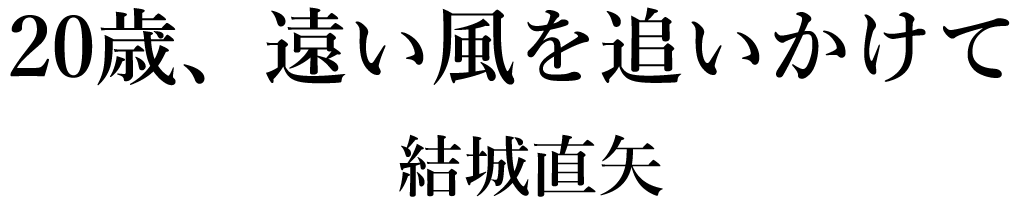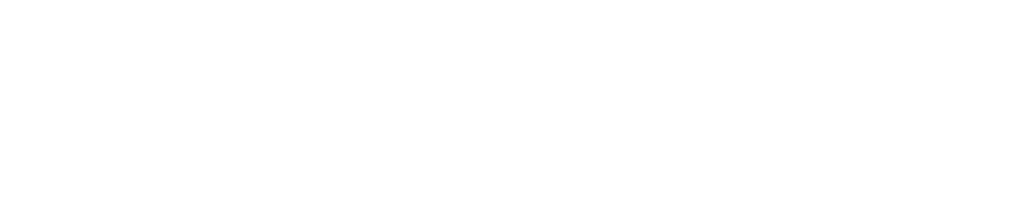No.11 杉町の秘密
7月後半。僕は杉町からある相談を受けた。
「クズミ、ひとつお願いがあるんだ。どこか、どこでもいいんだけど、大学に連れてってくんないか」
切実な杉町の目だった。この目にはバイクの試し乗りで何度もやられている。
「わるいけど、女子大ならかんべんしてくれ」
無精ひげの汗臭いがさつな男2人がオフロードバイクを吹かして乗り込もうものなら、間違いなく校門前で警備員に制止されるにきまってる。そこは僕にとっては想像の及ばない未知の領域だ。2、3日前から、バイクごと体も洗浄して、すっかりアク抜きしなきゃいけない。
「ちょっと、小奇麗にしてからな。サウナ行って、髭剃って、こざっぱりして」
「どこでもいいんだ。クズミの大学でもいい。ちょっとぶらつくだけでいいんだ」
切羽詰まったような杉町の目から、何か失った記憶を呼び戻すかもしれないと思った。
「しょうがない。そいじゃあ、隊長に言って休みをもらうか」 隊長に無理を承知で頼み込むと、なんとか1日だけ休みをとることができた。1週間後、警備会社からアルバイトの学生が応援にやって来た。 僕は杉町をバイクの後ろに乗せ、都内にある僕の通っていた大学へと向かった。沢村たちに構内で会ったらどんな話をしようかと胸が高鳴った。 彼らとは3ケ月ぶりだ。会いたくもあり、あったらどんな話をしようかと、気持ちは複雑だった。ひょっとしたら口のまわりを覆っている不精ひげで僕と気づかず彼らは通り過ぎるかもしれない。想像しているだけでときめき、ハンドルを握る手があまくなった。 大学には11時過ぎに着いた。校門を入ったすぐ脇の駐車場にバイクを止めると、杉町を連れてキャンパスをぶらついた。方々から、耳をつんざくようなセミの鳴き声が聞こえてきた。時々すれ違う女の子たちが僕と杉町を物珍しげに一瞥して行った。 僕は日に焼けて髪も長く、おまけに口ひげまでたくわえ、白いTシャツにモトクロスパンツにオフロードブーツといったどうにもバランスのとれない格好をしていた。杉町はTシャツにジーンズだった。 太陽の照射を背に、木陰と陽だまりでまだらになったキャンパスを踏みしめ、中央講堂や学部ごとに分かれた校舎を杉町に案内し、「ほら、あそこでテレビに出てる教授がインタビューをよくやってんだ。株だの金融だのって」と指し示した。 いつもなら学生で賑わうガラス張りの学生ラウンジも閑散として、事務員が暇そうにしていた。体育館は補終工事の最中でバケツやはけを手にした職人や機材を乗せたトラックが慌ただしく出入りしていた。 図書館の横の入り組んだ迷路のような道なりに運動部やサークルの部室があった。その奥に演劇部の部室があったが、足が遠のいた。仲間達に会いたくもあったが、やはりひけ目を感じた。部にほとんど顔を出さず、20歳の誕生日祝いの翌日に忽然と姿を消すような僕を、きっと誰もが身勝手な奴と思っているに違いない。 少し風に吹かれたいと思った。歩調を早め、小高くなった土手に立ち、そこからテニスコートを見下ろした。テニス部員達が四角いコートを縦横に走り、切れの良い音が照り輝く空に響いていた。生暖かい風が頬をよぎった。
「なあ、杉町、俺はここにいても自分の居場所がないような気がしてしょうがないんだ」
フェンスごしにふと僕は杉町に言った。
「一体、自分は何しにここに来たんだか、わからないんだ。とりあえず大学だけは、なんて思って、英単語丸暗記して、数式がむしゃらに解いて……。入れない人達からすればぜいたくな話かもしんないけど。何の目標もなきゃ、どこにいようが同じことだよな」 杉町はそれに何も答えず、遠くでボールを追いかけるテニス部員たちの姿を虚ろに眺めていた。<いいよなぁ……>杉町のかすかにつぶやいたそんな声を聞いたような気がした。 僕はしばらくテニス部員たちの軽快な動きに見入った。ムダのない身のこなしで、ボールを受け、打ち返し、また受けては目標を定め、全力で打ちこんでいる。力を振りしぼり、汗だくで、何の迷いもない直球をピンポイントで打ちこんでいる。白いユニホームが真夏の光に溶けていた。 正午近くに、杉町を学食へ案内した。食堂は試験を終えた学生たちであふれていた。杉町は同年代の若者で賑わう空間に酔ったような面持ちで胸のあたりを抑えていた。確かにここは、飯場からみれば、いや世間からだって、隔絶され、温存された未熟な若者達の見果てぬ夢の、何か浮ついた空気に支配された、異空間のような所かもしれない。 入り口付近に席をとり、2人分の食券を買い、定食を注文した。飯場の食堂と違って、トレーから食器からなにもかも小奇麗で、大根の煮付けまでも上等なものに見えた。ただそれだけの、見かけだけのことなのに、杉町は嬉しそうに顔をゆるませていた。飯場では決して見たことのない顔だった。 僕達の傍をあわただしく学生が出入りし、その中にオレンジ色のタンクトップを着て小麦色に焼けた両肩をむき出しにした長い髪の女の子が通り過ぎ、色っぽいじゃねえかと目で追いかけながらスパゲティを頬ばっていると、誰かが後ろから僕の頭を強く叩いた。
振り向くと、そこに沢村と演劇部の仲間たちが3、4人立っていた。
「誰かと思ったぜ。ヒゲなんかのばしやがって。熊と同棲するってのは本当だったのか」
沢村は今まで見たことのないような笑みを浮かべ、珍獣でも探しあてたような光を目にたたえていた。
「最初、わかんなかったぜ、クズミだって、そんな格好してるから」
「熊は惚れ直したって言ってくれてる」
僕はふざけてやり返した。
「いつ帰ってきた」
「いや、帰ってきたわけじゃなくて」
最後まで言い終えないうちに、沢村は
「今日、飲みに行かねえか」
と、誘った。このまま沢村たちと別れるのも名残り惜しくもあったが、杉町のこともあったので断った。沢村は傍にいる若者が僕の連れだと気がついたようで無理押しはしなかった。「また電話しろよ」と言って僕の肩に手を強く押し付けると、演劇部の仲間たちと行ってしまった。 本当は沢村に話したいことが山ほどあった。沢村よ、お前は女にモテるけど、やっぱり役者目指すんなら手痛い失恋の一つでもやってみなきゃな。惚れた女に振られてヤケっぱちになって、傷心の旅というやつに出てみるのもいいもんだぜ。社会人になったらそんなことできやしないんだから。つらい経験をしてはじめて本物の演技が磨けるってものさ。挫折も痛みも知らない人間が、脚本家と頭の中でこねくりまわした架空の世界でいくら演じたって、たかが知れてるさ。薄っぺらでうわっつらな嫌味な演技に決まってる、響いてくるものなんてありゃしないよ。そんなふうな話を久しぶりに酒を交わしながらしてみたかった。 僕はふと、沢村との会話を思い出し、杉町に話した。
「あいつ、ああ見えてもいい奴でね。『所詮おれらがやってる芝居なんて、世間知らずのおぼっちゃんの道楽にすぎやしないのさ』って、食いついたことがあるんだ。『さんざんぜいたくをしてる文化人が付け焼刃のテレビコメンテーターになって庶民の暮らしは大変ですねって同情しているようなもんさ。人様に何か影響を与えようと思ったら、世間の人以上に辛い経験を味わう必要があるんだよ』って、そしたらあいつなんて言ったと思う。『だからお前は、ダメなんだよ。そいじゃ、人殺ししなきゃ殺人者のリアルな演技はできねえっていうの。演技ってものは、そういうものを超越したものなんだよ』だって。だから『じゃあ、あいつらはアカデミー賞級の役者かい』って言ったら、『いや、その上をいってるかもな』だとさ。奴は将来役者希望でね、確かに顔もいいけど、『食えるようになるまで結構大変かもしんないぞ』って言ったんだ。そしたら、『若いころ役者が食えないってのは、食えないような辛い経験を神さんにさせられてんだろうな。そうやって人様の痛みがわかれば、いつか売れるようになった時に誰をも納得させるような演技ができるから。だから下積みが長くて苦労していた役者のほうが味があるもんな。この味って奴なんだよな、たぶん世間が評価するのは』って、今度はわかったふうなことをぬかすわけさ。それで、結局、最後はね、『ということは、女に振られたことのないお前なんかより、さんざん振られまくった俺のほうが、それはそれは人情の機微というものに数倍長けてるから、人間味じゃ俺のほうが数段上ってもんさ』って締めるわけ。そうすると、また奴は『お前はただの失恋の有段者だ』とくるわけさ」 杉町はそんな僕のとりとめのない話を可笑しそうに聞いていた。 食事をしたせいか、急に眠気に襲われた。食堂を出て、横になれそうな所を探した。木陰の下のベンチを見つけ、そこに体を横えていると、杉町が気を利かして、氷入りのグレープジュースを買って戻ってきた。 仰向けになると、木々の間から夏の強い日差しが直接顔の上に落ちてきた。うず高く積まれた陽光をまぶたの上に感じた。 鋭い直射をまともにまぶたに浴びたせいだろうか。薄目を開けると、いままで見えていた世界が急に色槌せ、違う世界に映って見えた。キャンパスを行き交う学生たちは同じような顔と装いで、足は地に付かず、踊っているようにも、足早に急ぎ足で駆けているようにも見える。みんなどこへ向かっているのだろうか……その先に、何があるのかさっぱり見当もつかない……彼らの中で確かな足どりで歩いている自分がどうしても思い浮かばない。 今、人波から逸れ、未踏の地を歩いているような気分だが、それでも、しっかりと地に足をつけて立っているという実感だけはある。 3ケ月前には感じたことのない感覚だ。 夏のまばゆい陽光が、僕の中でつかえていたわだかまりを溶かし、流してくれたような気がした。体の一部にぽっかりと穴が空き、そこから清涼な風が入り込んでくるような心地良さを感じた。 ベンチから体を起こし、氷の溶けたジュースを飲み干した。隣で杉町も同じようにジュースに口をつけていた。杉町は目の前を談笑しながら通り過ぎていく男子学生たちや肌をむき出しにした女の子たちをまぶしげに見つめていた。 「なにか、思い出しそうか」
ふと、僕は杉町にたずねた。それまでそのことは触れないでいた。ふいをつかれたような顔で、杉町は僕のほうを振り向いた。
「オヤジさんから聞いてた。記憶を失ってるって」
僕がそう言うと、杉町はうつむいて、足元に目を這わせた。こころなしか目もとが潤んでいるようにも見えた。
「記憶がないってのいうのは嘘だ……」
杉町は顔を上げ、遠くを見て、ぼそりとつぶやいた。
「このことは絶対に黙っててくれ」
杉町はそう言うと、また顔を伏せた。
「俺は今まであの人をだまし続けてきた……」
杉町はうつむいたまま答えた。
「あの人は本当の父親じゃない……俺は金沢で生まれて……3年ほど前だ……進路のことで親と喧嘩になって……夜、家を飛び出して……夜道をあてもなく歩いている時、車にはねられた……その時通りすがりにあの人が俺を助けてくれた……俺はその時、記憶喪失を装った……どうしても家に帰りたくなくて」 杉町の思わぬ告白に僕は言葉を失った。聞けば、杉町の本当の父親というのは金沢でもかなりの資産家という。地元の政治家にも影響力を及ぼすほどの名士で、杉町を政治の世界へ進ませることに固執したという。 「あの人は俺を飯場に連れて行って、本当の父親以上に面倒を見てくれた……もう3年になる……いろいろな飯場を渡り歩いて」
「なぜ、大学が見たいって……」
そのことが気にかかった。杉町は顔を上げて溜め息をつきながら、
「ほんとだったら今頃、みんなと同じように大学に行ってたかなぁって、バカだよなぁ……今さら」と自嘲するように答えた。
「オヤジさんからお前が記憶を失ってるって聞かされた時、なんとなく変だとは思ってた……こう見えても俺は演劇部だ。お前も俺と一緒で芝居が下手クソだ」 僕が、そう言うと杉町は口もとを緩め、微かに笑みを浮かべた。
「クズミ、もう一つだけ頼みがある。バイクをしばらく貸してくれないか」
「どうする」
「金沢に行って……本当の親に会ってきたい……会ってきたらまた飯場へ帰ってくる」
杉町は真剣な眼差しで懇願した。
「必ず飯場に戻ってくる、必ず……。あの人は白内障で目が悪くて、だから俺が傍に付いていてやらないと」
杉町は畳みかけるように、真剣な目で僕に訴えかけた。
「俺はあの人の傍にいてずっと面倒を見ることに決めたんだ。だからその前に一度金沢の親に会っておきたいと思って……」
杉町は涙で声を曇らせていた。 「バイクで……俺はあの人と歩いてきた飯場をもう一度見ながら金沢まで帰りたいと思って」
そこまで言うと、杉町はしばらく黙ったままでいた。杉町の意外な過去を聞いて、胸が重くなった。取り敢えず、その場は杉町の頼みをのんだ。 それから1週間後、杉町は金沢へ向け、朝まだ早いうちに僕のバイクで旅立った。ひょっとしたら僕以上かも知れないと思われるほどバイクの腕前は上達していて運転技術に問題はなかったが、無免許だったので、ばれないよう金沢までたどり着けるかどうか心配だった。1週間もあれば金沢に行って飯場に帰って来れるさ。そう言って、杉町は旅立って行った。 杉町は養父に簡単な書き置きを残して飯場を出たようだった。むろんそれに行き先は書かれてない。たぶん以前僕が沢村の部屋に残してきた書き置き程度のものであっただろう。そのことで、後で養父に行き先に心当たりがないかと尋ねられ、冷や汗ものだったが、バイクが気に入って遠乗りしてみたくなったんじゃないですかと答え、ごまかした。
No.12 杉町の養父から預かったもの
「クズミ、ひとつお願いがあるんだ。どこか、どこでもいいんだけど、大学に連れてってくんないか」
切実な杉町の目だった。この目にはバイクの試し乗りで何度もやられている。
「わるいけど、女子大ならかんべんしてくれ」
無精ひげの汗臭いがさつな男2人がオフロードバイクを吹かして乗り込もうものなら、間違いなく校門前で警備員に制止されるにきまってる。そこは僕にとっては想像の及ばない未知の領域だ。2、3日前から、バイクごと体も洗浄して、すっかりアク抜きしなきゃいけない。
「ちょっと、小奇麗にしてからな。サウナ行って、髭剃って、こざっぱりして」
「どこでもいいんだ。クズミの大学でもいい。ちょっとぶらつくだけでいいんだ」
切羽詰まったような杉町の目から、何か失った記憶を呼び戻すかもしれないと思った。
「しょうがない。そいじゃあ、隊長に言って休みをもらうか」 隊長に無理を承知で頼み込むと、なんとか1日だけ休みをとることができた。1週間後、警備会社からアルバイトの学生が応援にやって来た。 僕は杉町をバイクの後ろに乗せ、都内にある僕の通っていた大学へと向かった。沢村たちに構内で会ったらどんな話をしようかと胸が高鳴った。 彼らとは3ケ月ぶりだ。会いたくもあり、あったらどんな話をしようかと、気持ちは複雑だった。ひょっとしたら口のまわりを覆っている不精ひげで僕と気づかず彼らは通り過ぎるかもしれない。想像しているだけでときめき、ハンドルを握る手があまくなった。 大学には11時過ぎに着いた。校門を入ったすぐ脇の駐車場にバイクを止めると、杉町を連れてキャンパスをぶらついた。方々から、耳をつんざくようなセミの鳴き声が聞こえてきた。時々すれ違う女の子たちが僕と杉町を物珍しげに一瞥して行った。 僕は日に焼けて髪も長く、おまけに口ひげまでたくわえ、白いTシャツにモトクロスパンツにオフロードブーツといったどうにもバランスのとれない格好をしていた。杉町はTシャツにジーンズだった。 太陽の照射を背に、木陰と陽だまりでまだらになったキャンパスを踏みしめ、中央講堂や学部ごとに分かれた校舎を杉町に案内し、「ほら、あそこでテレビに出てる教授がインタビューをよくやってんだ。株だの金融だのって」と指し示した。 いつもなら学生で賑わうガラス張りの学生ラウンジも閑散として、事務員が暇そうにしていた。体育館は補終工事の最中でバケツやはけを手にした職人や機材を乗せたトラックが慌ただしく出入りしていた。 図書館の横の入り組んだ迷路のような道なりに運動部やサークルの部室があった。その奥に演劇部の部室があったが、足が遠のいた。仲間達に会いたくもあったが、やはりひけ目を感じた。部にほとんど顔を出さず、20歳の誕生日祝いの翌日に忽然と姿を消すような僕を、きっと誰もが身勝手な奴と思っているに違いない。 少し風に吹かれたいと思った。歩調を早め、小高くなった土手に立ち、そこからテニスコートを見下ろした。テニス部員達が四角いコートを縦横に走り、切れの良い音が照り輝く空に響いていた。生暖かい風が頬をよぎった。
「なあ、杉町、俺はここにいても自分の居場所がないような気がしてしょうがないんだ」
フェンスごしにふと僕は杉町に言った。
「一体、自分は何しにここに来たんだか、わからないんだ。とりあえず大学だけは、なんて思って、英単語丸暗記して、数式がむしゃらに解いて……。入れない人達からすればぜいたくな話かもしんないけど。何の目標もなきゃ、どこにいようが同じことだよな」 杉町はそれに何も答えず、遠くでボールを追いかけるテニス部員たちの姿を虚ろに眺めていた。<いいよなぁ……>杉町のかすかにつぶやいたそんな声を聞いたような気がした。 僕はしばらくテニス部員たちの軽快な動きに見入った。ムダのない身のこなしで、ボールを受け、打ち返し、また受けては目標を定め、全力で打ちこんでいる。力を振りしぼり、汗だくで、何の迷いもない直球をピンポイントで打ちこんでいる。白いユニホームが真夏の光に溶けていた。 正午近くに、杉町を学食へ案内した。食堂は試験を終えた学生たちであふれていた。杉町は同年代の若者で賑わう空間に酔ったような面持ちで胸のあたりを抑えていた。確かにここは、飯場からみれば、いや世間からだって、隔絶され、温存された未熟な若者達の見果てぬ夢の、何か浮ついた空気に支配された、異空間のような所かもしれない。 入り口付近に席をとり、2人分の食券を買い、定食を注文した。飯場の食堂と違って、トレーから食器からなにもかも小奇麗で、大根の煮付けまでも上等なものに見えた。ただそれだけの、見かけだけのことなのに、杉町は嬉しそうに顔をゆるませていた。飯場では決して見たことのない顔だった。 僕達の傍をあわただしく学生が出入りし、その中にオレンジ色のタンクトップを着て小麦色に焼けた両肩をむき出しにした長い髪の女の子が通り過ぎ、色っぽいじゃねえかと目で追いかけながらスパゲティを頬ばっていると、誰かが後ろから僕の頭を強く叩いた。
振り向くと、そこに沢村と演劇部の仲間たちが3、4人立っていた。
「誰かと思ったぜ。ヒゲなんかのばしやがって。熊と同棲するってのは本当だったのか」
沢村は今まで見たことのないような笑みを浮かべ、珍獣でも探しあてたような光を目にたたえていた。
「最初、わかんなかったぜ、クズミだって、そんな格好してるから」
「熊は惚れ直したって言ってくれてる」
僕はふざけてやり返した。
「いつ帰ってきた」
「いや、帰ってきたわけじゃなくて」
最後まで言い終えないうちに、沢村は
「今日、飲みに行かねえか」
と、誘った。このまま沢村たちと別れるのも名残り惜しくもあったが、杉町のこともあったので断った。沢村は傍にいる若者が僕の連れだと気がついたようで無理押しはしなかった。「また電話しろよ」と言って僕の肩に手を強く押し付けると、演劇部の仲間たちと行ってしまった。 本当は沢村に話したいことが山ほどあった。沢村よ、お前は女にモテるけど、やっぱり役者目指すんなら手痛い失恋の一つでもやってみなきゃな。惚れた女に振られてヤケっぱちになって、傷心の旅というやつに出てみるのもいいもんだぜ。社会人になったらそんなことできやしないんだから。つらい経験をしてはじめて本物の演技が磨けるってものさ。挫折も痛みも知らない人間が、脚本家と頭の中でこねくりまわした架空の世界でいくら演じたって、たかが知れてるさ。薄っぺらでうわっつらな嫌味な演技に決まってる、響いてくるものなんてありゃしないよ。そんなふうな話を久しぶりに酒を交わしながらしてみたかった。 僕はふと、沢村との会話を思い出し、杉町に話した。
「あいつ、ああ見えてもいい奴でね。『所詮おれらがやってる芝居なんて、世間知らずのおぼっちゃんの道楽にすぎやしないのさ』って、食いついたことがあるんだ。『さんざんぜいたくをしてる文化人が付け焼刃のテレビコメンテーターになって庶民の暮らしは大変ですねって同情しているようなもんさ。人様に何か影響を与えようと思ったら、世間の人以上に辛い経験を味わう必要があるんだよ』って、そしたらあいつなんて言ったと思う。『だからお前は、ダメなんだよ。そいじゃ、人殺ししなきゃ殺人者のリアルな演技はできねえっていうの。演技ってものは、そういうものを超越したものなんだよ』だって。だから『じゃあ、あいつらはアカデミー賞級の役者かい』って言ったら、『いや、その上をいってるかもな』だとさ。奴は将来役者希望でね、確かに顔もいいけど、『食えるようになるまで結構大変かもしんないぞ』って言ったんだ。そしたら、『若いころ役者が食えないってのは、食えないような辛い経験を神さんにさせられてんだろうな。そうやって人様の痛みがわかれば、いつか売れるようになった時に誰をも納得させるような演技ができるから。だから下積みが長くて苦労していた役者のほうが味があるもんな。この味って奴なんだよな、たぶん世間が評価するのは』って、今度はわかったふうなことをぬかすわけさ。それで、結局、最後はね、『ということは、女に振られたことのないお前なんかより、さんざん振られまくった俺のほうが、それはそれは人情の機微というものに数倍長けてるから、人間味じゃ俺のほうが数段上ってもんさ』って締めるわけ。そうすると、また奴は『お前はただの失恋の有段者だ』とくるわけさ」 杉町はそんな僕のとりとめのない話を可笑しそうに聞いていた。 食事をしたせいか、急に眠気に襲われた。食堂を出て、横になれそうな所を探した。木陰の下のベンチを見つけ、そこに体を横えていると、杉町が気を利かして、氷入りのグレープジュースを買って戻ってきた。 仰向けになると、木々の間から夏の強い日差しが直接顔の上に落ちてきた。うず高く積まれた陽光をまぶたの上に感じた。 鋭い直射をまともにまぶたに浴びたせいだろうか。薄目を開けると、いままで見えていた世界が急に色槌せ、違う世界に映って見えた。キャンパスを行き交う学生たちは同じような顔と装いで、足は地に付かず、踊っているようにも、足早に急ぎ足で駆けているようにも見える。みんなどこへ向かっているのだろうか……その先に、何があるのかさっぱり見当もつかない……彼らの中で確かな足どりで歩いている自分がどうしても思い浮かばない。 今、人波から逸れ、未踏の地を歩いているような気分だが、それでも、しっかりと地に足をつけて立っているという実感だけはある。 3ケ月前には感じたことのない感覚だ。 夏のまばゆい陽光が、僕の中でつかえていたわだかまりを溶かし、流してくれたような気がした。体の一部にぽっかりと穴が空き、そこから清涼な風が入り込んでくるような心地良さを感じた。 ベンチから体を起こし、氷の溶けたジュースを飲み干した。隣で杉町も同じようにジュースに口をつけていた。杉町は目の前を談笑しながら通り過ぎていく男子学生たちや肌をむき出しにした女の子たちをまぶしげに見つめていた。 「なにか、思い出しそうか」
ふと、僕は杉町にたずねた。それまでそのことは触れないでいた。ふいをつかれたような顔で、杉町は僕のほうを振り向いた。
「オヤジさんから聞いてた。記憶を失ってるって」
僕がそう言うと、杉町はうつむいて、足元に目を這わせた。こころなしか目もとが潤んでいるようにも見えた。
「記憶がないってのいうのは嘘だ……」
杉町は顔を上げ、遠くを見て、ぼそりとつぶやいた。
「このことは絶対に黙っててくれ」
杉町はそう言うと、また顔を伏せた。
「俺は今まであの人をだまし続けてきた……」
杉町はうつむいたまま答えた。
「あの人は本当の父親じゃない……俺は金沢で生まれて……3年ほど前だ……進路のことで親と喧嘩になって……夜、家を飛び出して……夜道をあてもなく歩いている時、車にはねられた……その時通りすがりにあの人が俺を助けてくれた……俺はその時、記憶喪失を装った……どうしても家に帰りたくなくて」 杉町の思わぬ告白に僕は言葉を失った。聞けば、杉町の本当の父親というのは金沢でもかなりの資産家という。地元の政治家にも影響力を及ぼすほどの名士で、杉町を政治の世界へ進ませることに固執したという。 「あの人は俺を飯場に連れて行って、本当の父親以上に面倒を見てくれた……もう3年になる……いろいろな飯場を渡り歩いて」
「なぜ、大学が見たいって……」
そのことが気にかかった。杉町は顔を上げて溜め息をつきながら、
「ほんとだったら今頃、みんなと同じように大学に行ってたかなぁって、バカだよなぁ……今さら」と自嘲するように答えた。
「オヤジさんからお前が記憶を失ってるって聞かされた時、なんとなく変だとは思ってた……こう見えても俺は演劇部だ。お前も俺と一緒で芝居が下手クソだ」 僕が、そう言うと杉町は口もとを緩め、微かに笑みを浮かべた。
「クズミ、もう一つだけ頼みがある。バイクをしばらく貸してくれないか」
「どうする」
「金沢に行って……本当の親に会ってきたい……会ってきたらまた飯場へ帰ってくる」
杉町は真剣な眼差しで懇願した。
「必ず飯場に戻ってくる、必ず……。あの人は白内障で目が悪くて、だから俺が傍に付いていてやらないと」
杉町は畳みかけるように、真剣な目で僕に訴えかけた。
「俺はあの人の傍にいてずっと面倒を見ることに決めたんだ。だからその前に一度金沢の親に会っておきたいと思って……」
杉町は涙で声を曇らせていた。 「バイクで……俺はあの人と歩いてきた飯場をもう一度見ながら金沢まで帰りたいと思って」
そこまで言うと、杉町はしばらく黙ったままでいた。杉町の意外な過去を聞いて、胸が重くなった。取り敢えず、その場は杉町の頼みをのんだ。 それから1週間後、杉町は金沢へ向け、朝まだ早いうちに僕のバイクで旅立った。ひょっとしたら僕以上かも知れないと思われるほどバイクの腕前は上達していて運転技術に問題はなかったが、無免許だったので、ばれないよう金沢までたどり着けるかどうか心配だった。1週間もあれば金沢に行って飯場に帰って来れるさ。そう言って、杉町は旅立って行った。 杉町は養父に簡単な書き置きを残して飯場を出たようだった。むろんそれに行き先は書かれてない。たぶん以前僕が沢村の部屋に残してきた書き置き程度のものであっただろう。そのことで、後で養父に行き先に心当たりがないかと尋ねられ、冷や汗ものだったが、バイクが気に入って遠乗りしてみたくなったんじゃないですかと答え、ごまかした。