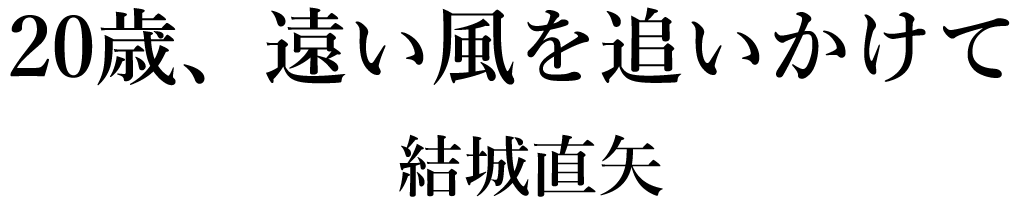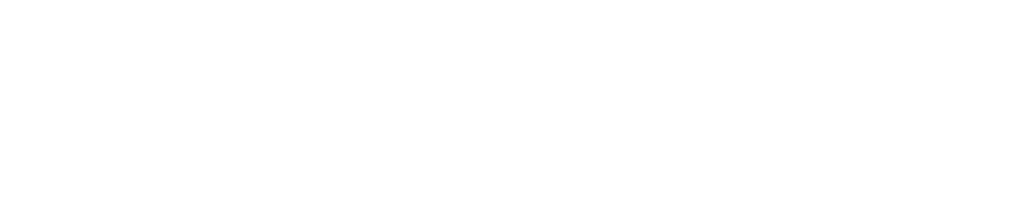No.12 杉町の養父から預かったもの
杉町が金沢へと旅立って、10日が経とうとしていた。日に日に僕は、奴の身に何か起きたのだろうかと不安に駆られた。金沢なら往復で1週間もあれば十分だと杉町は言っていた。
勤務場所にいても1日中、杉町のことが頭から離れなかった。飯場が嫌になり、金沢に留まることにしたのだろうか……両親に泣きつかれ、金沢に居残ったままなのだろうか……まさか途中で事故に会ったのでは……。日増しにそんな思いがつのり、仕事が手につかなかった。
杉町がいなくなって2週間ほど経ったある日のことだった。仕事を終え、部屋に戻ると、隊長から杉町と名乗る老人から僕宛に預かったという茶封筒を手渡された。
封筒は文庫本の一回りくらいの大きさでていねいに糊付けされていた。封を破ると、中に預金通帳と印鑑と手紙が入っていた。通帳をみて驚いた。300万円を超える金額が記帳されていた。急いで手紙を読んでみた。
久住様 健治といつも仲良くしてもらってありがとうございます。
健治がいなくなって2週間が経とうとしています。もしやあの子は自分の生まれ故郷に向けて旅立ったのではありませんか。長い間一緒に暮らしていればあの子の考えていることはわかります。 健治からすでにお聞きになっているかも知れませんが、私は健治の本当の父親ではありません。健治というのも私があの子にかってにつけた名前です。 3年前、金沢で交通事故にあって記憶を失ったあの子に私は偶然出会い、それ以来あの子は私と一緒に飯場を渡り歩いてきました。妻に先立たれ、子供に縁のなかった私にはあの子がまるで自分の子供のような気がして、生きる支えでした。 いつの頃からだったでしょうか、この子は本当は記憶を取り戻してるのではと度々思うようになりました。何かよほどの事情があってそのことを黙っているのではと思いました。一生懸命私の前で演技をしているあの子がふびんで、私はわざと知らぬ振りをしてそのことには触れませんでした。ずっとあの子を手元においておきたいという気持ちがあったのです。 健治がオートバイの練習しているのを見て、もしや里心がついて故郷に帰りたくなったのではと思いました。それも当然かと思います。私と一緒にいつまでも飯場をまわっていてもあの子の将来のためにはなりません。もし健治が故郷に帰りたくなったら私は健治の望むようにさせてやりたいと思っていました。 通帳のお金は健治が学校に行きたいと言い出したら使ってもらおうと思い、今日まで貯めてきたものです。私は無学で飯場を渡り歩く生活ですが、あの子には学校を出て人並みな生活を送ってもらいたいと思います。 たぶんもうすぐ健治は帰ってくるはずです。近いうちに帰ってくるはずです。健治が帰ってきたらこのお金を渡してもう故郷に帰るように言ってください。あの子にはそのほうがいいのです。私はあの子と暮らした3年間の思い出さえあればこれから生きていけます。 杉町久治
手紙を読み終えると、部屋を飛び出し、杉町たちのいた別棟に駆け込んだ。確か、入口から3番目の6畳の部屋に杉町親子と男が一人居住していたはず。部屋のドアは開いたままで、戸口付近には、泥のついた長靴と埃にまみれた作業服やヘルメットが散乱していた。 部屋には誰もいなかった。戸口に座り込み、どうしたものかと思いに暮れた。しばらくして、見かけたことのある40過ぎの痩せた長身の男が鼻歌まじりに帰ってきた。男は部屋の前に座り込んでいる僕を見て、一瞬驚いたような顔をした。
「あの、すいません。杉町さん知りませんか?」
男に詰め寄り、早口で訊いた。
「杉町のジイさん。ちょっと前に、出てったよ。なんでも新しい仕事が見つかったとか言って」
「どこへ行ったか知りませんか」
「さあ、知らねえな」
男は首を振り、怪訝な顔をした。
どうしよう。預かった300万もの大金をどうしたらいい。ともかく、ここにいても埒が明かない。男に頭を下げ、外に飛び出した。 日が長くなり、外は十分遠目がきいた。部屋に戻り、急いで制服を脱ぎ、Tシャツとジーパンに着替えると、自転車に飛び乗った。 今さらこんなことをしても無駄かもしれない。そう思いながらも、柏の駅方面に向けて自転車を走らせた。ねばついたような橙色の光を放つ太陽を追い駆けながら懸命に自転車をこいだ。 バイクばかりに乗りつけていたせいか、いつまでも風景が変わらない自転車にいらついた。こんな時にバイクさえあれば方々を探し回ることが出来たのに。それにしても2週間ちかく経ってもまだ帰ってこない杉町が腹立たしかった。運転事故を起こしたとは考えられない。なにしろ旅立つ前にはすでに僕以上と思われるほどの技量を身につけていた。金沢の親元に留まったままでいるという以外、考えられなかった。 杉町の奴、やっぱり飯場に帰ってくるのが嫌になったか……あのウソつきめ、あんないいオヤジさんを放ったらかしやがって……。 埃にまみれた灰色の作業服に深めのバッグを手に暗い路をとぼとぼ歩いている杉町の養父の姿が頭に浮かんだ。僕のせいかもしれない。杉町と知り合いにさえならなかったら。バイクの乗り方を奴に教えさえしなかったらこんなことにならなかったかも……。遣る瀬なさばかりが空回りした。やけっぱちで自転車のペダルを踏んだ。 雑木林の影が路面に長く落ち、太陽は木々の間に半分隠れつつあった。路の先がどんどん細く狭まっていくような感覚にとらわれた。サドルから尻を浮かし全力で自転車をこいだ。 柏の駅前に着くと自転車をデパートの前に置き、杉町の養父を探した。駅の構内や周辺は通勤の人々で大変な混み様だった。目を凝らし、人波を掻き分け、それらしき人物を探した。夕食をとらないで出ていったかもしれない。 横丁の一杯飲み屋のある通りに駆け込み、ラーメン屋や焼き鳥屋や屋台をのきなみ覗いて回った。通りすがりに、ジャージ姿の体格の良い50がらみの男と肩がぶつかり、一瞬睨まれた。因縁をつけるならどうか明日にしてくれ。僕は男に深々と頭を下げ突っ走った。 幾つ小道に分け入り、どれほど店を覗いただろうか。短めの白髪頭の男を見かけるや、何人に後ろから前に回り込んだことだろう。喉がカラカラに乾き、汗が下着に沁み渡り、足がふらついた。 もうすでに、柏から出ていったかもしれない。走り疲れ、自販機を見つけると、冷たいコーヒーで喉を潤し、しばしそこにへたり込み途方に暮れた。杉町がもし帰ってきたら、何て言えばいいんだ。2人がこうなったのも、僕にも原因がある。キャバレーのかすれた呼び込みの声が虚ろに耳に響いた。しばらくそこにしゃがみ込み、呆然とした。
No.13 帰らない杉町
久住様 健治といつも仲良くしてもらってありがとうございます。
健治がいなくなって2週間が経とうとしています。もしやあの子は自分の生まれ故郷に向けて旅立ったのではありませんか。長い間一緒に暮らしていればあの子の考えていることはわかります。 健治からすでにお聞きになっているかも知れませんが、私は健治の本当の父親ではありません。健治というのも私があの子にかってにつけた名前です。 3年前、金沢で交通事故にあって記憶を失ったあの子に私は偶然出会い、それ以来あの子は私と一緒に飯場を渡り歩いてきました。妻に先立たれ、子供に縁のなかった私にはあの子がまるで自分の子供のような気がして、生きる支えでした。 いつの頃からだったでしょうか、この子は本当は記憶を取り戻してるのではと度々思うようになりました。何かよほどの事情があってそのことを黙っているのではと思いました。一生懸命私の前で演技をしているあの子がふびんで、私はわざと知らぬ振りをしてそのことには触れませんでした。ずっとあの子を手元においておきたいという気持ちがあったのです。 健治がオートバイの練習しているのを見て、もしや里心がついて故郷に帰りたくなったのではと思いました。それも当然かと思います。私と一緒にいつまでも飯場をまわっていてもあの子の将来のためにはなりません。もし健治が故郷に帰りたくなったら私は健治の望むようにさせてやりたいと思っていました。 通帳のお金は健治が学校に行きたいと言い出したら使ってもらおうと思い、今日まで貯めてきたものです。私は無学で飯場を渡り歩く生活ですが、あの子には学校を出て人並みな生活を送ってもらいたいと思います。 たぶんもうすぐ健治は帰ってくるはずです。近いうちに帰ってくるはずです。健治が帰ってきたらこのお金を渡してもう故郷に帰るように言ってください。あの子にはそのほうがいいのです。私はあの子と暮らした3年間の思い出さえあればこれから生きていけます。 杉町久治
手紙を読み終えると、部屋を飛び出し、杉町たちのいた別棟に駆け込んだ。確か、入口から3番目の6畳の部屋に杉町親子と男が一人居住していたはず。部屋のドアは開いたままで、戸口付近には、泥のついた長靴と埃にまみれた作業服やヘルメットが散乱していた。 部屋には誰もいなかった。戸口に座り込み、どうしたものかと思いに暮れた。しばらくして、見かけたことのある40過ぎの痩せた長身の男が鼻歌まじりに帰ってきた。男は部屋の前に座り込んでいる僕を見て、一瞬驚いたような顔をした。
「あの、すいません。杉町さん知りませんか?」
男に詰め寄り、早口で訊いた。
「杉町のジイさん。ちょっと前に、出てったよ。なんでも新しい仕事が見つかったとか言って」
「どこへ行ったか知りませんか」
「さあ、知らねえな」
男は首を振り、怪訝な顔をした。
どうしよう。預かった300万もの大金をどうしたらいい。ともかく、ここにいても埒が明かない。男に頭を下げ、外に飛び出した。 日が長くなり、外は十分遠目がきいた。部屋に戻り、急いで制服を脱ぎ、Tシャツとジーパンに着替えると、自転車に飛び乗った。 今さらこんなことをしても無駄かもしれない。そう思いながらも、柏の駅方面に向けて自転車を走らせた。ねばついたような橙色の光を放つ太陽を追い駆けながら懸命に自転車をこいだ。 バイクばかりに乗りつけていたせいか、いつまでも風景が変わらない自転車にいらついた。こんな時にバイクさえあれば方々を探し回ることが出来たのに。それにしても2週間ちかく経ってもまだ帰ってこない杉町が腹立たしかった。運転事故を起こしたとは考えられない。なにしろ旅立つ前にはすでに僕以上と思われるほどの技量を身につけていた。金沢の親元に留まったままでいるという以外、考えられなかった。 杉町の奴、やっぱり飯場に帰ってくるのが嫌になったか……あのウソつきめ、あんないいオヤジさんを放ったらかしやがって……。 埃にまみれた灰色の作業服に深めのバッグを手に暗い路をとぼとぼ歩いている杉町の養父の姿が頭に浮かんだ。僕のせいかもしれない。杉町と知り合いにさえならなかったら。バイクの乗り方を奴に教えさえしなかったらこんなことにならなかったかも……。遣る瀬なさばかりが空回りした。やけっぱちで自転車のペダルを踏んだ。 雑木林の影が路面に長く落ち、太陽は木々の間に半分隠れつつあった。路の先がどんどん細く狭まっていくような感覚にとらわれた。サドルから尻を浮かし全力で自転車をこいだ。 柏の駅前に着くと自転車をデパートの前に置き、杉町の養父を探した。駅の構内や周辺は通勤の人々で大変な混み様だった。目を凝らし、人波を掻き分け、それらしき人物を探した。夕食をとらないで出ていったかもしれない。 横丁の一杯飲み屋のある通りに駆け込み、ラーメン屋や焼き鳥屋や屋台をのきなみ覗いて回った。通りすがりに、ジャージ姿の体格の良い50がらみの男と肩がぶつかり、一瞬睨まれた。因縁をつけるならどうか明日にしてくれ。僕は男に深々と頭を下げ突っ走った。 幾つ小道に分け入り、どれほど店を覗いただろうか。短めの白髪頭の男を見かけるや、何人に後ろから前に回り込んだことだろう。喉がカラカラに乾き、汗が下着に沁み渡り、足がふらついた。 もうすでに、柏から出ていったかもしれない。走り疲れ、自販機を見つけると、冷たいコーヒーで喉を潤し、しばしそこにへたり込み途方に暮れた。杉町がもし帰ってきたら、何て言えばいいんだ。2人がこうなったのも、僕にも原因がある。キャバレーのかすれた呼び込みの声が虚ろに耳に響いた。しばらくそこにしゃがみ込み、呆然とした。