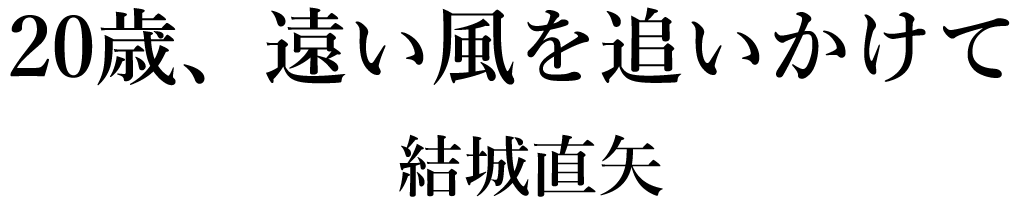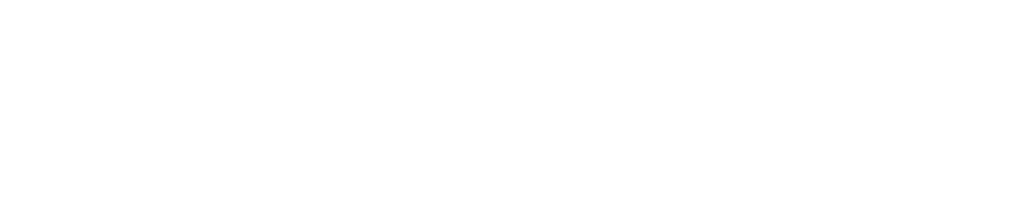No.5 飯場での生活
田牧隊長に2ケ月働くと約束したものの、はたして飯場の生活になじめるかどうか不安だった。
簡素な板張りの廊下には何本も細いビニールロープが宙を這い、そこに洗った下着や泥のついたズボンが無造作にかけられ、その下を足もとのおぼつかない男がペタペタとサンダルでうろつき、真夜中にマージャンの音や花札で遊ぶ声がドアの隙間から洩れてきた。
時おり、「このあぶれ者が」と怒鳴る声が聞こえたかと思うと、悲哀を帯びたネコの鳴き声が耳に届いた。かさついた空気が漂っていた。
初日、僕は木沼さんの横に付いて仕事を覚えた。木沼さんは初印象からはとても想像もできないような手際の良さできびきびと車両をさばき、時に笛をけたたましく響かせ、時に誘導灯を放り投げオーバーアクションでダンプを止めた。
木沼さんの誘導を見ながら半日で大方の要領をつかんだ。さほど難しくはない、が、あなどってはいけないと思った。不注意で誘導を誤ると玉突き事故のような大惨事を引き起こしかねない。機敏な判断力が要求される、一瞬たりとも気が抜けない仕事だ。1日を終えると、いいようのない脱力感に見舞われた。
2日目から1人になった。まだ不慣れということで、隊長の計らいで交通量の少ない裏門の一つを任された。そこはほとんど一般車両が通らず、ダンプの往来に支障がないように、辺りの草木は刈り取られ、地肌は平らにされ、視界が開けていた。
そこから10数メートル離れたところに点在する民家は一様に濃い緑の木々で覆われていた。空はどこまでも青く澄み渡り、平和でのどかなで、見ようによっては物寂しい風景が広がっていた。はたしてこんな所に警備の必要があるのか、と首をひねるほど穏やかな風がサワサワと吹いていた。
が、それでもそこに警備員が立っていないとダンプが我が物顔で横断し、地元のドライバーたちは肝を潰しているという。よく晴れた日にけたたましく舞い上がる土埃もドライバーの目をかすめ危険だと、警備員の常勤を地元から要請されていた。当分の間、僕がそこに立つことになった。
1週間も警備していると、ダンプの往来の回数や一般車両の交通量が大体把握出来た。最初に予想した通りさほど苦ではないとわかった。唯一つらいと思ったことはダンプがほとんど通らないことくらいであろうか。
頻繁にダンプが通ればそれなりに緊張感があって時間が経つのも早いだろうが、なにもすることがなく、つっ立ったままというのも時間ばかりが長く感じられ手持無沙汰でやりきれない。
僕の勤務場所の500メートルほど先に土砂の捨て場があって、その手前のほんの2メートル幅の道の前に川瀬老人が立っていた。そこはほとんど車も通らない山道で、さぞや川瀬さんも退屈で仕方ないでしょうと木沼さんに尋ねると、狸や狐がダンプに引かれないように川瀬さんがしっかり見張り番をしているのだという。
川瀬さんのミスで狸がダンプに引かれた時は狸汁にして飯場のみんなで供養するという。その日は、事務所の幹部も総出で食堂はいかつい男どもが悲嘆に暮れながらも、狸汁をすするという罰当たりな絵図が展開するらしい。
まあ、たぶん嘘だ。今時、公道をぶらつき、あげくにおめおめと釜ゆでにされ、大根や人参と一緒にだし汁にされるような、そんなマヌケな狸はいない。それに、狸一匹のため老齢とはいえ警備員を雇うゼネコンなどどこにいるか。
飯場の朝は早かった。空のしらけた色が窓に映り始めた頃、6時にセットされた目覚まし時計が部屋中に鳴り響くと、田牧隊長が福島なまりのとぼけた声で「朝だよ」と言って木沼さんと僕を起こしにかかった。
が、残念ながら、木沼さんがそれにすぐに反応することはなく、その後しばらく、ひそやかに畳にしみ入る隊長の起床を促すうなり念仏を聞かされるはめになり、次第にそれは地鳴りのようにヒタヒタと畳に沁み入るかのように僕の耳にも届いた。
眠くもあったし、いつまでも布団にくるまっていたかったが、え~い、どうせ起きなきゃならないんだからと観念して布団をはだけ、その勢いをかりて、フラフラと顔も洗わず食堂へと駆け降りていった。そんなふうにして1日が始まった。
朝の6時というと食堂は早出の職人さんたちが5、6人いる程度で閑散としていた。僕は誰にはばかることもなく、心おきなく湯気のあがった御飯を2杯以上軽く食べ、定番の生卵に海苔に味噌汁の付いた朝飯をすきっ腹に詰め込んだ。
6時半頃、部屋に戻ると、ようやく木沼さんが布団から這い出したところで、まぶたを腫らしたしまりのない顔で、正座したまま制服のボタンをかけ、隊長はそんな木沼さんを統括責任者としての威信が地に落ちたとでもいった顔で一瞥していた。
7時には勤務場所にいなければならないため、5分くらいで手早く身支度をして早めに部屋を出ることにしていた。ダンプの誘導の際に必要な棒状の赤い誘導灯を脇にはさみ、白いヘルメットをかぶり、長靴を履き、制服の上に蛍光帯の反射チョッキを身に付け、自転車に股がって勤務地へ赴く。
警備に立ち、30分ほどすると、小学生の一団が幼い声を元気にはりあげて通り過ぎ、その少し後で自転車に乗った高校生たちがほとんど無言で風を切って通り、人通りが途切れ始めると、まるで冬眠から覚めた凶暴な熊のように勢いよく周囲に挨を撒き散らしてダンプが遠方から暴走してくる。
すかさず赤い誘導灯を取り出し、ダンプを道路の手前で一旦止め、左右から一般車両が来ないか確かめ、問題なければダンプを通過させる。中には一時停止がまどろっこしくて、無視してかかる輩もいる。
ダンプに乗っている運転手のほうが僕よりはるかに遠目がきく。だからかってに判断し、道を突っ切ろうとするが、頑としてそれを許さなかった。たとえ、左右に車が全く見えなくともいちいちダンプを止め、杓子定規に左右を確認させてから、横断させた。運転手にしてみればいい迷惑だ。よほど融通の利かない新人が入ったものだと思ったことだろう。
どこの世界でも、古株は新参者ににらみをきかしたいものだ。手のうちに納められたとなればこけんに関わる。遥か彼方まで見通しの利く、だだっぴろい野原は一触即発の抗争の様相を呈した。
時々、背中すれすれのところまでダンプを止めないでいたり、ひどいのになると僕の腕がぶつかっても平然とし、道路に乗り出したところでやっと止めるといった連中もいた。そうなると頭にきて、誘導灯など打ち捨て、わざと体を前のめりにし、ダンプを急停車させた。まるで人柱だ。失恋で果てしなく増幅した捨て鉢の気性がこんなところで露わになった。
運転手にすれば、まるで非日常的な尋常ならざる光景だ。「てめえ、引き殺されてえか」という声がたまに僕の耳に届いたが、何食わぬ顔で過ごした。失恋の痛手を癒すにはこれぐらいがちょうどいい。
まさか、運転手も、身を焼き尽した恋に破れた男が、こんなうら淋しい野っ原で腹いせに赤い棒を振り回し、体を盾に嬉々としてバイトにいそしんでいるとはよもや知るまい。失恋だろうが何だろうが、いつかどこかで役に立つものだ。
さすがにそんなことが何度かあると彼らも僕の偏屈さにあきれ、それからは誘導灯で指示など出さなくとも、自発的に一時停止するようになった。たぶん僕を見ながら、自暴自棄だとか、何も失うものがない男ほどやっかいなものはない、という言葉でも思い出したに違いない。
そのことを木沼さんに話すと、「新人はみんな遊ばれるからね」と言い、「中には正真正銘怖いおにいさんもいて下手につっかかるとボコボコにされかねないよ」と僕をさとした。が、そうはいっても事故になれば、当然大型車に非が問われる。身を呈して彼らを守っているわけで、連中に因縁をつけられる覚えはないと僕は開き直った。
1日の仕事が終わるのが夕方の6時で、その1時間くらい前になるとダンプの往来もぐんと減ってくる。僕はその頃から今日の晩飯のおかずはなんだろうかと思いを巡らし始める。飯場は工場と原っぱに囲まれた人里離れた所にあって、周りに遊び場があるわけでもなく、楽しみといったら食事くらいしかない。
仕事を終え、飯場に帰り着くと、隊長にその日の状況を簡単に報告し、それを終えると一目散に食堂に駆け込む。
夕食を終え、部屋に戻ると、木沼さんからミュージックテープを借りて聞いたり、皆で画像の不鮮明なテレビを見たり、風呂に入ったりして過ごし、10時頃になると布団を敷いて床に就く。そんなふうにして飯場での日々を過ごした。
No.6 金は無くとも休日は楽し
夕食を終え、部屋に戻ると、木沼さんからミュージックテープを借りて聞いたり、皆で画像の不鮮明なテレビを見たり、風呂に入ったりして過ごし、10時頃になると布団を敷いて床に就く。そんなふうにして飯場での日々を過ごした。