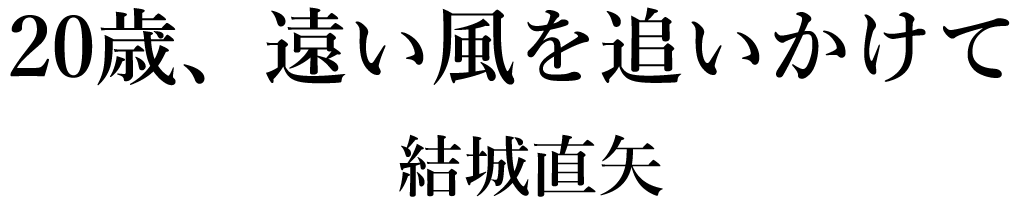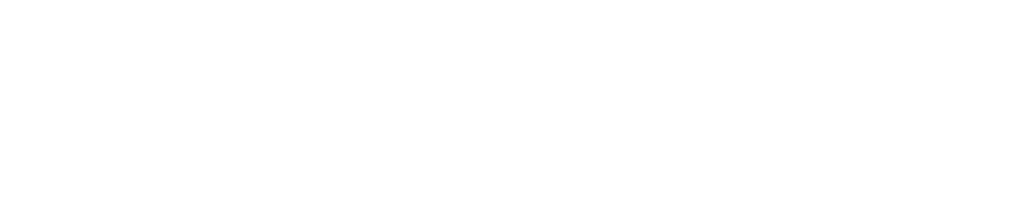No.6 金は無くとも休日は楽し
週に1度の休みの朝、「今日は何をしようかな」と木沼さんはきまって僕に暇のつぶし方を尋ねる。
「朝から飲みに行くわけにもいきませんから、飯を食って 1日中寝てるってのはどうですか」
ふざけて僕が言うと、
「そんなふうじゃあ、人間がだめになるよ。クズミくん」
木沼さんはきまってそう言う。 ふだんの木沼さんからはまるで想像もできない返答に返す言葉もないが、まだ給料を手にしてない僕はせいぜい休日でもやっている飯場の食堂でただ飯を食い、日頃の疲れを癒すために横になっておとなしく寝ているか、バイクの手入れでもしているしかない。 僕より2つ年上の木沼さんは年齢がちかいこともあり話がよく合った。度を越した酒好きと半月に1度しか風呂に入らないことが難点だったが、心ねの優しい人だった。 休日は田牧隊長が部屋にいないせいか、木沼さんは1日中晴れやいだ顔をしている。隊長がそこに居合わせたら、さぞや木沼さんの普段とちがう相好に驚くに違いない。全く、春の陽気に顔を出したモグラと一緒で、腰が落ち着かない。 田牧隊長は休みの前の晩から、奥さんと来年受験を控えた中学3 年生の娘さんの待つ土浦にあるまだローンの支払いがかなり残っているという一戸建ての家へ帰る。週に1度のそれが唯一の楽しみのようで、時折日報を書く手を休めては、机の上に置かれた家族の写真に目を細めている。 「隊長の奥さんって、奇麗な方ですよねえ」そう僕が言うと、ふん、と木沼さんは鼻を鳴らすようにして、
「隊長はああ見えてもけっこう強引なところがあるからね」と言ってのけた。
「つきまとったとか、いわゆるストーカーっていうやつですか?大雪の日に一晩中花束かかえて、玄関の前に雪だるまのように立っていたとか」カール隊長も、たぶんやる時はやる。
「ちかいね。なんでもね。僕は君と結婚したいとか言って、台風の日を狙って、家を訪ねていったらしいよ」
かなりの知能犯だ。大雨でぬれ鼠になった男を、無碍に追い返すこともできない。とりあえずは、家に上げるだろう。そういえば、セールスマンの成約率もそういった日のほうが高いと何かで聞いたことがある。訪問先もあらまあ、こんな日に、と同情するだろうし、外出もできないから、じっくり話に耳を傾ける。
「そいでね、電話も毎日決まった時間にやったらしいよ」思い出したように木沼さんが言った。
「それ、何かの恋愛マニュアル本で読んだことがありますよ。毎日来ていた電話がたまに途切れると、不安になって、気にかけるようになるってやつでしょ」あのカールおやじも中々の策士だ。 隊長の若い頃は、ストーカーなどという言葉はまだ無い。「男は押しの一手」というような言葉を胸に、鼻息も荒くせっせと通い詰めていたに違いない。今時は、携帯に毎日求愛のメッセージでも送ろうものなら、変態ストーカー男からのセクハラメールの物証として当局に差し押さえられかねない。だいたい、携帯などという直截的なデジタル文化が男と女の古き良き慣習まで粉々に打ち砕いているのだ。 「ストーカーって、なんか暴走車みたいな響きでいいよね」あくびをしながら木沼さんが言った。
「英語で、しつこくつきまとうって意味らしいですけどね」一体、いつからこんな言葉が日本中に広まったのだろうかと思う。全く、ストーカーなどという余計なメディア用語が浸透したおかげで、男どもの腰がひるみ、果ては晩婚化を招いたとしか考えられない。 隊長のような、台風の日にまで通いつめる男などストーカーの鏡のような御仁だが、これを女性が「なんて熱心なお方」と心和ませるか、「ストーカー」として身を強張らせるかは、メディアでコントロールされた心象で、全て裁断されるというものだ。 「ストーカーって、昔は女の尻を追いかけ回すとかって言ってたんでしょ。僕はそっちのほうが臨場感があっていいな」そう言って、僕は新聞の番組欄を見ながら、TVのスイッチを押した。といっても、ニュース番組で正統派美人キャスターが顔色ひとつ変えず、『ここ1年ほど、雨の日も風の日も、女の尻をしつこく追いかけ回していた男が遂に逮捕され、西葛西署に連行されました。現場に春日アナウンサーがいます。春日さ~ん、女の尻ばかり追いかけ回していた男の現在の様子はどうでしょう。やはり反省の色が見られないでしょうか』などと報道する絵柄というのもまた悩ましいものだ。日本中の男どもは虚空を仰ぎながら何を思うだろう。 「だけど、隊長みたいな人がじっと家の前にいたら、どうする、クズミくん」
「まあ、気持ち悪いでしょうね」
僕が若き日の隊長の奥さんだったら、豪雨の中で傘もささず立ちすくむ口の周りを黒々とさせた風采のあがらない挙動不審な若い衆を見た日には、即座に警察に通報し、しょっぴいてもらうけれど。
「今は、なんでも携帯ですからね。なんか雰囲気がないですよね。隊長の頃のように、相手の家に電話かけて、もしかしたらむこうのオヤジかなんか出てね、うちにはそんな娘はおらんが、どちらへおかけですかなんて、どやされたらどうしようかってハラハラするのもいいもんなんですけどね、スリルがあって」
「でも、メールは楽だもんね」そう言うと、木沼さんは、傍においていた自分の携帯を手にとり、待ち受け画面の掘北真希をしげしげと見つめた。
「木沼さん、携帯のメールなんかよりね、伝書鳩に愛のメッセージでも付けて飛ばしたほうがよっぽど乙女心をそそるってもんですよ」
僕は携帯文化なるものがどうも肌に合わない。どんなものでも手のかかった物ほど感動も大きい。女性から見てどれほどキモい木沼さんだって、伝書鳩でも放てば、イギリスの霧深い城に幽閉されていた眉目秀麗の王子様から、海を渡って来たのかしらん、とでも勘違いされるに違いない。 「クズミくんもね、ストーカーでも何でもやって早くいい子を見つけなきゃね」目の端に笑みを浮かべ、同情でもするかのように木沼さんが言った。 女の影もない木沼さんにそんなことを言われる筋合いはない。
「たぶん、女性はね、コツコツ、ジワジワ迫られると弱いんですよね。僕も隊長を見習って頑張りますよ」と僕は返した。とはいえ、すでに人妻となってしまった由里先輩にちょっかいを出すことは人の道に外れるというもの。 今頃、不動産屋の跡取り息子の大バカヤローの手が由里さんの白い肌に伸びているかと思うと、この鬱憤をダンプ連中にどうぶつけてやろうかと腹の底から力が湧いた。不動産屋のぼんくら男には「今でもあなたのことを心からお慕いしております。私を捨てたことを、一生お怨み申し上げます」とでも書いた恋文を伝書鳩の足に赤い糸でしっかりくくりつけ、確実に京都の嵐山まで届くように5,6羽放ってやろうかと思った。 休日の隊長のもう一つの楽しみは競輪場通いで、これまでにかなり金を注ぎ込んでいるらしい。世界中で嫌煙の嵐が吹きまくっているというこのご時世に、まるでむさぼり食うようにタバコを吸いながら、鬼のように競輪のことを語る。放っておけば、一晩中でも、しゃべっている。 僕は、最近はどこいっても喫煙者が締め出され、白い目でみられるのがうっとうしくて20歳になった記念にタバコをやめようかと思っていて、隊長、タバコは隣にいる人のほうが結構被害が大きいとかいわれてんですけど、副流煙とかって、どうなんですかと聞くと、クズミくんね、タバコは20歳になってから正式に吸うもんでしょ。それにあんなものは自動車産業の陰謀でね、排気ガスを吸ってるほうがよっぽど肺にくるんだから、と吸殻で山となった灰皿を見ながら平然としている。 いつだったか、それじゃ、隊長はタバコと排気ガスのダブル攻撃で大変じゃないですか、と言ったが、まあ、あんなものは、個人差だからね、とまるめこまれてしまった。
「隊長、今頃戸田の競輪場でも行ってんじゃないですか」僕が言うと、
「また、負けてるよ」くしゃみをしながら木沼さんが答えた。 隊長は3年前に50万近く儲けたが競輪場に通いつめた10数年間に負けた金額はそんなものに比べようもなく、家のローンの支払いにまわせばよかったと後悔していて、僕や木沼さんには賭け事なんかやるもんじゃないと忠告するがどうやら当人は辞めるつもりは毛ほどもないようだ。競輪は仕事への英気を養うためにどうしても必要な息抜きだと言って涼しい顔をしている。 隊長はなかなか愉快な人だった。飯場に来て、3週間ほど経った頃、休みの前の晩に隊長に誘われ、木沼さんと3人で国道から少しばかり離れた所にある「小雪」という一杯飲み屋に行ったことがある。 10人も人が入ればいっぱいになるような小さな店で、縄暖簾をくぐると、小股のきれあがった和服姿の美人の女将さんが、カウンターの中で1人できりもりしていた。
「あら、お久しぶり」と女将さんが隊長に声をかけると、「いや~、商社は海外出張が多くてね、やっとアイダホの農家と大豆の栽培契約をしてね」と、どうみても商社マンとはほど遠い麦わら帽子のよく似合う隊長が、やにさがった顔で答えた。 隊長は自分だけ串と熱燗を頼むと、僕と木沼さんに、おしんこを好きに頼んでいいからと言い、熱燗をぐいぐいやり、僕の隣でタバコを吸いまくり、鼻から副流煙をたなびかせた。 30分ほど僕らは、飯場の朝飯には調理人らの熱意が全く感じられないだの食堂主任の角さん(エラがはった顔をしていたからそんなふうに呼んでいた)は40半ばで嫁さんをもらわず、もしかしたら男色かもしれないなどと、どうでもいいようなことをぐだぐだと真顔で話した。 そのうち、客が一人二人いなくなって、カウンターは飯場組3人衆だけになり、女将さんも、僕らの話にのってきた。近くでみると、淡い蛍光灯に照らされたうなじがぞくっとするほどなめらかで、どこかで会ったような気がすると思ったら、隊長が机の上に置いていたCDジャケット、そうあの写真の美人歌手、若き日のあべ静江によく似ていた。なるほど、それでここにやってきたわけだ、と僕は得心した。女将さんは40前くらいに見えた。もしかして、シーちゃんとでも呼ばれているのだろうか。 「ぼくらはダンコンの世代って呼ばれてるけど、今なんかよりよっぽど良かったんだから。イチゴ狩りはあったけどオヤジ狩りなんてのはなかったしね、シーちゃん」かなり酒が入って、顔から湯気でも立ち昇りそうな隊長が女将さんのうなじをうっとり見つめながら言った。何が良かったのか知らないが、遂に出たか、エロおやじのシモネタギャグが、多分、ダンコンというのは男の根と書くのだろう。けっ、酒がまずい。それに、案の定、女将さんはシーちゃんと呼ばれていた。 「あら、や~ね、タヌマさん。ダンコンだなんて、ダイコンでしょ、いまよそいますから」と、さすがに客あしらいに慣れているシーちゃんは小皿を手に大根を竹輪やらがんもどきと一緒に盛り、隊長の身の毛もよだつシモネタに頬を赤らめるわけでもなく、如才なくかわした。 「オキツグじゃないよ、ぼくはタマキ、タマキ、、、タマキンじゃないよ」と言い、ガアハハと隊長が笑った。あんたら二人でいつまでもそうやってるといい。ダンカイだろ、ダ・ン・カ・イ。隊長の隣で、僕は遂に我慢ならなくなって、「もしかして、ダンカイですか」と訊いた。すると、隊長が、「そう・・・」と言い、一拍長く置いて、「・・・とも言うね」と答えた。まあ、本当に腐りそうなほど長い溜めだった。木沼さんが隊長のいない時に、タマキではなく、タヌキ隊長と呼んでいるわけがわかったような気がする。 「隊長さんって、いつもこうなんですよ」シーちゃんが、しれっと言うと、「職場だとね、セクハラになりますから。かんべんしてください」と、木沼さんがぐるぐるまなこで横からろれつの回らない口をはさんだ。と言っても、職場には、食堂に野太い声のパンチパーマのおばちゃんが3,4人いるくらいで、むしろ僕としてはパワハラの脅威さえ背後で感じるくらいなのだが。セクハラなどしようものなら待ってましたとばかりに羽交い絞めにされかねない。 「でも、こちらの方、ちょっと藤岡弘、さんの若い頃に似てらっしゃるわね」とシーちゃんが僕に流し目を送った。
「藤岡弘、って、仮面ライダー1号の人ですか」と僕が言うと、
「そう、かっこよかったのよね~。私の憧れの人」
あべ静江似の女将さんにそう言われて悪い気はしなかったが、隣で隊長があからさまに面白くなさそうな顔をしていたので、明日急に勤務場所をハードな所に変えられてもまずいと思い、僕もダンコン世代のエロ話に加わるしかないと腹を決め、こんな話をした。 「僕と木沼さんがね。自転車で飯場に帰る途中に、高校生の一団と出くわしたんですけどね。中にズボンをずり下げてゾロゾロ歩いてる連中がいて、木沼さんが、『あれは、ウンコでも、もらしたんだろうか』と聞くんで、『いや、そうじゃなくて、あれはですね、けっこういい物を持っていて、重くて歩くたびにズボンがずりさがるんですよ』と言ったんですよ」シーちゃんには大受けで、笑いが漏れないように、口の辺りに白い可憐な指を当てていた。 横で、隊長がまたよせばいいのに、「そうだよね~。ぼくらの頃はね、コカンがヒイヒイ言うくらいに、ズボンを上げて、ついでに上げ底のブーツまで履いて、1ミリでも足を長く見せようとね、もう涙ぐましい努力をしたんだけどね」と口をはさんだ。 となりで木沼さんはどうでもいいような顔をして、やってられねえや、そうやって死ぬまで話してろ、といった顔できんぴらをつまみながら熱燗を手じゃくで浴びるように飲んでいた。 僕は酒の酔いにつられ、「でも、本当のところはですね、隊長。彼らはあそこに、武器を隠し持ってましてね、日本が攻められた時には、決起しようと日々備えているんですよ。彼らにしてみれば戦闘服みたいなもんでね。感心な奴らですよ、全く。まあ、見たことはありませんがね」と珍説を展開した。 すると、すかさず「水鉄砲かい」と隊長。が、何と言われようが、「ここだけの話ですが。公安もね、あそこに目を光らせているらしいですよ」と僕は自説を曲げなかった。公安と聞いて、一瞬、角棒を振り回していた頃の記憶がよみがえったのだろうか。「股ぐらをかい」と隊長。しばらく、溜をおいて、さとすように「そう」と僕。シーちゃんは始終笑いをこらえながら、この3バカトリオを早く帰らせてお開きにしなきゃというような顔をしていた。 くだらない話ばかりだと男っぷりが下がるとでも思ったのか、急に隊長が話題を変え、「でも、女将さんもずいぶん痩せたよね」と訊いた。
「聞いてくださいよ、タヌマさん、これに150万もかかったのよ」だからタマキだって、この女将さんも、よっぽどタヌマオキツグを日本史で暗唱させられたんだろう。隊長は、タヌマだろうが、タマキだろうが、タヌキだろうが、はてはタマキンと呼ばれようが、もうどうでもいいような顔をして、僕のとなりでつっぷして寝ている木沼さんに、だらしねえぞ、とか声をかけていた。 僕は、女将さんに、「ダイエットの機械とか買ったんですか?」と尋ねた。女将さんは、この3人の中じゃ、まあ、このおにいちゃんが一番まともに聞いてくれそうだわ、といった顔で、とつとつと話し始めた。 聞けば、150万で高価なダイエットマシーンを購入したわけでもなく、ダイエット食品をセットでしこたま買わされたわけでもなく、ご主人が糖尿病で入院したり、店をしばらく閉じたりしていて、150万ほど欠損が出て、食費や衣類の出費を極端に抑えたらしい。おそらく心労も重なったのだろう。それまでどんなに涙ぐましいダイエットをしてもびくりともしなかった体重が、1年間で20キロ近く減ったという。 それはつまり、150万の欠損金のおかげというわけだ。20キロ減量で女っぷりがあがれば、また隊長のような鼻の下をのばした輩が店に群がることだろう。 こういうのを、捨てる神あれば、拾う神あり、というのかどうか知らないが、なるほどダンコンの世代というのは、転んでもタダでは起きないしたたかな連中なのだと僕は得心した。 帰りしな、隊長と木沼さんを両脇で支えながら、それにしても綺麗な女将さんだった、店先に塩でも撒かれていなければいいがと、夜空にくっきり映えた三日月を見ながら千鳥足で飯場に帰り着いた。
ごろりと横になり、開けた窓の隙間から入り込む暖かな日差しにうとうとしていると、「今日飲みに連れて行ってあげようか」と木沼さんが声をかけてくるが、「金ありませんよ。自慢じゃないですけど。一銭もないんですから」と僕は念を押す。 飯場に来て、1週間ほど経った頃、金が無いのも何かと不便だからと、隊長が5,000円ほど貸してくれたが、とりあえず街に出て、下着を買い、ガソリンをバイクに詰め込み、腹を満たした。
「だいじょうぶ、そういう人の為にツケのきく所があるんだから」
木沼さんの言う、そういう人というのが妙にひっかかって、
「まさか、あのシーちゃん女将の店ですか、あそこはいくらなんでもまずいでしょう。隊長に知れますよ」
「もっとね、いいとこがあるんよ」金のない木沼さんの行き着けの店となると、たぶん、と思い、「その辺の野良猫の頭の煮込みとかでるんじゃないでしょうね」と言うと、「鼠の串焼きもでるよ」と木沼さんは言い、口元からよだれを垂らしそうにして笑った。 僕は、「粛々と寝ます」と言い、それを無視した。「粛々」というのは、「静かに、おごそかに執り行う」という意味だが、ある時、TVのニュースで、政治家が「法案の成立に向け、粛々と行う」とインタビューに答えていて、その語勢に、何か強行採決でもやるかのようなヒタヒタとした執念のような凄みを感じて、やけに可笑しかったので、しばらく僕は、「粛々とメシを食べてきます」だの「粛々とトイレに行ってきます」だのと使い回していた。 ついでに、言葉のことで思い出すことがある。僕が大学1年の頃の話だが、グラントというコロラド州ののどかな町からやってきたアメリカの交換留学生が沢村の高輪の実家に3カ月ばかりホームステイしていた。気の良い奴だったから、上野だの浅草だの東京の名所を案内した。 グラントは僕と同い年で、背丈もほぼ同じくらいだったが、さすがにジャンクフードで培った腹はでっぷりとして、ジーンズもパンパンに張り、肩も背中も腕もそこいら中から肉汁が絞り出そうなほど脂肪がたっぷりのっていた。おまけに顔はそばかすだらけでブヨブヨと白く、眼と鼻が顔の真ん中で小さく座り、はっきりいってキモかった。日本で言うところのオタクフェイスだ。 そのグラントをここが日本が世界に誇るオタク文化の発祥の地だといって、秋葉原に連れて行ったことがある。いやいや、全く、奴ほど秋葉原が似合う外人もいなかった。完璧にアキバの空気に馴染んでいて、リュックを背負った体を丸め、熱いおでん缶をフウフウすする姿など妙に哀愁を誘うものがあった。アキバに来たついでにと、ラオックスのパソコン館の脇を入った所のメイド喫茶につれていった。 店の中は学園祭の延長のようなもので、ゴシュジンサマオカエリナサイマセの一斉連呼が響き渡り、メイド服姿の胸の谷間の深い八重歯の可愛いいありさちゃんがグラントの横にぴったり座り、おしぼりのサービスで奴の顔に浮き出た脂をふきとると、奴は顔中の皮膚を緩ませ、やにさがっていた。 で、その後が大変だった。ありさちゃんの過剰なサービスにメロメロになったのか、はたまたメイド喫茶をワビサビの日本文化と勘違いしたのか、帰りしな何を思ったか、道行く人々にゴシュジンサマ、ゴシュジンサマと声を掛けまくり、うかれまくっていた。一緒に歩いていると、これがまたうっとうしくて、要するにウザかった。 それで、グラントとかなり親しくなった頃に、ゴシュジンサマもオトノサマもキモイもウザイも同じようなもんだからと、冗談で、いやあ、グラント、今日もキモイね、と言ってやった。 すると奴は、その言葉の意味がわからず、ナンデスカソレ、と聞いてきた。それで僕は、「キモイ」というのは今時の日本の女子高生の間で流行っている最上級の褒め言葉で「あなたのためなら死んでもいい。この身をささげたい」という意味だ。ついでに、「ウザイ」というのは、「あなたのような美男子はこの世に二人といない」という意味だと言ってやった。 それから僕は、グラントに会うたびに、やあ、グラント、相変わらずキモイねえ、今日のそのストライプのシャツいいねえ、ベリーキモイよ。それにチョ~ウザイよ、とニコニコしながら言ってやった。もちろんグラントもホクホク顔だ。たぶん、これまでの人生で、「あなたのためなら死んでもいい」などと言われたことはないだろうから。ただ、男からそんなことを言われてもちょっと気色悪いだろうが。 ともかく、僕はグラントがアメリカに帰る1カ月くらいの間、日米友好親善のつもりでずっとそれを通した。相手が喜んでいる顔を見るのは楽しいものだ。そんなことで喜ぶのなら幾らでも連呼してやる。 たまに、グラントがニヤケ顔で、「ヌード、ヌード」とささやけば、両国に連れて行き、たいそう肥えた男たちがまわし一本で抱き合うところを飽きるほど見せ、帰りに駅前のおたふく食堂でタンメンをたらふく食わせてやった。 ところが、ある日、このオタク系アメリカ人が、2ちゃんねるの掲示板に、キモイだのウザイだのとかなり書き込まれているのを見て、ナゼデスカ、ウラサイトって何ですかと不思議がった。 そこで、僕は、自信たっぷりに、あれは祭りって言ってな、若い人たちはね、小さい頃から、あなたキモイだのウザイだのと言い合っては、民族意識を高めあっているのよ。若い人っていろいろあって大変なのね。だから、あなたキモイ、おめえウザイって、みんなで褒め讃え、励ましあって、互助の精神を若い頃から培っているわけさ。 なんてたって、資源の乏しい国で、食糧自給率もどんどん下がってんだから。それでも頑張ってやっていきましょう、さあ、あなたも、きみも、そこのコンビニの前でうんこ座りしてるバカヤローも、振り込め詐欺やってる連中も、ついでに新橋で焼き鳥つまみながら給料上がらねえってぼやいてるサラリーマンも、みんなで手を取り合って、サウンドオブミュージックみたいに、明るく生きていきましょうって。な、ステキな国だろ、日本ってのは、と吹いてやった。 そんなふうだったから、グラントは1カ月ばかり僕からキモイだのウザイだの言われて、もう脳からβ―エンドロフィンだのドーパミンだのセロトニンだの脳内麻薬物質が溢れ出て、恍惚感に浸りきっていたに違いない。といっても、僕に好意を寄せられても困るのだが。 一つ心配だったのは、アメリカに帰って、キモイだのウザイだのの意味を知って、僕のことをロクデモナイニホンジンと知り合いになったと思われるかもしれないということだったけれど。 でもね、グラント、言葉なんて、そんなもんだから。言葉ひとつでブルーになるより、間違って覚えてハッピーになるんなら、そっちのほうがいいってもんさ。 ついでに、もう一つ僕が心配しているのは、メイド喫茶のありさちゃん似の日本の女子高生がアメリカに行って、コロラドでグラントに会って、クラスメイトに奴のことをキモイだのウザイだとささやいた日には、それこそ奴は花束抱えて、ハリケーンだろうが竜巻だろうがおかまいなしに、女子高生を追い掛け回し、ストーカー道をまっしぐらに突き進むんだろうな、ということだ。
僕は、目を閉じ眠ったふりをして、ほんの少しの間、鼠の串暁きは焼き鳥に近い味なんだろうかと想像した。木沼さんはよほど猫の頭の煮込みが可笑しかったのか笑い呆けていた。 「そんなにおかしいですか。猫の頭が」
そう言うと、木沼さんはさらに手を叩いて笑い、それが部屋中に響くような笑い声だったものだから、休みの日になると隣の部屋で読書にふけっている川瀬老人のことを思い出し、「あんまり笑うとうるさいって、川瀬さんに言われますよ」と小声で言った。 川瀬さんは今年で68才になる。本好きで、休日になると部屋に籠もり読書に明け暮れていた。好みの本も歴史から精神世界まで多岐に渡り、風呂場でたまに一緒になると川瀬さんから司馬遼太郎の『坂の上の雲』の何ページ目がどれほど感動的だったかなどとよく講釈を受けた。 ある時、部屋でTVを見ていると、「あんたさ、将来何か目標あるのか」と川瀬さんに訊かれたことがある。ちょうどその時、就職活動に奔走する学生達の企業訪問の様子を放映していた。学生達は面接試験に出そうな想定問答を完璧に頭に叩き込み、上場企業の内定を3、4つ取っただのと誇らしげにしていた。僕もあと2年後には彼らと同じような状況に置かれることになる。と言っても、僕には、どういう職種についたらいいのか、いまだ漠然としていた。 番組では、大方の学生達が「経済的な安定」を一番に掲げ、当然のように、大手企業を優先的に選んでいた。職種はまるで違うのに、ただ上場企業だからと順に面接を受け、内定を取り付けたとほくそえんでいた。そんでもって、六本木あたりで祝勝会だと浮かれ騒いでいる。よくよく考えると不思議な光景だった。タイタニックだって沈む時は沈む。何を根拠に大手を選び、さして本意でもない仕事をやらなきゃいけない。 僕がそんな顔をしていると、隣で川瀬さんが、「わしもあんな頃があったけんど、病気で全部パーだ」とぼそりとつぶやいた。川瀬さんは東北の出身で、若い頃は秀才の誉れも高く、周囲から将来を嘱望されていたという。 「若い頃、大手の証券会社に入って、会社に大損かけて、病気になって、あんたみたいにバイクで旅に出たさ」川瀬さんはぽつりと言った。隊長と木沼さんもTVを見ながらそれをぼんやりと聞いていた。あいにく外は雨降りで、4人で湿った部屋で酒をちびちび飲んでいた。カップラーメンを口にしながら、川瀬さんはいつになく饒舌だった。メガネの奥の細い眼が心なしか潤んでいるようにも見えた。 「ひどい鬱になって、病院行って山ほど薬さもらって、どんどん頭がおかしゅうなって、もうどうにもならんようになって、もう死んでもいいと思って、昔好きだった彼女と見た美瑛の富士の日の出をもう一度みたくなって、薬を全部捨てて、バイクで旅に出て、、、ほんとに目の覚めるような朝日で心が洗われたさ、帰ってきたらすっかり病気も治ってたけんど、会社は利用価値のない人間だとワシをゴミのように捨てた。冷たいとこだっちゃ」 川瀬さんは名の知れた国立大を卒業していた。当然エリート街道をまっしぐらに歩むはずだった。どこに落とし穴が待ち受けているかわからないものだ。会社が潰れなくても、自身が病気で潰れたらそれで終わりだ。 たぶん、会社にではなく自分に寄って立つべきだということを川瀬さんは言いたかったのだろう。「会社に面倒をみてもらうっていう根性じゃだめよ。会社の面倒を見てやるぐらいじゃないと。会社も契約で人を雇って、いつでもクビにすんだから、人も会社を契約で雇ってるぐらいに考えて、いつでも見限ってやるくらいの根性じゃないと」そんな事も言っていた。 年齢の割にはかなり先鋭的な個人主義のアングロサクソン的な考え方だが、グローバリズムに席捲された世界ではそうとでも考えなきゃやっていけないかもしれない。 改革か改悪か知らないが、労働者派遣法が改正され、大幅に規制緩和されたおかげで僕らはある日突然、グローバリズムという名の市場原理主義の渦の中に放り込まれた。企業はこれ幸いと、人件費のカットのために派遣を多く雇い入れ、今では社員の3人に1人が非正規社員といった有様だ。 特別賞与も保険もない派遣は、非人間的な扱いでこき使われ、ワーキングプアなる言葉も生まれ、明確な階層社会が現出した。将来に希望を持てない連中は刹那的なゲームに埋没し、果ては現実の世界をバーチャルにシュミレーションし、ゲーム感覚で詐欺を仕掛ける輩まで現れた。 企業ばかりか派遣を生業とする連中にまで搾取され、労働者は貧困というループから中々抜け出せないでいる。あれよあれよという間に日本は貧困率でアメリカに次いで第2位になってしまった。 グローバリズムというのはとりわけ狩猟民族の論理で動いている世界だ。世界中に拝金が巣くい、全てが生産性という物差しで計られ、貨幣価値に転換できない人や物は容赦なく片隅に追いやられる。日本は農耕民族だからなどといっていられない。ネットでワンワールド化はさらに加速し、中国だのインドだのロシアだのと個々人が能力を競い合う、大競争時代となる。 これからどう生きていけばいいのか、川瀬さんに聞いてみたかった。僕は大学では経済を専攻したが、はたして、"人に幸福な経済論"があるとすれば、一体どういうものなのか尋ねてみたかった。川瀬さんは挫折し、ドロップアウトした、いわば反面教師のような存在ではあるが、著名な経済学者や政治家の話よりはまだ耳を傾ける価値があるかもしれない。 だいたい、彼らの提唱する近代の経済論がもう少しまともなものだったら、世界はもっと貨幣と共存した幸福なものになっていたはずだ。世界的な食糧危機が迫っているにも関わらず、貴重な食糧をバイオ燃料に使い、世界各地で食糧の奪い合いが起きているというのに、一方で、食糧相場を恣意的に操作し、株の投機に明け暮れている。 「株の博打」で濡れ手に泡の巨利を手にした博徒らを、メディアは「勝ち組み」と讃えるが、彼らは足下が薄氷なのを誰よりも知っている。満たされた物欲の代償に闇のような深い不安を抱え、憑かれたように株の仕手戦に奔走する。そうしたいびつな世界の構築に手を貸してきた経済論だ。「種銭作って、株の投機で一山当てろ」といった株成金長者がのたまる話はもう聞き飽きた。 ある時、川瀬さんの警備している現場に缶コーヒーを持って行ったことがある。そこは確かに木沼さんから聞いていた通り、ダンプが横断するためだけに存在しているような小道で、人通りもまばらだった。空気がひんやりとして、木漏れ日が気持ち良かった。捨てられた土砂が辺りに山のように盛られ、時折、乾いた土埃が煙のように舞っていた。 「もう、昼時ですからね、ご飯にいきましょう」木陰にぼんやりと立ちすくむ川瀬さんの後ろ背に声をかけ、缶コーヒーを差し出すと、川瀬さんは少し驚いたように振り返り、「ありがと」と小さく言い、薄くなった白髪の頭を軽く下げた。 二人で傍にあった大きな石にもたれかかり、缶コーヒーに口をつけた。僕は、2,3日前からダンプの行き来が急に増えたことを話題にし、見掛けないダンプや車両がゲート前に滞留していることを話し、その後、おもむろに、「若いもんはこれからどうやって生きていけばいいですかねえ」と、少しため息まじりに川瀬さんに訊いた。 川瀬さんはそれにすぐ答えることはなく、しばらく空を仰ぎ、自身の人生を反芻するかのようにしていた。そして、ぽつりと、「やりたいことをやればいいっちゃ」とつぶやいた。その後、川瀬さんは何も語らず誘導灯とヘルメットを手にして帰り仕度を始めた。 僕は川瀬さんの言葉を噛み締めながら、薄暗い林道を飯場へ向かって歩いた。道すがら、川瀬さんは「好きなことは、本当の自分が出せるちゃ」とも言った。好きなこと?何か、本心から満足の得られるもの、生きている実感のようなものが得られるものを見つけろと言っているのだろうか?木漏れ日の道を歩きながら、半生を振り返った。まるで、ギリシャ時代の哲学者に教えを請うているようなふうだった。 いつしか林道を抜け、広々とした空き地に出た。川瀬さんは明るい日差しに屈んだ背を伸ばし、大きく息を吸い込んだ。
「クズミさんは、大学でたら、何やりたい。まずそれをあんたが決めることさ」
それに僕は何も答えることができなかった。川瀬さんは続けて言った。
「金を取るか、好きな道に進むか。あんたの自由だ。わしは金をとった。証券会社で若い頃は羽振りもよかった。だけんど病気してみんなだめになって、死ぬつもりでバイクで旅に出て、山ん中で、いざ死のうと死に場所を探しながら、ああ、自分にはこんな生き方しかなかったんだろうかと思った。どんなに金があっても心の中はすさんでた。金ばかり追いかけ回しているさもしい人間だったって振り返ったさ。こんな人生でほんとうに良かったんだろうかって思ったさ」
「でも、お金がないと好きなこともできませんし」
「本当は何をやりたいか、あんた自身が一番ようわかっとるはずだ。自分にウソはつけんさ。クズミさん、あんた、金が好きなら金を追いかけたっていいさ。地位だの名声だの欲しけりゃ、それ追いかけたっていいさ。だけんどな、クズミさん、大事なのは、死ぬ時になって、ああ、自分は本当に満足のいく人生だった、人のためになることもした、本当に良い人生だったなあって思えるかってことさ。それが一番さ」 僕は黙ったまま、うなだれるように川瀬さんの話を聞いていた。道の先に、連れ立って飯場へ向かう作業員の群れが見えた。
締めくくるように、川瀬さんは「人になんと言われようと、自分で自分に誇りが持てれば、それでええんだ」と言った。
木沼さんは、僕との話が尽きるとヘッドホーンを耳に掛け、カセットケース入れに入っているミュージックテープを端から順番に取り出して聞き、突然思い出したように部屋の外に置いてある高価なスポルティーフの自慢の自転車を磨き、飽きると部屋に戻り、再び音楽に耳を傾けた。 木沼さんが部屋を出入りする音で僕のうたた寝は中断され、天井を眺めながら昼間から寝てばかりいると夜眠れなくなってつらいかなと思ったりもした。 「クズミくん。あんまり寝てばかりいると人生がもったいないよ」
木沼さんが戸口から顔を覗かせて言った。廊下で自転車磨きに専念しているらしい。僕は久しぶりにバイクの手入れでもしようかと、立ち上がって、部屋から出た。 廊下には日差しが窓から斜めに射し込み、明暗がくっきりと分かれ、気持ちのよい温もりが満ちていた。僕は大きく背伸びをして、木沼さんにバイクを磨いてきますからと言って下に降りた。 休日とはいえ、飯場の男たちは街に出掛けるのがおっくうなのか、ほとんどが飯場にいて、真っ昼間から酒を飲み花札やマージャンに興じ、部屋の中も外もふだんと同じように騒々しかった。下に降りると足もとのあやしげな男たちがあわただしく部屋を出入りするのが見えた。 建物の脇に回ると、上に被せてあったビニールシートを取り、バイクと久し振りに対面した。薄いビニールをかけたままでほとんど野ざらし状態になっていた。しばらく仕事に追われ、手入れをしていなかった。よく見るとハンドルやマフラーが白い粉をふいたように曇り、切なくなった。 シートにあったはずの光沢も心無しかくすんで見えた。頻繁に手入れをしなければ手のほどこしようのないほど腐食が進むにちがいない。最初の給料でクリーナーやワックスを揃えなければ……。油をしみ込ませた布でスポークを1本1本丁寧に拭きながら、北海道へ旅立つ日までに揃えておかなければならないものをあれこれと考えた。 バイク磨きに専念していると、2階の窓から、「そろそろ、昼飯が出来てるかなぁ」
と言って木沼さんが顔を出した。もうそんな時刻かと時計を見ると、あと5分ほどで正午になろうとしていた。 僕はバイク磨きを一旦やめ、木沼さんに付いて行った。ちょうどその時。真向かいにある別の棟からざわざわと男たち数人出てきた。彼らは食堂へと向かっていたが、その中の1人が、僕のバイクに目をとめた。 年令は僕や木沼さんと同じくらいであろうか。淡いブルーのシャツをジーンズの外に出し、サンダルがけで足元が少しふらついていたが、どことなく風貌に品があった。日に焼けた精悍な顔つきに賢こそうな目もとが印象的だった。若者は僕と目が合うのを避けるようにして、食堂へと駆け込んで行った。 昼食はカレーだった。僕は木沼さんと後ろの席に並び、これじゃあ夜まで持ちませんよねえと言いながら、これ以上は入らないというくらい腹に詰め込んだ。カレーを頬張りながら先程の若者のことが気になり、時々少し離れたところで後ろ向きに座っている彼の背に目をとめた。 飯場に来てすでに1ケ月ほど過ぎていたが彼を見るのは初めてだった。最近来たアルバイトの大学生かも知れないと思い、木沼さんにそれとなく尋ねると、木沼さんも初めて見る顔だと言い、せわしげに残り少なくなったカレーのルウを御飯に混ぜ合わせ、口に運んだ。
No.7 北海道への旅仕度
ふざけて僕が言うと、
「そんなふうじゃあ、人間がだめになるよ。クズミくん」
木沼さんはきまってそう言う。 ふだんの木沼さんからはまるで想像もできない返答に返す言葉もないが、まだ給料を手にしてない僕はせいぜい休日でもやっている飯場の食堂でただ飯を食い、日頃の疲れを癒すために横になっておとなしく寝ているか、バイクの手入れでもしているしかない。 僕より2つ年上の木沼さんは年齢がちかいこともあり話がよく合った。度を越した酒好きと半月に1度しか風呂に入らないことが難点だったが、心ねの優しい人だった。 休日は田牧隊長が部屋にいないせいか、木沼さんは1日中晴れやいだ顔をしている。隊長がそこに居合わせたら、さぞや木沼さんの普段とちがう相好に驚くに違いない。全く、春の陽気に顔を出したモグラと一緒で、腰が落ち着かない。 田牧隊長は休みの前の晩から、奥さんと来年受験を控えた中学3 年生の娘さんの待つ土浦にあるまだローンの支払いがかなり残っているという一戸建ての家へ帰る。週に1度のそれが唯一の楽しみのようで、時折日報を書く手を休めては、机の上に置かれた家族の写真に目を細めている。 「隊長の奥さんって、奇麗な方ですよねえ」そう僕が言うと、ふん、と木沼さんは鼻を鳴らすようにして、
「隊長はああ見えてもけっこう強引なところがあるからね」と言ってのけた。
「つきまとったとか、いわゆるストーカーっていうやつですか?大雪の日に一晩中花束かかえて、玄関の前に雪だるまのように立っていたとか」カール隊長も、たぶんやる時はやる。
「ちかいね。なんでもね。僕は君と結婚したいとか言って、台風の日を狙って、家を訪ねていったらしいよ」
かなりの知能犯だ。大雨でぬれ鼠になった男を、無碍に追い返すこともできない。とりあえずは、家に上げるだろう。そういえば、セールスマンの成約率もそういった日のほうが高いと何かで聞いたことがある。訪問先もあらまあ、こんな日に、と同情するだろうし、外出もできないから、じっくり話に耳を傾ける。
「そいでね、電話も毎日決まった時間にやったらしいよ」思い出したように木沼さんが言った。
「それ、何かの恋愛マニュアル本で読んだことがありますよ。毎日来ていた電話がたまに途切れると、不安になって、気にかけるようになるってやつでしょ」あのカールおやじも中々の策士だ。 隊長の若い頃は、ストーカーなどという言葉はまだ無い。「男は押しの一手」というような言葉を胸に、鼻息も荒くせっせと通い詰めていたに違いない。今時は、携帯に毎日求愛のメッセージでも送ろうものなら、変態ストーカー男からのセクハラメールの物証として当局に差し押さえられかねない。だいたい、携帯などという直截的なデジタル文化が男と女の古き良き慣習まで粉々に打ち砕いているのだ。 「ストーカーって、なんか暴走車みたいな響きでいいよね」あくびをしながら木沼さんが言った。
「英語で、しつこくつきまとうって意味らしいですけどね」一体、いつからこんな言葉が日本中に広まったのだろうかと思う。全く、ストーカーなどという余計なメディア用語が浸透したおかげで、男どもの腰がひるみ、果ては晩婚化を招いたとしか考えられない。 隊長のような、台風の日にまで通いつめる男などストーカーの鏡のような御仁だが、これを女性が「なんて熱心なお方」と心和ませるか、「ストーカー」として身を強張らせるかは、メディアでコントロールされた心象で、全て裁断されるというものだ。 「ストーカーって、昔は女の尻を追いかけ回すとかって言ってたんでしょ。僕はそっちのほうが臨場感があっていいな」そう言って、僕は新聞の番組欄を見ながら、TVのスイッチを押した。といっても、ニュース番組で正統派美人キャスターが顔色ひとつ変えず、『ここ1年ほど、雨の日も風の日も、女の尻をしつこく追いかけ回していた男が遂に逮捕され、西葛西署に連行されました。現場に春日アナウンサーがいます。春日さ~ん、女の尻ばかり追いかけ回していた男の現在の様子はどうでしょう。やはり反省の色が見られないでしょうか』などと報道する絵柄というのもまた悩ましいものだ。日本中の男どもは虚空を仰ぎながら何を思うだろう。 「だけど、隊長みたいな人がじっと家の前にいたら、どうする、クズミくん」
「まあ、気持ち悪いでしょうね」
僕が若き日の隊長の奥さんだったら、豪雨の中で傘もささず立ちすくむ口の周りを黒々とさせた風采のあがらない挙動不審な若い衆を見た日には、即座に警察に通報し、しょっぴいてもらうけれど。
「今は、なんでも携帯ですからね。なんか雰囲気がないですよね。隊長の頃のように、相手の家に電話かけて、もしかしたらむこうのオヤジかなんか出てね、うちにはそんな娘はおらんが、どちらへおかけですかなんて、どやされたらどうしようかってハラハラするのもいいもんなんですけどね、スリルがあって」
「でも、メールは楽だもんね」そう言うと、木沼さんは、傍においていた自分の携帯を手にとり、待ち受け画面の掘北真希をしげしげと見つめた。
「木沼さん、携帯のメールなんかよりね、伝書鳩に愛のメッセージでも付けて飛ばしたほうがよっぽど乙女心をそそるってもんですよ」
僕は携帯文化なるものがどうも肌に合わない。どんなものでも手のかかった物ほど感動も大きい。女性から見てどれほどキモい木沼さんだって、伝書鳩でも放てば、イギリスの霧深い城に幽閉されていた眉目秀麗の王子様から、海を渡って来たのかしらん、とでも勘違いされるに違いない。 「クズミくんもね、ストーカーでも何でもやって早くいい子を見つけなきゃね」目の端に笑みを浮かべ、同情でもするかのように木沼さんが言った。 女の影もない木沼さんにそんなことを言われる筋合いはない。
「たぶん、女性はね、コツコツ、ジワジワ迫られると弱いんですよね。僕も隊長を見習って頑張りますよ」と僕は返した。とはいえ、すでに人妻となってしまった由里先輩にちょっかいを出すことは人の道に外れるというもの。 今頃、不動産屋の跡取り息子の大バカヤローの手が由里さんの白い肌に伸びているかと思うと、この鬱憤をダンプ連中にどうぶつけてやろうかと腹の底から力が湧いた。不動産屋のぼんくら男には「今でもあなたのことを心からお慕いしております。私を捨てたことを、一生お怨み申し上げます」とでも書いた恋文を伝書鳩の足に赤い糸でしっかりくくりつけ、確実に京都の嵐山まで届くように5,6羽放ってやろうかと思った。 休日の隊長のもう一つの楽しみは競輪場通いで、これまでにかなり金を注ぎ込んでいるらしい。世界中で嫌煙の嵐が吹きまくっているというこのご時世に、まるでむさぼり食うようにタバコを吸いながら、鬼のように競輪のことを語る。放っておけば、一晩中でも、しゃべっている。 僕は、最近はどこいっても喫煙者が締め出され、白い目でみられるのがうっとうしくて20歳になった記念にタバコをやめようかと思っていて、隊長、タバコは隣にいる人のほうが結構被害が大きいとかいわれてんですけど、副流煙とかって、どうなんですかと聞くと、クズミくんね、タバコは20歳になってから正式に吸うもんでしょ。それにあんなものは自動車産業の陰謀でね、排気ガスを吸ってるほうがよっぽど肺にくるんだから、と吸殻で山となった灰皿を見ながら平然としている。 いつだったか、それじゃ、隊長はタバコと排気ガスのダブル攻撃で大変じゃないですか、と言ったが、まあ、あんなものは、個人差だからね、とまるめこまれてしまった。
「隊長、今頃戸田の競輪場でも行ってんじゃないですか」僕が言うと、
「また、負けてるよ」くしゃみをしながら木沼さんが答えた。 隊長は3年前に50万近く儲けたが競輪場に通いつめた10数年間に負けた金額はそんなものに比べようもなく、家のローンの支払いにまわせばよかったと後悔していて、僕や木沼さんには賭け事なんかやるもんじゃないと忠告するがどうやら当人は辞めるつもりは毛ほどもないようだ。競輪は仕事への英気を養うためにどうしても必要な息抜きだと言って涼しい顔をしている。 隊長はなかなか愉快な人だった。飯場に来て、3週間ほど経った頃、休みの前の晩に隊長に誘われ、木沼さんと3人で国道から少しばかり離れた所にある「小雪」という一杯飲み屋に行ったことがある。 10人も人が入ればいっぱいになるような小さな店で、縄暖簾をくぐると、小股のきれあがった和服姿の美人の女将さんが、カウンターの中で1人できりもりしていた。
「あら、お久しぶり」と女将さんが隊長に声をかけると、「いや~、商社は海外出張が多くてね、やっとアイダホの農家と大豆の栽培契約をしてね」と、どうみても商社マンとはほど遠い麦わら帽子のよく似合う隊長が、やにさがった顔で答えた。 隊長は自分だけ串と熱燗を頼むと、僕と木沼さんに、おしんこを好きに頼んでいいからと言い、熱燗をぐいぐいやり、僕の隣でタバコを吸いまくり、鼻から副流煙をたなびかせた。 30分ほど僕らは、飯場の朝飯には調理人らの熱意が全く感じられないだの食堂主任の角さん(エラがはった顔をしていたからそんなふうに呼んでいた)は40半ばで嫁さんをもらわず、もしかしたら男色かもしれないなどと、どうでもいいようなことをぐだぐだと真顔で話した。 そのうち、客が一人二人いなくなって、カウンターは飯場組3人衆だけになり、女将さんも、僕らの話にのってきた。近くでみると、淡い蛍光灯に照らされたうなじがぞくっとするほどなめらかで、どこかで会ったような気がすると思ったら、隊長が机の上に置いていたCDジャケット、そうあの写真の美人歌手、若き日のあべ静江によく似ていた。なるほど、それでここにやってきたわけだ、と僕は得心した。女将さんは40前くらいに見えた。もしかして、シーちゃんとでも呼ばれているのだろうか。 「ぼくらはダンコンの世代って呼ばれてるけど、今なんかよりよっぽど良かったんだから。イチゴ狩りはあったけどオヤジ狩りなんてのはなかったしね、シーちゃん」かなり酒が入って、顔から湯気でも立ち昇りそうな隊長が女将さんのうなじをうっとり見つめながら言った。何が良かったのか知らないが、遂に出たか、エロおやじのシモネタギャグが、多分、ダンコンというのは男の根と書くのだろう。けっ、酒がまずい。それに、案の定、女将さんはシーちゃんと呼ばれていた。 「あら、や~ね、タヌマさん。ダンコンだなんて、ダイコンでしょ、いまよそいますから」と、さすがに客あしらいに慣れているシーちゃんは小皿を手に大根を竹輪やらがんもどきと一緒に盛り、隊長の身の毛もよだつシモネタに頬を赤らめるわけでもなく、如才なくかわした。 「オキツグじゃないよ、ぼくはタマキ、タマキ、、、タマキンじゃないよ」と言い、ガアハハと隊長が笑った。あんたら二人でいつまでもそうやってるといい。ダンカイだろ、ダ・ン・カ・イ。隊長の隣で、僕は遂に我慢ならなくなって、「もしかして、ダンカイですか」と訊いた。すると、隊長が、「そう・・・」と言い、一拍長く置いて、「・・・とも言うね」と答えた。まあ、本当に腐りそうなほど長い溜めだった。木沼さんが隊長のいない時に、タマキではなく、タヌキ隊長と呼んでいるわけがわかったような気がする。 「隊長さんって、いつもこうなんですよ」シーちゃんが、しれっと言うと、「職場だとね、セクハラになりますから。かんべんしてください」と、木沼さんがぐるぐるまなこで横からろれつの回らない口をはさんだ。と言っても、職場には、食堂に野太い声のパンチパーマのおばちゃんが3,4人いるくらいで、むしろ僕としてはパワハラの脅威さえ背後で感じるくらいなのだが。セクハラなどしようものなら待ってましたとばかりに羽交い絞めにされかねない。 「でも、こちらの方、ちょっと藤岡弘、さんの若い頃に似てらっしゃるわね」とシーちゃんが僕に流し目を送った。
「藤岡弘、って、仮面ライダー1号の人ですか」と僕が言うと、
「そう、かっこよかったのよね~。私の憧れの人」
あべ静江似の女将さんにそう言われて悪い気はしなかったが、隣で隊長があからさまに面白くなさそうな顔をしていたので、明日急に勤務場所をハードな所に変えられてもまずいと思い、僕もダンコン世代のエロ話に加わるしかないと腹を決め、こんな話をした。 「僕と木沼さんがね。自転車で飯場に帰る途中に、高校生の一団と出くわしたんですけどね。中にズボンをずり下げてゾロゾロ歩いてる連中がいて、木沼さんが、『あれは、ウンコでも、もらしたんだろうか』と聞くんで、『いや、そうじゃなくて、あれはですね、けっこういい物を持っていて、重くて歩くたびにズボンがずりさがるんですよ』と言ったんですよ」シーちゃんには大受けで、笑いが漏れないように、口の辺りに白い可憐な指を当てていた。 横で、隊長がまたよせばいいのに、「そうだよね~。ぼくらの頃はね、コカンがヒイヒイ言うくらいに、ズボンを上げて、ついでに上げ底のブーツまで履いて、1ミリでも足を長く見せようとね、もう涙ぐましい努力をしたんだけどね」と口をはさんだ。 となりで木沼さんはどうでもいいような顔をして、やってられねえや、そうやって死ぬまで話してろ、といった顔できんぴらをつまみながら熱燗を手じゃくで浴びるように飲んでいた。 僕は酒の酔いにつられ、「でも、本当のところはですね、隊長。彼らはあそこに、武器を隠し持ってましてね、日本が攻められた時には、決起しようと日々備えているんですよ。彼らにしてみれば戦闘服みたいなもんでね。感心な奴らですよ、全く。まあ、見たことはありませんがね」と珍説を展開した。 すると、すかさず「水鉄砲かい」と隊長。が、何と言われようが、「ここだけの話ですが。公安もね、あそこに目を光らせているらしいですよ」と僕は自説を曲げなかった。公安と聞いて、一瞬、角棒を振り回していた頃の記憶がよみがえったのだろうか。「股ぐらをかい」と隊長。しばらく、溜をおいて、さとすように「そう」と僕。シーちゃんは始終笑いをこらえながら、この3バカトリオを早く帰らせてお開きにしなきゃというような顔をしていた。 くだらない話ばかりだと男っぷりが下がるとでも思ったのか、急に隊長が話題を変え、「でも、女将さんもずいぶん痩せたよね」と訊いた。
「聞いてくださいよ、タヌマさん、これに150万もかかったのよ」だからタマキだって、この女将さんも、よっぽどタヌマオキツグを日本史で暗唱させられたんだろう。隊長は、タヌマだろうが、タマキだろうが、タヌキだろうが、はてはタマキンと呼ばれようが、もうどうでもいいような顔をして、僕のとなりでつっぷして寝ている木沼さんに、だらしねえぞ、とか声をかけていた。 僕は、女将さんに、「ダイエットの機械とか買ったんですか?」と尋ねた。女将さんは、この3人の中じゃ、まあ、このおにいちゃんが一番まともに聞いてくれそうだわ、といった顔で、とつとつと話し始めた。 聞けば、150万で高価なダイエットマシーンを購入したわけでもなく、ダイエット食品をセットでしこたま買わされたわけでもなく、ご主人が糖尿病で入院したり、店をしばらく閉じたりしていて、150万ほど欠損が出て、食費や衣類の出費を極端に抑えたらしい。おそらく心労も重なったのだろう。それまでどんなに涙ぐましいダイエットをしてもびくりともしなかった体重が、1年間で20キロ近く減ったという。 それはつまり、150万の欠損金のおかげというわけだ。20キロ減量で女っぷりがあがれば、また隊長のような鼻の下をのばした輩が店に群がることだろう。 こういうのを、捨てる神あれば、拾う神あり、というのかどうか知らないが、なるほどダンコンの世代というのは、転んでもタダでは起きないしたたかな連中なのだと僕は得心した。 帰りしな、隊長と木沼さんを両脇で支えながら、それにしても綺麗な女将さんだった、店先に塩でも撒かれていなければいいがと、夜空にくっきり映えた三日月を見ながら千鳥足で飯場に帰り着いた。
ごろりと横になり、開けた窓の隙間から入り込む暖かな日差しにうとうとしていると、「今日飲みに連れて行ってあげようか」と木沼さんが声をかけてくるが、「金ありませんよ。自慢じゃないですけど。一銭もないんですから」と僕は念を押す。 飯場に来て、1週間ほど経った頃、金が無いのも何かと不便だからと、隊長が5,000円ほど貸してくれたが、とりあえず街に出て、下着を買い、ガソリンをバイクに詰め込み、腹を満たした。
「だいじょうぶ、そういう人の為にツケのきく所があるんだから」
木沼さんの言う、そういう人というのが妙にひっかかって、
「まさか、あのシーちゃん女将の店ですか、あそこはいくらなんでもまずいでしょう。隊長に知れますよ」
「もっとね、いいとこがあるんよ」金のない木沼さんの行き着けの店となると、たぶん、と思い、「その辺の野良猫の頭の煮込みとかでるんじゃないでしょうね」と言うと、「鼠の串焼きもでるよ」と木沼さんは言い、口元からよだれを垂らしそうにして笑った。 僕は、「粛々と寝ます」と言い、それを無視した。「粛々」というのは、「静かに、おごそかに執り行う」という意味だが、ある時、TVのニュースで、政治家が「法案の成立に向け、粛々と行う」とインタビューに答えていて、その語勢に、何か強行採決でもやるかのようなヒタヒタとした執念のような凄みを感じて、やけに可笑しかったので、しばらく僕は、「粛々とメシを食べてきます」だの「粛々とトイレに行ってきます」だのと使い回していた。 ついでに、言葉のことで思い出すことがある。僕が大学1年の頃の話だが、グラントというコロラド州ののどかな町からやってきたアメリカの交換留学生が沢村の高輪の実家に3カ月ばかりホームステイしていた。気の良い奴だったから、上野だの浅草だの東京の名所を案内した。 グラントは僕と同い年で、背丈もほぼ同じくらいだったが、さすがにジャンクフードで培った腹はでっぷりとして、ジーンズもパンパンに張り、肩も背中も腕もそこいら中から肉汁が絞り出そうなほど脂肪がたっぷりのっていた。おまけに顔はそばかすだらけでブヨブヨと白く、眼と鼻が顔の真ん中で小さく座り、はっきりいってキモかった。日本で言うところのオタクフェイスだ。 そのグラントをここが日本が世界に誇るオタク文化の発祥の地だといって、秋葉原に連れて行ったことがある。いやいや、全く、奴ほど秋葉原が似合う外人もいなかった。完璧にアキバの空気に馴染んでいて、リュックを背負った体を丸め、熱いおでん缶をフウフウすする姿など妙に哀愁を誘うものがあった。アキバに来たついでにと、ラオックスのパソコン館の脇を入った所のメイド喫茶につれていった。 店の中は学園祭の延長のようなもので、ゴシュジンサマオカエリナサイマセの一斉連呼が響き渡り、メイド服姿の胸の谷間の深い八重歯の可愛いいありさちゃんがグラントの横にぴったり座り、おしぼりのサービスで奴の顔に浮き出た脂をふきとると、奴は顔中の皮膚を緩ませ、やにさがっていた。 で、その後が大変だった。ありさちゃんの過剰なサービスにメロメロになったのか、はたまたメイド喫茶をワビサビの日本文化と勘違いしたのか、帰りしな何を思ったか、道行く人々にゴシュジンサマ、ゴシュジンサマと声を掛けまくり、うかれまくっていた。一緒に歩いていると、これがまたうっとうしくて、要するにウザかった。 それで、グラントとかなり親しくなった頃に、ゴシュジンサマもオトノサマもキモイもウザイも同じようなもんだからと、冗談で、いやあ、グラント、今日もキモイね、と言ってやった。 すると奴は、その言葉の意味がわからず、ナンデスカソレ、と聞いてきた。それで僕は、「キモイ」というのは今時の日本の女子高生の間で流行っている最上級の褒め言葉で「あなたのためなら死んでもいい。この身をささげたい」という意味だ。ついでに、「ウザイ」というのは、「あなたのような美男子はこの世に二人といない」という意味だと言ってやった。 それから僕は、グラントに会うたびに、やあ、グラント、相変わらずキモイねえ、今日のそのストライプのシャツいいねえ、ベリーキモイよ。それにチョ~ウザイよ、とニコニコしながら言ってやった。もちろんグラントもホクホク顔だ。たぶん、これまでの人生で、「あなたのためなら死んでもいい」などと言われたことはないだろうから。ただ、男からそんなことを言われてもちょっと気色悪いだろうが。 ともかく、僕はグラントがアメリカに帰る1カ月くらいの間、日米友好親善のつもりでずっとそれを通した。相手が喜んでいる顔を見るのは楽しいものだ。そんなことで喜ぶのなら幾らでも連呼してやる。 たまに、グラントがニヤケ顔で、「ヌード、ヌード」とささやけば、両国に連れて行き、たいそう肥えた男たちがまわし一本で抱き合うところを飽きるほど見せ、帰りに駅前のおたふく食堂でタンメンをたらふく食わせてやった。 ところが、ある日、このオタク系アメリカ人が、2ちゃんねるの掲示板に、キモイだのウザイだのとかなり書き込まれているのを見て、ナゼデスカ、ウラサイトって何ですかと不思議がった。 そこで、僕は、自信たっぷりに、あれは祭りって言ってな、若い人たちはね、小さい頃から、あなたキモイだのウザイだのと言い合っては、民族意識を高めあっているのよ。若い人っていろいろあって大変なのね。だから、あなたキモイ、おめえウザイって、みんなで褒め讃え、励ましあって、互助の精神を若い頃から培っているわけさ。 なんてたって、資源の乏しい国で、食糧自給率もどんどん下がってんだから。それでも頑張ってやっていきましょう、さあ、あなたも、きみも、そこのコンビニの前でうんこ座りしてるバカヤローも、振り込め詐欺やってる連中も、ついでに新橋で焼き鳥つまみながら給料上がらねえってぼやいてるサラリーマンも、みんなで手を取り合って、サウンドオブミュージックみたいに、明るく生きていきましょうって。な、ステキな国だろ、日本ってのは、と吹いてやった。 そんなふうだったから、グラントは1カ月ばかり僕からキモイだのウザイだの言われて、もう脳からβ―エンドロフィンだのドーパミンだのセロトニンだの脳内麻薬物質が溢れ出て、恍惚感に浸りきっていたに違いない。といっても、僕に好意を寄せられても困るのだが。 一つ心配だったのは、アメリカに帰って、キモイだのウザイだのの意味を知って、僕のことをロクデモナイニホンジンと知り合いになったと思われるかもしれないということだったけれど。 でもね、グラント、言葉なんて、そんなもんだから。言葉ひとつでブルーになるより、間違って覚えてハッピーになるんなら、そっちのほうがいいってもんさ。 ついでに、もう一つ僕が心配しているのは、メイド喫茶のありさちゃん似の日本の女子高生がアメリカに行って、コロラドでグラントに会って、クラスメイトに奴のことをキモイだのウザイだとささやいた日には、それこそ奴は花束抱えて、ハリケーンだろうが竜巻だろうがおかまいなしに、女子高生を追い掛け回し、ストーカー道をまっしぐらに突き進むんだろうな、ということだ。
僕は、目を閉じ眠ったふりをして、ほんの少しの間、鼠の串暁きは焼き鳥に近い味なんだろうかと想像した。木沼さんはよほど猫の頭の煮込みが可笑しかったのか笑い呆けていた。 「そんなにおかしいですか。猫の頭が」
そう言うと、木沼さんはさらに手を叩いて笑い、それが部屋中に響くような笑い声だったものだから、休みの日になると隣の部屋で読書にふけっている川瀬老人のことを思い出し、「あんまり笑うとうるさいって、川瀬さんに言われますよ」と小声で言った。 川瀬さんは今年で68才になる。本好きで、休日になると部屋に籠もり読書に明け暮れていた。好みの本も歴史から精神世界まで多岐に渡り、風呂場でたまに一緒になると川瀬さんから司馬遼太郎の『坂の上の雲』の何ページ目がどれほど感動的だったかなどとよく講釈を受けた。 ある時、部屋でTVを見ていると、「あんたさ、将来何か目標あるのか」と川瀬さんに訊かれたことがある。ちょうどその時、就職活動に奔走する学生達の企業訪問の様子を放映していた。学生達は面接試験に出そうな想定問答を完璧に頭に叩き込み、上場企業の内定を3、4つ取っただのと誇らしげにしていた。僕もあと2年後には彼らと同じような状況に置かれることになる。と言っても、僕には、どういう職種についたらいいのか、いまだ漠然としていた。 番組では、大方の学生達が「経済的な安定」を一番に掲げ、当然のように、大手企業を優先的に選んでいた。職種はまるで違うのに、ただ上場企業だからと順に面接を受け、内定を取り付けたとほくそえんでいた。そんでもって、六本木あたりで祝勝会だと浮かれ騒いでいる。よくよく考えると不思議な光景だった。タイタニックだって沈む時は沈む。何を根拠に大手を選び、さして本意でもない仕事をやらなきゃいけない。 僕がそんな顔をしていると、隣で川瀬さんが、「わしもあんな頃があったけんど、病気で全部パーだ」とぼそりとつぶやいた。川瀬さんは東北の出身で、若い頃は秀才の誉れも高く、周囲から将来を嘱望されていたという。 「若い頃、大手の証券会社に入って、会社に大損かけて、病気になって、あんたみたいにバイクで旅に出たさ」川瀬さんはぽつりと言った。隊長と木沼さんもTVを見ながらそれをぼんやりと聞いていた。あいにく外は雨降りで、4人で湿った部屋で酒をちびちび飲んでいた。カップラーメンを口にしながら、川瀬さんはいつになく饒舌だった。メガネの奥の細い眼が心なしか潤んでいるようにも見えた。 「ひどい鬱になって、病院行って山ほど薬さもらって、どんどん頭がおかしゅうなって、もうどうにもならんようになって、もう死んでもいいと思って、昔好きだった彼女と見た美瑛の富士の日の出をもう一度みたくなって、薬を全部捨てて、バイクで旅に出て、、、ほんとに目の覚めるような朝日で心が洗われたさ、帰ってきたらすっかり病気も治ってたけんど、会社は利用価値のない人間だとワシをゴミのように捨てた。冷たいとこだっちゃ」 川瀬さんは名の知れた国立大を卒業していた。当然エリート街道をまっしぐらに歩むはずだった。どこに落とし穴が待ち受けているかわからないものだ。会社が潰れなくても、自身が病気で潰れたらそれで終わりだ。 たぶん、会社にではなく自分に寄って立つべきだということを川瀬さんは言いたかったのだろう。「会社に面倒をみてもらうっていう根性じゃだめよ。会社の面倒を見てやるぐらいじゃないと。会社も契約で人を雇って、いつでもクビにすんだから、人も会社を契約で雇ってるぐらいに考えて、いつでも見限ってやるくらいの根性じゃないと」そんな事も言っていた。 年齢の割にはかなり先鋭的な個人主義のアングロサクソン的な考え方だが、グローバリズムに席捲された世界ではそうとでも考えなきゃやっていけないかもしれない。 改革か改悪か知らないが、労働者派遣法が改正され、大幅に規制緩和されたおかげで僕らはある日突然、グローバリズムという名の市場原理主義の渦の中に放り込まれた。企業はこれ幸いと、人件費のカットのために派遣を多く雇い入れ、今では社員の3人に1人が非正規社員といった有様だ。 特別賞与も保険もない派遣は、非人間的な扱いでこき使われ、ワーキングプアなる言葉も生まれ、明確な階層社会が現出した。将来に希望を持てない連中は刹那的なゲームに埋没し、果ては現実の世界をバーチャルにシュミレーションし、ゲーム感覚で詐欺を仕掛ける輩まで現れた。 企業ばかりか派遣を生業とする連中にまで搾取され、労働者は貧困というループから中々抜け出せないでいる。あれよあれよという間に日本は貧困率でアメリカに次いで第2位になってしまった。 グローバリズムというのはとりわけ狩猟民族の論理で動いている世界だ。世界中に拝金が巣くい、全てが生産性という物差しで計られ、貨幣価値に転換できない人や物は容赦なく片隅に追いやられる。日本は農耕民族だからなどといっていられない。ネットでワンワールド化はさらに加速し、中国だのインドだのロシアだのと個々人が能力を競い合う、大競争時代となる。 これからどう生きていけばいいのか、川瀬さんに聞いてみたかった。僕は大学では経済を専攻したが、はたして、"人に幸福な経済論"があるとすれば、一体どういうものなのか尋ねてみたかった。川瀬さんは挫折し、ドロップアウトした、いわば反面教師のような存在ではあるが、著名な経済学者や政治家の話よりはまだ耳を傾ける価値があるかもしれない。 だいたい、彼らの提唱する近代の経済論がもう少しまともなものだったら、世界はもっと貨幣と共存した幸福なものになっていたはずだ。世界的な食糧危機が迫っているにも関わらず、貴重な食糧をバイオ燃料に使い、世界各地で食糧の奪い合いが起きているというのに、一方で、食糧相場を恣意的に操作し、株の投機に明け暮れている。 「株の博打」で濡れ手に泡の巨利を手にした博徒らを、メディアは「勝ち組み」と讃えるが、彼らは足下が薄氷なのを誰よりも知っている。満たされた物欲の代償に闇のような深い不安を抱え、憑かれたように株の仕手戦に奔走する。そうしたいびつな世界の構築に手を貸してきた経済論だ。「種銭作って、株の投機で一山当てろ」といった株成金長者がのたまる話はもう聞き飽きた。 ある時、川瀬さんの警備している現場に缶コーヒーを持って行ったことがある。そこは確かに木沼さんから聞いていた通り、ダンプが横断するためだけに存在しているような小道で、人通りもまばらだった。空気がひんやりとして、木漏れ日が気持ち良かった。捨てられた土砂が辺りに山のように盛られ、時折、乾いた土埃が煙のように舞っていた。 「もう、昼時ですからね、ご飯にいきましょう」木陰にぼんやりと立ちすくむ川瀬さんの後ろ背に声をかけ、缶コーヒーを差し出すと、川瀬さんは少し驚いたように振り返り、「ありがと」と小さく言い、薄くなった白髪の頭を軽く下げた。 二人で傍にあった大きな石にもたれかかり、缶コーヒーに口をつけた。僕は、2,3日前からダンプの行き来が急に増えたことを話題にし、見掛けないダンプや車両がゲート前に滞留していることを話し、その後、おもむろに、「若いもんはこれからどうやって生きていけばいいですかねえ」と、少しため息まじりに川瀬さんに訊いた。 川瀬さんはそれにすぐ答えることはなく、しばらく空を仰ぎ、自身の人生を反芻するかのようにしていた。そして、ぽつりと、「やりたいことをやればいいっちゃ」とつぶやいた。その後、川瀬さんは何も語らず誘導灯とヘルメットを手にして帰り仕度を始めた。 僕は川瀬さんの言葉を噛み締めながら、薄暗い林道を飯場へ向かって歩いた。道すがら、川瀬さんは「好きなことは、本当の自分が出せるちゃ」とも言った。好きなこと?何か、本心から満足の得られるもの、生きている実感のようなものが得られるものを見つけろと言っているのだろうか?木漏れ日の道を歩きながら、半生を振り返った。まるで、ギリシャ時代の哲学者に教えを請うているようなふうだった。 いつしか林道を抜け、広々とした空き地に出た。川瀬さんは明るい日差しに屈んだ背を伸ばし、大きく息を吸い込んだ。
「クズミさんは、大学でたら、何やりたい。まずそれをあんたが決めることさ」
それに僕は何も答えることができなかった。川瀬さんは続けて言った。
「金を取るか、好きな道に進むか。あんたの自由だ。わしは金をとった。証券会社で若い頃は羽振りもよかった。だけんど病気してみんなだめになって、死ぬつもりでバイクで旅に出て、山ん中で、いざ死のうと死に場所を探しながら、ああ、自分にはこんな生き方しかなかったんだろうかと思った。どんなに金があっても心の中はすさんでた。金ばかり追いかけ回しているさもしい人間だったって振り返ったさ。こんな人生でほんとうに良かったんだろうかって思ったさ」
「でも、お金がないと好きなこともできませんし」
「本当は何をやりたいか、あんた自身が一番ようわかっとるはずだ。自分にウソはつけんさ。クズミさん、あんた、金が好きなら金を追いかけたっていいさ。地位だの名声だの欲しけりゃ、それ追いかけたっていいさ。だけんどな、クズミさん、大事なのは、死ぬ時になって、ああ、自分は本当に満足のいく人生だった、人のためになることもした、本当に良い人生だったなあって思えるかってことさ。それが一番さ」 僕は黙ったまま、うなだれるように川瀬さんの話を聞いていた。道の先に、連れ立って飯場へ向かう作業員の群れが見えた。
締めくくるように、川瀬さんは「人になんと言われようと、自分で自分に誇りが持てれば、それでええんだ」と言った。
木沼さんは、僕との話が尽きるとヘッドホーンを耳に掛け、カセットケース入れに入っているミュージックテープを端から順番に取り出して聞き、突然思い出したように部屋の外に置いてある高価なスポルティーフの自慢の自転車を磨き、飽きると部屋に戻り、再び音楽に耳を傾けた。 木沼さんが部屋を出入りする音で僕のうたた寝は中断され、天井を眺めながら昼間から寝てばかりいると夜眠れなくなってつらいかなと思ったりもした。 「クズミくん。あんまり寝てばかりいると人生がもったいないよ」
木沼さんが戸口から顔を覗かせて言った。廊下で自転車磨きに専念しているらしい。僕は久しぶりにバイクの手入れでもしようかと、立ち上がって、部屋から出た。 廊下には日差しが窓から斜めに射し込み、明暗がくっきりと分かれ、気持ちのよい温もりが満ちていた。僕は大きく背伸びをして、木沼さんにバイクを磨いてきますからと言って下に降りた。 休日とはいえ、飯場の男たちは街に出掛けるのがおっくうなのか、ほとんどが飯場にいて、真っ昼間から酒を飲み花札やマージャンに興じ、部屋の中も外もふだんと同じように騒々しかった。下に降りると足もとのあやしげな男たちがあわただしく部屋を出入りするのが見えた。 建物の脇に回ると、上に被せてあったビニールシートを取り、バイクと久し振りに対面した。薄いビニールをかけたままでほとんど野ざらし状態になっていた。しばらく仕事に追われ、手入れをしていなかった。よく見るとハンドルやマフラーが白い粉をふいたように曇り、切なくなった。 シートにあったはずの光沢も心無しかくすんで見えた。頻繁に手入れをしなければ手のほどこしようのないほど腐食が進むにちがいない。最初の給料でクリーナーやワックスを揃えなければ……。油をしみ込ませた布でスポークを1本1本丁寧に拭きながら、北海道へ旅立つ日までに揃えておかなければならないものをあれこれと考えた。 バイク磨きに専念していると、2階の窓から、「そろそろ、昼飯が出来てるかなぁ」
と言って木沼さんが顔を出した。もうそんな時刻かと時計を見ると、あと5分ほどで正午になろうとしていた。 僕はバイク磨きを一旦やめ、木沼さんに付いて行った。ちょうどその時。真向かいにある別の棟からざわざわと男たち数人出てきた。彼らは食堂へと向かっていたが、その中の1人が、僕のバイクに目をとめた。 年令は僕や木沼さんと同じくらいであろうか。淡いブルーのシャツをジーンズの外に出し、サンダルがけで足元が少しふらついていたが、どことなく風貌に品があった。日に焼けた精悍な顔つきに賢こそうな目もとが印象的だった。若者は僕と目が合うのを避けるようにして、食堂へと駆け込んで行った。 昼食はカレーだった。僕は木沼さんと後ろの席に並び、これじゃあ夜まで持ちませんよねえと言いながら、これ以上は入らないというくらい腹に詰め込んだ。カレーを頬張りながら先程の若者のことが気になり、時々少し離れたところで後ろ向きに座っている彼の背に目をとめた。 飯場に来てすでに1ケ月ほど過ぎていたが彼を見るのは初めてだった。最近来たアルバイトの大学生かも知れないと思い、木沼さんにそれとなく尋ねると、木沼さんも初めて見る顔だと言い、せわしげに残り少なくなったカレーのルウを御飯に混ぜ合わせ、口に運んだ。