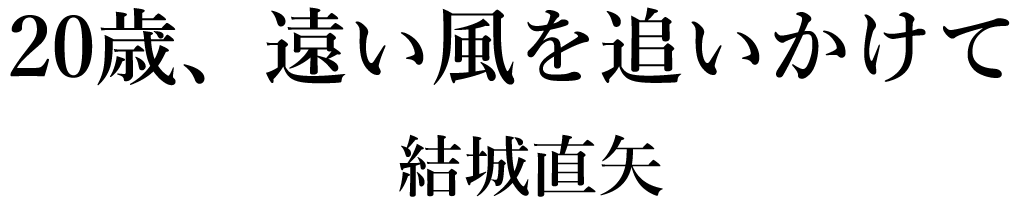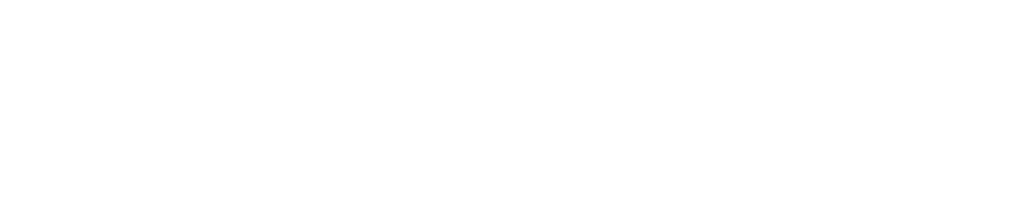No.7 北海道への旅仕度
5月下旬のある日。仕事を終え、風呂でひと汗流し、部屋に戻ると、見知らぬ来訪者が2人いた。
1人は 50過ぎの恰幅のいい紺の縦縞の背広を着た大柄の押しの強そうな男で、もう1人は大学出たての色白のひ弱そうな若者だった。
男たちは黒い革張りの大型のマッサージ機を部屋に持ち込んでいた。飯場にはこうした営業マンがよく顔を出すらしい。
2人は部屋の中央に陣取り、アタッシュケースを開け、年配の男のほうが「これでもうばっちりですよ」と親しげな声色で、畳の上に色とりどりのパンフレットを並べた。
男は終始にこやかに顔をつくろいながらも、黒ぶちのメガネの奥から獲物を狙うような目を光らせ、わざわざこんな重いものを持って来てやったんだ、是が非でも買ってもらおうかといわんばかりの高圧的な雰囲気をかすかに漂わせ、低周波だの高周波だのどれほどこれで体を癒せるかと、虚ろな眼で聞いている木沼さんにこんこんとさとし、横で眠そうにしている隊長には、競輪など行かずともこれでストレスが発散できてこんな経済的かつ効率的なものはないといった目で睥睨し、ついでに人生の懊悩まで霧散するかのようなかなり無理のある話を川瀬さんを相手にまくしたてた。
色白ひ弱男は、この人はいつもこんなふうですからといった情けない顔で、時おり相づちを打っていた。 高圧男ははなから僕を相手にせず最後まで目を合わせなかった。セールスマン人生で鍛えた特異の臭覚で、さすがに僕に金がないことを瞬時にかぎわけたに違いない。けっ、どんな高機能のマッサージ機だろうが、木沼さんと一緒にいる限り、隊長にストレスは一生ついてまわるもんねと、自慢の臭覚も鈍りつつあることを指摘するかのような目で、僕は男を見降ろしてやった。 30分ほど経ち、いよいよ大柄男に疲れが見え始めたところで、「僕の母親もこれを使っていましてね。とても喜んでるんですよ」と色白男がここぞというタイミングで助け舟を出してきた。部屋の空気が微妙に変わるのがわかった。 「木沼くんさ。お父さんやお母さんに買ってあげたら。どうせ給料が出ても酒代に消えるんだから」
色白男の説得が効を奏したのか、ベテランの鬼刑事と新米刑事のやさ男におとされた容疑者のような格好で、隊長がマッサージ機の購入を木沼さんに勧めた。 「んなさ。木沼くん。気持ちいいよ」
川瀬さんは黒革のマッサージイスに寝そべり、時にしなだれかかるようにとろんとした目をして、身体のどのあたりに懊悩が潜んでいるのか探るように微妙に体勢を変え、苦悩のほぐれ具合を確かめていた。 遂に川瀬さんまで加勢し、そうなると鬼刑事と新米刑事の猛攻は容赦なかった。白羽の矢を完全に木沼さん一本に定め、色白男が「父親が2年前に亡くなりましてね。すぐに母親に買ってあげたんですよ。もっと早くから親孝行しておけばよかったといまだに悔やんでます」と、嘘か本当か知らないが、畳かけるように必死の攻勢をかけてきた。おそらくノルマをかけられ、売れなかったらしばらく飯場でめし炊きでもしてろと上司に発破をかけられたに違いない。 肝心の木沼さんにはいくら給料が出たあととはいえ、およそ1ケ月分の給料に相当するそれの購入をおいそれとは即決出来ない事情がいろいろとあるのだろう。いつになく困惑した顔で考え込んでいた。 「分割で毎月1万円からでもよろしいですから、いかがでしょう」
高圧男が柄にもないニヤけた顔で腰をかがめ、下から見上げるようにして木沼さんをくどきにかかった。 木沼さんは男の言葉にうなずきながら、真剣な眼差しで現物とパンフレットを交互に何度も見比べていた。島根にいるという両親のことを思い、マッサージ機の購入に食指が動きかけていたようだった。
「何だったら僕が保証人になってあげてもいいよ。木沼くん」
隊長のその言葉で木沼さんはふんぎりがついたようだ。顔を上げ、
「じゃあ、そうしましょうか」
と言ってにんまり笑い、木沼さんは隊長に頭を下げた。
「喜ぶよ、送ってあげたら。田舎のお父さんやお母さんに、いままでずいぶん心配をかけてきたんだから、木沼くんよ」
隊長の言葉を照れたような顔で木沼さんは聞いていた。 その日の夜、布団に入ってから、僕は広島にいる両親のことを思い出した。頑固者の父親や体がさほど丈夫ではない母親のことが瞼の裏に浮かんだ。2人ともどうしているだろうか。 母親は今頃父親似の何事も言い出したら聞かない、無分別な僕のことを心配しているかもしれない。子供の頃からどうにも手につけられない次男坊だったと今頃2人で噂しているだろうか。家業の旅館業はうまくいっているだろうか。そういえば仕送りが銀行に振り込まれている頃だ。さまざまな思いが湧いてそのたびに熟睡が遠のいていった。 布団に入って20分ほど経った頃。もう寝なければ明日の仕事に差し支えると思い、寝返りをうった時、両親が荻窪のアパートに電話をしていたらどうしようかと急に心配になった。飯場に泊まり込むようになってすでに1ケ月が過ぎようとしている。 1ケ月に1度、あるかないか程度の親からの電話だが、間が悪く、両親が僕の部屋に電話をかけて、何度電話しても出ないのを心配していたらどうしようかと不安になった。携帯も部屋に置いたままだ。 ほんの1ケ月くらいの旅行のつもりで何も考えずに飛び出してきたが、飯場での滞在があと1ケ月延び、それから北海道へ向けて旅立つとすると、荻窪の部屋代もきちんと済ませておかなければならないだろう。大学には休学届けを出したほうがいいのだろうか。が、そうなると当然僕の企てがばれてしまう。多分、親は仕送りを止めると言うに違いない。次から次にさまざまな悩み事が頭の中をうろついた。 考えているうちに面倒臭くなって、明日の夜でも広島の実家へ電話を入れ、次の休日に一度荻窪のアパートに帰って部屋代を納め、学校へは届けなど出さなくともかまわないだろうと勝手に決め込んだ。そのうち瞼にほの暗い闇がかかり、そのまま僕は眠りについた。 翌日、夜の8時過ぎに飯場から広島へ電話を入れると、母親が出た。久しぶりの僕の声に上機嫌で、「3日前に町内の温泉旅行から帰ってきたところなのよ」とか、「電話をしてくるのはきまってお金がなくなった頃なのに銀行にはまだ振り込まれてないの」などと声を弾ませた。僕は、「仕送りもちゃんと届いてるし、元気で力がありあまっていて使い道に因っているほどだ」と答え、もちろん女に振られ、やけになって旅に出たことや飯場でバイトしていることは隠した。 僕との会話に満足すると母親は父親と代わった。父親は僕に「元気でやっているか」と尋ね、僕が「元気だ。心配いらない」とそっけなく答えると、もともと無口で話し上手ではない父親は僕の声を聞いただけで安心したらしく、すぐに母親に電話を代わった。母親はとりとめのない話で会話を1分でも延ばそうとしたが、電話代の小銭が残り少なかったので、母親に「ちゃんと食べてるし、元気だから心配いらない」と念を押し、電話をきった。 電話を終えて、本当のことを彼らに話さなかったことに少なからず罪悪感を覚えた。また一つ嘘の衣を羽織って生きていかなければならなくなったような気がした。いつかきっと、その重みで身動きが取れなくなるに違いない。が、正直に話せば、彼らに無用な心配を与えることになる。今は何も語らず、自身が招いた重みに耐えるしかない。そう思い、自らを納得させた。 待望の1ケ月分の給料を手にした休みの日、僕は朝食を終えるとバイクで柏の街に出てガソリンを詰め、荻窪のアパートヘと向かった。部屋代やら身の周りのことを整理し、心おきなく北海道へ旅立ちたいと思った。 笠間由里の結婚話で気が動転し、バイクで逃げるように古巣から飛び出したのが遠い昔のことのようだ。意気込んで旅立ったにもかかわらず、志半ばで挫折したかのような気分だった。20歳の無鉄砲な自我は飯場での生活で偏狭な衣をはぎとられ、分別を身につけつつあったのかもしれない。 荻窪までの最短距離をひたすら飛ばしたせいか、昼前にアパートに着いた。バイクを脇に停め、2階に駆け上ると偶然隣の部屋の小太りの予備校生と出くわした。出会いがしらに、「しばらく見えなかったですね」と声をかけてきたので、「今、飯場にいるんだよ」と答えると、「冗談でしょ」と言って笑いながら階段を降りて行った。どうも僕の場合、本当のことを言っても中々信じてもらえないらしい。 およそ1ケ月ぶりに部屋に入ると、生暖かいこもったような空気に包まれた。6畳のフローリングには、ジーンズや読みかけの雑誌が散らかり、台所ではコップや皿に淀んだ水が溜まり、おまけに生ゴミの腐敗臭まで漂い、こりぁ飯場よりひどいやと思わず息をつめた。 部屋中の窓を開け放し、空気を入れ換え、FM放送を聞きながらいらないものをどんどんゴミ箱に放り込み、そういえば高校時代に彼女を部屋に呼んだ時もこんなふうに前の日にせっせと掃除したなあと思い出しながら掃除機をかけた。 1時間半ほどして、まるで引っ越し当時のような真新しい空間が部屋の方々に出来ると、疲れ果てそのままベッドで寝入ってしまった。 2時間ほど横になっていただろうか。目が覚めるとやけに喉の渇きを覚えた。生ぬるい水道水より、炭酸の喉の奥にひっかかるような刺激を体が欲していた。近くの酒屋の自販機でコーラを買い、部屋に戻り、ラジオを聞きながらそれを飲んだ。 タバコを吸いながらぼんやりしていると、ラジオからジョン・レノンの「スタンド・バイ・ミー」が流れてきた。僕はそれを聞きながらぼんやりとこれからのことを考えた。 起きぬけの頭が次第にはっきりしてくるにしたがって、なんて無分別なことをしたんだろう、少し衝動的になりすぎたのでは、と愚かさを責めたてるような声が頭の隅で湧いてきた。部屋中をすっかり掃除して空気まできれいに入れ替わったせいだろうか。僕の頭の中の思考もそれぞれがあるべき所へときちんと分別され、整然と秩序立っていた。 確かに思慮に欠けた行為だったかもしれない。だが、たぶんあの日沢村の部屋を出てそのままこの部屋へ戻り、また何事もなかったかのように大学生活を送っていたとしたら相変わらず僕はあの時のままの、ただ安逸な生活のみを追い求めるだけの僕でいただろう。 あの日、20歳になったことを契機に精神的な変革を強く望んだ。きっかけが由里先輩への失恋だったにすぎない。そのためにとった行動は多少無謀だったが、19年かけて培った固い殻を破るためには避けられない選択であったと思う。 コーラを飲み終えて、なにげなく沢村に電話をしてみようかと思った。たぶんいないだろうと思ったが、5 回ほどの呼び出しの後、沢村が電話口に出た。傍で若い女の声が聞こえた。 「おう、クズミ、本当にクズミか、今、どこにいるんだよ、急にいなくなって、みんな心配してたんだ」
鋭い沢村の声だった。僕は沢村がいたことにうろたえ、どう答えていいか因って、
「ああ、、今、旅の途中だ」
と、うわずった声で取りつくろった。1ケ月近くも姿を消して、旅の途中地点が中野と目と鼻の先の荻窪だと知ったら沢村は怒るだろうなと思った。
「いつ帰ってくるんだよ。大学はどうすんだよ」
「ああ、わかってるよ。いろいろと考えるところがあって。しばらく休もうかと思ってる」
「おい、よせよ、クズミ、、バカなこと言ってないで、考え直して早く帰ってこいよ」
電話口で怒鳴るように沢村は僕に忠告した。
「ひょっとして、お前、由里先輩のことで」
声をひそめて沢村が言った。
「うん、ああ、そうかも知れんが、他にもいろいろとあってな」
「お前の気持ちもわかんなくないけど、女なんていっぱいいるんだから、とにかく早く帰ってこいよ」
「また、電話するよ。今度会う時は北海道の白熊を連れてきてお前に紹介するから」
「いらねえよ。おことわりだよ」
「まあ、そう言うな。俺は北海道へ行って美貌の白熊のメスとしばらく暮らそうかと思ってる。そのうち子供でも出来たら、お前んとこへ宅急便で送ってやる」
「お前は、ほんとに救いようがねえな。だいいち白熊が北海道なんかにいるもんか。あれはもっと上の北極とかじゃねえのか」
電話口で沢村は僕の冗談に憤慨していた。本気で僕のことを心配してくれていた。
「時々、旅先で電話するから、な、そう怒るな」
「ところで、クズミ、、、今、どのあたりにいるんだよ」
僕はまさか沢村の部屋からバイクで10分ほどの自分の部屋にいるとも言えず、とっさに、「お前の想像もつかないようなところだ」
と答えた。明確さを欠いているが、当たっていなくもない。僕は電話の声が近いことに沢村が不審を抱いたのではと思った。
「とにかく早く帰ってこいよ。みんな心配してんだから」
「ああ、わかったよ。1日も早く美貌の白熊を見つけてくる」
「まだ言ってる」 あきれて物も言えないといった沢村の声だった。僕は沢村の友情が身にしみ、最後に、これから自分が生きていくために必要な何かをつかむまでは戻らないと、日頃口にしたこともないような言葉で締め、電話を切った。 僕のことを本気で心配してくれている友人がいて嬉しかった。が、一方で僕自身の選んだ生き方をはばまれそうな気がして、少しばかり負担を感じたのも確かだった。 はたして友人や親に心配を掛けないような生き方というのはどんな生き方なのだろうか。学生としての本分をわきまえ、大勢から逸脱することなく、周囲に同調し、波風の立たないよう凡庸につつましやかに生きろとでも言うのだろうか。そんな生き方は僕にとっては窮屈で愚劣で息が詰まりそうだ。 いつの頃だったか、僕は僕の周囲を取り巻く大勢がどこへ向かっているのかどうにもあやしく思えて、素直にそれに適応することに疑問を感じ、一度それを斜めから切り取って、その断面をじっくりと気の済むまで眺めてみたいと思うようになった。 違う次元に立つことで、見落としていた何か大切な物が見つかるような気がした。それ以来僕は大学の有りようや世の中をちょうど分度器でも当てて計るようにして過ごすようになった。 20歳になったばかりの日の突拍子もない行動も、そんな僕のどこかひねた習癖が急に頭をもたげたせいかもしれない。僕の関わっている現実の脇を切り裂いて別の次元に紛れ、違う角度から自身を見つめ、進むべき方向を見つけてみたくなったのだ。 沢村との電話の後、1時間ほどベッドに横になり、2時過ぎに起きると、アパートの大家に、「しばらく旅行しますから」と言って3ケ月分の部屋代を手渡した。大家に「広島に帰るんですか」と訊かれ、つい「北海道へ行ってくるんです」と答え、後でそれが実家の両親の耳に届くかも知れないと思い、言わなければよかったと後悔した。 僕は数ケ月の留守を考え、冷蔵庫の中の物を整理し、台所やトイレを掃除し、雨戸を締め、思いつく限りのことをし終えると部屋に鍵をかけ、バイクに股がった。時計を見ると4時半を少し回っていた。全力で飛ばせば飯場の晩飯に間に合うかもしれない。木沼さんや隊長の顔が妙になつかしく感じられた。
No.8 木沼さんの誘導ミス
色白ひ弱男は、この人はいつもこんなふうですからといった情けない顔で、時おり相づちを打っていた。 高圧男ははなから僕を相手にせず最後まで目を合わせなかった。セールスマン人生で鍛えた特異の臭覚で、さすがに僕に金がないことを瞬時にかぎわけたに違いない。けっ、どんな高機能のマッサージ機だろうが、木沼さんと一緒にいる限り、隊長にストレスは一生ついてまわるもんねと、自慢の臭覚も鈍りつつあることを指摘するかのような目で、僕は男を見降ろしてやった。 30分ほど経ち、いよいよ大柄男に疲れが見え始めたところで、「僕の母親もこれを使っていましてね。とても喜んでるんですよ」と色白男がここぞというタイミングで助け舟を出してきた。部屋の空気が微妙に変わるのがわかった。 「木沼くんさ。お父さんやお母さんに買ってあげたら。どうせ給料が出ても酒代に消えるんだから」
色白男の説得が効を奏したのか、ベテランの鬼刑事と新米刑事のやさ男におとされた容疑者のような格好で、隊長がマッサージ機の購入を木沼さんに勧めた。 「んなさ。木沼くん。気持ちいいよ」
川瀬さんは黒革のマッサージイスに寝そべり、時にしなだれかかるようにとろんとした目をして、身体のどのあたりに懊悩が潜んでいるのか探るように微妙に体勢を変え、苦悩のほぐれ具合を確かめていた。 遂に川瀬さんまで加勢し、そうなると鬼刑事と新米刑事の猛攻は容赦なかった。白羽の矢を完全に木沼さん一本に定め、色白男が「父親が2年前に亡くなりましてね。すぐに母親に買ってあげたんですよ。もっと早くから親孝行しておけばよかったといまだに悔やんでます」と、嘘か本当か知らないが、畳かけるように必死の攻勢をかけてきた。おそらくノルマをかけられ、売れなかったらしばらく飯場でめし炊きでもしてろと上司に発破をかけられたに違いない。 肝心の木沼さんにはいくら給料が出たあととはいえ、およそ1ケ月分の給料に相当するそれの購入をおいそれとは即決出来ない事情がいろいろとあるのだろう。いつになく困惑した顔で考え込んでいた。 「分割で毎月1万円からでもよろしいですから、いかがでしょう」
高圧男が柄にもないニヤけた顔で腰をかがめ、下から見上げるようにして木沼さんをくどきにかかった。 木沼さんは男の言葉にうなずきながら、真剣な眼差しで現物とパンフレットを交互に何度も見比べていた。島根にいるという両親のことを思い、マッサージ機の購入に食指が動きかけていたようだった。
「何だったら僕が保証人になってあげてもいいよ。木沼くん」
隊長のその言葉で木沼さんはふんぎりがついたようだ。顔を上げ、
「じゃあ、そうしましょうか」
と言ってにんまり笑い、木沼さんは隊長に頭を下げた。
「喜ぶよ、送ってあげたら。田舎のお父さんやお母さんに、いままでずいぶん心配をかけてきたんだから、木沼くんよ」
隊長の言葉を照れたような顔で木沼さんは聞いていた。 その日の夜、布団に入ってから、僕は広島にいる両親のことを思い出した。頑固者の父親や体がさほど丈夫ではない母親のことが瞼の裏に浮かんだ。2人ともどうしているだろうか。 母親は今頃父親似の何事も言い出したら聞かない、無分別な僕のことを心配しているかもしれない。子供の頃からどうにも手につけられない次男坊だったと今頃2人で噂しているだろうか。家業の旅館業はうまくいっているだろうか。そういえば仕送りが銀行に振り込まれている頃だ。さまざまな思いが湧いてそのたびに熟睡が遠のいていった。 布団に入って20分ほど経った頃。もう寝なければ明日の仕事に差し支えると思い、寝返りをうった時、両親が荻窪のアパートに電話をしていたらどうしようかと急に心配になった。飯場に泊まり込むようになってすでに1ケ月が過ぎようとしている。 1ケ月に1度、あるかないか程度の親からの電話だが、間が悪く、両親が僕の部屋に電話をかけて、何度電話しても出ないのを心配していたらどうしようかと不安になった。携帯も部屋に置いたままだ。 ほんの1ケ月くらいの旅行のつもりで何も考えずに飛び出してきたが、飯場での滞在があと1ケ月延び、それから北海道へ向けて旅立つとすると、荻窪の部屋代もきちんと済ませておかなければならないだろう。大学には休学届けを出したほうがいいのだろうか。が、そうなると当然僕の企てがばれてしまう。多分、親は仕送りを止めると言うに違いない。次から次にさまざまな悩み事が頭の中をうろついた。 考えているうちに面倒臭くなって、明日の夜でも広島の実家へ電話を入れ、次の休日に一度荻窪のアパートに帰って部屋代を納め、学校へは届けなど出さなくともかまわないだろうと勝手に決め込んだ。そのうち瞼にほの暗い闇がかかり、そのまま僕は眠りについた。 翌日、夜の8時過ぎに飯場から広島へ電話を入れると、母親が出た。久しぶりの僕の声に上機嫌で、「3日前に町内の温泉旅行から帰ってきたところなのよ」とか、「電話をしてくるのはきまってお金がなくなった頃なのに銀行にはまだ振り込まれてないの」などと声を弾ませた。僕は、「仕送りもちゃんと届いてるし、元気で力がありあまっていて使い道に因っているほどだ」と答え、もちろん女に振られ、やけになって旅に出たことや飯場でバイトしていることは隠した。 僕との会話に満足すると母親は父親と代わった。父親は僕に「元気でやっているか」と尋ね、僕が「元気だ。心配いらない」とそっけなく答えると、もともと無口で話し上手ではない父親は僕の声を聞いただけで安心したらしく、すぐに母親に電話を代わった。母親はとりとめのない話で会話を1分でも延ばそうとしたが、電話代の小銭が残り少なかったので、母親に「ちゃんと食べてるし、元気だから心配いらない」と念を押し、電話をきった。 電話を終えて、本当のことを彼らに話さなかったことに少なからず罪悪感を覚えた。また一つ嘘の衣を羽織って生きていかなければならなくなったような気がした。いつかきっと、その重みで身動きが取れなくなるに違いない。が、正直に話せば、彼らに無用な心配を与えることになる。今は何も語らず、自身が招いた重みに耐えるしかない。そう思い、自らを納得させた。 待望の1ケ月分の給料を手にした休みの日、僕は朝食を終えるとバイクで柏の街に出てガソリンを詰め、荻窪のアパートヘと向かった。部屋代やら身の周りのことを整理し、心おきなく北海道へ旅立ちたいと思った。 笠間由里の結婚話で気が動転し、バイクで逃げるように古巣から飛び出したのが遠い昔のことのようだ。意気込んで旅立ったにもかかわらず、志半ばで挫折したかのような気分だった。20歳の無鉄砲な自我は飯場での生活で偏狭な衣をはぎとられ、分別を身につけつつあったのかもしれない。 荻窪までの最短距離をひたすら飛ばしたせいか、昼前にアパートに着いた。バイクを脇に停め、2階に駆け上ると偶然隣の部屋の小太りの予備校生と出くわした。出会いがしらに、「しばらく見えなかったですね」と声をかけてきたので、「今、飯場にいるんだよ」と答えると、「冗談でしょ」と言って笑いながら階段を降りて行った。どうも僕の場合、本当のことを言っても中々信じてもらえないらしい。 およそ1ケ月ぶりに部屋に入ると、生暖かいこもったような空気に包まれた。6畳のフローリングには、ジーンズや読みかけの雑誌が散らかり、台所ではコップや皿に淀んだ水が溜まり、おまけに生ゴミの腐敗臭まで漂い、こりぁ飯場よりひどいやと思わず息をつめた。 部屋中の窓を開け放し、空気を入れ換え、FM放送を聞きながらいらないものをどんどんゴミ箱に放り込み、そういえば高校時代に彼女を部屋に呼んだ時もこんなふうに前の日にせっせと掃除したなあと思い出しながら掃除機をかけた。 1時間半ほどして、まるで引っ越し当時のような真新しい空間が部屋の方々に出来ると、疲れ果てそのままベッドで寝入ってしまった。 2時間ほど横になっていただろうか。目が覚めるとやけに喉の渇きを覚えた。生ぬるい水道水より、炭酸の喉の奥にひっかかるような刺激を体が欲していた。近くの酒屋の自販機でコーラを買い、部屋に戻り、ラジオを聞きながらそれを飲んだ。 タバコを吸いながらぼんやりしていると、ラジオからジョン・レノンの「スタンド・バイ・ミー」が流れてきた。僕はそれを聞きながらぼんやりとこれからのことを考えた。 起きぬけの頭が次第にはっきりしてくるにしたがって、なんて無分別なことをしたんだろう、少し衝動的になりすぎたのでは、と愚かさを責めたてるような声が頭の隅で湧いてきた。部屋中をすっかり掃除して空気まできれいに入れ替わったせいだろうか。僕の頭の中の思考もそれぞれがあるべき所へときちんと分別され、整然と秩序立っていた。 確かに思慮に欠けた行為だったかもしれない。だが、たぶんあの日沢村の部屋を出てそのままこの部屋へ戻り、また何事もなかったかのように大学生活を送っていたとしたら相変わらず僕はあの時のままの、ただ安逸な生活のみを追い求めるだけの僕でいただろう。 あの日、20歳になったことを契機に精神的な変革を強く望んだ。きっかけが由里先輩への失恋だったにすぎない。そのためにとった行動は多少無謀だったが、19年かけて培った固い殻を破るためには避けられない選択であったと思う。 コーラを飲み終えて、なにげなく沢村に電話をしてみようかと思った。たぶんいないだろうと思ったが、5 回ほどの呼び出しの後、沢村が電話口に出た。傍で若い女の声が聞こえた。 「おう、クズミ、本当にクズミか、今、どこにいるんだよ、急にいなくなって、みんな心配してたんだ」
鋭い沢村の声だった。僕は沢村がいたことにうろたえ、どう答えていいか因って、
「ああ、、今、旅の途中だ」
と、うわずった声で取りつくろった。1ケ月近くも姿を消して、旅の途中地点が中野と目と鼻の先の荻窪だと知ったら沢村は怒るだろうなと思った。
「いつ帰ってくるんだよ。大学はどうすんだよ」
「ああ、わかってるよ。いろいろと考えるところがあって。しばらく休もうかと思ってる」
「おい、よせよ、クズミ、、バカなこと言ってないで、考え直して早く帰ってこいよ」
電話口で怒鳴るように沢村は僕に忠告した。
「ひょっとして、お前、由里先輩のことで」
声をひそめて沢村が言った。
「うん、ああ、そうかも知れんが、他にもいろいろとあってな」
「お前の気持ちもわかんなくないけど、女なんていっぱいいるんだから、とにかく早く帰ってこいよ」
「また、電話するよ。今度会う時は北海道の白熊を連れてきてお前に紹介するから」
「いらねえよ。おことわりだよ」
「まあ、そう言うな。俺は北海道へ行って美貌の白熊のメスとしばらく暮らそうかと思ってる。そのうち子供でも出来たら、お前んとこへ宅急便で送ってやる」
「お前は、ほんとに救いようがねえな。だいいち白熊が北海道なんかにいるもんか。あれはもっと上の北極とかじゃねえのか」
電話口で沢村は僕の冗談に憤慨していた。本気で僕のことを心配してくれていた。
「時々、旅先で電話するから、な、そう怒るな」
「ところで、クズミ、、、今、どのあたりにいるんだよ」
僕はまさか沢村の部屋からバイクで10分ほどの自分の部屋にいるとも言えず、とっさに、「お前の想像もつかないようなところだ」
と答えた。明確さを欠いているが、当たっていなくもない。僕は電話の声が近いことに沢村が不審を抱いたのではと思った。
「とにかく早く帰ってこいよ。みんな心配してんだから」
「ああ、わかったよ。1日も早く美貌の白熊を見つけてくる」
「まだ言ってる」 あきれて物も言えないといった沢村の声だった。僕は沢村の友情が身にしみ、最後に、これから自分が生きていくために必要な何かをつかむまでは戻らないと、日頃口にしたこともないような言葉で締め、電話を切った。 僕のことを本気で心配してくれている友人がいて嬉しかった。が、一方で僕自身の選んだ生き方をはばまれそうな気がして、少しばかり負担を感じたのも確かだった。 はたして友人や親に心配を掛けないような生き方というのはどんな生き方なのだろうか。学生としての本分をわきまえ、大勢から逸脱することなく、周囲に同調し、波風の立たないよう凡庸につつましやかに生きろとでも言うのだろうか。そんな生き方は僕にとっては窮屈で愚劣で息が詰まりそうだ。 いつの頃だったか、僕は僕の周囲を取り巻く大勢がどこへ向かっているのかどうにもあやしく思えて、素直にそれに適応することに疑問を感じ、一度それを斜めから切り取って、その断面をじっくりと気の済むまで眺めてみたいと思うようになった。 違う次元に立つことで、見落としていた何か大切な物が見つかるような気がした。それ以来僕は大学の有りようや世の中をちょうど分度器でも当てて計るようにして過ごすようになった。 20歳になったばかりの日の突拍子もない行動も、そんな僕のどこかひねた習癖が急に頭をもたげたせいかもしれない。僕の関わっている現実の脇を切り裂いて別の次元に紛れ、違う角度から自身を見つめ、進むべき方向を見つけてみたくなったのだ。 沢村との電話の後、1時間ほどベッドに横になり、2時過ぎに起きると、アパートの大家に、「しばらく旅行しますから」と言って3ケ月分の部屋代を手渡した。大家に「広島に帰るんですか」と訊かれ、つい「北海道へ行ってくるんです」と答え、後でそれが実家の両親の耳に届くかも知れないと思い、言わなければよかったと後悔した。 僕は数ケ月の留守を考え、冷蔵庫の中の物を整理し、台所やトイレを掃除し、雨戸を締め、思いつく限りのことをし終えると部屋に鍵をかけ、バイクに股がった。時計を見ると4時半を少し回っていた。全力で飛ばせば飯場の晩飯に間に合うかもしれない。木沼さんや隊長の顔が妙になつかしく感じられた。